 | きょうの奈良―まほろばの国の三六五日 |
| 小野久仁子 | |
| 紫紅社 |
人と会うごとに、「奈良県下では、毎日お祭りがあります」と話している。「だから、奈良に来て下さい」と。具体的な行事内容は、ええ古都なら(観光情報サイト)の「イベントカレンダー」などを見ていただいているのだが、昨年末、とても便利な本が出版された。それが小野久仁子著『きょうの奈良』(紫紅社刊)1,365円である。
版元の紹介文によると《奥の深い大和奈良の魅力を日暦で語る》《どの時期にくれば秘仏が公開されているのか、花の時期はどこの方面へ行けばいいのか、その季節にはどんな野菜が食べられるのかなど、修学旅行では訪れない奈良の魅力を、日めくりでご紹介。寺院の法会125項目、神社の祭礼77項目、奈良の四季の日々108項目、花と味の話48項目の読みごたえのあるボリュームを新書版にまとめました。大和路を歩きたくなる、奈良のイベントカレンダーの決定版!はてしなく奥行のある国、奈良。遷都1300年イベントの熱気がさめやらぬ今、もっと深い奈良をご案内します!》。
この本のことは、読売新聞奈良版(1/15付)にも、詳しく紹介されていて、著者の小野さんは「秘仏の公開はいつで、花の時期はどこに行けばよいかなど奈良の魅力を具体的に知るきっかけにしてほしい。私が読者の方々と一緒に訪れたい所を、短い文章でも臨場感を大切にして載せました」とコメントされている。
たとえば今日(3/30)のところには、薬師寺の花会式が1ページにわたって紹介されている。《「花会式(はなえしき)」とは、薬師寺の修二会のことである。東大寺二月堂の修二会が本尊十一面観音像に捧げる香水(こうずい)を汲むことから「お水取り」といわれるように、薬師寺の修二会(薬師悔過法要)は十種類の造花を本尊薬師如来像に捧げることからこうよばれる。旧暦の2月末からおこなわれていた法要を新暦に移して、3月30日から4月5日まで国家安泰、五穀豊穣、万民豊楽が祈られる》。
締めの文章は《花会式の期間中、午後1時からの日中の行の間、能や舞楽、大正琴、稚児行列などが奉納されて国家鎮護の祈りの場でありながら、春らしい華やかさが見られる法会である》。やさしい言葉でありながら正確・簡潔に、しかも情景が目に浮かぶように紹介されている。隣のページでは、ちょうど私が「開花情報」を当ブログにアップしている「奈良で最初に咲く桜 氷室神社(奈良市)」が紹介されている。
この本は、これから奈良を訪ねようとされる人はもちろん、記述が正確なので、奈良まほろばソムリエ検定(奈良検定)の最上級資格「奈良まほろばソムリエ」にチャレンジする人にも、自信を持ってお奨めできる。「こんな行事があったのか」と驚くことも多いだろうし、達意の文章は、論述試験の良いお手本になる。格好の奈良入門書として、2級受験者にもお奨めしたい。
当ブログ読者のchiyoさんも《ソムリエに81点で合格しました。実は、昨年の暮れに、偶然『きょうの奈良』という本を見つけ、試験勉強の仕上げに読んでいたのですが、大変役に立ちました。高得点で合格出来たのも、この本を読んでいたおかげかもしれません。私も、『きょうの奈良』はソムリエ受験者向けの良き参考書だと思います》と推薦されている。
目次の一部を抜粋して紹介すると
【一月】
奈良の初詣 / 陀々堂の鬼はしり / 国栖奏 / えんまもうで / 若草山山焼き ほか
【二月】
粥占い / 追儺会 / おんだ祭 / 三大梅林 / 砂かけ祭 / だだ押し / 大和まな ほか
【三月】
東大寺二月堂修二会 / 町家のひなめぐり / 春日祭 / 奈良三名椿 / 花会式 ほか
【四月】
ちゃんちゃん祭 / 桜の名所 / おたいまつ / 春の大茶盛式 / 春のけまり祭 ほか
【五月】
献氷祭 / 大和茶 / すすつけ祭 / 練供養 / うちわまき / 薪御能 / 業平忌 ほか
【六月】
蛇巻き / 黄金ちまき会式 / あきの螢能 / 虫送り三枝祭 / 柿の葉寿司 / でんでん祭 ほか
【七月】
風鈴まつり / 俊乗忌蛙飛び / 風鎮祭風神花火 / 山百合 / 子安地蔵会式 / お峰デンソソ ほか
【八月】
なら燈花会 / 中元万燈籠 / 大文字送り火 / 阿礼祭 / 大柳生の太鼓踊り / 地蔵会万燈供養 ほか
【九月】
放生会 / 山の辺の道ハイキング / 曽爾高原山灯り / 稲渕の彼岸花 / 采女祭 / 安倍仲麻呂観月祭 ほか
【十月】
塔影能 / 翁舞題目立 / 鹿の角きり / 正岡子規と奈良正倉院展 ほか
【十一月】
渡御行列 / 紅葉の名所慈恩会 / 酒まつりかぎろひを観る会 / 竜田川紅葉まつり ほか
【十二月】
厄除大根炊き / お身ぬぐい / おん祭 / ロウバイの名所 / 奈良の大晦日 ほか
冒頭のAmazonのサイトでは「なか見!検索」という立ち読みもできる。ソムリエ受験者にも2級受験者にも、奈良に詳しい人にも詳しくない人にも、辞書的に使う人にもまるごと読む人にも、とても重宝するスグレモノである。ぜひ、お読みいただきたい。















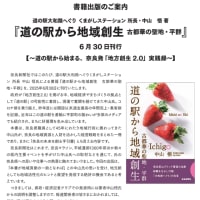









(しつこいようですが、私は「きょうの奈良」の広報担当ではありません。念のため。)
それと、本文に私のことを書いていただきなんか恐縮です。
トリビアネタ満載、要点を押さえわかりやすく書かれた良い本ですが、やはりこれだけ読んだだけではだめですよね。
私もかなりの数の奈良に関する本を読みました。「きょうの奈良」は、そのうちの一冊にすぎません。
ちなみに、たくさん読んだ本の中に、「奈良県の歴史散歩(上・下)があります。
この2冊は、2級受験時から準テキストのような感じで使っていたので、今では2冊ともボロボロです。
実は、初めて2級を受ける時、公式テキストがあまりにも読みづらいというかわかりにくかったので、何かほかに良い本はないかと書店に探しに行ったところ、「奈良県の歴史散歩(上・下)の2冊と出会ったのです。
その当時はまだ、tetsudaさんのこともこのブログのことも知りませんでしたから、インスピレーションで「これだ!」と選んだだけなのですが、最近このブログの読者となり、tetsudaさんが再三この2冊をお薦めしていることを知り、
「やはりこの本を選んで正解だったんだ。」
「やはり、この本を選んで良かった。」と実感しています。
それと、やはり現地訪問は大事ですよね。
実際に現地に足を運んで実物を見たら、本で学んで得た知識が、より一層記憶に定着しやすくなりますから。
来年1級合格を目指してがんばります。
> パラパラめくれる紙の本はまだまだ手放せま
> せんね。来年1級合格を目指してがんばります。
私はいつも通勤カバンに入れて「今日はどんな行事があるのかな」とワクワクしながらページを繰っています。初級者から、ソムリエ合格まで使える本です。あと1級対策としては、毎日新聞社刊の過去問集と、テキストの精読ですね。
> これだけ読んだだけではだめですよね。私もかなりの数の奈良に関する本を
> 読みました。「きょうの奈良」は、そのうちの一冊にすぎません。ちなみに、
> たくさん読んだ本の中に、『奈良県の歴史散歩(上・下)』があります。
私も、20冊は読みました。超精読したのは数冊ですが…。『歴史散歩』は良書です。
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/c/2c163bc707ea2f2468a2c85f89c9f6fe/2
> それと、やはり現地訪問は大事ですよね。実際に現地に足を運んで実物を
> 見たら、本で学んで得た知識が、より一層記憶に定着しやすくなりますから。
その通り、「百聞を一見で実らす」です。ソムリエは論述問題が出ますから、なおさら現地訪問が大事です。その意味で、奈良商工会議所の「体験学習プログラム」(1級受験者用ですが、1級合格者でも空きがあれば参加可)とか、南都銀行の萬葉ウォーク(年2回開催・参加無料)などは、おススメです。
http://www.nantobank.co.jp/syohin/manyou/circle/n1850w.htm
でも、それにあやかりたい気持ちもあります。
この本もしっかり読んで来年の試験合格に一歩近づきたいです。
> この本もしっかり読んで来年の試験合格に一歩近づきたいです。
夏頃までは、できるだけ手を広げて多くの本を読み、多くの場所を訪ね、秋以降は、サブノートなどにまとめながら、シッカリと暗記する、という勉強法が良いと思います。記述対策も、お忘れなく。