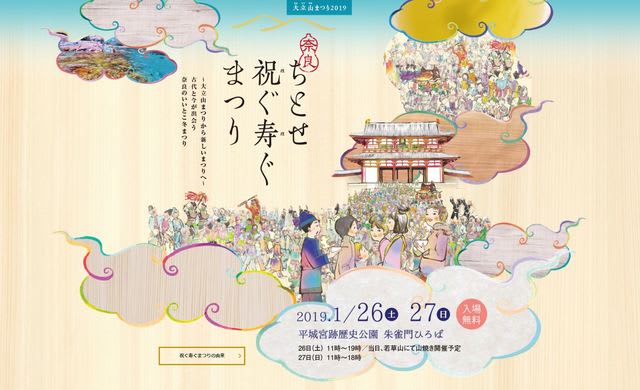「奈良ちとせ祝(ほ)ぐ寿(ほ)ぐまつり」と銘打った「大立山まつり 2019」実行委員会会長の石川重元師(海龍王寺住職)がご自身のFacebookで、「人生賭けた執念(か?!)」のタイトルでこのお祭りへの思いをお書きになっていた。師の考えがよく伝わってくる良い文章なので、ここに再掲載させていただく(Facebookのレイアウトでは、どうも読みづらいので)。ぜひ熟読玩味していただきたい。なお小見出しは私がつけた。
■人生賭けた執念
1月5日、まほろば館でさせていただいたお話について、奈良県の職員さんが「何を言っているのか、ようわからん」とおっしゃられたことに加え、元来、言葉での表現力が乏しいものですから説明しきれない部分がございました。また、会場にお見えになれなかった方にも、私がどのように考えているのかを知っていただきたいと思い、文章にさせていただくことにいたしました。
長い文章になってしまい申し訳ございませんが、平城宮跡および周辺に関しては2001年から足掛け20年弱携わっておりますし、人生賭けた執念みたいなもの(笑)もありますから、なにとぞご容赦ください。
■平城宮跡になぜ仏像(四天王像)か
大立山まつりが始まった際、会場の平城宮跡に四天王さんの立山が据えられました。据えられた理由は様々ありましたが、私自身「何で据えられたのか」腑に落ちる理由がわかりませんでした。
私の性格から「実際に四天王さんを見てきたらわかるかな?」と思い、寒い中、会場に赴き、「何で、ここに居てはるんやろう?」と思いながら四天王さんを見上げていたら「我々がここに居る理由を、誰か説明してくれへんやろか?」という思いが頭に浮かびました。「そらそうや。平城宮跡と四天王さんとのつながりを一回調べてみよう」と思い、調べ出したものの、なかなか行き当たることができません。
■1月8日から7日間行われた「御斎会」
そのような中、他の用件で後七日御修法について調べていた際、「大極殿(だいごくでん)で行われた御斎会(ごさいえ)と顕密(けんみつ)相対する」という末文に目が留まりました。密教立の後七日御修法に相対する形で「御斎会」というのがあるのだ?と。
「御斎会(ごさいえ)」て何やろう?と思い、このことについて調べてみたら、『南都三会の一つ。新春の宮廷仏事として毎年1月8日から7日間,大極殿に斎(とき)を設けて本尊盧遮那仏,観音・虚空蔵の2菩薩,四天王像を安置し,《金光明最勝王経》を講説して国家の安寧を祈願した法会。創始については766年(天平神護2)説』という一文が目に飛び込んできました。
『これやがな!』。時期もピッタリやがなと。「御斎会」に則れば、平城宮の文脈に則ったまつりになるし、何より四天王さんが平城宮跡に居はる理由を説明できると思いました。(実行委員長に就いてから、一緒に仕事をしたことがある善友が「御斎会と称徳天皇の礼服は、この時期に平城宮で四天王を祀る意味として、大立山まつりの初回からご住職が仰られていたことで云々」とのメールを送ってくれました)
■歴史の文脈を踏まえる
さてさて、実際に催しを行うことを考えた際、様々な思いが浮かびましてね。当たり前のことですが、催しって公開ですやんか。実行委員長が持っている歴史や場所に対する概念が「催し・祭事に対する軸」になってくるわけで、どのような概念を持ち、どのように表現するかが委員長のセンスに直結し、表現の方法や手段というものが、部会員のセンスに直結します。ええか悪いかということが、来ている人、事前広報を見ている人に公開審査されることになるわけです。
おまけに奈良はしっかりとした歴史的文脈の上に成り立っているわけですから「君のやっていることが歴史的文脈・場所の文脈に則っているかどうか?」を含め、私自身・部会員が、人々と歴史とに審査されることになるわけです。とりわけ奈良に関しては「厳しい審査員の方々がたくさんおられます」から、それはそれは大変なことです。
■古代をわかりやすく表現
歴史的に重要な場所での催しは「古代の例にちなんでいることを説明すること」が最も重要になりますし「主催者が場所の歴史的文脈を理解し、現代社会において意味のある文脈に編集しなおせているかどうか」という「解釈の度合い」が問われるわけですから、間違った文脈を出したら大変なことになるとともに、批判をされてしまいます。「こいつ、わかってない」って思われるわけです。えらいリスクを背負いますわ。
そやから、通常のイベントや催しの代表みたいな「華やかなええ仕事ではない」と思うわけですが、地味やけれども歴史的事象(事柄)を発展的に活かして、わかりやすく説明することが平城宮跡と我々とに求められているのではないかと思いますし、どうしたら説明できるのかを考えて、形にしていけたらと思っています。
■奈良時代の天皇は祭政一致だった
先に述べました御斎会のことを知っていくにつれ、奈良時代の天皇の信仰がわからなくなり、知られることなく埋もれてしまっているのは勿体ないことであるとともに、非常に残念なことやと思うようになりましてね。古代(奈良時代)の天皇に関しては、歴史上の人物という印象が強くなっていて、政(まつりごと)に関する出来事のみが紹介されるケースが大半になっています。
そやけど、古代においては祭祀を司る者と政治を司る者(この場合は天皇)が一致する「祭政一致の体制」であり、天皇が宮に於いて祭祀の祭りと、政治のまつり事の「2つのまつり」を執り行っておられました。(「奈良時代の天皇が古代以来の司祭者の機能を引き継ぐが故に」冠を唐風化させても、服は伝統的な白を用いたと考えられています)
■大極殿と前庭は神聖な場所
今上天皇に関する祭祀の様子は、たびたび報じられる機会があり国民もおぼろげながらに知ることができますが、古代の天皇に関しては祭祀を司る者という意識が薄くなっているように感じられていることから、認識の改革をしてゆかなくてはならないと思っていて、こうすることが大極殿と前庭が極めて重要かつ神聖な場所であったかを知っていただけるのではないかと考えています。
そうはいうものの、現在は、儀式も祭りも形式的に行われているだけならば、やらないほうがマシや、という声があることも事実です。それやったら「平城宮跡(平城宮)は、いったい次世代に何を残せるのやろう?」と、平城宮跡でイベントが始まった時から考えていて、まさに今、平城宮跡は、次世代に何を残します?と、いう状態になりつつあるのではないかと思っています。
■単なるイベント空間ではない
建物を残しても、場所(建物)の本質を知ることなく、あるいは場所(建物)の本質が残らないと、単なるイベント空間化してしまう可能性が極めて高いのではないかと考えていて、このことが「単なるイベント空間」やという烙印を押されるとともに、そういった意識が強くなっている原因ではないのかと思っていて、この意識・イメージを払拭するため、平城宮跡に関しては、ルーツ(歴史的文脈)を上手にアレンジ(再構成)して発信することをやっていかなくてはならないと考えています。(特定のイベントに関しては、すでに実践を始めています)
先ほど述べた御斎会について言うなら、復原にはほど遠いでしょうが、女帝・古代楽器の演奏者・僧侶の方々に登場していただくことで、ルーツ(歴史的文脈)である天皇の信仰および祭祀を上手にアレンジすることで古代行事の再現として行い、当時の儀式(仏事)と実際の場所とを関連づけることで、平城宮跡・大極殿に対する、今までとは違う理解を深めていただけるのではないかと思っています。
■天皇の「祈り」の場
たとえ、儀礼儀式(仏事)が形式的、再現であっても、実際に執り行われていた場所での儀礼儀式を再現することで、確かな歴史的文脈の上に脈絡のあるイベント(まつり)が行われることになり、古代を彷彿されることで、イベント(まつり)の場所が、さらに魅力的になり、その場所を「蘇生させること」になると思っています。
天皇が直接執行していた場所であるなら、なおさらですし、平城宮跡が、なぜ大事なのかと問われたら「天皇の祈りがあった場所だから」と、しっかり答えられるようにできればと思っています。
■人生賭けた執念
1月5日、まほろば館でさせていただいたお話について、奈良県の職員さんが「何を言っているのか、ようわからん」とおっしゃられたことに加え、元来、言葉での表現力が乏しいものですから説明しきれない部分がございました。また、会場にお見えになれなかった方にも、私がどのように考えているのかを知っていただきたいと思い、文章にさせていただくことにいたしました。
長い文章になってしまい申し訳ございませんが、平城宮跡および周辺に関しては2001年から足掛け20年弱携わっておりますし、人生賭けた執念みたいなもの(笑)もありますから、なにとぞご容赦ください。
■平城宮跡になぜ仏像(四天王像)か
大立山まつりが始まった際、会場の平城宮跡に四天王さんの立山が据えられました。据えられた理由は様々ありましたが、私自身「何で据えられたのか」腑に落ちる理由がわかりませんでした。
私の性格から「実際に四天王さんを見てきたらわかるかな?」と思い、寒い中、会場に赴き、「何で、ここに居てはるんやろう?」と思いながら四天王さんを見上げていたら「我々がここに居る理由を、誰か説明してくれへんやろか?」という思いが頭に浮かびました。「そらそうや。平城宮跡と四天王さんとのつながりを一回調べてみよう」と思い、調べ出したものの、なかなか行き当たることができません。
■1月8日から7日間行われた「御斎会」
そのような中、他の用件で後七日御修法について調べていた際、「大極殿(だいごくでん)で行われた御斎会(ごさいえ)と顕密(けんみつ)相対する」という末文に目が留まりました。密教立の後七日御修法に相対する形で「御斎会」というのがあるのだ?と。
「御斎会(ごさいえ)」て何やろう?と思い、このことについて調べてみたら、『南都三会の一つ。新春の宮廷仏事として毎年1月8日から7日間,大極殿に斎(とき)を設けて本尊盧遮那仏,観音・虚空蔵の2菩薩,四天王像を安置し,《金光明最勝王経》を講説して国家の安寧を祈願した法会。創始については766年(天平神護2)説』という一文が目に飛び込んできました。
『これやがな!』。時期もピッタリやがなと。「御斎会」に則れば、平城宮の文脈に則ったまつりになるし、何より四天王さんが平城宮跡に居はる理由を説明できると思いました。(実行委員長に就いてから、一緒に仕事をしたことがある善友が「御斎会と称徳天皇の礼服は、この時期に平城宮で四天王を祀る意味として、大立山まつりの初回からご住職が仰られていたことで云々」とのメールを送ってくれました)
■歴史の文脈を踏まえる
さてさて、実際に催しを行うことを考えた際、様々な思いが浮かびましてね。当たり前のことですが、催しって公開ですやんか。実行委員長が持っている歴史や場所に対する概念が「催し・祭事に対する軸」になってくるわけで、どのような概念を持ち、どのように表現するかが委員長のセンスに直結し、表現の方法や手段というものが、部会員のセンスに直結します。ええか悪いかということが、来ている人、事前広報を見ている人に公開審査されることになるわけです。
おまけに奈良はしっかりとした歴史的文脈の上に成り立っているわけですから「君のやっていることが歴史的文脈・場所の文脈に則っているかどうか?」を含め、私自身・部会員が、人々と歴史とに審査されることになるわけです。とりわけ奈良に関しては「厳しい審査員の方々がたくさんおられます」から、それはそれは大変なことです。
■古代をわかりやすく表現
歴史的に重要な場所での催しは「古代の例にちなんでいることを説明すること」が最も重要になりますし「主催者が場所の歴史的文脈を理解し、現代社会において意味のある文脈に編集しなおせているかどうか」という「解釈の度合い」が問われるわけですから、間違った文脈を出したら大変なことになるとともに、批判をされてしまいます。「こいつ、わかってない」って思われるわけです。えらいリスクを背負いますわ。
そやから、通常のイベントや催しの代表みたいな「華やかなええ仕事ではない」と思うわけですが、地味やけれども歴史的事象(事柄)を発展的に活かして、わかりやすく説明することが平城宮跡と我々とに求められているのではないかと思いますし、どうしたら説明できるのかを考えて、形にしていけたらと思っています。
■奈良時代の天皇は祭政一致だった
先に述べました御斎会のことを知っていくにつれ、奈良時代の天皇の信仰がわからなくなり、知られることなく埋もれてしまっているのは勿体ないことであるとともに、非常に残念なことやと思うようになりましてね。古代(奈良時代)の天皇に関しては、歴史上の人物という印象が強くなっていて、政(まつりごと)に関する出来事のみが紹介されるケースが大半になっています。
そやけど、古代においては祭祀を司る者と政治を司る者(この場合は天皇)が一致する「祭政一致の体制」であり、天皇が宮に於いて祭祀の祭りと、政治のまつり事の「2つのまつり」を執り行っておられました。(「奈良時代の天皇が古代以来の司祭者の機能を引き継ぐが故に」冠を唐風化させても、服は伝統的な白を用いたと考えられています)
■大極殿と前庭は神聖な場所
今上天皇に関する祭祀の様子は、たびたび報じられる機会があり国民もおぼろげながらに知ることができますが、古代の天皇に関しては祭祀を司る者という意識が薄くなっているように感じられていることから、認識の改革をしてゆかなくてはならないと思っていて、こうすることが大極殿と前庭が極めて重要かつ神聖な場所であったかを知っていただけるのではないかと考えています。
そうはいうものの、現在は、儀式も祭りも形式的に行われているだけならば、やらないほうがマシや、という声があることも事実です。それやったら「平城宮跡(平城宮)は、いったい次世代に何を残せるのやろう?」と、平城宮跡でイベントが始まった時から考えていて、まさに今、平城宮跡は、次世代に何を残します?と、いう状態になりつつあるのではないかと思っています。
■単なるイベント空間ではない
建物を残しても、場所(建物)の本質を知ることなく、あるいは場所(建物)の本質が残らないと、単なるイベント空間化してしまう可能性が極めて高いのではないかと考えていて、このことが「単なるイベント空間」やという烙印を押されるとともに、そういった意識が強くなっている原因ではないのかと思っていて、この意識・イメージを払拭するため、平城宮跡に関しては、ルーツ(歴史的文脈)を上手にアレンジ(再構成)して発信することをやっていかなくてはならないと考えています。(特定のイベントに関しては、すでに実践を始めています)
先ほど述べた御斎会について言うなら、復原にはほど遠いでしょうが、女帝・古代楽器の演奏者・僧侶の方々に登場していただくことで、ルーツ(歴史的文脈)である天皇の信仰および祭祀を上手にアレンジすることで古代行事の再現として行い、当時の儀式(仏事)と実際の場所とを関連づけることで、平城宮跡・大極殿に対する、今までとは違う理解を深めていただけるのではないかと思っています。
■天皇の「祈り」の場
たとえ、儀礼儀式(仏事)が形式的、再現であっても、実際に執り行われていた場所での儀礼儀式を再現することで、確かな歴史的文脈の上に脈絡のあるイベント(まつり)が行われることになり、古代を彷彿されることで、イベント(まつり)の場所が、さらに魅力的になり、その場所を「蘇生させること」になると思っています。
天皇が直接執行していた場所であるなら、なおさらですし、平城宮跡が、なぜ大事なのかと問われたら「天皇の祈りがあった場所だから」と、しっかり答えられるようにできればと思っています。