ミナツキハツヒ(旧暦六月朔・西暦二〇一九年七月三日)
南の夜空に、天の川がひときわ輝く、夏の至りの新月。
この旧暦六月一日に、
志摩町和具では天下の奇祭といわれる『潮かけ祭り』や富士講の『おしょうじ』が行われ、
鳥羽の国崎(くざき)では、近年まで海女の祭り『御潜神事』が行われていました。
『御潜神事』(ミカヅキシンジ・海士潜女神社)
旧暦六月一日に行われる御潜(ミカヅキ)神事は、
伊勢神宮へ奉納するアワビを採る、ヤマトヒメの志摩巡行に由来する、
遥か二千年の歴史を誇る海女の神事。
御潜神事の伝わる鳥羽市国崎町は、志摩半島の最東端。
「志摩の国の先」にあることから「くざき」と呼ぶそうです。
伊勢神宮に奉納するのは、身をそいで乾燥させた熨斗鮑です。
※国崎の「熨斗鰒づくり」の伝統技法は、平成十六年三重県無形民俗文化財に指定されました。

過去には国崎を含め、答志村、神島村、菅島村、石鏡村、相差村、安乗村が
参加して行われた志摩地方で一番大きな祭りとして知られていましたが、
明治四年の御贄献身制度の廃止に伴い、盛大な神事は絶えてしまいました。
平成十五年、パールロードの一部無料化により百三十二年ぶりに復活。
平成十八年、再び断絶。国崎の海女だけが参加する祭りとして再興されました。
平成二三・ニ四年は東日本大震災の影響で開催自粛。
平成二五年、神宮式年遷宮記念として開催。
平成二八年、伊勢志摩サミット記念として開催。
それ以降は残念ながら行われていないようです。
令和元年、復活して欲しかったですね。
また、同日に開催される海士潜女(アマカヅキメ)神社の例大祭では、
伊勢神宮から神職や舞姫(巫女)が訪れて神楽を奉納し、
海女が総出で一年の操業の安全を祈願します。
海士潜女(アマカヅキメ)神社の主祭神の潜女神(カヅキメノカミ)は、
垂仁天皇二十六年(紀元前四年)、
伊勢神宮への御贄地を求めて諸国巡幸していたヤマトヒメが国崎を訪れた際に、
アワビを献上した伝説の海女「おべん」さん。
以来、国崎は伊勢神宮の神戸に選定され、
外宮旧神楽歌に「ひめ社」として歌われていたそうです。
また、潜女神はめまい除け、トモカヅキ除けにもご利益があるとされ、
地元の海女だけでなく、日本中のダイバーの信仰も集めています。
「トモカヅキ」とは、、
鳥羽・志摩に伝わる海に潜る者にそっくりに化けるという海の妖怪で、
鉢巻の尻尾を長く伸ばしているのが特徴で、、
人を暗い場所へと誘ったり、鮑を差し出したりして、
この誘いに乗ってしまうと、命を奪われると恐れられています。
海女たちはこの怪異から逃れるため、
五芒星と格子の模様を描いた「セーマンドーマン」と呼ばれる、
魔除けを描いた服、手ぬぐいを身につけるとの説もあります。

「セーマンドーマン」は、陰陽道に由来するともいわれますが、
陰陽五行の発祥が古代中国の夏(カ)の時代というのも、
ヲシテ的には大変興味をそそられます。
ニ千年の歴史を誇る御潜神事、日頃から自然に感謝と祈りを捧げ、
海女の祭りとして伝えられた神事、、大切に遺してゆきたいですね。
参考文献・参考資料
◎ウィキペディア「海士潜女神社」「御潜神事」
◎日本紀行「国崎に海女の祭り御潜神事」
『おしょうじ・煙かぶり』(富士講・八雲神社)
志摩町和具の八雲神社の天下の奇祭『潮かけ祭り』の
前夜祭(新月前夜)に行われる、富士講の『おしょうじ・煙かぶり』は、
ヲシテ的に大変興味深いご神事。



夜七時半より行われるこのご神事、八雲神社の神主さんの御祭りの後、
ハッピ姿の若衆が真っ暗な浜辺に移動し、海に潜り、那智黒の石を拾います。
このときの掛け声が、「アートートー・アートート!」。
ご神事に参加の方々も掛け声の意味はわからないそうですが、、
真っ暗な南の夜空には、うっすらと天の川が海に架かります。
ヲシテでは、アメ・アマ(天)を「ア」で表わします。
そして、季節・方位方角の守り「ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ」、
夏は南の「ト」の守りです。
「アートートー・アートート」の掛け声は、
まさに新月の夜の「南天から降り注ぐ天の川」を祭っているのかもしれません。
那智黒の石をいただいて持ち帰り、一年間お守りとします。
漁港広場では、藁を燃やして火をおこし、海に潜った若衆が、
集まった人々の頭をひとりひとりお数珠でなでながら、無病息災を祈ります。
私も石をいただき、頭をなでてもらいました♡ありがたや


初代アマカミ・クニトコタチのヤミコ(八皇子・トホカミヱヒタメ)のうち、
「ト」のミコトは、富士山南麓(富士宮浅間大社付近)に繁栄しました。
富士山は南の象徴、そして一番天に近いところです。
那智黒石を拾う若衆は、事前に富士山頂へお参りする風習も大変興味深いです。
参考文献・参考資料 ◎志摩市ホームページ。
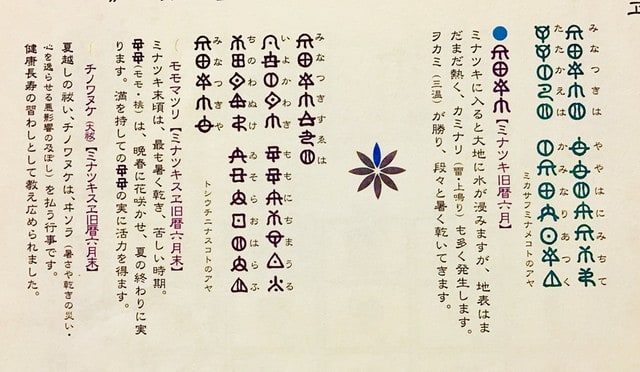
みなつきは ややはにみちて
たたかえは かみなりあつく ミカサフミナメコトのアヤ
●【ミナツキ:旧暦六月】
ミナツキに入ると大地に水が浸みますが、
地表はまだまだ熱く、カミナリ(雷・上鳴り)も多く発生します。
ヲカミ(三温)が勝り、段々と暑く乾いてきます。
みなづきすえは
いよかわき ももにちまうる
ちのわぬけ ゐそらおはらふ
みなつきや トシウチニナスコトのアヤ
☾モモマツリ【ミナツキスヱ(旧暦六月末)】
ミナツキ末頃は、最も暑く乾き、苦しい時期。
モモ(桃)は、晩春に花咲かせ、夏の終わりに実ります。
満を持してのモモの実に活力を得ます。
☾チノワヌケ(大祓)【ミナツキスヱ(旧暦六月末)】
夏越しの祓い。
チノワヌケは、ヰソラ(暑さや乾きの災い・心を逸らせる悪影響の及ぼし)を払う行事です。
健康長寿の習わしとして教え広められました。
チノワヌケ、、紀元前からの行事とは驚きです!
※ホツマツタヱ《十アヤ・カシマタチ・ツリタイのアヤ》より
ミホヒコのつま
スヱツミが イクタマヨリメ
ソヤコうむ コシアチハセの
シラタマメ ソヤのひめうむ
ミソムたり ゆだねひたせは
みことのり たまふヲシテは
コモリカミ セミのおかわに
みそぎして チノワにたゝす
ミナツキや タミながらふる
はらいなりけり
クシヒコ(二代モノヌシ)とミホツヒメとの間に一人産まれたミホヒコは、
ヨロギマロと呼ばれ、薬草園のおかげで医学に秀でた特技を得、
後にニニキネの病を治したりと大活躍します。
ミホヒコ(三代モノヌシ・コモリカミ)は、妻を二人迎えます。
スヱツミの娘、イクタマヨリヒメは、十八人の男の子を産みました。
※スヱツミ:陶荒田神社・大阪府堺市中区。弥生土器の量産に成功したと考えられます。
コシのアチハセの娘、シラタマヒメは、十八人の女の子を産み、
合せて三十六人の子宝に恵まれ、アマテルカミより「コモリカミ」の称号の
ヲシテ(文書)を授けられました。
コモリカミは病除けに、夏の終わりにミソギをして体調を整えます。
ミナツキの末は、一年の折り返しの時、その隙間に魔が入り込まないよう、
セミの小川(下鴨神社・糺すの森の瀬見の小川)にミソギをして、
障りを払うため、さらにチノワ(茅の輪・大自然のエネルギーの集まる循環の輪)を潜り、
夏から秋への季節の変わりを心身に実感させるのです。
ミナツキ(旧暦六月)の末のミソギとチノワ抜けの行事は、
健康長寿への習わしとコモリカミは一般の人にも教え広めました。
※セミのオガワ:下鴨神社社叢の糺すの森を流れる小川
コモリカミの父クシヒコが、京都盆地の開発に携わっていたことから、
タタスのモリにもよく来ていたと推察されます。
当時は、下鴨神社創建以前でしたので、鬱蒼とした原生林に近い森であったと思われます。
※コモリの子供達は、京都盆地の開発に貢献し、神社や地名としても残っています。
八坂神社(京都市東山区祇園町北側) ヤサカヒコ(八男)
太田神社(京都市北区上賀茂本山) オオタ(十一男)
石座神社(京都市左京区岩倉上蔵町) イワクラ(十二男):
参考:
◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社
◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」
http://www.zb.ztv.ne.jp/woshite/index.html
◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社
◎『よみがえる日本語』青木純雄・平岡憲人著・明治書院
※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。
南の夜空に、天の川がひときわ輝く、夏の至りの新月。
この旧暦六月一日に、
志摩町和具では天下の奇祭といわれる『潮かけ祭り』や富士講の『おしょうじ』が行われ、
鳥羽の国崎(くざき)では、近年まで海女の祭り『御潜神事』が行われていました。
『御潜神事』(ミカヅキシンジ・海士潜女神社)
旧暦六月一日に行われる御潜(ミカヅキ)神事は、
伊勢神宮へ奉納するアワビを採る、ヤマトヒメの志摩巡行に由来する、
遥か二千年の歴史を誇る海女の神事。
御潜神事の伝わる鳥羽市国崎町は、志摩半島の最東端。
「志摩の国の先」にあることから「くざき」と呼ぶそうです。
伊勢神宮に奉納するのは、身をそいで乾燥させた熨斗鮑です。
※国崎の「熨斗鰒づくり」の伝統技法は、平成十六年三重県無形民俗文化財に指定されました。

過去には国崎を含め、答志村、神島村、菅島村、石鏡村、相差村、安乗村が
参加して行われた志摩地方で一番大きな祭りとして知られていましたが、
明治四年の御贄献身制度の廃止に伴い、盛大な神事は絶えてしまいました。
平成十五年、パールロードの一部無料化により百三十二年ぶりに復活。
平成十八年、再び断絶。国崎の海女だけが参加する祭りとして再興されました。
平成二三・ニ四年は東日本大震災の影響で開催自粛。
平成二五年、神宮式年遷宮記念として開催。
平成二八年、伊勢志摩サミット記念として開催。
それ以降は残念ながら行われていないようです。
令和元年、復活して欲しかったですね。
また、同日に開催される海士潜女(アマカヅキメ)神社の例大祭では、
伊勢神宮から神職や舞姫(巫女)が訪れて神楽を奉納し、
海女が総出で一年の操業の安全を祈願します。
海士潜女(アマカヅキメ)神社の主祭神の潜女神(カヅキメノカミ)は、
垂仁天皇二十六年(紀元前四年)、
伊勢神宮への御贄地を求めて諸国巡幸していたヤマトヒメが国崎を訪れた際に、
アワビを献上した伝説の海女「おべん」さん。
以来、国崎は伊勢神宮の神戸に選定され、
外宮旧神楽歌に「ひめ社」として歌われていたそうです。
また、潜女神はめまい除け、トモカヅキ除けにもご利益があるとされ、
地元の海女だけでなく、日本中のダイバーの信仰も集めています。
「トモカヅキ」とは、、
鳥羽・志摩に伝わる海に潜る者にそっくりに化けるという海の妖怪で、
鉢巻の尻尾を長く伸ばしているのが特徴で、、
人を暗い場所へと誘ったり、鮑を差し出したりして、
この誘いに乗ってしまうと、命を奪われると恐れられています。
海女たちはこの怪異から逃れるため、
五芒星と格子の模様を描いた「セーマンドーマン」と呼ばれる、
魔除けを描いた服、手ぬぐいを身につけるとの説もあります。

「セーマンドーマン」は、陰陽道に由来するともいわれますが、
陰陽五行の発祥が古代中国の夏(カ)の時代というのも、
ヲシテ的には大変興味をそそられます。
ニ千年の歴史を誇る御潜神事、日頃から自然に感謝と祈りを捧げ、
海女の祭りとして伝えられた神事、、大切に遺してゆきたいですね。
参考文献・参考資料
◎ウィキペディア「海士潜女神社」「御潜神事」
◎日本紀行「国崎に海女の祭り御潜神事」
『おしょうじ・煙かぶり』(富士講・八雲神社)
志摩町和具の八雲神社の天下の奇祭『潮かけ祭り』の
前夜祭(新月前夜)に行われる、富士講の『おしょうじ・煙かぶり』は、
ヲシテ的に大変興味深いご神事。



夜七時半より行われるこのご神事、八雲神社の神主さんの御祭りの後、
ハッピ姿の若衆が真っ暗な浜辺に移動し、海に潜り、那智黒の石を拾います。
このときの掛け声が、「アートートー・アートート!」。
ご神事に参加の方々も掛け声の意味はわからないそうですが、、
真っ暗な南の夜空には、うっすらと天の川が海に架かります。
ヲシテでは、アメ・アマ(天)を「ア」で表わします。
そして、季節・方位方角の守り「ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ」、
夏は南の「ト」の守りです。
「アートートー・アートート」の掛け声は、
まさに新月の夜の「南天から降り注ぐ天の川」を祭っているのかもしれません。
那智黒の石をいただいて持ち帰り、一年間お守りとします。
漁港広場では、藁を燃やして火をおこし、海に潜った若衆が、
集まった人々の頭をひとりひとりお数珠でなでながら、無病息災を祈ります。
私も石をいただき、頭をなでてもらいました♡ありがたや


初代アマカミ・クニトコタチのヤミコ(八皇子・トホカミヱヒタメ)のうち、
「ト」のミコトは、富士山南麓(富士宮浅間大社付近)に繁栄しました。
富士山は南の象徴、そして一番天に近いところです。
那智黒石を拾う若衆は、事前に富士山頂へお参りする風習も大変興味深いです。
参考文献・参考資料 ◎志摩市ホームページ。
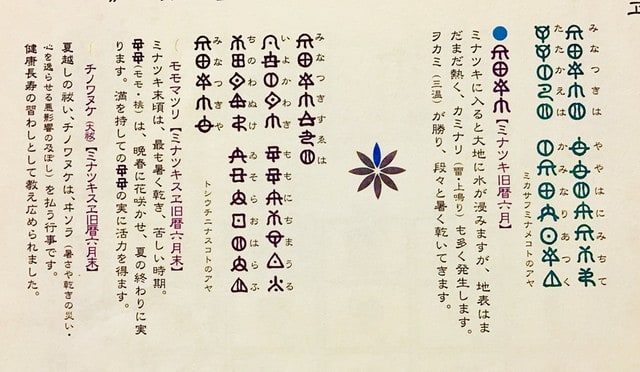
みなつきは ややはにみちて
たたかえは かみなりあつく ミカサフミナメコトのアヤ
●【ミナツキ:旧暦六月】
ミナツキに入ると大地に水が浸みますが、
地表はまだまだ熱く、カミナリ(雷・上鳴り)も多く発生します。
ヲカミ(三温)が勝り、段々と暑く乾いてきます。
みなづきすえは
いよかわき ももにちまうる
ちのわぬけ ゐそらおはらふ
みなつきや トシウチニナスコトのアヤ
☾モモマツリ【ミナツキスヱ(旧暦六月末)】
ミナツキ末頃は、最も暑く乾き、苦しい時期。
モモ(桃)は、晩春に花咲かせ、夏の終わりに実ります。
満を持してのモモの実に活力を得ます。
☾チノワヌケ(大祓)【ミナツキスヱ(旧暦六月末)】
夏越しの祓い。
チノワヌケは、ヰソラ(暑さや乾きの災い・心を逸らせる悪影響の及ぼし)を払う行事です。
健康長寿の習わしとして教え広められました。
チノワヌケ、、紀元前からの行事とは驚きです!
※ホツマツタヱ《十アヤ・カシマタチ・ツリタイのアヤ》より
ミホヒコのつま
スヱツミが イクタマヨリメ
ソヤコうむ コシアチハセの
シラタマメ ソヤのひめうむ
ミソムたり ゆだねひたせは
みことのり たまふヲシテは
コモリカミ セミのおかわに
みそぎして チノワにたゝす
ミナツキや タミながらふる
はらいなりけり
クシヒコ(二代モノヌシ)とミホツヒメとの間に一人産まれたミホヒコは、
ヨロギマロと呼ばれ、薬草園のおかげで医学に秀でた特技を得、
後にニニキネの病を治したりと大活躍します。
ミホヒコ(三代モノヌシ・コモリカミ)は、妻を二人迎えます。
スヱツミの娘、イクタマヨリヒメは、十八人の男の子を産みました。
※スヱツミ:陶荒田神社・大阪府堺市中区。弥生土器の量産に成功したと考えられます。
コシのアチハセの娘、シラタマヒメは、十八人の女の子を産み、
合せて三十六人の子宝に恵まれ、アマテルカミより「コモリカミ」の称号の
ヲシテ(文書)を授けられました。
コモリカミは病除けに、夏の終わりにミソギをして体調を整えます。
ミナツキの末は、一年の折り返しの時、その隙間に魔が入り込まないよう、
セミの小川(下鴨神社・糺すの森の瀬見の小川)にミソギをして、
障りを払うため、さらにチノワ(茅の輪・大自然のエネルギーの集まる循環の輪)を潜り、
夏から秋への季節の変わりを心身に実感させるのです。
ミナツキ(旧暦六月)の末のミソギとチノワ抜けの行事は、
健康長寿への習わしとコモリカミは一般の人にも教え広めました。
※セミのオガワ:下鴨神社社叢の糺すの森を流れる小川
コモリカミの父クシヒコが、京都盆地の開発に携わっていたことから、
タタスのモリにもよく来ていたと推察されます。
当時は、下鴨神社創建以前でしたので、鬱蒼とした原生林に近い森であったと思われます。
※コモリの子供達は、京都盆地の開発に貢献し、神社や地名としても残っています。
八坂神社(京都市東山区祇園町北側) ヤサカヒコ(八男)
太田神社(京都市北区上賀茂本山) オオタ(十一男)
石座神社(京都市左京区岩倉上蔵町) イワクラ(十二男):
参考:
◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社
◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」
http://www.zb.ztv.ne.jp/woshite/index.html
◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社
◎『よみがえる日本語』青木純雄・平岡憲人著・明治書院
※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。

























