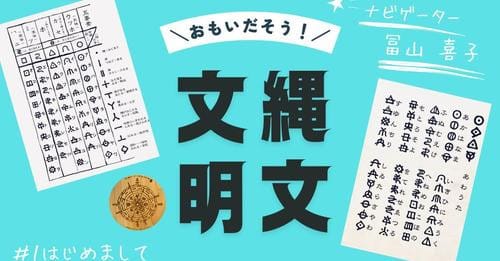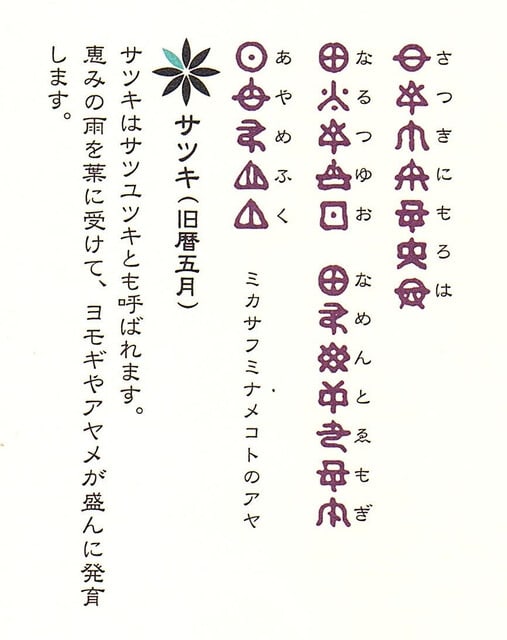「縄文ヲシテ勉強会」・「縄文カレンダーワークショップ」
現在、gooブログよりamebloに手作業でお引越し中です。
夏休み中の宿題ということで、、💦💦
更新した勉強会のお知らせは
【こちら】です!
お手数おかけいたします。
よろしくお願いします。
旧暦では6/25がミナツキハツヒ、旧暦6月1日新月を迎えます。
しかも今年は7/25より旧暦閏ミナツキ!
旧暦の夏越の茅の輪抜けはなんと8/22!!
今年は「夏が長い」と思っていれば間違いないです
 【縄文ヲシテ勉強会】
【縄文ヲシテ勉強会】
アーカイブでご利用いただけます(*^^)v
※縄文ヲシテの基礎知識やヲシテ文字の仕組みなど、
ぎゅっと詰まった
アーカイブ動画もお求めいただけます。
・はじめに 縄文カレンダーワークショップ@イトナミダイセン芸術祭より
・第一回アワウタのお話(ホツマツタヱ1アヤ・キツのナとホムシさるアヤ)
・第二回縄文の素晴らしきワカの叡智(ホツマツタヱ1アヤ・キツのナとホムシさるアヤ)
・第三回縄文の尊き祖先の軌跡(ホツマツタヱ2アヤ・アメナナヨ トコミキのアヤ)
・第四回あなにえや再興の軌跡(ホツマツタヱの3アヤ・ヒヒメ ミヲうむトノのアヤ)
お申し込みは↓こちらから
【縄文ヲシテ勉強会】シェアガイド冨山喜子
7月8月の勉強会のお知らせです。
7月26日現在の開催予定です。
随時更新いたします。
初めての方でもどうぞお気軽にご参加ください(*^^)v
🌟youtubeヲシテム:
https://www.youtube.com/@%E3%83%B2%E3%82%B7%E3%83%86%E3%83%A0
🌟Xヲシテム:
https://x.com/yoshico10380
🌟Instagram:
https://www.instagram.com/yoshico449/
youtubeヲシテム✨️Live配信「ほつまことほぎ」
https://www.youtube.com/@%E3%83%B2%E3%82%B7%E3%83%86%E3%83%A0
◎毎月1日・15日21時~22時
8月は1日(金曜)と15日(金曜)21時から。
トホカミヱヒタメ暦・縄文カレンダーを通して、
縄文の宇宙観、季節感、マツリの由来や
ヲシテ文字を読み解くヒントなどゆるく楽しくシェアしています。
アワウタコーナーでは、
♪真夏の夜の夢♪などなど~お楽しみに♪
アーカイブでいつでもお聴きいただけます。
ご活用ください(*^^)v
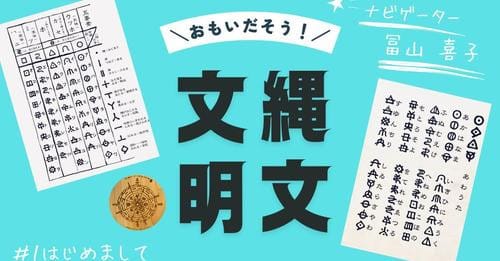 ◆7月18日(金) 【志摩】
◆7月18日(金) 【志摩】あめつちの館2F遊なぎ
※遊なぎは空調設備不良のため開催場所が変更となりました。
急遽、協賛者の中村さんのご自宅(磯部町的矢)での開催となりました。
参加ご希望の方はご一報ください。yoshico1018@yahoo.co.jp
◎20時~22時
◎協賛金2000円/テキスト1000円
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」後半
◆7月20日(日) 【多気】菜食ゆにわ
◎12時~15時
◎場所:菜食ゆにわ 多気郡多気町片野1213 ☎0598-49-2812
◎縄文・ほつまことほぎ勉強会
◎参加費:3000/(菜食ランチ付)・2000/(ランチ無・13時~15時)
※縄文カレンダー2025版別途1000/・テキスト⑨(25-26アヤ)別途1000/
お持ちの方はご持参ください。
※要予約!
◎内容:ホツマツタヱ25アヤ「ヒコミコト チおヱルのアヤ」
◆7月29日(火)【東京】久我山LaniHonua
『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半
◎場所 : LaniHonua 杉並区久我山
◎参加費:2000/ 縄文カレンダー2025年度版別途1000/ テキスト⑤(15-16アヤ)別途1000/
◎内容:ホツマツタヱ14アヤ「ヨツキノル ノトコトのアヤ」
◎内容:ホツマツタヱ15アヤ「ミケヨロズナリソメのアヤ」
※参加ご希望の方はご一報ください。yoshico1018@yahoo.co.jp
◆7月30日(水) 【飯能】名栗の杜
◎12時半~15時半
◎場所:名栗の杜 埼玉県飯能市上名栗571 ☎042-979-0646
◎ホツマツタヱの23~24アヤ 古代の叡知への誘い
◎参加費:2500/ 定員:10名
※縄文カレンダー2025版別途1500/・テキスト⑧(23-24アヤ)別途1000/
お持ちの方はご持参ください。
◎内容:ホツマツタヱ23アヤ「ミハサタメ ツルギナのアヤ」
※当日は休業日になります。
ご希望の方、酵素玄米のお稲荷さんと具沢山のお味噌汁を800円にてお出しいたします。
ご予約ください。
◆8月6日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ
◎13時~15時 ※ランチタイム;12時~
◎場所:ゲストハウスなごみ 度会郡大紀町永会2692-2
◎ほつまことほぎ勉強会
◎参加費:3000/(ランチ付)・2000/(ランチ無・13時~15時)
※縄文カレンダー2025版別途1500/・テキスト⑥(15-16アヤ)別途1000/
◎定員;10名 要予約! 携帯090-2140-9707
◎内容:ホツマツタヱ16アヤ「ハラミツツシムオビのアヤ」
◆8月8日(金)【志摩】ホツマなんばり勉強会
◎内容:ホツマツタヱ2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」
◆8月18日(月)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】
◎ 19時~20時半
◎内容【アマテルカミご誕生秘話】
ホツマツタヱの4アヤ「ヒノカミのミツミナのアヤ」
※当日ZOOM参加できなくても(*^^)vアーカイブあります。
※対面参加もあります。(大阪市北区)参加ご希望の方はご一報ください。
yoshico1018@yahoo.co.jp
◆8月24日(日) 【明和町】
◎内容:ホツマツタヱ2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」
◆8月26日(火)【東京】久我山LaniHonua
『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半
◎場所 : LaniHonua 杉並区久我山
◎参加費:2000/ 縄文カレンダー2025年度版別途1000/ テキスト⑤(15-16アヤ)別途1000/
◎内容:ホツマツタヱ15アヤ「ミケヨロズナリソメのアヤ」
※参加ご希望の方はご一報ください。yoshico1018@yahoo.co.jp
◆8月27日(水) 【飯能】名栗の杜
◎12時半~15時半
◎場所:名栗の杜 埼玉県飯能市上名栗571 ☎042-979-0646
◎ホツマツタヱの23~24アヤ 古代の叡知への誘い
◎参加費:2500/ 定員:10名
※縄文カレンダー2025版別途1500/・テキスト⑧(23-24アヤ)別途1000/
お持ちの方はご持参ください。
◎内容:ホツマツタヱ23アヤ「ミハサタメ ツルギナのアヤ」
※当日は休業日になります。
ご希望の方、酵素玄米のお稲荷さんと具沢山のお味噌汁を800円にてお出しいたします。
ご予約ください。
◆9月21日(日) 【多気】菜食ゆにわ
◎12時~15時
◎場所:菜食ゆにわ 多気郡多気町片野1213 ☎0598-49-2812
◎縄文・ほつまことほぎ勉強会
◎参加費:3000/(菜食ランチ付)・2000/(ランチ無・13時~15時)
※縄文カレンダー2025版別途1000/・テキスト⑨(25-26アヤ)別途1000/
お持ちの方はご持参ください。
※要予約!
◎内容:ホツマツタヱ26アヤ「ウカヤ アオイカツラのアヤ」
 『縄文カレンダー』2025年度・令和7年度版
『縄文カレンダー』2025年度・令和7年度版
詳細はこちら↓
https://blog.goo.ne.jp/ten380445/e/a0491dc7a142930a62a3a4e708b84fbe
ご希望の際は、
お送り先のご住所、氏名、希望冊数を明記の上、
メールにてお知らせください。
メッセンジャーでもOKです。
夏至を過ぎましたので、1冊送料込1000円でお願いします。
mail:yoshico1018@yahoo.co.jp
どうぞよろしくお願いいたします!
※終了しました。
◆1月7日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ
◎ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ12アヤ「アマガツのアヤ」
◆1月12日(日) 【明和町】
◎縄文カレンダーワークショップ
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」
◆1月19日(日) 【多気】菜食ゆにわ
◎縄文・ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ23アヤ「ミハさため・ツルギナのアヤ」
◆1月24日 【志摩】ホツマなんばり勉強会
◆1月28日(火・旧暦大晦日)【東京】久我山LaniHonua
『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半
◎内容:ホツマツタヱ12アヤ「アマガツのアヤ」
◆1月29日(水・旧暦元旦) 【飯能】名栗の杜
◎ホツマツタヱの17~19アヤ 古代の叡知への誘い
◎内容:ホツマツタヱ18アヤ「オノコロとマジナフのアヤ」
◆2月16日(日) 【多気】菜食ゆにわ
◎縄文・ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ23アヤ「ミハさため・ツルギナのアヤ」
◆2月18日(火)【東京】久我山LaniHonua
『ヲシテ勉強&お話会』
◎内容:ホツマツタヱ12アヤ「アマガツのアヤ」
◆2月19日(水) 【飯能】名栗の杜
◎ホツマツタヱの17~19アヤ 古代の叡知への誘い
◎内容:ホツマツタヱ19アヤ「ノリノリ・ヒトヌキマのアヤ」
◆3月4日(火)【志摩】ホツマなんばり勉強会
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」前半
◆3月16日(日) 【多気】菜食ゆにわ
◎縄文・ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ24アヤ「コヱクニ・ハラミヤマのアヤ」前半
◆3月21日(金) 【明和町】
◎縄文カレンダーワークショップ
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」前半
◆3月25日(火)【東京】久我山LaniHonua
『ヲシテ勉強&お話会』
◆3月26日(水) 【飯能】名栗の杜
◎ホツマツタヱの20~22アヤ 古代の叡知への誘い
◎内容:ホツマツタヱ20アヤ「スメミマコ・トクサヱルアヤ」
◆4月11日(金)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】
◎内容【アワウタのお話】
◆4月13日(日) 【明和町】
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」
◆4月15日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ
◎内容:ホツマツタヱ13アヤ「ワカヒコ・イセススカのアヤ」
◆4月18日(金)【志摩】ホツマなんばり勉強会
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」後半
◆4月20日(日) 【多気】菜食ゆにわ
◎縄文・ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ24アヤ「コヱクニ・ハラミヤマのアヤ」後半
◆4月22日(火)【東京】久我山LaniHonua
『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半
◎内容:ホツマツタヱ13アヤ「ワカヒコ・イセススカのアヤ」
◆4月23日(水) 【飯能】名栗の杜
◎ホツマツタヱの20~22アヤ 古代の叡知への誘い
◎内容:ホツマツタヱ21アヤ「ニハリミヤ・ノリサタムアヤ」
◆5月9日(金) 【志摩】あめつちの館2F遊なぎ
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」
◆5月12日(月)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】
◎内容【縄文のワカの叡智お話】ホツマツタヱの1アヤ
◆5月13日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ
◎ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ14アヤ「ヨツキノル・ノトコトのアヤ」
◆5月18日(日) 【明和町】
◎縄文カレンダーワークショップ
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」
◆5月25日(日) 【多気】菜食ゆにわ
◎縄文・ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ24アヤ「コヱクニ・ハラミヤマのアヤ」後半
◆5月27日(火)【東京】久我山LaniHonua
『ヲシテ勉強&お話会』
◎内容:ホツマツタヱ13アヤ「ワカヒコ・イセススカのアヤ」
◆5月28日(水) 【飯能】名栗の杜
◎ホツマツタヱの20~22アヤ 古代の叡知への誘い
◎内容:ホツマツタヱ21アヤ「ニハリミヤ・ノリサタムアヤ」
◆6月9日(月)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】
◎内容【縄文の尊き祖先の軌跡】
ホツマツタヱの2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」
婚儀の際の「ミキ(お酒)」の謂れを、「宇宙のはじまり」から説いています。
初代アマカミ・クニトコタチから七代イサナギ・イサナミまでの歴史と
ヒマナツリの起源についてのお話も!
※対面参加も可能です。(大阪市北区)
◆6月10日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ
◎ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ15アヤ「ミケヨロズ ナリソメのアヤ」
◆6月13日(金)【志摩】ホツマなんばり勉強会
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」後半
◆6月15日(日) 【明和町】
◎内容:ホツマツタヱ2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」
◆6月20日(金) 【志摩】あめつちの館2F遊なぎ
◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」前半
◆6月22日(日) 【多気】菜食ゆにわ
◎縄文・ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ25アヤ「ヒコミコト チおヱルのアヤ」
◆6月24日(火)【東京】久我山LaniHonua
『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半
◎内容:ホツマツタヱ14アヤ「ヨツキノル ノトコトのアヤ」
◆6月25日(水) 【飯能】名栗の杜
◎ホツマツタヱの20~22アヤ 古代の叡知への誘い
◎内容:ホツマツタヱ22アヤ「オキツヒコ ヒミツのハラヒ」
◆7月7日(月)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】
◎内容【あなにえや再興の軌跡】
ホツマツタヱの3アヤ「ヒヒメ ミヲうむトノのアヤ」
◆7月8日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ
◎ほつまことほぎ勉強会
◎内容:ホツマツタヱ16アヤ「ハラミツツシムオビのアヤ」
◆7月13日(日) 【明和町】
◎内容:ホツマツタヱ2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」