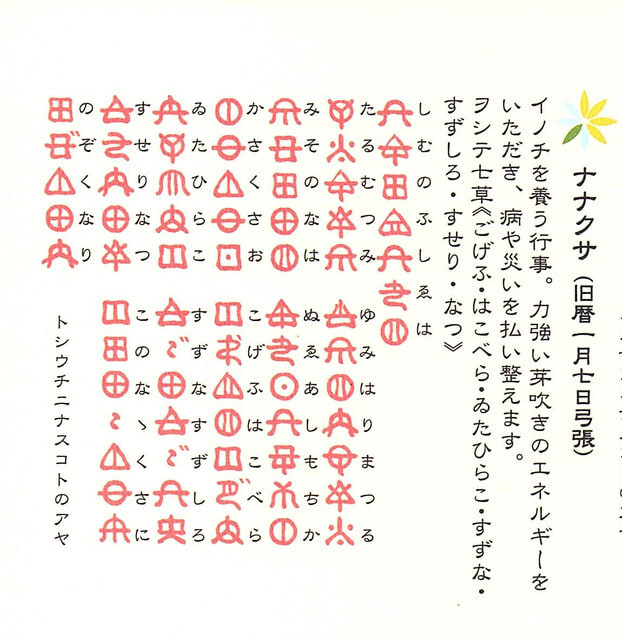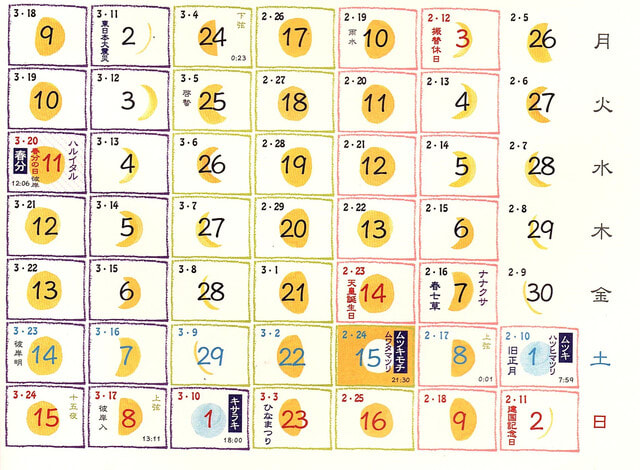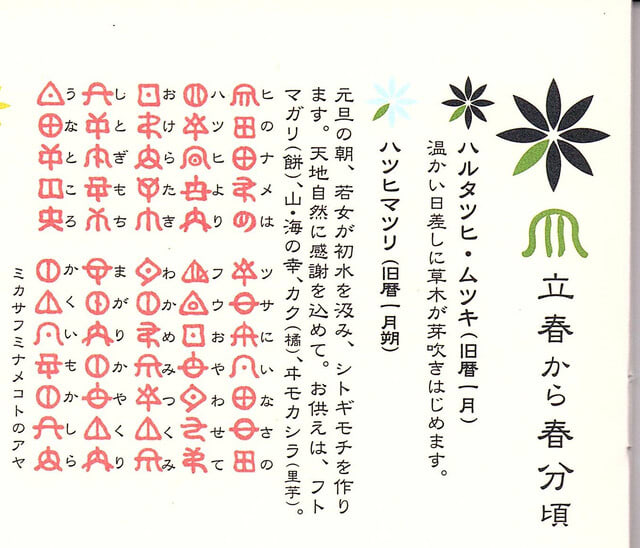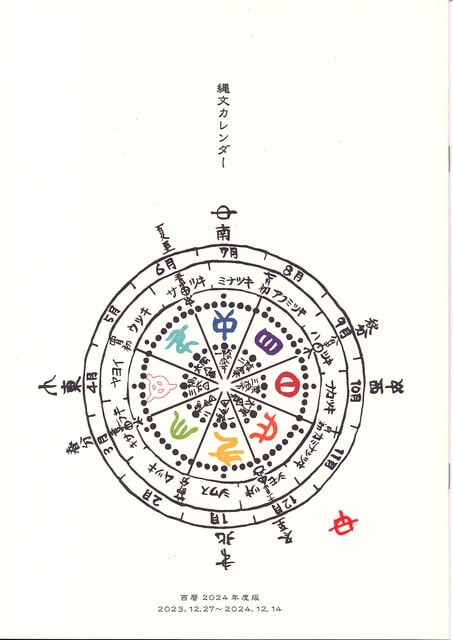●ムワタマツリ・トンドモチ【ムツキモチ(旧暦一月望・小正月)】
初春の満月!
旧暦ムツキ十五夜お月さま
西暦2024.2.24、21:30にmaxとなります。
日暮れからご来光までの夜空を一晩中照らす満月!
その朝にいただく小豆粥!
満月のエネルギー♡水に浸した小豆の月光浴!
アツキカユ、ヲシテ文字で感じるとまさにまさになヒモロケです!
恐るべし縄文の叡智✨
1月15日といえば、数年前までは成人式の祝日でした。
初春の満々の満月のエネルギーに因んでいたのではと思います。
成人を迎えられた方々へ謹んでお祝い申し上げます。
春、キザス東、のぼる朝日の波に乗り~いよいよです!

いつかの月の出。

もちのあさほぎ
あつきかゆ さむさにやふる
わたゑやみ さやけをけらに
とんどもち ゑさるかみあり トシウチニナスコトのアヤ
モチ(満月)の明けた朝に、ヒモロケ(日月のエネルギーの備わった食物)の
アツキ・カユ(小豆粥)で祝い、ワタ(内臓)へのヱヤミ(病気)を防ぎます。
ササ(笹・竹)、オケラ(薬草)を焚き、
モチ(トンドモチ・餅)を焼いてカユ(粥)に入れます。
小豆粥にお餅♡おしるこちゃんですね♪
現在でも1月15日は「鏡開き」・「トンド焼き」(左義長・小正月の火祭行事)が
全国各地で行われていますが、なんとヒノモト縄文起源の風習といえます!
日本のお正月♡
めをおえば もちのあしたは
ひもろけの あづきのかゆに
ゑやみよけ ささおけとんど
もちやきて かゆはしらなす
かみありの かゆふとまにや ミカサフミナメコトのアヤ
カユハシラナスカミアリのカユフトマニとは、
かゆ(カユ・来たりて跳ね返る様)のウラナイ(見えない世界の成り行く方向を知る)です。
※『宇治山田市史』宇治山田市役所編の年中行事より、
◎御竈木神事【正月十五日】「宮中神事」
神宮に御薪を奉納することで、これは昔、
朝廷にて臣下の薪を献ずる儀のあったのを移して、神前にも奉る式としたものであろう。
この日、一禰宜七荷、余の禰宜各六荷、権禰宜は各五荷、六位の権禰宜・大内人等は各三荷、
小内人は各二荷、諸社の祝部等は各一荷という定であった。
其の木は長さ七尺余りの白削りの細木で、九本を一荷としてある。
之を石壺の上に据えて「御木の数三千五百荷御入り候ふ」と申し、
政所が祝詞を奏し了って、御薪をば忌火屋殿に納める。
神事の祝詞には、
「吾々のかく奉るさまをば、平らけく安らけく聞食して朝廷賓位(みかどのみくらい)」は
動くことなく、常磐(ときわ)に堅磐(かきわ)に、夜の守日の守に護り幸い奉りたまひ
生まれまさむ皇子達をも慈しみ給ひ、百官(ももつかさ)に奉仕(つかえまつ)る人等をも
平らけく、安らけく、天下四方(あめのしたよも)の人民(おほみたから)の作る
五穀(いつくさのたなつもの)も豊かにめぐみ幸ひ給へ」
と祈る所に国民思想の明らかなる反映を見る。
訓読みのやまとことはのなんと美しい響き♡
◎小豆粥【正月十五日】「民間行事」
松飾りは、十四日の夜に納めるので、十五日朝に粥柱の角切餅を入れた小豆粥を煮、
飾りを取り去った跡へ供えるので、飾揚げの祝とも云った。※五十鈴落葉
参考文献・参考資料
◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社
◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」
◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社
◎『縄文カレンダー』冨山喜子編
◎『宇治山田市史』宇治山田市役所編 国書刊行会
◎『志摩の民俗』三重県郷土史料刊行会 著者:鈴木敏雄
◎『伊勢神宮』ホームページhttp://www.isejingu.or.jp/index.html
※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。
初春の満月!
旧暦ムツキ十五夜お月さま
西暦2024.2.24、21:30にmaxとなります。
日暮れからご来光までの夜空を一晩中照らす満月!
その朝にいただく小豆粥!
満月のエネルギー♡水に浸した小豆の月光浴!
アツキカユ、ヲシテ文字で感じるとまさにまさになヒモロケです!
恐るべし縄文の叡智✨
1月15日といえば、数年前までは成人式の祝日でした。
初春の満々の満月のエネルギーに因んでいたのではと思います。
成人を迎えられた方々へ謹んでお祝い申し上げます。
春、キザス東、のぼる朝日の波に乗り~いよいよです!

いつかの月の出。

もちのあさほぎ
あつきかゆ さむさにやふる
わたゑやみ さやけをけらに
とんどもち ゑさるかみあり トシウチニナスコトのアヤ
モチ(満月)の明けた朝に、ヒモロケ(日月のエネルギーの備わった食物)の
アツキ・カユ(小豆粥)で祝い、ワタ(内臓)へのヱヤミ(病気)を防ぎます。
ササ(笹・竹)、オケラ(薬草)を焚き、
モチ(トンドモチ・餅)を焼いてカユ(粥)に入れます。
小豆粥にお餅♡おしるこちゃんですね♪
現在でも1月15日は「鏡開き」・「トンド焼き」(左義長・小正月の火祭行事)が
全国各地で行われていますが、なんとヒノモト縄文起源の風習といえます!
日本のお正月♡
めをおえば もちのあしたは
ひもろけの あづきのかゆに
ゑやみよけ ささおけとんど
もちやきて かゆはしらなす
かみありの かゆふとまにや ミカサフミナメコトのアヤ
カユハシラナスカミアリのカユフトマニとは、
かゆ(カユ・来たりて跳ね返る様)のウラナイ(見えない世界の成り行く方向を知る)です。
※『宇治山田市史』宇治山田市役所編の年中行事より、
◎御竈木神事【正月十五日】「宮中神事」
神宮に御薪を奉納することで、これは昔、
朝廷にて臣下の薪を献ずる儀のあったのを移して、神前にも奉る式としたものであろう。
この日、一禰宜七荷、余の禰宜各六荷、権禰宜は各五荷、六位の権禰宜・大内人等は各三荷、
小内人は各二荷、諸社の祝部等は各一荷という定であった。
其の木は長さ七尺余りの白削りの細木で、九本を一荷としてある。
之を石壺の上に据えて「御木の数三千五百荷御入り候ふ」と申し、
政所が祝詞を奏し了って、御薪をば忌火屋殿に納める。
神事の祝詞には、
「吾々のかく奉るさまをば、平らけく安らけく聞食して朝廷賓位(みかどのみくらい)」は
動くことなく、常磐(ときわ)に堅磐(かきわ)に、夜の守日の守に護り幸い奉りたまひ
生まれまさむ皇子達をも慈しみ給ひ、百官(ももつかさ)に奉仕(つかえまつ)る人等をも
平らけく、安らけく、天下四方(あめのしたよも)の人民(おほみたから)の作る
五穀(いつくさのたなつもの)も豊かにめぐみ幸ひ給へ」
と祈る所に国民思想の明らかなる反映を見る。
訓読みのやまとことはのなんと美しい響き♡
◎小豆粥【正月十五日】「民間行事」
松飾りは、十四日の夜に納めるので、十五日朝に粥柱の角切餅を入れた小豆粥を煮、
飾りを取り去った跡へ供えるので、飾揚げの祝とも云った。※五十鈴落葉
参考文献・参考資料
◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社
◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」
◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社
◎『縄文カレンダー』冨山喜子編
◎『宇治山田市史』宇治山田市役所編 国書刊行会
◎『志摩の民俗』三重県郷土史料刊行会 著者:鈴木敏雄
◎『伊勢神宮』ホームページhttp://www.isejingu.or.jp/index.html
※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。