
本日、 の予報。
の予報。
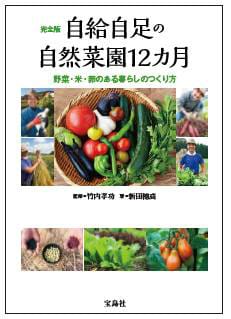
いよいよ拙著『自然菜園で自給自足12か月』(宝島社)3/10に無事発売できました。ありがとうございます。
今までにない、田んぼ(水稲)や鶏、こんにゃくなど目白押しで、
写真と文章は、有機農業暦の暮らしが長い、フリーライターの新田穂高さんが2年間「取材田舎暮らしの本」(同社)で連載したものを再編集した力作です。
実践者が取材したことで、これは知っておきたいというちょっとしたことも逃さず網羅してあるので、これから自給自足の暮らしを夢見る方や、実践者からは目から鱗かもしれません。
今回も写真・情報量がとても多く、価格は1,600円(税別)なので、かなりお得な1冊かと思います。
読まれた方は、感想やご質問をコメント欄からおよせください。
次回の書籍や雑誌が出る際に参考にさせていただきたいと思います。
いよいよ今週末から3日連続、自然菜園スクールも開講です。今週は準備に余念がありません。
今日から、4日間、長野⇔安曇野4往復で準備・開催です。
今朝、興味深いご質問がありました。
そこで、耕作放棄地にお困りの方に、


エンバクです。


クリムソンクローバーです。
この2種類の1年草(種で殖える)緑肥作物を使い、耕作放棄地を景観良く綺麗に、超簡単に、肥えたの畑に改良に持っておく裏技をご紹介します。
本当に簡単ですよ。

秋か、春の梅が咲く頃に、畑が乾いているときにエンバク・クリムソンクローバーを比重で2:1で、10a(1,000㎡)あたり、
総量5~8kgになるように(荒れていたり、痩せている方が多めに)混ぜて播いてから、トラクターで耕して終わり。
エンバクが先に生育し、草を抑えてくれ、その中で、クリムソンクローバーが守られながら生育します。
エンバクが枯れてもそのまま、クリムソンクロバーが綺麗に赤く全面に咲いて綺麗です。
その後、クリムソンクローバーが枯れて、タネをつけ始めたら、そのまますき込むみます。
そうすると、その後も、エンバクかクリムソンクローバーが、自然に生えてきます。
エンバクが枯れたら、鋤き込むとエンバク優先になりますし、
クリムソンクローバーをメインで生やしたい場合は、秋口に、敷き込む前に、クリムソンクローバーをの種子を追い播きしてから鋤き込みます。
エンバクはイネ科で、クリムソンクローバーはマメ科なので、相性が良く、お互いに生育を促進します。
イネ科のエンバクは、土を団粒構造を発達させ、土を水持ち良く、水はけ良く、耕し肥沃にします。
マメ科のクリムソンクローバーは、根に共生する根粒菌などの働きで、チッソを固定し、花は綺麗なので景観緑化によく、ミツバチなどの蜜源になります。
この方法で、数年間、育てると、エンバクがどんどん大きく育つようになってきます。
つまり、年1~2回タネをつけて耕すだけで、雑草化した緑肥たちによって、土がどんどん良くなっていく裏技です。
その後、数年エンバクが倒れそうななるほどまで繰り返すと、立派な畑になっているから不思議です。
畑に戻してからも、雑草化した緑肥作物たちが旺盛に何年か出てくるので、草マルチとして活用したり、ビニールマルチなどで被覆して抑えて栽培すると野菜が負けず、無肥料でも見事に育つようになります。

田んぼの耕作放棄地の場合は、秋口のレンゲの播種時期にあわせて、エンバクとレンゲを同様に混ぜて、播きトラクターで鋤き込むことで、
翌年田んぼがレンゲ畑になり、枯れた後に鋤き込むことで、毎年更新できますが、
数年育てて、レンゲが大きく育つようになった肥沃な場合、翌年田んぼに戻して稲を育てると倒れますので、レンゲを春に刈り取り、すべて持ちだしてから耕し、田植えします。

最近では、ホームセンターなどで、小袋でも購入可能なので、庭や小さな畑でも可能です。

混ぜたものを市民農園など1年更新で借りる畑の通路の真ん中などに緑肥mixとして播くことで、
通路が固くならず、草マルチの材料にも、益虫を増やし、実つきも良くなるのでお奨めです。
注意点としては、都会や耕作放棄地の場合、鳥などによってタネがすべて食べられてしまうことがありますうので、
その場合は、農薬処理してある種子を選ぶと、鳥の被害が減ります。
もし、禿げて一部分生えない場合は、再度空いた所に、緑肥mixを播き、クン炭などを播いて被覆しておきます。
4/6(水)よろ2016年内容充実で、『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートします。
、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

自然菜園スクール2016(旧Azumino自給農スクール)
コースは、安曇野インターから車で30分の長野県安曇野市三郷にある自然菜園各コース(安曇野校)と、
更埴インターから30分の長野県長野市信更町にある自然菜園見学コース、自然育苗タネ採りコース、自然稲作の勉強会で会場が異なります。
Ⅰ.~育苗を学びたい~
■自然育苗タネ採りコース(長野校) ※残り若干名
自家採種した種子で育てる自然苗を学びたい方にお奨め
Ⅱ.~3つから選べる自然菜園コース~
新設コース
■自然菜園/入門コース(安曇野校) ※不耕起区残り若干名
半日のワークで、タネまき~収穫まで、20種類の野菜を一通り1年を通じて基本から学べます。
子育て中やお仕事でお忙しい方でも学ぶことができます。
■自然菜園・実践コース(安曇野校)
1日のワークで、少量多品目の無農薬野菜の自給の基礎から応用まで学びたい方。
30種類以上の野菜や雑穀などを体験学習し、総合的に自給農園のつくり方を学びます。
不耕起と耕起の菜園区画を選べます。
■自然菜園見学コース(長野校)
実際の自然菜園の田畑を見学し、講座と質疑応答で見聞を深めたい方。
自分の田畑があり、忙しい方や見学希望者にお奨め。
Ⅲ.~無農薬のお米作りを学びたい~
■自然稲作の勉強会(長野校)
お米を無農薬で自給したい方、実際に育てている方にお奨め
各種菜園教室の募集は始まっております。1次募集〆切が2月末です。
各コース共、定員があり、先着順になっておりますので、お早めにお申し込みください。
お申し込みお問い合わせはホームページからお願いいたします。
 の予報。
の予報。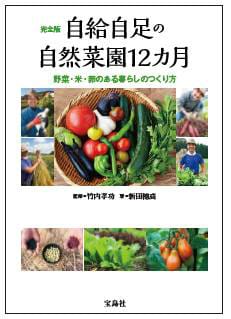
いよいよ拙著『自然菜園で自給自足12か月』(宝島社)3/10に無事発売できました。ありがとうございます。
今までにない、田んぼ(水稲)や鶏、こんにゃくなど目白押しで、
写真と文章は、有機農業暦の暮らしが長い、フリーライターの新田穂高さんが2年間「取材田舎暮らしの本」(同社)で連載したものを再編集した力作です。
実践者が取材したことで、これは知っておきたいというちょっとしたことも逃さず網羅してあるので、これから自給自足の暮らしを夢見る方や、実践者からは目から鱗かもしれません。
今回も写真・情報量がとても多く、価格は1,600円(税別)なので、かなりお得な1冊かと思います。
読まれた方は、感想やご質問をコメント欄からおよせください。
次回の書籍や雑誌が出る際に参考にさせていただきたいと思います。
いよいよ今週末から3日連続、自然菜園スクールも開講です。今週は準備に余念がありません。
今日から、4日間、長野⇔安曇野4往復で準備・開催です。

今朝、興味深いご質問がありました。
そこで、耕作放棄地にお困りの方に、


エンバクです。


クリムソンクローバーです。
この2種類の1年草(種で殖える)緑肥作物を使い、耕作放棄地を景観良く綺麗に、超簡単に、肥えたの畑に改良に持っておく裏技をご紹介します。
本当に簡単ですよ。

秋か、春の梅が咲く頃に、畑が乾いているときにエンバク・クリムソンクローバーを比重で2:1で、10a(1,000㎡)あたり、
総量5~8kgになるように(荒れていたり、痩せている方が多めに)混ぜて播いてから、トラクターで耕して終わり。
エンバクが先に生育し、草を抑えてくれ、その中で、クリムソンクローバーが守られながら生育します。
エンバクが枯れてもそのまま、クリムソンクロバーが綺麗に赤く全面に咲いて綺麗です。
その後、クリムソンクローバーが枯れて、タネをつけ始めたら、そのまますき込むみます。
そうすると、その後も、エンバクかクリムソンクローバーが、自然に生えてきます。
エンバクが枯れたら、鋤き込むとエンバク優先になりますし、
クリムソンクローバーをメインで生やしたい場合は、秋口に、敷き込む前に、クリムソンクローバーをの種子を追い播きしてから鋤き込みます。
エンバクはイネ科で、クリムソンクローバーはマメ科なので、相性が良く、お互いに生育を促進します。
イネ科のエンバクは、土を団粒構造を発達させ、土を水持ち良く、水はけ良く、耕し肥沃にします。
マメ科のクリムソンクローバーは、根に共生する根粒菌などの働きで、チッソを固定し、花は綺麗なので景観緑化によく、ミツバチなどの蜜源になります。
この方法で、数年間、育てると、エンバクがどんどん大きく育つようになってきます。
つまり、年1~2回タネをつけて耕すだけで、雑草化した緑肥たちによって、土がどんどん良くなっていく裏技です。
その後、数年エンバクが倒れそうななるほどまで繰り返すと、立派な畑になっているから不思議です。
畑に戻してからも、雑草化した緑肥作物たちが旺盛に何年か出てくるので、草マルチとして活用したり、ビニールマルチなどで被覆して抑えて栽培すると野菜が負けず、無肥料でも見事に育つようになります。

田んぼの耕作放棄地の場合は、秋口のレンゲの播種時期にあわせて、エンバクとレンゲを同様に混ぜて、播きトラクターで鋤き込むことで、
翌年田んぼがレンゲ畑になり、枯れた後に鋤き込むことで、毎年更新できますが、
数年育てて、レンゲが大きく育つようになった肥沃な場合、翌年田んぼに戻して稲を育てると倒れますので、レンゲを春に刈り取り、すべて持ちだしてから耕し、田植えします。

最近では、ホームセンターなどで、小袋でも購入可能なので、庭や小さな畑でも可能です。

混ぜたものを市民農園など1年更新で借りる畑の通路の真ん中などに緑肥mixとして播くことで、
通路が固くならず、草マルチの材料にも、益虫を増やし、実つきも良くなるのでお奨めです。
注意点としては、都会や耕作放棄地の場合、鳥などによってタネがすべて食べられてしまうことがありますうので、
その場合は、農薬処理してある種子を選ぶと、鳥の被害が減ります。
もし、禿げて一部分生えない場合は、再度空いた所に、緑肥mixを播き、クン炭などを播いて被覆しておきます。
4/6(水)よろ2016年内容充実で、『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートします。
、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

自然菜園スクール2016(旧Azumino自給農スクール)
コースは、安曇野インターから車で30分の長野県安曇野市三郷にある自然菜園各コース(安曇野校)と、
更埴インターから30分の長野県長野市信更町にある自然菜園見学コース、自然育苗タネ採りコース、自然稲作の勉強会で会場が異なります。
Ⅰ.~育苗を学びたい~
■自然育苗タネ採りコース(長野校) ※残り若干名
自家採種した種子で育てる自然苗を学びたい方にお奨め
Ⅱ.~3つから選べる自然菜園コース~
新設コース
■自然菜園/入門コース(安曇野校) ※不耕起区残り若干名
半日のワークで、タネまき~収穫まで、20種類の野菜を一通り1年を通じて基本から学べます。
子育て中やお仕事でお忙しい方でも学ぶことができます。
■自然菜園・実践コース(安曇野校)
1日のワークで、少量多品目の無農薬野菜の自給の基礎から応用まで学びたい方。
30種類以上の野菜や雑穀などを体験学習し、総合的に自給農園のつくり方を学びます。
不耕起と耕起の菜園区画を選べます。
■自然菜園見学コース(長野校)
実際の自然菜園の田畑を見学し、講座と質疑応答で見聞を深めたい方。
自分の田畑があり、忙しい方や見学希望者にお奨め。
Ⅲ.~無農薬のお米作りを学びたい~
■自然稲作の勉強会(長野校)
お米を無農薬で自給したい方、実際に育てている方にお奨め
各種菜園教室の募集は始まっております。1次募集〆切が2月末です。
各コース共、定員があり、先着順になっておりますので、お早めにお申し込みください。
お申し込みお問い合わせはホームページからお願いいたします。
































このページは、スレッドが大変長く読むのに大変なので、このご質問のご返信以外は、次回からは最新のページか、関連記事からお願いいたします。
お久しぶりです。
そうですね、根元に撒いたのがよくない点と、米ぬかは、直接土の上に撒かず、野菜の株周りに草マルチをして、草の上から野菜の状態に応じて薄っすら撒くのが基本です。
もし土の上に直接米ぬかをまいてしまうと、米ぬかの油分が土の通気を邪魔し、米ぬかが腐敗しやすくなります。腐敗すると、カビの色が白い以外の色になり、根腐れ、病虫害の原因になりますので、除去いたします。
また、まだ野菜も草もよく育たない畑では、米ぬかを一度発酵させたボカシがお奨めです。草マルチでサンドするように、少量ずつ使用するのが一番です。
あれから米ぬかを購入し、根本に一握りくらいの感覚で生のまま使用しました。最初は白いカビのようなものが生えてきたと思ったら、その後、赤色、黒色、茶色など問題ありそうな色になっています。
これはまずい状態でしょうか?
だとしたら何が悪かったのでしょうか?
色々調べたのですが、悪いカビなのか
問題ないものなのか見つけることが出来ませんでした。もしご存知でしたら教えてください。
(白いものだけが麹カビ??で良性?)
そうですね。
砂壌土は、いかに腐植を蓄積できるかが、そして団粒構造が発達するかがカギになります。
有機物が分解され、腐植化され、団粒構造が発達するように、微生物たちと一緒にお世話できるといいですね。
また、砂壌土などにはゼオライトもお奨めでなので、1㎡に100~200g混ぜると、ずいぶん土が野菜を育てやすくなりますよ。参考にしてみてください。
鶏糞は肥料としての要素が強そうですが
確かに抗生物質とか残留成分が気になりますね。
米ぬかぼかし堆肥は作ったことがないので
挑戦してみたいと思っていました。
緑肥育てるのにもいいかもと思います。
この冬トライしてみます。
ありがとうございました。
そうですね。ただ養分として鋤き込むのであれば、鶏糞でもいいのですが、
目的が、善玉の微生物を増やし、団粒構造を発達させるのであれば、米ぬかがベストです。
市販の鶏糞であれば、遺伝子く変えのエサと、抗生物質が与えられていて、鶏糞は食べたものがそのまま出る傾向があることと、養分としての即効性はあるものの、腐敗しやすく、鶏のエサに緑肥も乏しく、腐植が乏しい点からもおすすめはできません。
私であれば、今後を見据えて、米ぬか30㎏を購入して起き、10㎏位は生で使い、20㎏は発酵させてボカシにし(数か月かかるので)、砂壌土の欠点、養分欠乏を、発酵済みのボカシで補う準備とします。
発酵したボカシは、菌の塊で、草マルチと併用すれば、腐植、団粒構造の発達に促進力になるからです。
微生物が喜ぶことを考えてみてください。
ちなみに緑肥+鶏糞ですきこむのは好ましくないですか?
手元に米ぬかがなく、近所の米屋では30㎏の米袋単位でしか購入できず多すぎです。
精米所で入手できるとも聞きますが、私の近所では入手できそうな感じがしませんでした。
そうでしたか。砂地の場合、基礎地力(腐植・団粒構造の発達)がとても重要です。
次の定植前には緑肥を鋤き込むにせよ、緑肥がより育っていた方が、鋤き込んでからの基礎地力アップ効果が高いので、
3)もし養分切れなどでしたら、条蒔きでしたら、条間に、米ぬかと腐葉土を1:1で混ぜたものを撒いて、5㎝で程度鍬で土と混ぜるように鋤き込んでみてください。
を行って、せっかく蒔いた緑肥をしっかり育ててみることが大切かと思います。
面積が多ければ、日中葉が乾いている時間帯に、米ぬかと油粕を半々に混ぜたものを撒くだけでもずいぶんいいですよ。
会社行く前に写真撮りましたが、朝早すぎたせいか、
今朝曇だったもので、、、写真が暗く不鮮明で、葉が黄色いのも伝わらない写真になってしまったので
アップロード断念しました。すみません。
1)該当していないです
2)関西地方で瀬戸内で温暖なため、10月〜11月でも播種しても大丈夫だと思っていました。
まだ霜は降りていないと思います。
朝の最低気温8度くらいです。
3)養分切れかと思ってます。地力がないのかもです。
4)育てる前に肥料と堆肥入れておいた方が良かったですね。
砂丘のようなサラサラの砂地ではありませんが、
砂の成分が多いようです。
耕すとしばらくはふわっとしていますが、雨が降った後、乾くと表面がカチカチなので流出が激しそうな感じがします。
ご指摘のように肥持ちも悪いのかもしれません。
砂地では無肥料では育ちにくいんですね。
ちょっとがっかりですが、もうちょっと緑肥で
頑張ってみます。
5)次の定植前には緑肥とご指摘のものをすき込んでみます。
もうしばらく様子見て枯れたり、大きくなりそうにないならそれはそれで基礎地力がないことが判明する気がしてきました。
色々アドバイスありがとうございました。
またお願いします。
そうですね。
今回のコメントだけだと、カリウム不足かどうか難しいところです。
写真があれば、リンク先をコピペしていただけると、観れば何とかなるかもしれませんが、
よくあるケースですと、
1)種まき前に、土の中に枯草や青草を土に混ぜて撒いてしまった場合、土の中で発酵しガスが湧き、緑肥の種まきから1か月程度したら、発根障害で葉が黄色くなった。もしくは、発酵による窒素飢餓で、成長が止まったケースもあるので、それはなさそうですか?
2)まだ蒔いて1か月くらいですと、場所にもよりますが、霜が降りる時期ですと、発芽したての弱い時期ですと、ただでさえ生育が弱い時期なので、霜枯れして、黄色い可能性はありませんか?蒔いた時期は、クリムソンクローバーの適期に遅くなかったですか?
3)もし養分切れなどでしたら、条蒔きでしたら、条間に、米ぬかと腐葉土を1:1で混ぜたものを撒いて、5㎝で程度鍬で土と混ぜるように鋤き込んでみてください。
4)気になるのは「緑肥を植えてないところはカチカチで、、、雨で表土が流れてカチカチになっているのかもしれません。」という記述。
砂地の場合、化学肥料では育っても、無農薬では育ちにくい傾向が高いので、緑肥作物といえど作物なので、緑肥作物や野菜を育てる1か月前に、
①1㎡あたり、クン炭1~2ℓ、完熟たい肥3ℓ、腐葉土3ℓ、ゼオライト100gを10~20㎝に鋤き込んで、基礎地力(腐植)を高めた方がいいかもしれません。
5)緑肥作物が4)で回復した場合、春になり、エン麦が穂が出たら、1㎡あたり、米ぬか1ℓと腐葉土3ℓ、ゼオライト100gを緑肥と一緒に鋤き込んで、2週間後にもう一度鋤き込み、1度目の鋤き込んでから1か月後に作付け(種まき、定植)すると、効果的だと思いました。
砂地は、水はけがよい分、養分抜けも激しく、化学肥料など従来の栽培で酷使した後では、基礎地力がほとんどないことが多いものです。
この機会に、緑肥と共に、基礎地力(腐植と団粒構造)を底上げできれば、野菜もよく育つと思いました。
他、貴著書の刺激を受けて、やってみました。
撒いてから1ヶ月程度になると思いますが
土地が痩せているせいか、播種時期が悪かったのか
クリムゾンクローバーは発芽はしたもののほとんど
背丈は大きくならず葉が黄色くなってきています。
えん麦はところどころ葉の色が薄いですが
10cmくらいには育っています。
撒く前に堆肥を入れたら良かったのかもしれませんが何もいれていませんでした。
葉が黄色になるのはカリウム不足でしょうか?
当方、砂地ですが、雨が降る毎に硬くなるようで、えん麦が生えてくると表面がひび割れするくらいです。
緑肥を植えてないところはカチカチで穴を掘るのも
力がいる始末。
いつ頃かは不明ですが昔、祖母が玉ねぎなどは作っていた土地で、しばらく休耕していたため雨で表土が流れてカチカチになっているのかもしれません。
緑肥を撒けば少しは改善するかとトライしたのですが
緑肥すら育つことができないのかと落胆気味です。
今からでも肥料を足したりした方が良いのか
待つべきなのかと悩んでいるのですが
アドバイスいただければ幸いです。
ちなみに水は自然に任せてます。
お忙しいところ申し訳ありませんが
お手数でなければ教えてください。
そうですか。中山間地域の耕作放棄地の回復は、狭くいびつなので、人手がかかるのですが、自然に恵まれ、風景もよく、根気よく、緑肥作物を活かしながらやってみてください。
コメント整理ありがとうございました!
はい(^^)/
八尾・東大阪市には、まだまだたくさんの
この畑に似た
耕作放棄地がありますので
地元のみなさんに
参考にしていただけるような
場所にもっともっと育てて
(今秋から、菜園プランに基づき
本格的に野菜を作ります)
しっかりと広めていけたらと思います!
ほんまに、ありがとうございました!
さらに、精進します!
内山勇人
そうですね。
ダブったコメントは消去しておきました。
緑肥作物は、時間はかかりますが、最短で最高の効果を長期間もたらしてくれます。
それは、肥料はほぼ化学性だけですが、緑肥作物は、生物性、物理性、化学性を同時に改善してくれるからです。
良き事例となって、地元発信で伝えて行ってください。
↓↓
ーーー
竹内さん
ブログ記事消し方分からず二通同じような
投稿失礼しましたm(_ _)m
はい
ハッピーヒルは、竹内さんのおかげさまです。
違う農園でも
同じ肥料を
使っていますが
やはり、一年間かけて、緑肥作物を漉き込んで
作ったベースのあるこの畑がダントツに生育がいいです
こころから感謝します!
この畑の、1年前の土質を知る地主さんからは
今日も驚きと感謝の言葉を頂きました(^^)/
今後とも何卒よろしくお願いしますm(_ _)m
内山勇人
写真ありがとうございます。
ハッピーヒルいいですね~。
今年は暑すぎるので、カボチャよりもスイカがぴったりだと思います。
暑いので、おからだご自愛ください。
8月10日に撮影してきました!
【農園の現況報告2】
https://www.evernote.com/shard/s203/sh/4699740a-9dd7-4475-866d-36506405eb2b/cf6f1718443941fd36547013616378b6
おかげさまで
とても順調です!
こころから感謝します😂🙏😂
うちやまはやと
8月10日金曜日に
農園で撮影してきました!
おかげさまで
とても順調です😊🙏😊
仲間もみんな
喜んでおります!
感謝😂🙏😂
内山勇人
すいません
連日暑すぎて
写真撮れてませんでしたが(汗)
仲間の方が
撮って丁寧にアップして下さいました
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1859867507468132&id=100003347010449
また私も追って写真記事
こちらに報告させて頂きます!
とにかく、写真では
伝わりにくいかもですが
強烈なエネルギーを
感じて感動しています
ほんまにありがとうございます!
そろそろ落ち着きますので
また講座にお伺いさせて頂きお話できること
こころから楽しみにしております(^^)
うちやまはやと
そうでしたか。それは、内山さんのお世話の結果です。コンサルしてよかったです。
後差し支えなければ、その後どうなったか写真見れたら嬉しいです。
コンサルや、生徒さんの生育の結果が、今後のご指導させていただくときに、とても参考になり、地元以外の風土を知る大切な機会になります。よろしくお願いいたします。
投稿に気づかず
ドタバタ農繁期がすすみ
お返事遅れて申し訳ありませんm(_ _)m
おかげさまで
立派に稲が育ってきていて
みんなも喜んでいます!
ほんまに
ありがとうございました!
来年は
自分の頭で考えられるように
自然との対話を
竹内さんの通訳なしで
できるよう
がんばります!
うちやまはやと
よかったです。
個別コンサルをした上でのご質問なので、実際に行ったことのある圃場(田畑)で、土壌分析、その方の計画を知った上で、写真があるとかなりしっかりアドバイスできると思います。来年からは、自分で判断できるように自分ならどうするのか、しっかり考えながら、草と作物に教わってみてください。
お返事遅れてしまいまして誠に申し訳ありません!m(_ _)m
表記の件承知しました!
いつもながら、的確で詳細なアドバイスありがとうございます(*^_^*)
だいぶ安心できました。
今後とも何卒よろしくお願いしますm(_ _)m内山勇人
そうですね、写真があるとわかりやすくていいですね。
1)セルトレーの土は、ハッピーヒルには養分過多だったようでしたが、小さなセルトレーで養分不足で黄色くなると、生育不足、回復が遅いので、ちょうどよかったのではと思っております。
黄色くなっているのは、根の痛みによるものだと思います。プール状態で、暑い水が溜まってしまったので根ぐされしたか、もしくは過乾燥になって一度葉が焼けた後に水をかけたが、回復しなかったのは?と思います。いずれも移植すると回復します。
野菜と花の培養土は、プランタ―がもう少し浅ければ、がっちりした苗になったと思います。ややモヤシ気味で軟弱なので、もう少し水を抑えたり、蒔く粒数を減らすとよかったと思います。
2)田植え(移植)はセルトレーから行った方がいいです。
理由1)セルトレーの根痛みや今後の水やりは、今後も難しくなってくると思うので、まだ土に(葉)に養分があるうちに、植えてしまうと回復してくるとでしょうし、水やりからも解放されます。
理由2)セルトレーの苗が足りなくなってから、プランタ―の苗を何本植えにするのか、過不足を調整しやすいから。
理由3)プランタ―の栽培の方が、土が多く、セルトレーよりも水管理や養分切れも起きにくいと思われるので、最後で大丈夫かと思いました。
セルトレーを植える場合、移植する直前までたっぷり水の中にしたしておいて、植えると活着が良く、逆にプランタ―の場合は、前日たっぷり水を吸わせておき、やや渇き気味で根を切らないように植え、移植後水をたっぷりかけるといいと思いますよ。
いつもありがとうございます!
おかげさまで、ハッピーヒル
田植え間近まで来ました!
それに際して、にさん2、3質問がありますが
お願いしますm(_ _)m
https://www.evernote.com/shard/s203/sh/fbcb72ed-b993-4658-bce4-37fc46768a1a/5d1158100ce82fe2e0f34cf754cdfb69
内山勇人
はい。
来年は、もう少しスムーズにできるように
したいと思います。
今回のハッピーヒルに関する
一連の苦労は
今年の竹内さんスクールで
もっともっと力をつけたいと思う
モチベーションを得る
良い機会になりました!
ありがとうございました!
内山勇人
そうですか、お役に立ててよかったです。
来年は、黒マルチに直播できるようにするか、今回のやり方をもっとスマートに改善できるといいですね。
毎年積み上げて持続できるといいですね。
はい
時間を作って
ぜひ育苗コース受講できたらと思います(^^)
本日、128穴セルトレイ✖20ケース
無事に籾まき完了しました!
【5月24日】
https://www.evernote.com/shard/s203/sh/baee9ed1-db89-438f-9781-e9c3176d0209/a466f4632651baf7243eddf4dda363e2
これから
なんとかリカバリーします!
ほんまに気持ちが楽になりました!
ほんまに
ありがとうございました!
内山勇人
どういたしまして。基礎を押さえて、臨機応変が栽培の基本です。
是非、一度自然育苗種採りコースにお越しください。きっと知りたい内容がてんこ盛りだと思いますよ。
お忙しい中、詳細なアドバイスほんまにありがとうございました!
心から感謝致します!
現在、農園の土の有機物の分解がまだ完全でない可能性がありますのでリスクは承知で
苗作りの方で挑戦してみます。
ありがとうございました!
取り急ぎ
内山勇人
そうですね。この時期いろいろ忙しいですから。
1)現在の土の状況がわかりませんが、大麦(緑肥)を鋤き込んだ畑が、もしすでに分解が終わっていたら、鋤き込んで、マルチを張ってから、穴に直接芽出しした種モミを蒔くはいかがでしょうか?
有機物の分解が終わっていない場合は、育苗してください。
というのは、予定よりも遅れており、現在、暑い中育苗してから定植するよりも直播の方が、直根が切れずに育つので、いいと思いました。
その場合
①ハッピーヒルは、休眠がないため、ネットに入れた種モミの水分を切ってから(洗濯機の脱水で1分)後、新聞紙で包み、ビニール袋に入れて、冷蔵庫(5~7℃)で7~10日以内であれば保存可能。(ただし、3日に一度、中を確認して、種モミの場所ムラの温度差を直し、空気が入るようにする)
②①の間に、
トラクターで、鋤き込んで畝立て、黒マルチを張って、穴を開けて、3~7日間放置。(緑肥の有機物の発酵ガスを逃がす)
③穴に種を3粒ずつ蒔いて、土を覆土し、鎮圧後、モミガラ(クン炭)を3㎝被覆。黒マルチの上に鳥よけの寒冷紗(もしくは不織布)などをべたがけして発芽させる(本葉2~3枚まで鳥よけ)
2)緑肥(大麦)が分解されていない場合、
⇒で訂正
①128穴のセルトレイに 稲作の育苗用の培土を入れるそこに セルトレイ1穴につき、米3粒を入れる。
②その後覆土する(覆土は必要ですか?)⇒そして鎮圧
③水をじょうろでかける⇒たっぷりかける
(覆土後水をかけると土が固まり発芽しづらくなりますか?)
④育苗トレイに、新聞紙を被せて加湿する(3日間)⇒加湿ではなく、保湿。鳥よけ対策。
⑤寒冷紗を全体にかけて 鳥害を防ぐ 防寒対策をする。⇒○
⑥この後のことですが 育苗のトレイは
水をはったプール↓(画像イメージ) につけておきますか?それとも毎日水をジョウロでかけたらいいのでしょうか?
⇒陸稲で育てる場合、プール育苗すると乾燥に弱い苗になるので、(水根が発達し、陸根が育たないから)、けれど毎日水やりは大変なので、写真のように、ブルーシートを張って、その上に並べて毎朝水やりし、しみ出た水が夕方にはなくなる位で育てる。
⑥一ヶ月間育苗して芽が3~5枚出た段階で田植えする。⇒芽が3枚になったら、定植。その後、毎日1週間水やりをする。(定植時期が、高温だから、梅雨に入って雨が降っているようであれば要らない)
⑦定植1週間後、濡れたモミガラと米ぬかを1:1に混ぜたものをマルチの穴に生えているハッピーヒルの株元に、うっすら撒くと、草抑えと追肥になる。(モミガラだけでもよいが、飛んでなくなってしまう)
いつもお世話になります。
大阪で以前個人コンサルをお願いしました
内山勇人です。
その後の状況報告と
ハッピーヒルの育苗について
ご質問させて頂きたく投稿させて頂きました。
お忙しい中、誠に恐縮ですが何卒よろしくお願いします。
【ご質問内容と近況報告】
http://www.evernote.com/l/AMtMvOA2pI1Ec7OEh7trozbEOe7diVCay4A/
内山勇人
そうですね。
こちらこそよろしくお願いいたします。
お返事気づかずご返信遅れて申し訳ありません
はい。もちろんあくまで自己責任で
自然に聴きながらトライしてみます。
無料でありながら
厚かましくも色々とご丁寧に
お教えくださいまして
大変感謝しております(^o^)
↑
有料コンサルについてもまた11/18訪問時に
お教えくだされば嬉しいです。
ちなみに、今年は、苗をプランターで育てて
から田植えしましたので、今年もアドバイスのやり方も考慮しつつさせて頂きますm(__)m
ありがとうございました!
内山勇人
そうですか。有料でのコンサルなら現場を観て、土壌分析をして、もう少し適切にアドバイスもできるのですが、まずは両方やってみて畑に正解を聴くのをお奨めします。
また、ばら蒔き、その後浅く鋤き込みの場合、その1カ月後に陸稲の植え付け(種まき)になるので、個人的には、苗をセルトレイなどで育てておいて、鋤き込み後、植え付けることがいいと思いました。
お忙しい中ご丁寧にありがとうございました!
まだまだ、雑草観察をさせて頂きますと
痩せ地と思いますので
ばら撒き→浅くすき込み
メインでさせて頂きますm(__)m
ありがとうございました!
内山勇人
そうですね。
①まず、バラ蒔きか条まき蒔きによって、来年の陸稲の育て方が違いますし、蒔き方によって量が倍近い違います。最初楽なばら蒔き、あと楽な条播きといった感じです。
②痩せ地の場合、ばら蒔きが基本。
10アールあたり、レンゲと大麦を混播する場合、レンゲ3~4㎏、オオムギ8kgといった感じです。
レンゲの播種時期に合わせて混播し、全体を浅く鋤き込むといった感じです。
③条播きの場合、肥沃地や草が多い畑にむいています。
大麦(5㎏)とレンゲ(2~3㎏)を交互に条播きし、レンゲの跡地に陸稲を条播きします。
②③は、一長一短で、むき不向きがあるので、ある程度畑が良くなったら③がお奨めです。
両方やってみて、ご検討ください。
とても初歩的な質問で
誠に恐縮ですが
2点ご質問が出てきてしまいました。
①2反の農地ですと、蓮華とマンネンボシ
それぞれどのくらいの量の種が必要でしょ
うか?
②蓮華とマンネンボシは、ばら撒いて
耕運機をかければよろしいでしょうか?
それとも、筋撒きがよろしいでしょうか?
以上何卒よろしくお願いしますm(__)m
内山勇人
そうですね。陸稲は田んぼでなくても育つお米なので、家庭菜園でも取り組みやすい作物ですが、やり方がわからない、知られていないものです。
また何かございましたら、ご報告、ご質問ください。
お返事に気づかず書き込み遅れてしまい
申し訳ありませんでしたm(__)m
表記の件承知しました。
来年本格的に、陸稲や稲と向き合うので
たくさん失敗すると思いますので
またご報告させて頂きます。
今後とも何卒よろしくお願いします!
内山勇人
そうですね。
陸稲に関してはお問い合わせが多いのですが、なかなか穀類はなど野菜でないので、取り上げてもらえず、雑誌、書籍化が難しいとのことです。
なので、お米や麦、雑穀などに関しての記事は多めにブログに投稿している次第です。
陸稲の失敗談や成功事例があればまたコメント欄にご質問、ご報告ください。
お返事遅れて申し訳ありませんm(__)m
この度は色々と
ご丁寧にアドバイスほんまにありがとうございました!
裸麦のこと
大変勉強になりました。
「裸麦マンネンボシ」
蓮華と一緒に 植えてみたいと思います。
★タイミング大切なのですね。
承知しました\(^o^)
自然を観察しながら楽しみながらトライしてみますm(__)m
ありがとうございました!
内山勇人
そうですね。
大麦の方が小麦より遅く播け、小麦よりも早く枯れるため、陸稲の種まき、収穫に余裕があるからです。
大麦の「てまいらず」は皮麦ですね。
大麦には、大きく分けて、皮を被った皮麦と裸麦の2種類があります。
皮麦には、麦茶の六条大麦、ビールの二条麦などがあり、食べるには皮をむいたり、押し麦にします。
裸麦には、皮がないため、圧力鍋があれば麦飯として食べることができます。
例えば、同じつる新種苗さんなら、
「裸麦マンネンボシ」
http://tane.jp/haruyasai/zakkoku/hinshu/hadakamugimannenboshi.html
などがあります。
耕す、不耕起、など栽培方法とタイミングの良い麦を見つけ、タイミングよくレンゲ、ムギを育て、タイミングよく陸稲を栽培することが一番大切な要点です。
楽しみながら、自分のあったもの見つけてみてください。
ご丁寧にありがとうございました。
なんとか農園を成功させなければいけないので
大変助かりますm(_ _)m
何から何まで教えて頂き誠に申し訳ありませんが
最後の質問です。
私は、今年 自宅前の菜園 で
マルチ大麦てまいらず
http://tane.jp/haruyasai/bokusou/hinshu/temairazu.html
を使用してかなり良い感じだったのですが
竹内さんの先日のアドバイスで
ーーー
個人的には、早生の裸麦がお奨めで、オオムギを刈ったら、陸稲苗を植えるのがお奨めです。
ーー
とありましたが
↑
「早生の裸麦」として、「てまいらず」は適切でしょうか?(てまいらずを調べましたが、裸麦なのか不明でして・・)
それとも何かオススメがありましたらお教えくだされば幸いですm(_ _)m
ーーー
★11/18自然農塾、休み確保できましたのでお申込みさせて頂きましたm(_ _)m
何卒よろしくお願いします。内山勇人
そうですね。
麦とレンゲは越冬するものが良いので、エンバクが越冬しない地域(霜が降りない)では、小麦か大麦が無難です。
個人的には、早生の裸麦がお奨めで、オオムギを刈ったら、陸稲苗を植えるのがお奨めです。
また、レンゲとムギを鋤き込む場合は、陸稲の種まき(もしくは植え付け)1ヶ月前までには鋤き込んで、しっかり土に還してから行う必要があります。
工夫してみてください。
大変わかりやすい説明ありがとうございました!
頂いたプランの中で
今年は
麦+蓮華⇔陸稲
で
させて頂きたく思いますm(__)m
「麦」は、初年度ですので
無難というところで
「エン麦(前進)」でさせて頂きたく思いますがよろしいでしょうか?
それとも、麦は何種類かミックスさせて頂いたほうがよろしいでしょうか?!
度々の質問失礼しますm(__)m
うちやまはやと
おはようございます。
これで少し見えてきました。私も以前陸稲を栽培していたので、
1)元水田であれば、陸稲はむいていると思います。
まずはリレープラン
①大豆&麦⇔陸稲
もしくは、麦(大豆)⇒大豆(麦)⇒陸稲
②レンゲ&麦⇔陸稲
混植は、
①エダマメ、ダイズ
②マクワウリ
③サツマイモ
といったところが、無難だと思います。
混植とリレープランを両方取り入れながら、ローテーションしていくことが一番いいと思います。
陸稲は、乾燥と夏草が大敵なので、手を入れやすく条間と株間をお世話に合わせて調節するといいですね。
お忙しい中、早速のアドバイスありがとうございます。
言葉足らずな所がありまして申し訳ありません。下記追記させて頂きますm(__)m
ーーー
内山勇人さんへ
そうですか。
もう少し教えていただかないと何とも言えません。
1)耕作放棄地(2反ほど)は、元田んぼですか。畑ですか。
→5年ほど前まで水田で、それ以降は耕作放棄地で荒れ地でした。
2)陸稲で育てたハッピーヒルは、今後も続けて行きますか?拡大する予定はありますか?それによっては、輪作体系を考えた方がいいので。
→はい。ハッピーヒル(陸稲)は今後拡大させながら継続するつもりです。
「陸稲の連作障害」は恥ずかしながら今まで知りませんでした。
私の農園は
↓
【私の農園配置図】
https://www.evernote.com/shard/s203/sh/72370d2c-1a30-4a9d-9964-871b5e897d20/398da2a08cebd7d245a22cb4e04166f7
です。
ーー
それは、陸稲は2年以上連作すると、収量が落ちやすく、育ちにくくなります。水田は水を張っているので、連作障害になりません。
↓
水田は、溜池が壊れていること
井戸もないので今のところ難しいです。
以上の条件で「おすすめの輪作体系」はございますでしょうか?
11月18日勉強会行けたらと思います。
後ほどお申込みさせて頂きます
何卒よろしくお願い致しますm(__)m
内山勇人
そうですか。
もう少し教えていただかないと何とも言えません。
1)耕作放棄地(2反ほど)は、元田んぼですか。畑ですか。
2)陸稲で育てたハッピーヒルは、今後も続けて行きますか?拡大する予定はありますか?それによっては、輪作体系を考えた方がいいので。
それは、陸稲は2年以上連作すると、収量が落ちやすく、育ちにくくなります。水田は水を張っているので、連作障害になりません。
先日10/21のスクールの問い合わせをした内山勇人です。
今年4月から今まで耕作放棄地(2反ほど)を貸して頂き 大阪で「ハッピーヒル」を「陸稲」で 育てています。
今年間もなく稲刈りが終わります。
来年は、「ハッピーヒル」を「陸稲」で本格的に植えようと考えております。
そこで「2点」ご質問がございます。
①今から「来年の田植え」までの間に「植えると良い緑肥」はありますか?
将来「水田」に戻す可能性がある場合「ライ麦」を植え「粘土層を貫通させる」のは避けるべきと以前「竹内さんの別記事」にありました。
私の農園では「陸稲」を将来も続けていきますが「陸稲」も「水稲」と同様に「ライ麦」は避けるべきでしょうか?
この記事にある「水田の耕作放棄地」と同様に「えん麦+蓮華」を撒いて 耕運機 をかけたらいいのでしょうか?
↑↑
「陸稲」は「畑」にならぬような「水はけの悪い土」が向いていると聞いたことがありますが本当でしょうか?
②この記事に「蓮華」は数年スキ込みを続けると「稲が倒れる」と書いてありました。1年間でしたら大丈夫でしょうか?
それとも、一年であっても、全部蓮華を刈って持ち出してから耕運機をかけ陸稲を植えた方がよろしいでしょうか?
今後は、(竹内さんの農園に学習に行き)今年以上にしっかりとした農園にしたいと考えております。
以上お忙しい中恐縮ですが、なにとぞよろしくお願い致します。 内山勇人
そうですね。
今年全面でライムギの生育がよければ、全部畑にでき始めます。
もし、全面というわけでなれかば、生育の悪いところをもう一年セズバニアで穴をあげると効果的です。
もし全面うまくいっても半分しか畑にしない場合は、ライムギをそのまま育てて、穂が出そろう前に、半分にカットします。
そうすると、すぐに1週間位で穂が出てきます。(そして穂が種になったら、その上から、エンバク、クリムソンクローバーを蒔いてすべて刈り倒します。
そうすることで、背丈が低く扱いやすくなりますし、草マルチもできます。うまくいけば、ライムギが秋に自然生えしてくるので、ライムギを蒔く必要がなくなりますよ。
しかし、ライムギの自然耕はすごそうですね!ライムギが育つのが楽しみです。
うまくいけば来年には畑にできると思いますが、1度に全部の面積を畝たてして畑にするのは大変そうなので、半分程度から始めようと思っています。
その際、残りの半分は再度緑肥で耕そうと思います。
そうですね。
1)セスバニアが4分の1になると、気候も涼しくなりさすがに元気いっぱい芽が吹くわけではありません。生きているのが精一杯ですよ。木化を遅らせるのが目的です。
要は、全部刈ってしまってから、次の緑肥作物のタネを蒔いてしまも発芽率が悪く、発芽ムラがおきます。
そこで、生かさず殺さずの状態にしておいて、最後の緑肥mixを種まきした後、覆土代わりに、4分の1を地際で刈って敷くと次の緑肥作物が良く発芽してくれます。
2)ライムギの自然耕の効果は、根の効果でいえば、秋から春にかけて、茎葉に先行して、地中深くまで根を待っている冬の間に発揮されます。そのため、春先の30㎝位に生育した頃には、十分耕されております。
30㎝以上になってしまった場合、鋤き込むのが遅くなること、大型トラクターでないと鋤き込めないこと(もしくは、ハンマーモアで裁断してからでないと鋤き込めない)があります。
1mを超えて、葉も固くなってから草払い機でカットしてから中型トラクターで鋤き込むと、ロータリーにからんでうまく鋤き込めないというわけです。
実際に、田んぼで、冬の間15㎝位までライムギを育てたことがありますが、小さいから大丈夫と思って鋤き込んだのちに、水を入れて鋤き込んだら、乗用トラクターがはまってしまって出れなくなるほど、自然耕されていた体験もあります。
1)2)とも私の体験に基づき、一般的なことを想定しての話なので、実際にやってみて、大丈夫だったらそれはそれだと思います。
ちょっとしたことが大切だと思います。
参考にさせていただきます。
質問です。
セスバニアをさらに半分にカットするとほとんど茎だけになると思いますが、それでも芽を出してくるでしょうか?
それと、「2~3月にライムギを15㎝~30㎝のうちに鋤こむ…」とありますが、この時点で鋤きこんでもライムギの自然耕などの効果はあるのでしょうか?
度々の質問でスイマセンです。。。
そうですね。
まだセスバニアはもう一度刈れるので、刈ってからライムギの播種まで2カ月以上ある場合は、その間エンバク、クリムソンクローバーを生やしておいて、その後ライムギ、エンバク、クリムソンクローバーが一緒に生えるように蒔くという意味でした。
つまり方法はタイミングによって違ってきますが、緑肥作物が絶え間なくリレーしていく様にできればと思います。
今までは場所がわからなかったので、現状から類推して、中間地~温暖地だと思っその場合を想定してのお話でしたが、
暖地の場合ライムギの品種によりますが、11月中下旬に播くとしたら、(霜が11月上旬におりる地域)
以下のようにお奨めし直します。
①半分にカットしたセスバニアから脇芽が出て、再度花が咲いた頃に、さらに半分に刈ります。刈る際は、一片がなるべく30㎝以内になるように数回に分けて刈るといいでしょう。
②10月中下旬に、エンバク2㎏、クリムソンクローバー1㎏、レンゲ1㎏、ライムギ3~4kg程度を混ぜてから、セスバニアの葉などがが良く乾いた晴れた日中に、セスバニアの上から播いて、セスバニアを根元から刈り敷きます。(その際にセスバニアが30㎝以内になるように数回に分けて細かく刈るとより効果的です。)
③2~3月に、ライムギが15~30㎝以内の内に鋤き込んでしまい、畝立てをします。
鋤き込む際に、ライムギが最終的に何センチに育つか確認できるようにどこか邪魔にならないところ、1㎡程度鋤き込まずに置くとよいでしょう。
2~3月にライムギが葉が濃く、元気に育っていれば、2m程度に最終的に育っていれば、元田んぼが肥えて、水はけも良くなっていることでしょう。
乗用トラクターで鋤き込む際に、ライムギの上から米ぬかを振ってから浅く鋤き込み、2収穫後に深く鋤き込むと一層緑肥として土を良くしてくれるでしょう。
ライムギを蒔くまで、エンバク、クリムソンクローバー等の緑肥を蒔いておく、ということでいいのでしょうか?
文中に、
「そのタイミングで、エンバクとクリムソンクローバー、タイミングが合えば、レンゲを合わせて、5~8kgほど播いてからセスバニアを30㎝以内の長さにカットしながら刈り敷きます。」
とありますが、セスバニアはこの時点で根元まで刈ってしまうのでしょうか?それとも、いくらか残しておくのでしょうか?
もう一点、ライムギを蒔いた後下草を15㎝残す・・・とありますが、生えてきているエンバク、クリムソン等の緑肥を刈って残す、ということでしょうか?
ちなみに、こちらは香川県高松市になります。暖地ですね。
よろしくお願いします。
以前の「同じ種類の緑肥でも品種がいろいろあるみたいですが、違いはあるのでしょうか?」の質問に気づかずご返信していなかったこと申し訳ございません。
今気づきました。
品種や種苗メーカーさんによって値段は様々です。
もし選べるのであれば、用途と風土に合っているものを選ぶといいと思います。
つまり、各社力を入れていて、今は同じ緑肥でも品種特性が違います。
もし価格を抑えたい場合は、高価な緑肥と安価な緑肥を混ぜて購入するのもお奨めですよ。
お久しぶりです。
そうですか、よかったですね。
それであれば、来年はいよいよ畑にできそうですね。
仕上げのライムギは、ライムギの播種時期に10アール当たり、8kg前後蒔くのが妥当ですが、
地域によっては、セズバニアが木化しないうちに刈りしくとしたら、ライムギの播種適期までに1カ月以上空いてしまう場合があります。
その場合、セズバニア背丈半分にカットし、すぐに脇芽が伸びてきて、再度花を咲かせます。
そのタイミングで、エンバクとクリムソンクローバー、タイミングが合えば、レンゲを合わせて、5~8kgほど播いてからセスバニアを30㎝以内の長さにカットしながら刈り敷きます。
その際は、イネ科とマメ科の比率が1:1位が妥当です。
セスバニアを刈り敷くとその間から蒔いた緑肥が発芽してきます。
5~8kgと幅があるのは、春に蒔いたクリムソンやエンバクが生えている場合は、少なめで、セスバニアの下草が生えていなかった場合は多めになります。
ライムギの播種期まで生やしておいて、生えている上からライムギを撒いて、15㎝程度下草を残して刈ります。
クリムソンクローバーやレンゲなどマメ科の緑肥が良く生えていた場合は、ライムギを5kg程度と少なめに撒いても大丈夫です。
約1反の元田んぼを畑に転換中です。
セスバニアが良く育ち、先日セスバニアを背丈半分ほどにカットしたところです。
このままでいくと、次回はライムギ、エンバク等の緑肥を蒔く予定ですが、1反ではどのくらいの量が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
緑肥の品種について質問です。
セスバニアでも「田助」、「ロストアラーター」、クロタラリアでは「ネマキング」や「ネマックス」など同じ種類の緑肥でも品種がいろいろあるみたいですが、違いはあるのでしょうか?
緑肥として使用するのに大きく変わらなければ、少しでも安い方が…と思うのですが。
よろしくお願いします。
そうですね。10a(1反)あたりセズバニアとクロタラリアを混ぜたものが4kg以上必要です。
本当は、前作の緑肥作物の生え方でどのような農地かがある程度検討がつくので、
その検討に合わせて、ブレンド比を考えてmixるします。
水はけが悪い畑では、セスバニアを多め。乾いている場合は、クロタラリアを多めといった感じです。
わからない場合は、全体量1~2kg標準より多めにし、半々で混ぜると効果的です。
イタリアンライグラスが良く育っているので安心しました。
6キログラムというのは、1反に対してでしょうか?
「もしくは緑肥(エンバク:前進、ヒエ:ホワイトパニック)を1kgずつ混ぜて6kgで播く…」とありますが、この場合、セスバニア・クロタラリアを2キロずつに、エンバク・ヒエを1キロずつまぜ、合わせて6キロということでしょうか?
よろしくお願いします。
そうですか。興味深いですね。
生き物目線でいうと北と南の田んぼは全く違うようですね。
いずれの田んぼもイタリアンライグラスが元気に生えているのであれば、夏の緑肥mixクロタラリアとセスバニアを基本半々合わせて6kg、もしくは緑肥(エンバク:前進、ヒエ:ホワイトパニック)を1kgずつ混ぜて6kgで播くとよりいいと思います。
良く晴れた風の弱い日中に、(緑肥イタリアンの葉の乾いた時)に、イタリアン葉の上から混播した6kgを田んぼに均一になるように播きます。
播いたその日の内に、草払い機で、イタリアンを地際から刈ってしまいます。
つまり、草の上から播いた種が地上に播かれた後、草を刈るので、種の上に草が敷かれることになります。
そうなると、土を被覆することなく、枯れた草の間から約1週間後に混播した緑肥が発芽してきます。
ちなみに、セスバニアの根粒菌は、日本に在来しないため、タキイ種苗さんの場合セスバニア:田助には、専用の根粒菌が小袋で入っております。播く直前にちょっと濡らした種子に、あらかじめ専用の根粒菌を付着させてから播いてくださいね。
発芽後、セスバニア、クロタラリアいずれかが花が咲いたら、そのタイミングでそれら緑肥の背丈半分に草払い機でカット。脇芽を伸ばし新たに花が咲いたら、またさらに半分にカットしていきます。次にその時に、合った緑肥を秋に播いて越冬させて、翌年春に鋤き込んで元水田の畑化は第一ステップ完了です。
セスバニア・クロタラリアが1m以上伸びたら、秋にライムギが良く育つ準備が調ったことを教えてくれます。
ご無沙汰しております。
緑肥による元田んぼから畑に転換中ですが現状を報告します。
元田んぼは、北と南にあぜ道で分かれており、合わせて1反あります。
3月上旬に、イタリアンライグラスとエンバクを蒔きました。
5月30日現在の状況ですが、北・南ともイタリアンライグラスが約80㎝~100㎝ほどに成長しています。
つい、10日前にはイタリアンライグラスが育っているのかどうかもわからなかったのですが、あっという間に大きくなりました。
北側の田んぼではエンバクが80㎝ほどに育ちイタリアンライグラスに埋もれている感じです。
しかし、南側ではエンバクはほとんど見られません。
エンバクの種は赤く色が付き農薬処理していましたが、蒔いた後に食べられたようなカラもありました。
それとも土が合わなかったのでしょうか?
この南側の田んぼは水はけが特に悪いです。
そして、両方とも今まで田んぼ全面に生えていた20~30センチほどの雑草が茶色くなり枯れていってます。
今後の緑肥mixはどう選べばいいのでしょうか?
ちなみに、あぜ道のカヤはほとんど取り除きました。
このカヤはこのまま朽ちて堆肥とかに使えるのでしょうか?
よろしくお願いします
そうですね。
緑肥作物も育たない土壌の場合以下の原因が考えられます。
1)草も生えない土壌
2)緑肥作物の種類の選び方が合っていない
3)緑肥作物が発芽生育できない条件がある
4)種子が食害されてしまった、もしくは発芽後食害された
もし無消毒の種子を播いて、鳥の食害があったのであれば、ほとんどの見つかった種子がなくなったと考えてもいいので、4)でしょう。
そして、水はけが悪く、根ぐされなどしてしまった場合は、3)も重なったと考えられますが、他に何か原因がありますか?
①2枚の違いはなんですか?
②今生えている草は、田んぼの草ですか?
その原因がわかった上で、現状想定内なら(※3)と4)なら)私なら以下のいずれかを選ぶと思います。
A)上策
今生えている草がある程度まんべんなく育てているなら、良く晴れた日中に、その草の上から、エンバク(前進)、イタリアンライグラス(ワセフドウ)、ヒエ(ホワイトパニック)を2:2:1で良く混ぜたものを播いてから、草をすべてその日の内に刈り敷き、刈った草の間から芽が出るようにします。
もし草が、あちこちまばらな場合は、土が良く乾いている日を選び、同様な緑肥mixを播いてから草ごと鋤き込んで、発芽させます。
そして、6月下旬に、良く茂った緑肥mixの上から、よく晴れた日中、セスバニアと、クロタラリア、エンバク(前進)を2:2:1で混ぜたものを播いて、、その日の内に生えている春の緑肥を地際で刈ってしまい、枯れ草の間から、セスバニア達夏の緑肥mixを発芽させます。
B)そのままにしておき、草ボーボーの場合、良く晴れた日に、草の上から夏のセスバニア緑肥mixを播き、刈り取ります。
もしくは、草がまばらな場合、鋤き込み発芽させます。その場合、梅雨に入る前に行う必要がどうしても出てきます。
つまり、A)では、原因を追及した結果をうけ、元水田でも良く発芽し、食害の少ない消毒種子を選びしっかり発芽させ、夏のセスバニアたちマメ科の良く育つ土壌を、これからでもイネ科の緑肥を育て準備し、夏の緑肥作物にリレーしていく積極的なやり方。
それに対して、B)は、積極案を用いず、とりあえず現状を活かし、セスバニアたち夏の緑肥作物からはじめるとい感じです。
現状が見えてこないので、あくまで一般的な草が生えていないことを想定してアドバイスしてみましたが、現状が詳しくわかるともっとそこにぴったりな案が出てくるかもしれません。
もちろん除草剤は使いません。
2枚合わせて約1反の元田んぼにエンバクとイタリアンライグラスを蒔いていますが、水はけの悪かった方の田んぼには、草以外ほとんど芽が出てきていません。
緑肥をまいた数日後、鳥に種を食べられたような跡があったので食害もあると思いますが、緑肥が育たない土壌なのでしょうか?
6月ごろにセスバニア、クロタラリアなどを蒔く予定ですが、このまままいても大丈夫でしょうか?
もう一方の方は、エンバクかイタリアンライグラスどちらかが25・6㎝ほどですが、ぼちぼちと育っています。
アドバイスあればよろしくお願いします。
芽と取り除いているというのは、カヤの芽でしょうか?
もしカヤの芽でしたら、芽だけでなく、芽の下の土の中の生長点(根も)も一緒に取り除かないと、あとが大変ですよ。
草を刈る時は、鎌も草払い機もいずれも一番適したものを使っております。
刈り方も大切ですが、それ以上に刈るタイミングがとても重要で、気にかけております。
なんとか、茅を取り除いているところです。
ところで、竹内さんは緑肥や草、イネなどを刈る時は草刈機で刈るのですか?
それともカマで刈るのですか?
場所にもよると思いますが、広い田んぼなど手刈りは大変だと思うのですが…
そうですね。
絶やすのに、一番いいのは、根が動かない期間(霜のある期間)に、根を残さず取り除きます。
その後復活してくるカヤを常に刈って、敷き草にしていくことで、根に養分を貯めることができないので、どんどん細くなっていくので、やがて枯れるか、多少残る程度になります。
どんどん草マルチの素材として活用していくのがいいと思います。
エンバクとイタリアンライグラスでの土作りですか、いいですね。
緑肥作物は、とても強いので、草も作物も抑えてしまいがちになり両刃の剣ですので、播く場所や扱いにご注意してくださいね。
畔道にかやが生えてきており畑に伸びてきそうです。
かやの対処法があれば教えて頂きたいと思います。
今年から緑肥による土作りをしています。
3月初めにエンバクとイタリアンライグラスをまいています。
お忙しいと思いますが、よろしくお願いします。
そうですね。
昔はとても大切な畦焼きで、秋と冬の風物詩でした。
むやみに草を生やすと、ネズミの越冬場所になり、肥えてくると崩れるので、注意が必要です。
私は、畦に、シロク―バーと背の低い牧草など傾斜合わせて播いて、草マルチの材料にしたり、草刈りを簡単にしております。
ありがとうございます。
やはり、惰性で焼いてる感はありますね。
自分は、やらないことにします。
火事も怖いし…
除草剤を畔に撒く人がいるのですが、畔がボロボロになってます。
そうですね。
関西地区でも場所(標高)によりけりだと思います。
エンバク、クリムソンクローバーのカタログや種苗会社のマニュアルを参考にしてみてください。
大量の草がある中、ばらまきで鋤き込むと、草が発酵などし、ガスなどで発芽障害を起こす場合があります。
その場合は、何回か耕して発芽障害をなくしてから播くことが大切です。
春先の低温で、草が多少ある分には、そのままばら蒔き、すぐにトラクターで鋤き込んで構いません。
水はけがよい場合は、そのままタネが5cm位覆土するように耕します。
食用エンバクは、オートミールと呼ばれております。
エンバクは、猫の草として売られていますし、家畜のエサとしても、硝酸値が高くない場合は使用できます。
刈ったもので、堆肥を造ると良質の堆肥ができますよ。
当方、関西地方なのですが、春蒔きはまだ間に合いますか?
エンバクまたは、エンバクとクリムソンクローバーを蒔く前に、ある程度耕しておく方がいいのでしょうか?現状、少しずつ草が生え始めてきました。このままばら蒔いてから、トラクターで耕してよいのでしょうか?
トラクターで耕すのは、ほんの浅くでいいのでしょうか?畝立てや溝は、なくていいですか?
ところで、エンバクは緑肥やマルチ以外の、収穫物としての使い道はあるのでしょうか?
以上、沢山で恐縮ですが、宜しくお願いします
ありがとうございます。
そうですね。
土手(畦)焼きについてですが、私見では、
古来から、病虫害は畦から入ってくるので、それを払うために行ってきた伝統的な野良仕事です。
狙った効果としては、
・病害虫を越冬させない。
・草を退治する。
・モグラやネズミの住処にしない。
などが主な狙いです。
すべて矛盾もするのですが、
畦を焼くことで、
・益虫なども住めない。
・焼畑効果で草はより強く復活する。
・田畑にいるねずみ・モグラは退路をなくし、居座る。
など両刃の剣でもあります。
個人的には、ネズミや病虫害は脅威だったので、いかに悪いものが入って来ないように、予防するか、畦を常に綺麗に保ち、崩れないように管理する知恵があった名残だと思いますが、
近年では、とりあえず焼こうと風などを無視し、山火事を起こしそうになったり、
焼く代わりに、除草剤を使い、草をむやみに枯らし、良したちの悪い草と戦うはめになったり、
伝統的な野良仕事も表面的な形になってきております。
御出版おめでとうございます。
さて、田んぼや畑の土手焼きについて質問てす。
この時期、皆さん盛んに土手を焼いていますが、土手焼きの効果は何でしょうか?
知り合いの農家に聞くと、害虫の卵を焼くのが主な目的だそうですが、実際にはどうなのでしょうか?
人によっては、焼くと、風雨で却って土手が脆くなるから、止めた方がいい、という意見もあり、混乱しています。
よろしくお願いします。