
現在、『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~
※有料サイトの都合、登録などの際に一部英語表記になっております。
※最新動画、「畑での野良仕事(実技編)」前編・後編もアップグレードできました。
本日、
 のち
のち 。
。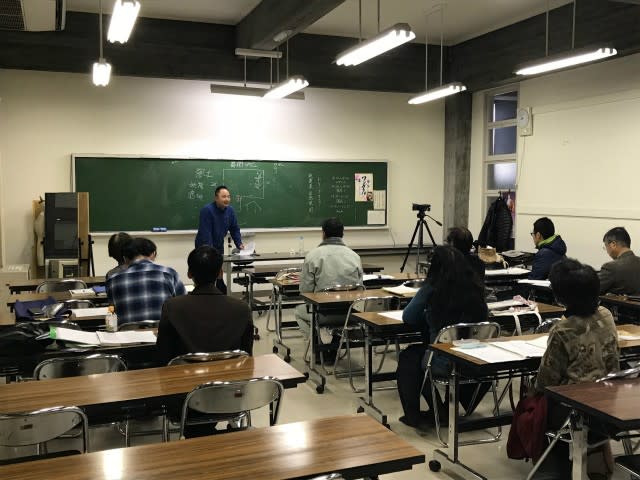
昨晩は、新春一番の「これならできる無農薬・自然菜園入門」講座でした。
この1~2月時期は、執筆や講演会、新年度の菜園教室の準備をしているだけで、この長野市の城山公民館での講座が唯一の講座なので、熱が入ってしまいます。

今回は、1月のテーマが「土づくり」、2月と3月のテーマが「菜園プラン」と、栽培していない時期だからこそ、一貫して無農薬家庭菜園の根本的な考え方、野菜が自然に育つ土とは、その土を鍛えてくれる菜園プランを学びます。
この3回の講座を受けるだけで、なぜ野菜が育たないのか、なぜ無農薬でも育つようになるのか、どのように多種多様の野菜を狭い菜園でも育て続けることができるのか、超基本~実践の仕方を学べる20年間のエッセンスギュッと詰まった大好きな内容になっております。
まずは、黒板にもあるように、①農薬・化学肥料を使った場合の土づくり、②有機肥料を使い無農薬にする場合の土づくり、そして③肥料農薬に依存せず野菜の本気を出させる土を育てる土づくりのイメージを学び、その違いがどこから来るのか、そしてそのメリットデメリットを知り、自分が目指す土づくりを明確にします。

そして、①~③の共通点と異なる点を踏まえた上で、野菜がどう変化するのか、どのような土を目指し、②と③の土づくりの共通点、そしてそのアプローチの違いを知ってもらいました。

通常の教室ではめったに深入りしないのですが、菜園のコンサルティングを受けた際には、必ず「土壌分析」を行って、その土の化学性を知り、生えている草や土を観察して物理性と生物性を知ってもらうアプローチを取ります。
「土壌分析」とは、土の健康診断であり、化学的な側面を数値で知ることによって、目ではなかなか見えてこない土の状態を観察できます。
味噌汁を作る際は、味見が不可欠のように、土づくりも途中で味が観れるといいのですが食べるわけにはいかないので、化学的、物理性、生物性を同時に観て、現状を知ることが、最も土づくりの基本的なことになるので、今回はそのアプローチをご紹介しました。
Ph、EC、CEC、塩基飽和度、塩基バランスの基本的な見方を知ることで、人でいうと血圧、尿酸値、土の器、レントゲンといった感じに、土(人)の性格まではわかりませんが、土の成分の過不足を知ることで、パッと見てわからないことがわかり、野菜が育ちやすいか、病虫害がでやすかどうかなど知ることができます。
土の成分の過不足を知ることは大切です。
味見をせずに、どんどん味噌を足したら、しょっぱいだけの味噌汁になりがちで、
実際、生徒さんが自分の菜園を土壌診断するとものすごくしょっぱい菜園や全然味がしない畑であることに気づけるからです。
土づくりをし続けた畑は、Phが高過ぎたり、石灰(カルシウム)が過剰で、他の塩基例えば苦土(マグネシウム)が少なすぎて、塩基バランスが崩れまくっていたりしがちですし、
庭や山際の畑は、Phが低過ぎたり、リン酸などが不足しすぎていて、他の養分やミネラルがあっても吸えないことが多く野菜が育たない欠乏症になっていることを知ることができます。

実際に生えている草や野菜の育ち方、育つ野菜と育たない野菜で土は色々語りかけています。
雨が降っても水たまりができている場合は、土の排水性に問題がありますし、
乾燥するとすぐに水やりをしなければいけない場合は、水持ちに問題があり、

野菜の根が健全に張ることができ、養分水分を吸収するためには、適度な水分・養分・空気を保持できる土、
いわゆる「水持ちが良く、水はけが良い、保肥力が高い」土が野菜が自然に育つ土であり、それは団粒構造が発達した土になってきます。
団粒構造の基本的なつくられ方を知り、その団粒化を促進することこそが、土づくりになります。
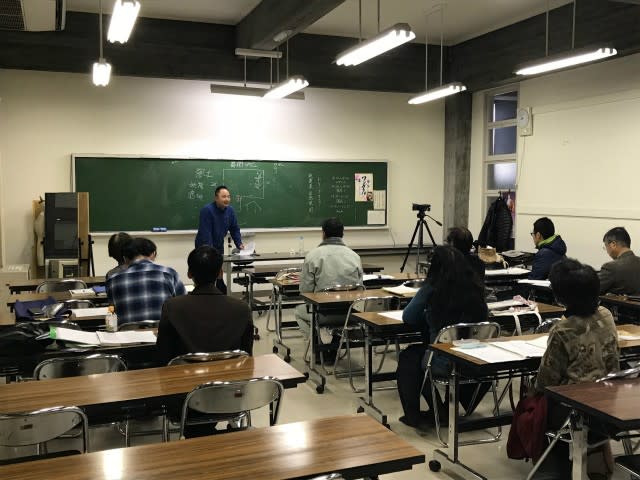
前半は、土壌分析などを知ることによって、目で見えない土の様子を観察するヒントを学び、
後半は、自然菜園の3ステップの土づくりのプロセスを学んでもらいました。
無肥料・不耕起栽培は、いわばフルマラソンのような過酷で人でいえば精神力や体力を天候や条件がいろいろある中で行うようなもので、いきなり野菜が育つ栽培方法ではありません。
そこで、菜園によっては、化学肥料(点滴)農薬(薬)を駆使してきた病虫害が出ている疲弊した(入院)菜園(人)の場合、まずはリハビリ(歩行訓練)が必要ですし、
毎日走っている基礎体力がある方(有機農業をし続けた畑)であれば、無肥料・不耕起(長距離走)に慣れるトレーニング(栽培方法)が必要ですし、その菜園の状況によって土づくりのアプローチが変わってくると思います。
この冬の菜園ができない時期にこそ、知っておいてほしい土づくりの基本を行いました。
次回から2回にわたって、今度は菜園の環境を調え、病虫害を出にくくし、体力や持久力をつけるトレーニング(菜園プラン)にするのかを行います。
少量多品目を育てることは農家さんでも難しく、家庭菜園ならではの最低限の知識や工夫を学び、病虫害、連作障害が起こりにくく、それでいて野菜を育てれば育てるほど土が良くなっていく菜園プランをご紹介する予定です。
お楽しみに~

2018年土内容充実で、
『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。
城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
今年度は、いつもの第1水曜日に
城山公民館 18:30~21:25
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~冬編~」
◆次回以降の予定
【今月のテーマ】
1/10(水) -病虫害に負けない無農薬栽培の土づくり
2/ 7(水)-菜園プラン① 連作障害の出ないプランの立て方
3/ 7(水)-菜園プラン② 菜園プランの極意

















