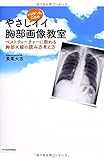実習中、上の先生方からブロガーであることをバレがちなわたくしですが(笑)、今の診療科では珍しくバレずに終わりそうだと思っていたのに、肩を叩かれ、
「よっ、ブロガー」
と。先生方、こんなに拙いブログをご覧いただきまして誠に恐縮です。医大生・たきいです。
さて、最近読み終わったのがこの一冊。感染症の世界では超有名な岩田先生のご著書です。
 | 神戸大学感染症内科版TBL: 問題解決型ライブ講義 集中!5日間 |
| 岩田健太郎 | |
| 金原出版 |
神戸大学医学部の4年生への講義録。講義といっても一方通行の講義というわけではなく、学生に課題が与えられてそれに応え、双方向で講義が進められていくイメージ。途中で台風が来て、講義が中止になるやならざるや、だなんていう場面もあって結構臨場感があります。
5日間の講義。講義の終わりには岩田先生から課題が出されます。「はじめに」にもちょっと言及がありましたが、この企画を本にしたことにはデメリットもあって、神戸大の学生が宿題として家に帰ってうんうん考えてきた時間が、本の上ではあっという間に過ぎてしまうということです。岩田先生が学生に課した課題を自力で取り組んで来ればいいのでしょうが、そこまでガッツをもってこの本を読み切れる人はほとんどいないでしょう。将棋の棋譜並べをするときに、対局者と同じだけの消費時間分考えて棋譜並べする人がどれだけいるのかという話です。少なくともわたくしには無理です。笑
この本を読み終わっての一番の感想は、今まで医学知識の蓄積の仕方間違えてたかも…ということでしょうか。
疾患に付随する徴候なり検査結果なりというのは多彩なものがありますが、今まで、どれもが並列な関係で多く言えれば勝ちみたいな感覚で勉強に取り組んでいた気がします。こういう頭の使い方では臨床ではつかえないのだ、と、この本を読めば少なくともそう思えるのです。それぞれにはグラデーションがあって、そのイメージで疾患を記憶しないといけない。グラデーションとともに疾患を記憶して行って、臨床では仮設生成の繰り返し。なるほど。何割がこうなるのか。感度と特異度は。陽性尤度比は。かなり大事なことで、ややもすれば誤診につながりかねないということにようやく気が付けました。感度も特異度も正しいお作法という認識くらいでしかありませんでしたが、岩田先生に神戸大の学生がすかさずツッコまれているシーンを読んで、ようやく大事さが直感的にも痛感できた気がしています。ビギナーのうちにこのことに気が付けてよかった。5日間の講義中、最終日になってもこのことに気が付けていなかった学生さんは岩田先生から怒られている一コマもありました。
読みどころは他にも。
「イ○ーノート」「ス○ップ」などといった医学生の所持率高めな本も岩田先生の手にかかればまさかのエロ本よばわりです。
「もっともああいった参考書ってさ、やっぱり知的レベル的にはちょっと微妙なので、あんまり人前では読まない方がいいと思うけど。何と言うのかな、エロ本と一緒だからさ。要するに読むことは否定しないけど、人前で読むのはやめた方がいいってことだよね。」(神戸大学感染症内科版TBL<金原出版>p.410より)
他にも「病み○」は教科書じゃないと頑なに主張する派の先生とか、医学生が使うカンタン教科書に対して難色を示すタイプの
因みに。「感染症」というタイトルは銘打ってありますが、感染症のことは置いといて、医学生が知るべき正しい勉強法が載っている本だと思ったほうがよいでしょう。ようやく感染症の症例が出てきたのは本書の後半に差し掛かって以降っすからね(笑)
うちの大学でもこういうエキサイティングな講義あればいいのになー。
(典型症例だけ集めた国試出題基準全疾患集とかあったら売れるんじゃないかなと思った人(笑))
▼エ○本も読みたいあなたはこちらから
 | イヤーノート 2016: 内科・外科編 |
| 岡庭豊 | |
| メディックメディア |