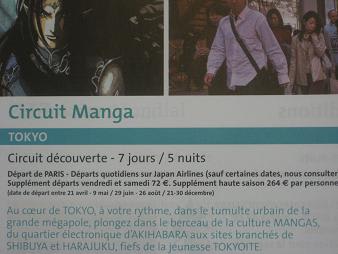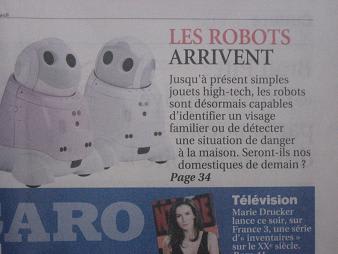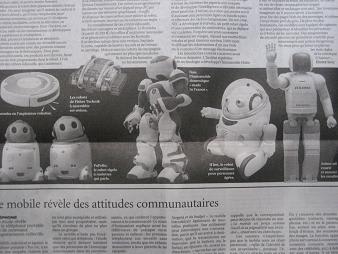まずはともあれ、11日のメトロ紙をご覧ください。

記事の内容よりも、見出しに注目を! “A la recherche du pouvoir d'achat perdu”(「失われた購買力を求めて」)・・・どこかで聞いたことのあるようなタイトルですよね・・・『失われた時を求めて』、プルーストの有名な小説のタイトルです。“A la Recherche du Temps perdu”・・・編集の担当者なのか、記者自身なのか、うまく決まった! といったところでしょうか。
こうした洒落た見出しは、ときどき目にします。

“Paris brille-t-il ?”(パリは輝いているか)・・・基になったのは、“Paris brule-t-il ?”(『パリは燃えているか』)、ご存知ですよね、パリ解放までのさまざまな人間模様を描いた、1966年のルネ・クレマン監督の作品。懐かしいのでちょっと調べてみたのですが、本当に豪華キャストだったんですね。ジャン=ポール・ベルモンド、シャルル・ボワイエ、アラン・ドロン、シモーヌ・シニョレ、イブ・モンタン、カーク・ダグラス、オーソン・ウェルズ、ジョージ・チャキリス、アンソニー・パーキンス。そして脚本は、まだライターだったフランシス=フォード・コッポラ。
このタイトルは11日に出た無料の情報誌“A nous Paris”(我等にパリを)の表紙に出ていたのですが、この情報誌の名前自体が洒落。基になったのは、たぶん、“A nous la liberte”(『我等に自由を』)。1931年のルネ・クレール監督作品。大量生産時代に生きることの大変さが描かれていますが、後に作られたチャプリンの『モダン・タイムス』に影響を与えたとか与えなかったとか、問題になっていたほどの名作ですね。
・・・名画の懐かしさに、思わず洒落の解説という、洒落にならないことを書いてしまいました。で、肝心の記事の内容なのですが・・・
まず、「我等にパリを」誌のほうは、イリュミネーションや店頭の飾り付けで、今パリが輝いている、という話題です。すでに何回かご紹介していますが、後日また別の写真をご紹介しようと思っています。
そして、メトロ紙のほうですが、フランス人の購買力が落ちている、それを向上させるには・・・ということで、今月、調査をしたようです。購買力が落ちているということは、要は収入の伸び以上に物価が上昇している。だから買いたいものが買えなくなってきている、ということですよね。こうした状況を改善するには、給与を上げる。しかし、今や「もっと働いて、もっと稼ごう」という、サルコジ時代。今までと同じように働いていては、収入の増加は期待薄。そこで、出てくるのが、残業と休日出勤!
残業分には課税しないという政府案を考慮に入れた上で、残業もいとわないですか、という質問には、何と78%がウイ。残業します!と言っています。今年7月の調査では65%だったウイが78%に増加。残業でもなんでもして、とにかくお金を、をいう層がふえているのでしょうか。
また、安息日である日曜日に働くことについては、平日よりも給与基準を高くするという条件の下、59%が働いても良いと答えています。男女別では、男性の63%、女性の55%ということで、男性のほうが日曜出勤に抵抗がより少ないようです。
この日曜出勤が最も影響するのがデパートなどの流通・サービス業。商店が日曜日も営業できるよう、現在の規制を緩和すべきかどうかという質問には、賛成が2004年の46%、06年の56%、そして今年の63%へと、一気に増えてきています。旅行者や週末時間をもてあましている人にとってはありがたい日曜営業、もしかすると、遠くない将来、実現するかもしれないですね。
しかし、働く人にとっては、残業や休日出勤が増えると、収入は増えるかもしれませんが、減るものがある。ここで、まさに洒落た見出しの基に戻るのですが、減少するのは自由な時間。『失われた時を求めて』になってしまうわけです。でも、自由な時間とより多くの収入、どちらかを選ばなければならないとしたらどちらを選ぶか、という質問に対しては、2001年の調査では47%と47%で、まさに均衡。それが今回の調査では、自由な時間が減っても、もっとお金を! という人が63%。逆に、武士は食わねど高楊枝、お金よりも自由な時間が大切さ、という人は37%に減少しています。このままでは、休暇を減らしてでも働いてもっと給料を、という声だって出てくるかもしれないですね。有給休暇が年間5週間、うらやましい、と思われていたフランス社会も、今、大きく変わりつつあるのかもしれません。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ

記事の内容よりも、見出しに注目を! “A la recherche du pouvoir d'achat perdu”(「失われた購買力を求めて」)・・・どこかで聞いたことのあるようなタイトルですよね・・・『失われた時を求めて』、プルーストの有名な小説のタイトルです。“A la Recherche du Temps perdu”・・・編集の担当者なのか、記者自身なのか、うまく決まった! といったところでしょうか。
こうした洒落た見出しは、ときどき目にします。

“Paris brille-t-il ?”(パリは輝いているか)・・・基になったのは、“Paris brule-t-il ?”(『パリは燃えているか』)、ご存知ですよね、パリ解放までのさまざまな人間模様を描いた、1966年のルネ・クレマン監督の作品。懐かしいのでちょっと調べてみたのですが、本当に豪華キャストだったんですね。ジャン=ポール・ベルモンド、シャルル・ボワイエ、アラン・ドロン、シモーヌ・シニョレ、イブ・モンタン、カーク・ダグラス、オーソン・ウェルズ、ジョージ・チャキリス、アンソニー・パーキンス。そして脚本は、まだライターだったフランシス=フォード・コッポラ。
このタイトルは11日に出た無料の情報誌“A nous Paris”(我等にパリを)の表紙に出ていたのですが、この情報誌の名前自体が洒落。基になったのは、たぶん、“A nous la liberte”(『我等に自由を』)。1931年のルネ・クレール監督作品。大量生産時代に生きることの大変さが描かれていますが、後に作られたチャプリンの『モダン・タイムス』に影響を与えたとか与えなかったとか、問題になっていたほどの名作ですね。
・・・名画の懐かしさに、思わず洒落の解説という、洒落にならないことを書いてしまいました。で、肝心の記事の内容なのですが・・・
まず、「我等にパリを」誌のほうは、イリュミネーションや店頭の飾り付けで、今パリが輝いている、という話題です。すでに何回かご紹介していますが、後日また別の写真をご紹介しようと思っています。
そして、メトロ紙のほうですが、フランス人の購買力が落ちている、それを向上させるには・・・ということで、今月、調査をしたようです。購買力が落ちているということは、要は収入の伸び以上に物価が上昇している。だから買いたいものが買えなくなってきている、ということですよね。こうした状況を改善するには、給与を上げる。しかし、今や「もっと働いて、もっと稼ごう」という、サルコジ時代。今までと同じように働いていては、収入の増加は期待薄。そこで、出てくるのが、残業と休日出勤!
残業分には課税しないという政府案を考慮に入れた上で、残業もいとわないですか、という質問には、何と78%がウイ。残業します!と言っています。今年7月の調査では65%だったウイが78%に増加。残業でもなんでもして、とにかくお金を、をいう層がふえているのでしょうか。
また、安息日である日曜日に働くことについては、平日よりも給与基準を高くするという条件の下、59%が働いても良いと答えています。男女別では、男性の63%、女性の55%ということで、男性のほうが日曜出勤に抵抗がより少ないようです。
この日曜出勤が最も影響するのがデパートなどの流通・サービス業。商店が日曜日も営業できるよう、現在の規制を緩和すべきかどうかという質問には、賛成が2004年の46%、06年の56%、そして今年の63%へと、一気に増えてきています。旅行者や週末時間をもてあましている人にとってはありがたい日曜営業、もしかすると、遠くない将来、実現するかもしれないですね。
しかし、働く人にとっては、残業や休日出勤が増えると、収入は増えるかもしれませんが、減るものがある。ここで、まさに洒落た見出しの基に戻るのですが、減少するのは自由な時間。『失われた時を求めて』になってしまうわけです。でも、自由な時間とより多くの収入、どちらかを選ばなければならないとしたらどちらを選ぶか、という質問に対しては、2001年の調査では47%と47%で、まさに均衡。それが今回の調査では、自由な時間が減っても、もっとお金を! という人が63%。逆に、武士は食わねど高楊枝、お金よりも自由な時間が大切さ、という人は37%に減少しています。このままでは、休暇を減らしてでも働いてもっと給料を、という声だって出てくるかもしれないですね。有給休暇が年間5週間、うらやましい、と思われていたフランス社会も、今、大きく変わりつつあるのかもしれません。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ