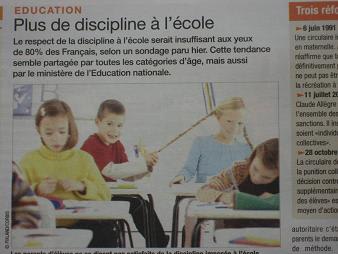SDF(Sans Domicile Fixe)と呼ばれるフランスの路上生活者、いわゆるホームレス。去年から何度かご紹介しているように、いろいろな団体が救済の手を差し伸べています。
例えばテントをサン・マルタン運河沿いに設置したり、食事を支給したり。政府は、郊外の軍施設を仮設住居に斡旋したりしていますが、この施策に関しては、要はパリの中心部から追い出したいだけだ、という声も聞かれます・・・
では、日本の場合は・・・

5日付のマタン・プリュス紙です。東京のわが小屋、といった見出しですが、写真の小屋が建っているのは、多摩川の河川敷・・・
バブルがはじけた後の90年代、数千人が路上生活の仲間入りをしたといわれています。新宿駅周辺のダンボールで囲った路上生活者の住まいが、海外のメディアによって広く紹介されました。しかしその後、役所の決定で撤去されてしまいました。都心を追われた人たちが新たに住みついたのが、河川敷。今、全国で5,653人が河川敷をねぐらにしているそうです。
そこに住む人たちの暮らしぶりは・・・例として、ベニヤや木材で立てた住まいを二人でシェアをしている人たちの場合が紹介されています。収入は、アルミ缶を拾い集めて売ること。回収車が来る前に出してあるカンを収集。1kg170円になるそうです。20日ほどそうして働いて、収入が12~20万円。支出は、食事(ご飯とスーパーで買ったおかず)、ビール、タバコ、週2回の銭湯・・・これで15万円ほどかかるそうです。
写真にも写っているように、住まいには多くの電化製品が・・・発電機、テレビ、ビデオ、冷蔵庫、掃除機、扇風機。そして、ペットに猫を2匹飼っている。
こうした気ままな暮らしに慣れてしまうと、もう元のような窮屈な暮らしには戻りたくない、という人が多いそうですが、そこはやはり河川敷。台風のシーズンなど、増水した川に住まいを流されたり、身に危険が及ぶことも。先日も、ヘリコプターで救助された人がいたそうです。
しかも、河川敷は国有地が多く、勝手に住めば、懲役1年になることも。監督官庁は、立ち退きを要求しているそうですが、でも、他に行くところがない・・・
一般の目に付きやすい都心から追い出され、さらには水辺からも追い出されようとしている・・・日仏ともに、路上生活者は追われる立場にあるようです。しかし、違うのが、自ら夜露をしのげる住まいを立て、自ら収入源を探し、掃除洗濯もきちんとして暮らす日本の路上生活者と、酒びたり、テントの支給がなければ、文字どおり路上やメトロの駅などで寝るフランスの路上生活者。フランス人の知人も言っていました、日本でビックリしたことの一つが、日本では路上生活者までが掃除洗濯をしている!!!
いろいろな事情があっての路上生活なのでしょうが、援助に依存しきったフランスと、自助努力の日本。なんとなく、それぞれの国民性が垣間見れるような気もします。
ただ、日本の河川敷で暮らす人たちの生活ぶりは、フランスのメディアに教えてもらいました。日本でも報道はされているのでしょうか(ネットカフェ難民とかは報道されているようですが)。それとも、弱者は切り捨てなのでしょうか。社会的援助が少なく、関心すら持ってもらえない。だから自助努力になるのか、それとも、それなりに暮らしているから、社会的支援の動きが少ないのか。ニワトリと卵。ただ、社会的弱者への思いやりと支援、日本にもっとあっていいように思います。今はそれなりに何とか暮らしていけていても、病気などの際には、どうしても支援が必要になる。異分子を排除する社会、とも言われる日本。しかし、社会の周辺に住まわざるを得なくなった人たちも、同胞です。もっと支援の手を。豊かな社会、そしてそれ以上に、温かな社会へ。そう思うのですが・・・
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ
例えばテントをサン・マルタン運河沿いに設置したり、食事を支給したり。政府は、郊外の軍施設を仮設住居に斡旋したりしていますが、この施策に関しては、要はパリの中心部から追い出したいだけだ、という声も聞かれます・・・
では、日本の場合は・・・

5日付のマタン・プリュス紙です。東京のわが小屋、といった見出しですが、写真の小屋が建っているのは、多摩川の河川敷・・・
バブルがはじけた後の90年代、数千人が路上生活の仲間入りをしたといわれています。新宿駅周辺のダンボールで囲った路上生活者の住まいが、海外のメディアによって広く紹介されました。しかしその後、役所の決定で撤去されてしまいました。都心を追われた人たちが新たに住みついたのが、河川敷。今、全国で5,653人が河川敷をねぐらにしているそうです。
そこに住む人たちの暮らしぶりは・・・例として、ベニヤや木材で立てた住まいを二人でシェアをしている人たちの場合が紹介されています。収入は、アルミ缶を拾い集めて売ること。回収車が来る前に出してあるカンを収集。1kg170円になるそうです。20日ほどそうして働いて、収入が12~20万円。支出は、食事(ご飯とスーパーで買ったおかず)、ビール、タバコ、週2回の銭湯・・・これで15万円ほどかかるそうです。
写真にも写っているように、住まいには多くの電化製品が・・・発電機、テレビ、ビデオ、冷蔵庫、掃除機、扇風機。そして、ペットに猫を2匹飼っている。
こうした気ままな暮らしに慣れてしまうと、もう元のような窮屈な暮らしには戻りたくない、という人が多いそうですが、そこはやはり河川敷。台風のシーズンなど、増水した川に住まいを流されたり、身に危険が及ぶことも。先日も、ヘリコプターで救助された人がいたそうです。
しかも、河川敷は国有地が多く、勝手に住めば、懲役1年になることも。監督官庁は、立ち退きを要求しているそうですが、でも、他に行くところがない・・・
一般の目に付きやすい都心から追い出され、さらには水辺からも追い出されようとしている・・・日仏ともに、路上生活者は追われる立場にあるようです。しかし、違うのが、自ら夜露をしのげる住まいを立て、自ら収入源を探し、掃除洗濯もきちんとして暮らす日本の路上生活者と、酒びたり、テントの支給がなければ、文字どおり路上やメトロの駅などで寝るフランスの路上生活者。フランス人の知人も言っていました、日本でビックリしたことの一つが、日本では路上生活者までが掃除洗濯をしている!!!
いろいろな事情があっての路上生活なのでしょうが、援助に依存しきったフランスと、自助努力の日本。なんとなく、それぞれの国民性が垣間見れるような気もします。
ただ、日本の河川敷で暮らす人たちの生活ぶりは、フランスのメディアに教えてもらいました。日本でも報道はされているのでしょうか(ネットカフェ難民とかは報道されているようですが)。それとも、弱者は切り捨てなのでしょうか。社会的援助が少なく、関心すら持ってもらえない。だから自助努力になるのか、それとも、それなりに暮らしているから、社会的支援の動きが少ないのか。ニワトリと卵。ただ、社会的弱者への思いやりと支援、日本にもっとあっていいように思います。今はそれなりに何とか暮らしていけていても、病気などの際には、どうしても支援が必要になる。異分子を排除する社会、とも言われる日本。しかし、社会の周辺に住まわざるを得なくなった人たちも、同胞です。もっと支援の手を。豊かな社会、そしてそれ以上に、温かな社会へ。そう思うのですが・・・
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ