かつて盛んに行われていた木炭の生産は時代とともに斜陽産業となり今で
は『絶滅危惧業種』となってしまった。この八雲町でも大小の数えきれないほ
どの窯があり、中には数人で共有する窯、持ち主から借用する窯などあった。
自前は当たり前で窯は定位置にあり周辺から材料を集めてきて炭焼きをする
ものとばかり思っていたのは違うと知り驚ろかされた。
ブログ管理人は街中で育ち木炭は使う側にいたから木炭の認識は生産側とは
全く異なり、そこに存在する苦労など何一つ知らず炭焼きに首を突っ込んだ。
昔の話を聞くと炭焼きの厳しさを改めて知る。炭焼きに参加する以前、友人か
ら昔話を聞いたが、その時は何一つ炭焼きの経験をしていなかったから苦労に
対しても『ふーん、大変だったのだ』としか思えなかった。
材料のある所に窯を築き、焼き上がったらそこから担いで里まで運ぶ。獣道の
ような所や急な所、悪天候の中など4Kと表現されるよりきつい超4Kの仕事だっ
たろう。窯の場所も段々と里から離れてしまうだろうから、作業の状況によって
は家に帰らず夜を通してお守りを必要としたこともあろう。
車による運搬、薪割機のない炭焼きを想像しただけで意気消沈して頓挫してし
まう。電気、ガスの普及は木炭を必要としなくなり限られた所のみで需要がある。
八雲町に幾つかの窯は残っているが今季、煙の上がっている窯は残念ながら
桑炭会のみと寂しい状況下にある。
日本から木炭が消えつつありネットでは代わりに『マレーシア産備長炭』なるも
のが闊歩している。
木炭を取り巻く厳しい中ではあるが
『自分たちで焼いた木炭でほんのり温まる』
たった、これだけのことだろうがその奥には沢山の意味が込められている。
島根県のホームページに県内の木炭生産活動を紹介している。
八名窯
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/tokuyo/yanagama.html
島根八名窯に挑戦
https://blog.goo.ne.jp/f-hamada/e/8889e6d82b220d9fb54c840655406396










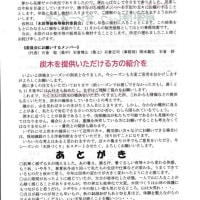

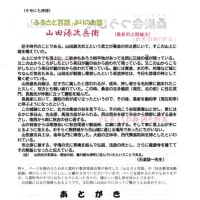

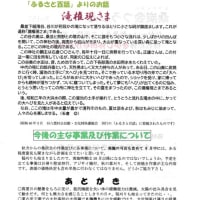

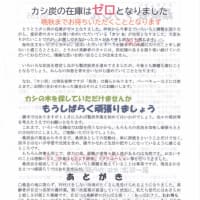
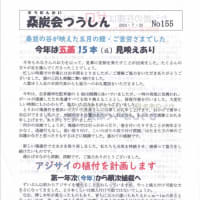
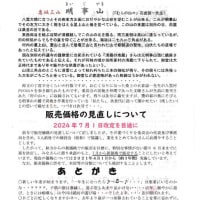
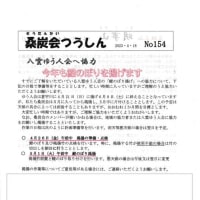
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます