たまには小説をと思い、手にしました。
菊池寛の「忠直卿行状記」です。
菊池寛って、文藝春秋の創刊者であるとともに、直木賞、芥川賞の創設者なんですね~。
いや~僕今日まで全く知りませんでした。
お恥ずかしい。
この小説は、センター試験の問題集か何かで全体の一部を読んだことがあって、その時以来でした。
ちょっと引用してみましょう。
---------------------------------------------------
【解説】
越前67万石の大名である松平忠直は、酒宴でしたたかに酔っていた。
昼間、家中で行われた槍術の紅白戦では、忠直卿自ら赤軍の大将として参加し獅子奮迅の活躍ぶりであった。
そのこともあり、気分良く酔っていた忠直卿であったが、少しばかり宴会の席を抜け、小さなあずまやで酔いをさますことにした。
【本文】
忠直卿は萩の中の小道を伝い、泉水の縁を回って小高い丘に在る四阿(あずまや)へと入った。そこからは信越の山々が、微かな月の光を含んでいる空気の中に、朧(おぼろ)に浮いて見える。忠直卿は、今までの大名生活においてまだ経験したことのないような感傷的な心持にとらわれて、思わずそこに小半刻を過した。
すると、ふと人声が聞える。今まで寂然として、虫の声のみが淋しかった所に人声が聞え出した。声の様子でみると、二人の人間が話しながら、四阿の方へ近よってくるらしい。
忠直脚は、今自分が享受している静寂な心持が、不意の侵入者によって掻き乱されるのが厭であった。
しかし、小姓をして、近寄って来る人間を追わしむるほど、今宵の彼の心は荒(すさ)んではいなかった。二人は話しながら、だんだん近づいて来る。四阿のうちへは月の光が射さぬので、そこに彼らの主君がいようとは、夢にも気付いていないらしい。
忠直卿は、その二人が誰であるか、見極めようとは思っていなかった。が、二人の声がだんだん近づいて来ると、それが誰と誰とであるかが自然と分かって来た。やや潰れたような声の方は、今日の大仕合に白軍の大将を務めた小野田右近である。甲高い上ずった声の方は、今日忠直卿に一気に突き伏せられた白軍の副大将、大島左太夫である。二人はさっきから、なんでも今日の紅白仕合について話しているらしい。
忠直卿は、大名として生れて初めて、立聞きをするという不思議な興味を覚えて、思わず注意を、その方へ集中させた。
二人は、四阿からは三間とは離れない泉水の汀(みぎわ)で、立ち止まっているらしい。左太夫は、心持声を潜めたらしく、
「時に、殿のお腕前をどう思う?」と、きいた。右近が、苦笑をしたらしい気配がした。
「殿のお噂か! 聞えたら切腹物じゃのう」
「陰では公方(くぼう)のお噂もする。どうじゃ、殿のお腕前は? 真実のお力量は?」と、左太夫は、かなり真剣にきいて、じっと息を凝(こ)らして、右近の評価を待っているようであった。
「さればじゃのう! いかい御上達じゃ」といったまま、右近は言葉を切った。忠直卿は、初めて臣下の偽らざる賞賛を聞いたように覚えた。が、右近はもっと言葉を続けた。
「以前ほど、勝ちをお譲りいたすのに、骨が折れなくなったわ」
二人の若武士は、そこで顔を見合せて会心の苦笑をしたらしい気配がした。
右近の言葉を聞いた忠直卿の心の中に、そこに突如として感情の大渦巻が声を立てて流れはじめたは無論である。
忠直卿は、生れて初めて、土足をもって頭上から踏み躙(にじ)られたような心持がした。彼の唇はブルブルと顫え、惣身の血潮が煮えくり返って、ぐんぐん頭へ逆上するように思った。
右近の一言によって、彼は今まで自分が立っておった人間として最高の脚台から、引きずり下ろされて地上へ投げ出されたような、名状し難い衝動(ショック)を受けた。
それは、確かに激怒に近い感情であった。しかし、心の中で有り余った力が外にはみ出したような激怒とは、まったく違ったものであった。その激怒は、外面はさかんに燃え狂っているものの、中核のところには、癒しがたい淋しさの空虚が忽然と作られている激怒であった。彼は世の中が急に頼りなくなったような、今までのすべての生活、自分の持っていたすべての誇りが、ことごとく偽りの土台の上に立っていたことに気がついたような淋しさに、ひしひしと襲われていた。

彼は小姓の持っている佩刀(はいとう)を取って、即座に両人を切って捨てようかと意気込んだが、そうした激しい意志を遂げる強い力は、この時の彼の心のうちには少しも残ってはいなかった。
その上、主君として臣下から偽りの勝利を媚びられて得意になっていた自分が浅ましいと同時に、今両人を手刃(しゅじん)して、その浅ましい事実を自分が知っているということを家中の者に知らせるのも、彼にとってはかなりの苦痛であった。忠直卿は、胸の内に湧き返る感情をじっと抑えて、いかなる行動に出ずるのが、いちばん適当であるかを考えた。余りに不用意にこうした経験に出合したため、たださえ興奮しやすい忠直卿の感情は、収拾のつかぬほど混乱した。
忠直卿のそばに、さっきから置物のようにじっとして蹲(うずくま)っていた聰明な小姓は、さすがにこの危機を十分に知っていた。二人の男に、ここに彼らの主君がいることを教えねば、どんな大事が起るかも知れぬと思った。彼は、主君の凄まじい顔色を窺いながら、二、三度小さい咳をした。
小姓の小さい咳は、この場合はなはだ有効であった。右近と左太夫とは、付近に人がいるのを知ると、はっとしてその冒涜(ぼうとく)な口をつぐんだ。
二人はいい合わしたように、足早く大広間の方へと去ってしまった。
----------------------------------------------------
いや~名文ですね。
心情の表現が実に巧みです。
全体の文は忠直卿行状記に載っているので良かったら見てみて下さい。
引用文には載せてませんが、僕が読んでて「おお!」と思ったのは、
「七寸に近い鋒先から迸(ほとばし)る殺気が、一座の人々の心を冷たく圧した。
」
という一文。
『冷たく圧した』って、表現格好良すぎです!
さっそくお俺もこの表現使ってみようかな。
こんなのはどうだろう。
------------------------------------
【支店の忘年会の席にて】
みな、一瞬何が起こったか分からないようであった。
しかし悲しいかな支店内は、支店長を頂点とする完全なる縦社会であった。
上司は,部下の生殺与奪を一手に握る権力者である。
支店内では、支店長を頂点とし、副支店長、課長、係長、主任、平社員、みなピラミッド構造の構成要員なのだ。
「上の者の機嫌を損ねること」、それはすなわち出世競争からの脱落を意味していた。
「布団が、吹っ飛んだ~!」
宴もたけなわ、支店長が、どうだと言わんばかりに温めていたギャグを上機嫌で言い放った。
「えっ....」
支店長の放ったその会心のギャグは、一座の人々の心を『冷たく圧した』。
しかし、しーんと静まりかえったのは、ほんの0コンマ何秒かであった。
すぐに「あはははは!!」という笑い声に満座が包まれた。
「もう、支店長ったらおもしろ~い☆」
若い女性社員の甘い声も、非常に心地良い。
宴の席が笑いに包まれたのを見て、支店長は痛く御機嫌であった。
----------------------------------
なんか『冷たく圧した』の使い方間違った気がしますが(笑)
てなことでまた(^_^)v
菊池寛の「忠直卿行状記」です。
菊池寛って、文藝春秋の創刊者であるとともに、直木賞、芥川賞の創設者なんですね~。
いや~僕今日まで全く知りませんでした。
お恥ずかしい。
この小説は、センター試験の問題集か何かで全体の一部を読んだことがあって、その時以来でした。
ちょっと引用してみましょう。
---------------------------------------------------
【解説】
越前67万石の大名である松平忠直は、酒宴でしたたかに酔っていた。
昼間、家中で行われた槍術の紅白戦では、忠直卿自ら赤軍の大将として参加し獅子奮迅の活躍ぶりであった。
そのこともあり、気分良く酔っていた忠直卿であったが、少しばかり宴会の席を抜け、小さなあずまやで酔いをさますことにした。
【本文】
忠直卿は萩の中の小道を伝い、泉水の縁を回って小高い丘に在る四阿(あずまや)へと入った。そこからは信越の山々が、微かな月の光を含んでいる空気の中に、朧(おぼろ)に浮いて見える。忠直卿は、今までの大名生活においてまだ経験したことのないような感傷的な心持にとらわれて、思わずそこに小半刻を過した。
すると、ふと人声が聞える。今まで寂然として、虫の声のみが淋しかった所に人声が聞え出した。声の様子でみると、二人の人間が話しながら、四阿の方へ近よってくるらしい。
忠直脚は、今自分が享受している静寂な心持が、不意の侵入者によって掻き乱されるのが厭であった。
しかし、小姓をして、近寄って来る人間を追わしむるほど、今宵の彼の心は荒(すさ)んではいなかった。二人は話しながら、だんだん近づいて来る。四阿のうちへは月の光が射さぬので、そこに彼らの主君がいようとは、夢にも気付いていないらしい。
忠直卿は、その二人が誰であるか、見極めようとは思っていなかった。が、二人の声がだんだん近づいて来ると、それが誰と誰とであるかが自然と分かって来た。やや潰れたような声の方は、今日の大仕合に白軍の大将を務めた小野田右近である。甲高い上ずった声の方は、今日忠直卿に一気に突き伏せられた白軍の副大将、大島左太夫である。二人はさっきから、なんでも今日の紅白仕合について話しているらしい。
忠直卿は、大名として生れて初めて、立聞きをするという不思議な興味を覚えて、思わず注意を、その方へ集中させた。
二人は、四阿からは三間とは離れない泉水の汀(みぎわ)で、立ち止まっているらしい。左太夫は、心持声を潜めたらしく、
「時に、殿のお腕前をどう思う?」と、きいた。右近が、苦笑をしたらしい気配がした。
「殿のお噂か! 聞えたら切腹物じゃのう」
「陰では公方(くぼう)のお噂もする。どうじゃ、殿のお腕前は? 真実のお力量は?」と、左太夫は、かなり真剣にきいて、じっと息を凝(こ)らして、右近の評価を待っているようであった。
「さればじゃのう! いかい御上達じゃ」といったまま、右近は言葉を切った。忠直卿は、初めて臣下の偽らざる賞賛を聞いたように覚えた。が、右近はもっと言葉を続けた。
「以前ほど、勝ちをお譲りいたすのに、骨が折れなくなったわ」
二人の若武士は、そこで顔を見合せて会心の苦笑をしたらしい気配がした。
右近の言葉を聞いた忠直卿の心の中に、そこに突如として感情の大渦巻が声を立てて流れはじめたは無論である。
忠直卿は、生れて初めて、土足をもって頭上から踏み躙(にじ)られたような心持がした。彼の唇はブルブルと顫え、惣身の血潮が煮えくり返って、ぐんぐん頭へ逆上するように思った。
右近の一言によって、彼は今まで自分が立っておった人間として最高の脚台から、引きずり下ろされて地上へ投げ出されたような、名状し難い衝動(ショック)を受けた。
それは、確かに激怒に近い感情であった。しかし、心の中で有り余った力が外にはみ出したような激怒とは、まったく違ったものであった。その激怒は、外面はさかんに燃え狂っているものの、中核のところには、癒しがたい淋しさの空虚が忽然と作られている激怒であった。彼は世の中が急に頼りなくなったような、今までのすべての生活、自分の持っていたすべての誇りが、ことごとく偽りの土台の上に立っていたことに気がついたような淋しさに、ひしひしと襲われていた。

彼は小姓の持っている佩刀(はいとう)を取って、即座に両人を切って捨てようかと意気込んだが、そうした激しい意志を遂げる強い力は、この時の彼の心のうちには少しも残ってはいなかった。
その上、主君として臣下から偽りの勝利を媚びられて得意になっていた自分が浅ましいと同時に、今両人を手刃(しゅじん)して、その浅ましい事実を自分が知っているということを家中の者に知らせるのも、彼にとってはかなりの苦痛であった。忠直卿は、胸の内に湧き返る感情をじっと抑えて、いかなる行動に出ずるのが、いちばん適当であるかを考えた。余りに不用意にこうした経験に出合したため、たださえ興奮しやすい忠直卿の感情は、収拾のつかぬほど混乱した。
忠直卿のそばに、さっきから置物のようにじっとして蹲(うずくま)っていた聰明な小姓は、さすがにこの危機を十分に知っていた。二人の男に、ここに彼らの主君がいることを教えねば、どんな大事が起るかも知れぬと思った。彼は、主君の凄まじい顔色を窺いながら、二、三度小さい咳をした。
小姓の小さい咳は、この場合はなはだ有効であった。右近と左太夫とは、付近に人がいるのを知ると、はっとしてその冒涜(ぼうとく)な口をつぐんだ。
二人はいい合わしたように、足早く大広間の方へと去ってしまった。
----------------------------------------------------
いや~名文ですね。
心情の表現が実に巧みです。
全体の文は忠直卿行状記に載っているので良かったら見てみて下さい。
引用文には載せてませんが、僕が読んでて「おお!」と思ったのは、
「七寸に近い鋒先から迸(ほとばし)る殺気が、一座の人々の心を冷たく圧した。
」
という一文。
『冷たく圧した』って、表現格好良すぎです!
さっそくお俺もこの表現使ってみようかな。
こんなのはどうだろう。
------------------------------------
【支店の忘年会の席にて】
みな、一瞬何が起こったか分からないようであった。
しかし悲しいかな支店内は、支店長を頂点とする完全なる縦社会であった。
上司は,部下の生殺与奪を一手に握る権力者である。
支店内では、支店長を頂点とし、副支店長、課長、係長、主任、平社員、みなピラミッド構造の構成要員なのだ。
「上の者の機嫌を損ねること」、それはすなわち出世競争からの脱落を意味していた。
「布団が、吹っ飛んだ~!」
宴もたけなわ、支店長が、どうだと言わんばかりに温めていたギャグを上機嫌で言い放った。
「えっ....」
支店長の放ったその会心のギャグは、一座の人々の心を『冷たく圧した』。
しかし、しーんと静まりかえったのは、ほんの0コンマ何秒かであった。
すぐに「あはははは!!」という笑い声に満座が包まれた。
「もう、支店長ったらおもしろ~い☆」
若い女性社員の甘い声も、非常に心地良い。
宴の席が笑いに包まれたのを見て、支店長は痛く御機嫌であった。
----------------------------------
なんか『冷たく圧した』の使い方間違った気がしますが(笑)
てなことでまた(^_^)v


















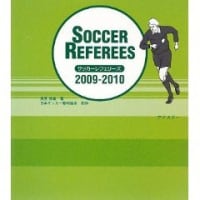

非常に勉強になる一冊ですよ
上杉鷹山、是非読んでみますね(^-^)