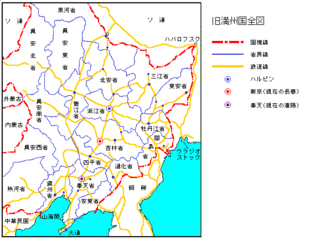敗戦からまもなく一年が過ぎようかというころ、やっと日本へ帰国の目処が立った。
祖国への船が出るというのである。
貨車に乗り、泰子は友人の千代乃や宿を借りていた堀夫妻ら多くの日本人とともに帰国の途に着いた。
泰子は堀夫妻の持つ大きな荷物を背負いふらふらになりながらも、広島に帰れる喜びでいっぱいだった。
日本への船は、アメリカ製の大きな貨物船である。
この船に乗る前、日本人の代表者が言った。
「日本に帰れば千円以上の金は没収され紙くずになります。
千円以上のお金を持っている人は、持っていない人に少しでも分けてあげてください。」
しかしこの期に及んでも堀婦人は
「人にやる金があるなら、日本海に捨ててやるわ!」
と叫び、周囲の人々をあぜんとさせるのであった。
千人ほどの乗客を乗せた貨物船は、大連近くのコロ島を出発し、一週間ほどで無事京都府の舞鶴に着いた。
そこからは国鉄の汽車を乗り継ぎ、郷土広島を目指すのみである。
「両親は、兄弟は果たして無事であろうか?」
はやる気持ちを抑え、ようやく夜中に泰子は広島駅に着いた。
そしてその日は広島駅で一夜を過ごした。
翌朝目覚めてみると、駅からの眺めはそれはひどいものであった。
原爆の被害を受けた広島は、被爆後一年経っても一面焼け野原のまま。
建物はぽつりぽつりとあるのみである。

「これはもう駄目かも知れない。」
泰子は路面電車に乗り広島駅から一つ西隣、3キロの位置にある横川駅へ降り立った。
泰子の生家は横川駅の北口から程近いところにある。
家に近づくと、近所のおばさんが泰子を見付け声をかけてきた。
「あら! やっちゃんじゃない! お母さんは生きとってよ。」
なんと母は生きていたのである。
泰子は高鳴る鼓動を抑えつつ、家路を急いだ。
家が近づくと、白い生家の蔵が見えた。
鉄筋作りのために、原爆に耐えたのだろう。
その横にバラックの粗末な建物も見えた。
「ただいいま~!」
「や、泰子!!」
台所に立っていたのは泰子の母であった。
「お母さん!!」
それは涙々の再会だった。
その朝は久しぶりの一家団欒となった。
母のアキ、兄早苗(さなえ)、弟稲造(いなぞう)、妹典子(ふみこ)がそろったのである。
泰子が聞くところによると、やはり原爆の被害は甚大なものであった。
泰子の父の与太郎は原爆が落とされた時、たまたま物陰だったので助かった。
外傷も無かったためにこのバラック小屋を建てたりして精力的に活動していたが、
放射能の影響で被爆から2ヶ月半後、原爆症により帰らぬ人となっていた。
泰子の兄もたまたま高等工業の物陰に隠れたため被爆を免れ、現在まで元気に生きている。
そして泰子の母は、被爆して顔の口から下に大やけどを負い、生死の境をさまよったのであった。
手に至っては蛙の水かきのようなかたちなっていたという。
一年の病床生活を経て、やっと台所に復帰した日が、まさにこの泰子帰宅の日であった。
やっと戻った家族団らんではあった。
しかし、シベリア抑留中の夫寛二の帰国までには、なお三年半もの歳月が必要だったのである。
おばあちゃんの満州記 完
祖国への船が出るというのである。
貨車に乗り、泰子は友人の千代乃や宿を借りていた堀夫妻ら多くの日本人とともに帰国の途に着いた。
泰子は堀夫妻の持つ大きな荷物を背負いふらふらになりながらも、広島に帰れる喜びでいっぱいだった。
日本への船は、アメリカ製の大きな貨物船である。
この船に乗る前、日本人の代表者が言った。
「日本に帰れば千円以上の金は没収され紙くずになります。
千円以上のお金を持っている人は、持っていない人に少しでも分けてあげてください。」
しかしこの期に及んでも堀婦人は
「人にやる金があるなら、日本海に捨ててやるわ!」
と叫び、周囲の人々をあぜんとさせるのであった。
千人ほどの乗客を乗せた貨物船は、大連近くのコロ島を出発し、一週間ほどで無事京都府の舞鶴に着いた。
そこからは国鉄の汽車を乗り継ぎ、郷土広島を目指すのみである。
「両親は、兄弟は果たして無事であろうか?」
はやる気持ちを抑え、ようやく夜中に泰子は広島駅に着いた。
そしてその日は広島駅で一夜を過ごした。
翌朝目覚めてみると、駅からの眺めはそれはひどいものであった。
原爆の被害を受けた広島は、被爆後一年経っても一面焼け野原のまま。
建物はぽつりぽつりとあるのみである。

「これはもう駄目かも知れない。」
泰子は路面電車に乗り広島駅から一つ西隣、3キロの位置にある横川駅へ降り立った。
泰子の生家は横川駅の北口から程近いところにある。
家に近づくと、近所のおばさんが泰子を見付け声をかけてきた。
「あら! やっちゃんじゃない! お母さんは生きとってよ。」
なんと母は生きていたのである。
泰子は高鳴る鼓動を抑えつつ、家路を急いだ。
家が近づくと、白い生家の蔵が見えた。
鉄筋作りのために、原爆に耐えたのだろう。
その横にバラックの粗末な建物も見えた。
「ただいいま~!」
「や、泰子!!」
台所に立っていたのは泰子の母であった。
「お母さん!!」
それは涙々の再会だった。
その朝は久しぶりの一家団欒となった。
母のアキ、兄早苗(さなえ)、弟稲造(いなぞう)、妹典子(ふみこ)がそろったのである。
泰子が聞くところによると、やはり原爆の被害は甚大なものであった。
泰子の父の与太郎は原爆が落とされた時、たまたま物陰だったので助かった。
外傷も無かったためにこのバラック小屋を建てたりして精力的に活動していたが、
放射能の影響で被爆から2ヶ月半後、原爆症により帰らぬ人となっていた。
泰子の兄もたまたま高等工業の物陰に隠れたため被爆を免れ、現在まで元気に生きている。
そして泰子の母は、被爆して顔の口から下に大やけどを負い、生死の境をさまよったのであった。
手に至っては蛙の水かきのようなかたちなっていたという。
一年の病床生活を経て、やっと台所に復帰した日が、まさにこの泰子帰宅の日であった。
やっと戻った家族団らんではあった。
しかし、シベリア抑留中の夫寛二の帰国までには、なお三年半もの歳月が必要だったのである。
おばあちゃんの満州記 完