
いささか古い話で恐縮だが、3月12日に汐留の浜離宮朝日ホールで行われたフランスのピアニスト、アンヌ・ケフェレック女史のリサイタルに赴いた。
その際の鑑賞メモを書き付けておくことにする。
プログラムは以下のとおり。
《前半》
モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第11番 イ長調 K.331『トルコ行進曲付き』
モーツァルト:幻想曲 ハ短調K.475
モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第14番 ハ短調 K.457
《後半》
ショパン:夜想曲第19番 ホ短調Op.72-1
ショパン:夜想曲第20番 嬰ハ短調(遺作)
ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調Op.66
ショパン:子守歌 変ニ長調Op.57
ショパン:舟歌 嬰へ長調Op.60
ショパン:バラード第4番 へ短調Op.52
《アンコール》
ヘンデル:メヌエット ト短調
J.S.バッハ:コラール変奏曲“主、イエス・キリストよ、我汝に呼ばわる”BWV639
前半にモーツァルトの好対照な聴き応えのあるソナタ2曲を含む3曲を、後半にはショパンの作品を連続して(途中で拍手を入れないよう要請して)演奏するという、かなり本格的と思わせるプログラムであった。
結論から言えば、バロック・古典を弾かせたら現代屈指の円熟の極みにあるピアニストの奏楽を心から堪能できてよかった・・・という感想に尽きる。
先にプログラムを“本格的”と評したのは、リサイタル全体を俯瞰して考え抜かれていることを思わせるから。
前半は、モーツァルトのイ長調の“トルコ行進曲つき”ソナタK.331という軽やかなイメージの変奏曲から始まる「明るい」曲を冒頭に置き、ブリッジでハ短調から彷徨うかのごとくいろんな調整を訪ね歩く文字通りの幻想曲を経て、同様にダークなイメージを持つハ短調のK.457のソナタへ移り行く・・・そんな構成。
モーツァルトの楽天的なところと、憂いを帯びた側面を著しく対比させるというコンセプトが見える。
しかし、これだけの規模の3曲をプログラムの前半分で消化するというのは、我が国のピアニストではあまりやらないことではなかろうか。
それを、オーディエンスに対し弛緩させずに聞きとおさせる集中力と力量はさすがと思わざるを得ない境地である。
女史によるモーツァルト演奏に関する感想はひとことでいってしまえば「どこまでもエレガント」とでも記しておけばよいのだろうか。
K.331は第一楽章の最後とトルコ行進曲の終盤だけ盛大に盛り上げたものの、他は敢えてセーブした音量で丁寧さを重視していた。
特に持続音の取扱には、慎重すぎるぐらいの神経を配っていたところが印象的。
変奏も性格をちゃんと強調し、装飾音の入りをわざと遅らせてみたり、走句をすばやく滑らせるように挿入してみたり・・・、テンポは揺らさないにもかかわらず決まった拍の中で自由にフレーズを伸縮させるワザは極めてフランス的エスプリのひとつの現れなのかもしれない。
多少やりすぎの感もなくはなかったが・・・。
音楽のつくりには非常に余裕があり、楽曲のテンションもことさらに感じさせないのに、常に耳をそばだてさせられてしまう・・・まさに聞かせ上手な演奏だった。
たとえばK.331第2楽章の冒頭など、多くの演奏家が鍵盤をぶったたいたような音でぶち壊してしまうところを、音量はそれほどでもないのにとてもイミシンに響かせることで、むしろ新鮮さを引き出している。
彼女のモーツァルトのリサイタルCDを持っているが、そこでもデュポールの主題による変奏曲という長調の曲から初めて、ダークな短調の曲を連ねるという手法を採っているので、こう聴かせたいという明確なコンセプトがあってそれを踏襲したものだといえましょう。
憶測だが、同様の曲目でリサイタルを進めたいとする女史の企画提案があったところに、主催者から「意図はわかるが“デュポール”のような1軍半の曲ではなく、バリバリの有名曲にしてください」的なオファーがあってのK.331演奏という筋書が想像されたりもする。
そんなことを無責任に考えるのも、かけがえのない楽しみなんだよな。
そして、K.457。
これは先のディスクにも収められていた曲であり、完全に手の内に入っていると知らしめられる奏楽だと感得できた。
ここでは衒うことのない毅然とした王道の演奏が聴かれたため、前半のK.331との対比はいやでも際立ったものとなって、畢竟女史の目論みは成功したといえるだろう。
「私は、こんなに歯切れのよい奏楽もできるのよ!」
ディスクでは端正な側面が記憶される女史の演奏だが、ここからは女史本来の主張が聴こえてきたといっておこう。
ライブならでは・・・なんだろうな。
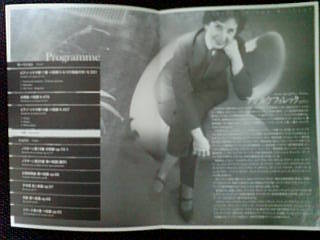
後半のショパン・・・
ポーランドの作曲家で言わずと知れた“ピアノの詩人”であるが、彼にせよ後年の活動の場はパリなので、彼もフランスで活躍した作曲家といえるのでこの後半はフランス特集と位置づけているのかもしれない。
女史にしてみれば、お国もののおいしいところを連作風に纏め上げる意図があるのだろう。
そして女史の演奏は、思いのほか曲の『表情』を意図的に“作りにいく”で驚いた。
プログラムは先に書いたとおり連続して演奏するよう構成され、先に作曲家の死後に遺作として出版された活動前期の3曲を並べ、子守歌以降は作曲家人生の晩年といっていい時期の泣く子も黙る名作を並べたもの。
若書きの3曲はいずれもマイナーの曲調で、後半はショパン独特の明るさを湛えた2曲とそれら全てを包含して昇華したようなバラード第4番という、ここでも対比と総合とを意識したプログラム構成。
誰が聴いても知っているうえに、飽きないで聴けちゃうというスグレモノプログラムだといえばそのとおりだろう。
果たしてその効果やいかに・・・?
ショパンであれば、私はその殆どの作品を知っている。
ここに並べられた曲は1軍レギュラー級の曲ばかりであり、私でなくとも多くの聴き手には自分勝手なそれぞれの曲のイメージができあがっているだろう曲ではあるまいか?
となれば、自分の感性とピアニストのそれがぴったり一致するなどと言うことは最初から望むべくも無いだろう。
というわけで、さまざまなピアニストを聴いて作り上げられた曲のイメージと、実演のそれの異同・乖離を風流として楽しむのが、ショパンのリサイタルを聴く場合の私の流儀となっている。
そんななか、女史の演奏は若書きの楽曲の演奏にはどんぴしゃではまるものだった。
夜想曲第20番“レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ”と呼ばれるこの曲のエレガンス、哀愁を実演でこれだけ胸に迫る演奏で聴かせられたのは初めてといってしまおう。
この曲で、ここまでフィーリングが会うとは思わなかったから。
そんな女史のショパン演奏におけるアプローチは、ここぞというところを除いて原則的にアタックの粒立ちを犠牲にしたタッチで、通奏低音のような音の絨毯・ウェーブを作り、そのうえで音型が推移するスタイルをとっている。
むしろ女史の手になる演奏であれば後期の作品の方が合っているのではないかと思われた後半半ば以降の楽曲、特に子守歌に関してはちょっと風流を通り越して疑問に思えるフレーズにも出くわしてこれまたサプライズ。
この曲は左手が同じ音型を繰り返すが、当初は厳格に守っていたテンポを途中でかなり自由に捉えるようになり、旋律線だけでなく普段は聞こえない内声部の音を浮き上がらせてみたりする。。。
その後、子守歌ってぐらいだから、子供をあやして揺らすかのように音の粒立ちをよくしてフレーズを揺らすこと揺らすこと・・・。
興に入りすぎちゃって、そこで暗譜が飛んじゃったのではないかと思われた瞬間を絶妙のブリッジを挿入して元に戻したところにはプロを感じたものの、やはりどうして走弾くのか疑問は残る。
ダイタンな、オモロイもん聴いた・・・って感じはあるのだが。
ちょっとね、女史のキャラではないような気がしてしかたない。
でもジンテーゼたる“バラード第4番”は極めて興味深い演奏となった。。。
ショパンは左手を指揮者と考えて絶対にテンポを揺らさないようにと言う指示を弟子達にしていたが、女史の演奏の特徴として、テンポの速いところではインテンポで通すのに、遅いところはかなり自由にとらえるという傾向がある。
もしかしたらショパン楽曲中で最高に私が愛してやまないこの楽曲の聴きどころは、冒頭からのロンド変奏が終結してからクライマックスに移る間のブリッジ部分・・・
である。
女史は、先の作法に則ってこのブリッジ部分を厳格なインテンポで極めて格調高く弾き上げてくれた。
これですよ! これ!
これが私の理想とする、この部分の弾き表し方・・・そういって過言ではない出来栄えだった。
そう言いたくなるような官能的なフレージングで、見事ショパン独特の世界を描ききってくれて感激もひとしお。
クライマックスが終わり、一瞬のブレスの後神秘的な5つの最弱音の和音が置かれるはずなのだが・・・
ここでも最初の和音の左手と右手をわざとずらしてみせるなど、耳が忙しい仕掛けを準備してグッと聴き手を前かがみにさせるなどニクイ演出・・・、そして、狂乱のコーダもインテンポでミスがないどころか味わい深く弾ききってプログラム全体の大団円を迎えるのであった。
そういえば幻想即興曲のラストの中間部旋律の回帰も、恐ろしいまでに印象深いメロディーの迫って来かたでゾクっとしたものである。
女史のロマン派の表現は、濃ゆ~いものだったのは意外に思えるなような、相応しくないように思えるような・・・
驚きでしたね。
でも、バラ4が素晴らしかったから、全部いいことにしてしまおう!(^^;)
アンコールはディスクにもなっている2曲。
音楽の母と音楽の父の憂いある楽曲でしたが、これらの曲を弾かせたら、当世ケフェレック女史の右に出る人はそうそういない。
これらには何も言うことはあろうはずがない。
そこには本当に美しい余韻が残って好ましかった。。。
それだけしかいえない。(^^;)
何度もカーテンコールに応えてくれた女史。
でも最後のバッハでオーディエンス全部が充足したのを確認し終わって、ひときわ丁寧にお辞儀をされて舞台袖に消えていった。
その姿に全ての聴衆が電気の付くのを待たずに拍手を収めて帰り支度を始めたことからも、演奏者と聴き手が通じ合ったリサイタルであったことが知れる。

写真は、終演後のサイン会で女史の新譜の『瞑想』と名づけられたバッハ作品集に貰ったサインである。
女史には「ありがとうございました。ラヴェルの全集を拝聴してからのファンです。」と伝えようと英単語を頭の中で組み立ててみたのだが・・・
並んでた人たちは音楽界演奏実務に造詣が深い人たちと見えて、女史にフランス語でぺらぺら話しかけているではないか・・・。
正直にいえば、英語でないことはわかるがフランス語であるかさえわからない言語なのだが・・・。
気後れしちゃったので結局「Thank you very much!」と言うのが精一杯であったのだ。。。
そんな私に、ケフェレック女史は深い笑みを湛え小声でひとこと・・・
「アリガト・・・」。
この言葉は私だけに向けられたもの。
このひとことだけで、私は心の底から充足感に浸ったものだ。
その際の鑑賞メモを書き付けておくことにする。
プログラムは以下のとおり。
《前半》
モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第11番 イ長調 K.331『トルコ行進曲付き』
モーツァルト:幻想曲 ハ短調K.475
モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第14番 ハ短調 K.457
《後半》
ショパン:夜想曲第19番 ホ短調Op.72-1
ショパン:夜想曲第20番 嬰ハ短調(遺作)
ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調Op.66
ショパン:子守歌 変ニ長調Op.57
ショパン:舟歌 嬰へ長調Op.60
ショパン:バラード第4番 へ短調Op.52
《アンコール》
ヘンデル:メヌエット ト短調
J.S.バッハ:コラール変奏曲“主、イエス・キリストよ、我汝に呼ばわる”BWV639
前半にモーツァルトの好対照な聴き応えのあるソナタ2曲を含む3曲を、後半にはショパンの作品を連続して(途中で拍手を入れないよう要請して)演奏するという、かなり本格的と思わせるプログラムであった。
結論から言えば、バロック・古典を弾かせたら現代屈指の円熟の極みにあるピアニストの奏楽を心から堪能できてよかった・・・という感想に尽きる。
先にプログラムを“本格的”と評したのは、リサイタル全体を俯瞰して考え抜かれていることを思わせるから。
前半は、モーツァルトのイ長調の“トルコ行進曲つき”ソナタK.331という軽やかなイメージの変奏曲から始まる「明るい」曲を冒頭に置き、ブリッジでハ短調から彷徨うかのごとくいろんな調整を訪ね歩く文字通りの幻想曲を経て、同様にダークなイメージを持つハ短調のK.457のソナタへ移り行く・・・そんな構成。
モーツァルトの楽天的なところと、憂いを帯びた側面を著しく対比させるというコンセプトが見える。
しかし、これだけの規模の3曲をプログラムの前半分で消化するというのは、我が国のピアニストではあまりやらないことではなかろうか。
それを、オーディエンスに対し弛緩させずに聞きとおさせる集中力と力量はさすがと思わざるを得ない境地である。
女史によるモーツァルト演奏に関する感想はひとことでいってしまえば「どこまでもエレガント」とでも記しておけばよいのだろうか。
K.331は第一楽章の最後とトルコ行進曲の終盤だけ盛大に盛り上げたものの、他は敢えてセーブした音量で丁寧さを重視していた。
特に持続音の取扱には、慎重すぎるぐらいの神経を配っていたところが印象的。
変奏も性格をちゃんと強調し、装飾音の入りをわざと遅らせてみたり、走句をすばやく滑らせるように挿入してみたり・・・、テンポは揺らさないにもかかわらず決まった拍の中で自由にフレーズを伸縮させるワザは極めてフランス的エスプリのひとつの現れなのかもしれない。
多少やりすぎの感もなくはなかったが・・・。
音楽のつくりには非常に余裕があり、楽曲のテンションもことさらに感じさせないのに、常に耳をそばだてさせられてしまう・・・まさに聞かせ上手な演奏だった。
たとえばK.331第2楽章の冒頭など、多くの演奏家が鍵盤をぶったたいたような音でぶち壊してしまうところを、音量はそれほどでもないのにとてもイミシンに響かせることで、むしろ新鮮さを引き出している。
彼女のモーツァルトのリサイタルCDを持っているが、そこでもデュポールの主題による変奏曲という長調の曲から初めて、ダークな短調の曲を連ねるという手法を採っているので、こう聴かせたいという明確なコンセプトがあってそれを踏襲したものだといえましょう。
憶測だが、同様の曲目でリサイタルを進めたいとする女史の企画提案があったところに、主催者から「意図はわかるが“デュポール”のような1軍半の曲ではなく、バリバリの有名曲にしてください」的なオファーがあってのK.331演奏という筋書が想像されたりもする。
そんなことを無責任に考えるのも、かけがえのない楽しみなんだよな。
そして、K.457。
これは先のディスクにも収められていた曲であり、完全に手の内に入っていると知らしめられる奏楽だと感得できた。
ここでは衒うことのない毅然とした王道の演奏が聴かれたため、前半のK.331との対比はいやでも際立ったものとなって、畢竟女史の目論みは成功したといえるだろう。
「私は、こんなに歯切れのよい奏楽もできるのよ!」
ディスクでは端正な側面が記憶される女史の演奏だが、ここからは女史本来の主張が聴こえてきたといっておこう。
ライブならでは・・・なんだろうな。
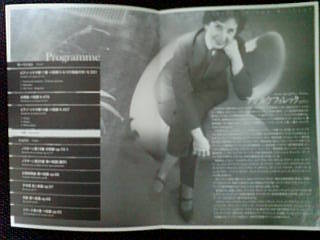
後半のショパン・・・
ポーランドの作曲家で言わずと知れた“ピアノの詩人”であるが、彼にせよ後年の活動の場はパリなので、彼もフランスで活躍した作曲家といえるのでこの後半はフランス特集と位置づけているのかもしれない。
女史にしてみれば、お国もののおいしいところを連作風に纏め上げる意図があるのだろう。
そして女史の演奏は、思いのほか曲の『表情』を意図的に“作りにいく”で驚いた。
プログラムは先に書いたとおり連続して演奏するよう構成され、先に作曲家の死後に遺作として出版された活動前期の3曲を並べ、子守歌以降は作曲家人生の晩年といっていい時期の泣く子も黙る名作を並べたもの。
若書きの3曲はいずれもマイナーの曲調で、後半はショパン独特の明るさを湛えた2曲とそれら全てを包含して昇華したようなバラード第4番という、ここでも対比と総合とを意識したプログラム構成。
誰が聴いても知っているうえに、飽きないで聴けちゃうというスグレモノプログラムだといえばそのとおりだろう。
果たしてその効果やいかに・・・?
ショパンであれば、私はその殆どの作品を知っている。
ここに並べられた曲は1軍レギュラー級の曲ばかりであり、私でなくとも多くの聴き手には自分勝手なそれぞれの曲のイメージができあがっているだろう曲ではあるまいか?
となれば、自分の感性とピアニストのそれがぴったり一致するなどと言うことは最初から望むべくも無いだろう。
というわけで、さまざまなピアニストを聴いて作り上げられた曲のイメージと、実演のそれの異同・乖離を風流として楽しむのが、ショパンのリサイタルを聴く場合の私の流儀となっている。
そんななか、女史の演奏は若書きの楽曲の演奏にはどんぴしゃではまるものだった。
夜想曲第20番“レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ”と呼ばれるこの曲のエレガンス、哀愁を実演でこれだけ胸に迫る演奏で聴かせられたのは初めてといってしまおう。
この曲で、ここまでフィーリングが会うとは思わなかったから。
そんな女史のショパン演奏におけるアプローチは、ここぞというところを除いて原則的にアタックの粒立ちを犠牲にしたタッチで、通奏低音のような音の絨毯・ウェーブを作り、そのうえで音型が推移するスタイルをとっている。
むしろ女史の手になる演奏であれば後期の作品の方が合っているのではないかと思われた後半半ば以降の楽曲、特に子守歌に関してはちょっと風流を通り越して疑問に思えるフレーズにも出くわしてこれまたサプライズ。
この曲は左手が同じ音型を繰り返すが、当初は厳格に守っていたテンポを途中でかなり自由に捉えるようになり、旋律線だけでなく普段は聞こえない内声部の音を浮き上がらせてみたりする。。。
その後、子守歌ってぐらいだから、子供をあやして揺らすかのように音の粒立ちをよくしてフレーズを揺らすこと揺らすこと・・・。
興に入りすぎちゃって、そこで暗譜が飛んじゃったのではないかと思われた瞬間を絶妙のブリッジを挿入して元に戻したところにはプロを感じたものの、やはりどうして走弾くのか疑問は残る。
ダイタンな、オモロイもん聴いた・・・って感じはあるのだが。
ちょっとね、女史のキャラではないような気がしてしかたない。
でもジンテーゼたる“バラード第4番”は極めて興味深い演奏となった。。。
ショパンは左手を指揮者と考えて絶対にテンポを揺らさないようにと言う指示を弟子達にしていたが、女史の演奏の特徴として、テンポの速いところではインテンポで通すのに、遅いところはかなり自由にとらえるという傾向がある。
もしかしたらショパン楽曲中で最高に私が愛してやまないこの楽曲の聴きどころは、冒頭からのロンド変奏が終結してからクライマックスに移る間のブリッジ部分・・・
である。
女史は、先の作法に則ってこのブリッジ部分を厳格なインテンポで極めて格調高く弾き上げてくれた。
これですよ! これ!
これが私の理想とする、この部分の弾き表し方・・・そういって過言ではない出来栄えだった。
そう言いたくなるような官能的なフレージングで、見事ショパン独特の世界を描ききってくれて感激もひとしお。
クライマックスが終わり、一瞬のブレスの後神秘的な5つの最弱音の和音が置かれるはずなのだが・・・
ここでも最初の和音の左手と右手をわざとずらしてみせるなど、耳が忙しい仕掛けを準備してグッと聴き手を前かがみにさせるなどニクイ演出・・・、そして、狂乱のコーダもインテンポでミスがないどころか味わい深く弾ききってプログラム全体の大団円を迎えるのであった。
そういえば幻想即興曲のラストの中間部旋律の回帰も、恐ろしいまでに印象深いメロディーの迫って来かたでゾクっとしたものである。
女史のロマン派の表現は、濃ゆ~いものだったのは意外に思えるなような、相応しくないように思えるような・・・
驚きでしたね。
でも、バラ4が素晴らしかったから、全部いいことにしてしまおう!(^^;)
アンコールはディスクにもなっている2曲。
音楽の母と音楽の父の憂いある楽曲でしたが、これらの曲を弾かせたら、当世ケフェレック女史の右に出る人はそうそういない。
これらには何も言うことはあろうはずがない。
そこには本当に美しい余韻が残って好ましかった。。。
それだけしかいえない。(^^;)
何度もカーテンコールに応えてくれた女史。
でも最後のバッハでオーディエンス全部が充足したのを確認し終わって、ひときわ丁寧にお辞儀をされて舞台袖に消えていった。
その姿に全ての聴衆が電気の付くのを待たずに拍手を収めて帰り支度を始めたことからも、演奏者と聴き手が通じ合ったリサイタルであったことが知れる。

写真は、終演後のサイン会で女史の新譜の『瞑想』と名づけられたバッハ作品集に貰ったサインである。
女史には「ありがとうございました。ラヴェルの全集を拝聴してからのファンです。」と伝えようと英単語を頭の中で組み立ててみたのだが・・・
並んでた人たちは音楽界演奏実務に造詣が深い人たちと見えて、女史にフランス語でぺらぺら話しかけているではないか・・・。
正直にいえば、英語でないことはわかるがフランス語であるかさえわからない言語なのだが・・・。
気後れしちゃったので結局「Thank you very much!」と言うのが精一杯であったのだ。。。
そんな私に、ケフェレック女史は深い笑みを湛え小声でひとこと・・・
「アリガト・・・」。
この言葉は私だけに向けられたもの。
このひとことだけで、私は心の底から充足感に浸ったものだ。











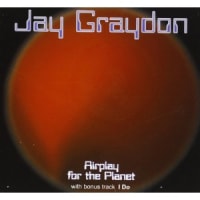
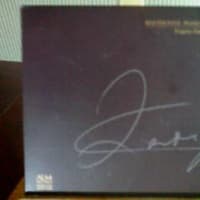
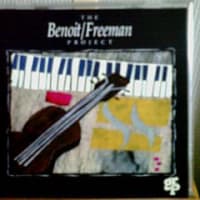
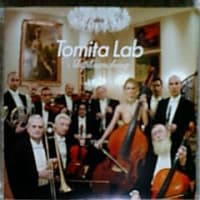
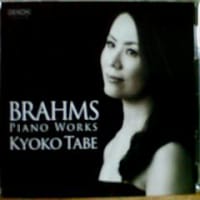

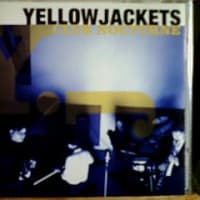


いささか肩に力が入ったというか、大仕事をしているんだという印象はなくもなかったのですが。
当日は、全般に・・・というより、随所にそのいい薫りを垣間見る・・・というコンディションだったかもしれません。
とはいえ一期一会の演奏という意味では、女史のそのときのすべてを投影した奏楽だと思ったので満足です。
似非アラウも本家アラウによるショパンのノクターンにはワン・アンド・オンリーの魅力を感じております。