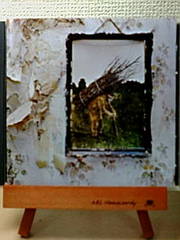★ショパンの旅路Ⅲ 「マヨルカの風」~マヨルカ島にて
(演奏:高橋 多佳子)
1.24の前奏曲 作品28
2.ノクターント短調 作品37-2
3.バラード第2番 ヘ長調 作品38
4.ポロネーズイ長調 作品40-1「軍隊」
5.4つのマズルカ 作品41
6.スケルツォ第3番 嬰ハ短調 作品39
(2001年録音)
(エクストン盤・直筆サイン入り(^^;))
クラシックギターの達人の先輩から調弦についてご教示いただいた。
当方とてアコースティックギター(フォークギター)とはいえ、手遊びに扱ってきた年季だけはそれなりに長い。
にもかかわらずそんなこともできんのか・・・とは思わないでほしい。
難しいんだから! (^^;)
そうはいいながら、力量に不相応な高級ギターを使用していると認識してはいるので、『モノ』にどうこう文句が言える筋合いではない・・・でも、やはり「チューニングが気持ちよく合っている」という感覚で演奏できないこともままある。
オカシイと思っても、その次弾いたときにはチャンとあってたりするものだから・・・という具合である。
今回、ほとんど実践していることを教えていただいたのだが次の2点には瞠目させられた。
曰く、開放のハーモニクスで調弦するときにあわせるほうのペグを回しながら調弦すべし。
その後、わずかにずれることを承知で和音を鳴らしてうまく響くように調整すべし。
これを心がけるようにとのご託宣であった。
そして積年の疑問に対しても回答をいただいた。
弦のコンディション、フレットやブリッジの温度や湿度等、そのときの環境によって必ずしもチューナーで完璧に合わせたとしても和音で響かせた時にヌケた気持ちよい音で鳴るか・・・というとそうでないらしい。
聞いてしまえば、こんなことで何十年もおかしいと思い続けていたのがむしろ可笑しい。(^^;)
早速、この稿を仕上げたら試してみたいと思っている。
★ショパンの旅路Ⅲ 「マヨルカの風」~マヨルカ島にて
(演奏:高橋 多佳子)

1.24の前奏曲 作品28
2.ノクターント短調 作品37-2
3.バラード第2番 ヘ長調 作品38
4.ポロネーズイ長調 作品40-1「軍隊」
5.4つのマズルカ 作品41
6.スケルツォ第3番 嬰ハ短調 作品39
(2001年録音)
(トライエム盤)
ところで、調弦の際に「両弦のハーモニクス音をペグを回しながら聞け」ということで思い当たったことがある。
ハーモニクスの音が近づくと音が共鳴してウヮンウヮンウヮンとうねる・・・さらに近づくとうねりがゆっくりになりワ~ンワ~ンという感じになる。
そして、うねりが消えたときにピタッとチューニングが合った状態になるわけである。
自分の越し方、どんな時間の使い方をしてどんな音楽をどのように嗜好してきたかという習慣やクセによって、自分の感性の弦の音程が、実は決まっているのではないだろうか?
そして、我々が新しい音楽や演奏を耳にするとき、この感性の弦いわば「心の弦」との共鳴の度合いで、自分の気に入る演奏かどうかが決まってくるのではないだろうか?
当然、自分の趣味とまったく違う楽曲、あるいは解釈・音色のものであるときには共鳴しないからピンと来ない・・・。
そして、実は味わい深いと思って楽しんでいるのはこの「うねり」の機微・加減なんじゃないだろうか?
自分の「心の弦」の共鳴する波長と、今そこで鳴っている音楽の波長・・・近いんだけどそのびみょ~な誤差から生じるうねりこそが、コクだの深みだのという感覚として感知されるのでは?
そしてそれがピタッと合ったとき・・・これこそが自分の理想とする解釈だと、何の違和感もなく受け入れられるときには、自分の心の中にある弦もそれこそ心置きなく共鳴して歌うんじゃないだろうか。
または歌っていることすら気づかないぐらい、居心地よく透明になれる・・・。(^^;)
ここで紹介した高橋多佳子さんの「ショパンの旅路」シリーズは、何度も書いているとおり私の心の弦にいつでもジャスト・チューンである。
もとより第Ⅴ集のバラード第4番以外は、当初少しずれていたところがあったかもしれない・・・でも、私のほうが心のペグをしらずしらず回したのか、今や完全に私の理想の演奏と一致していると思える。
この第Ⅲ集にせよバラード第2番、スケルツォ第3番のコーダなどでは、どんなに高名な方であっても他の演奏家からは絶対に聴けない多佳子さんの魅力が炸裂している。
それが体の中を音が何の抵抗もなく突き抜けていくような感じ・・・。(^^;)
寸分の違いもない同質な響きが私の心の中にあるからだと、ファンである私は一方的に信じている。
もとより研鑽を積んだ音楽家が渾身の力を込めて世に問う演奏は、どれも尊い。
やはり大家あるいは飛ぶ鳥を落とす勢いのアーティストによるそれは、普遍的に多くの人の「心の弦」を揺らすことができるのだろう。
でも「音ガク」のガクが「楽しみ」である以上、聴き手が一方的に好き、キライを判断することも許されてよいのでは・・・?
いかがなものだろうか?(^^;)
そして、エクストン盤とトライエム盤。
私にとって、雰囲気よくリラックスして聴けるのがトライエム盤であり、すこしチャレンジャブルになっているときに聴いてスカッとするのがエクストン盤である。
そんなことでも、心の弦の揺れ方は変わる。
もとよりオーディオもかじっている私は、プレーヤーも気分によって使い分けている。
楽しみは尽きない。(^^;)
(演奏:高橋 多佳子)
1.24の前奏曲 作品28
2.ノクターント短調 作品37-2
3.バラード第2番 ヘ長調 作品38
4.ポロネーズイ長調 作品40-1「軍隊」
5.4つのマズルカ 作品41
6.スケルツォ第3番 嬰ハ短調 作品39
(2001年録音)
(エクストン盤・直筆サイン入り(^^;))
クラシックギターの達人の先輩から調弦についてご教示いただいた。
当方とてアコースティックギター(フォークギター)とはいえ、手遊びに扱ってきた年季だけはそれなりに長い。
にもかかわらずそんなこともできんのか・・・とは思わないでほしい。
難しいんだから! (^^;)
そうはいいながら、力量に不相応な高級ギターを使用していると認識してはいるので、『モノ』にどうこう文句が言える筋合いではない・・・でも、やはり「チューニングが気持ちよく合っている」という感覚で演奏できないこともままある。
オカシイと思っても、その次弾いたときにはチャンとあってたりするものだから・・・という具合である。
今回、ほとんど実践していることを教えていただいたのだが次の2点には瞠目させられた。
曰く、開放のハーモニクスで調弦するときにあわせるほうのペグを回しながら調弦すべし。
その後、わずかにずれることを承知で和音を鳴らしてうまく響くように調整すべし。
これを心がけるようにとのご託宣であった。
そして積年の疑問に対しても回答をいただいた。
弦のコンディション、フレットやブリッジの温度や湿度等、そのときの環境によって必ずしもチューナーで完璧に合わせたとしても和音で響かせた時にヌケた気持ちよい音で鳴るか・・・というとそうでないらしい。
聞いてしまえば、こんなことで何十年もおかしいと思い続けていたのがむしろ可笑しい。(^^;)
早速、この稿を仕上げたら試してみたいと思っている。
★ショパンの旅路Ⅲ 「マヨルカの風」~マヨルカ島にて
(演奏:高橋 多佳子)

1.24の前奏曲 作品28
2.ノクターント短調 作品37-2
3.バラード第2番 ヘ長調 作品38
4.ポロネーズイ長調 作品40-1「軍隊」
5.4つのマズルカ 作品41
6.スケルツォ第3番 嬰ハ短調 作品39
(2001年録音)
(トライエム盤)
ところで、調弦の際に「両弦のハーモニクス音をペグを回しながら聞け」ということで思い当たったことがある。
ハーモニクスの音が近づくと音が共鳴してウヮンウヮンウヮンとうねる・・・さらに近づくとうねりがゆっくりになりワ~ンワ~ンという感じになる。
そして、うねりが消えたときにピタッとチューニングが合った状態になるわけである。
自分の越し方、どんな時間の使い方をしてどんな音楽をどのように嗜好してきたかという習慣やクセによって、自分の感性の弦の音程が、実は決まっているのではないだろうか?
そして、我々が新しい音楽や演奏を耳にするとき、この感性の弦いわば「心の弦」との共鳴の度合いで、自分の気に入る演奏かどうかが決まってくるのではないだろうか?
当然、自分の趣味とまったく違う楽曲、あるいは解釈・音色のものであるときには共鳴しないからピンと来ない・・・。
そして、実は味わい深いと思って楽しんでいるのはこの「うねり」の機微・加減なんじゃないだろうか?
自分の「心の弦」の共鳴する波長と、今そこで鳴っている音楽の波長・・・近いんだけどそのびみょ~な誤差から生じるうねりこそが、コクだの深みだのという感覚として感知されるのでは?
そしてそれがピタッと合ったとき・・・これこそが自分の理想とする解釈だと、何の違和感もなく受け入れられるときには、自分の心の中にある弦もそれこそ心置きなく共鳴して歌うんじゃないだろうか。
または歌っていることすら気づかないぐらい、居心地よく透明になれる・・・。(^^;)
ここで紹介した高橋多佳子さんの「ショパンの旅路」シリーズは、何度も書いているとおり私の心の弦にいつでもジャスト・チューンである。
もとより第Ⅴ集のバラード第4番以外は、当初少しずれていたところがあったかもしれない・・・でも、私のほうが心のペグをしらずしらず回したのか、今や完全に私の理想の演奏と一致していると思える。
この第Ⅲ集にせよバラード第2番、スケルツォ第3番のコーダなどでは、どんなに高名な方であっても他の演奏家からは絶対に聴けない多佳子さんの魅力が炸裂している。
それが体の中を音が何の抵抗もなく突き抜けていくような感じ・・・。(^^;)
寸分の違いもない同質な響きが私の心の中にあるからだと、ファンである私は一方的に信じている。
もとより研鑽を積んだ音楽家が渾身の力を込めて世に問う演奏は、どれも尊い。
やはり大家あるいは飛ぶ鳥を落とす勢いのアーティストによるそれは、普遍的に多くの人の「心の弦」を揺らすことができるのだろう。
でも「音ガク」のガクが「楽しみ」である以上、聴き手が一方的に好き、キライを判断することも許されてよいのでは・・・?
いかがなものだろうか?(^^;)
そして、エクストン盤とトライエム盤。
私にとって、雰囲気よくリラックスして聴けるのがトライエム盤であり、すこしチャレンジャブルになっているときに聴いてスカッとするのがエクストン盤である。
そんなことでも、心の弦の揺れ方は変わる。
もとよりオーディオもかじっている私は、プレーヤーも気分によって使い分けている。
楽しみは尽きない。(^^;)