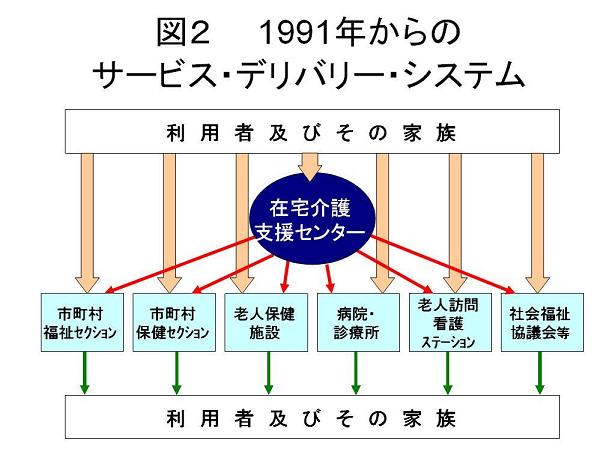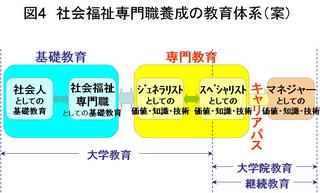「出し惜しみはしない」は橋田壽賀子さんが連載ドラマを脚本するときの信条であるということを、内館牧子さんが彼女から教えてもらったとある雑誌のエッセイで書いていた。内館さんが初めてNHKの朝の連続テレビ「ひらり」で脚本を書くことが決まった時の、橋田さんのアドバイスであった。
私は橋田壽賀子の作品が大好きで、「おしん」は私が家族と一緒にアメリカに留学していた20数年前に放映されたものであるが、日本からビデオを送ってもらって、日曜日にまとめてみることを日課としていた。特に、この時少女期の「おしん」を演じていた小林綾子と娘(当時小学校2年生)がよく似ていたため、涙して鑑賞した記憶がよみがえる。今でも、テレビ番組の「渡る世間は鬼ばかり」は、単純ではあるが、心休まるためによく観ている。
この橋田さんの「出し惜しみはするな」という教訓は、すべての人生に当てはまるような気がする。仕事に全力を注入せよとのことであろう。確かに、そうだと納得するのであるが、そこには継続して全力を注入できるエネルギーが大事であろう。ただ、このエネルギーをもっているのが橋田さんの強さであろう。一方、その時点で全力を出し切ると、次に新たなアイデアが出てこないのではないかという不安になる。これには、さらに良いアイデアが出せる自信が橋田さんにはあってのことであろう。
今後の原稿作成については、「出し惜しまず」を信条にしたい。そうすれば、少しはまとまりが悪いかもしれないが、魅力的な論文になるような気がする。また、現在(社)日本社会福祉士養成校協会会長として、その日その日を全力で走り切ることに努めたいと思う。ブログについても、時々書き惜しむことがあり、今後のために、これは残しておこうとすることもあったが、今後は「出し惜しない」ことにしたい。乞うご期待下さい。
なお、内館さんのエッセイでは、伊東に向かう「踊り子号」で、50代の男が嗚咽しており、妻を最近亡くし、涙声で「旅行とか人気のレストランとか温泉とか、行きたがっていたのに、俺は『定年後はいつでも行ける』とか言って、仕事や自分のことを優先してーー」の後悔話が続いている。妻にも出し惜しみはできないと自覚した。
皆さんも、出し惜しみをしない人生を送って下さい。そうすれば、後悔のない人生を送れるように思えます。(内館牧子「「踊り子号」の男」『トランヴェール』11月号、2008年)
私は橋田壽賀子の作品が大好きで、「おしん」は私が家族と一緒にアメリカに留学していた20数年前に放映されたものであるが、日本からビデオを送ってもらって、日曜日にまとめてみることを日課としていた。特に、この時少女期の「おしん」を演じていた小林綾子と娘(当時小学校2年生)がよく似ていたため、涙して鑑賞した記憶がよみがえる。今でも、テレビ番組の「渡る世間は鬼ばかり」は、単純ではあるが、心休まるためによく観ている。
この橋田さんの「出し惜しみはするな」という教訓は、すべての人生に当てはまるような気がする。仕事に全力を注入せよとのことであろう。確かに、そうだと納得するのであるが、そこには継続して全力を注入できるエネルギーが大事であろう。ただ、このエネルギーをもっているのが橋田さんの強さであろう。一方、その時点で全力を出し切ると、次に新たなアイデアが出てこないのではないかという不安になる。これには、さらに良いアイデアが出せる自信が橋田さんにはあってのことであろう。
今後の原稿作成については、「出し惜しまず」を信条にしたい。そうすれば、少しはまとまりが悪いかもしれないが、魅力的な論文になるような気がする。また、現在(社)日本社会福祉士養成校協会会長として、その日その日を全力で走り切ることに努めたいと思う。ブログについても、時々書き惜しむことがあり、今後のために、これは残しておこうとすることもあったが、今後は「出し惜しない」ことにしたい。乞うご期待下さい。
なお、内館さんのエッセイでは、伊東に向かう「踊り子号」で、50代の男が嗚咽しており、妻を最近亡くし、涙声で「旅行とか人気のレストランとか温泉とか、行きたがっていたのに、俺は『定年後はいつでも行ける』とか言って、仕事や自分のことを優先してーー」の後悔話が続いている。妻にも出し惜しみはできないと自覚した。
皆さんも、出し惜しみをしない人生を送って下さい。そうすれば、後悔のない人生を送れるように思えます。(内館牧子「「踊り子号」の男」『トランヴェール』11月号、2008年)