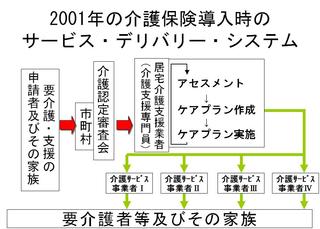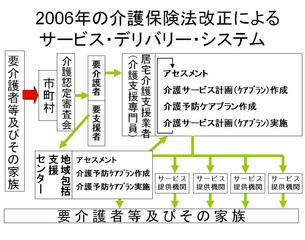我々研究者の世界では、自分が新しく書いた著書を多くの知っている方々に送ることが習わしである。これを献本というが、本を読んでいただいて、意見や評価を頂くためのものである。
そのため、『福祉のアゴラ』や『ストレングスモデルのケアマネジメント』も多くの皆さんに献本させていただいた。特に、『福祉のアゴラ』は出版社との約束で、印税をお金でなく著書ですべて頂くことになっていたため、本当に多くの皆さんにお送りさせていただいた。
そこで、唖然とすることが起こった。献本は、本屋に並ぶ前に送ることになるが、一方、販売が始まる直前からアマゾンでは予約を取ることになっている。私は、ブログに貼り付けるため、アマゾンでの『福祉のアゴラ』を開くと、なんと中古品が1冊販売に出されていた。
これは、未だ一般に販売される前での中古品であるから、私が献本した中の誰かが、読んでか、読まずか分からないが、アマゾンに、献本が自宅に届くか届かない時期に、中古品として出したということになる。当たり前のことであるが、そこには、汚れの程度が「新品同様」と書かれていた。
これはショックを超えて、素早い動きをした被献本者に拍手を送りたくなった。ただ、それほど魅力がない本なのかと少し悲しくなった。
随分以前に、岡村重夫先生が亡くなられ、私が『福祉新聞』に追悼文を書かせて頂いた時に、朝日新聞であれば天声人語の欄に相当する「三念帖」というコーナーがあるが、ここに書かれていた内容が今も忘れられない。これは、当然この福祉新聞の記者が書かれたものであろう。
大学を卒業し、就職のため東京に出てくる時に、ボストンバックの中に、今まで何度も読んだ一冊の本を入れてきた。それが、岡村重夫の『社会福祉学原論』であったという。この本があれば、私が困った時に、助けてくれるであろうと思ったというような内容であったことを覚えている。
ちょうど、岡村先生が亡くなられた時であり、素晴らしい文章を書いていただいたと感激した。そして、私もいつか、学生の方々が就職のため家を出て行く時に是非持っていきたいと思ってもらえるような一冊の本を、いつかは書きたいと思った。これはまだまだ実現するものではないが、まずは献本して直ぐに中古に出されることのないよう、魅力にある著書を書いていきたい。
そのため、『福祉のアゴラ』や『ストレングスモデルのケアマネジメント』も多くの皆さんに献本させていただいた。特に、『福祉のアゴラ』は出版社との約束で、印税をお金でなく著書ですべて頂くことになっていたため、本当に多くの皆さんにお送りさせていただいた。
そこで、唖然とすることが起こった。献本は、本屋に並ぶ前に送ることになるが、一方、販売が始まる直前からアマゾンでは予約を取ることになっている。私は、ブログに貼り付けるため、アマゾンでの『福祉のアゴラ』を開くと、なんと中古品が1冊販売に出されていた。
これは、未だ一般に販売される前での中古品であるから、私が献本した中の誰かが、読んでか、読まずか分からないが、アマゾンに、献本が自宅に届くか届かない時期に、中古品として出したということになる。当たり前のことであるが、そこには、汚れの程度が「新品同様」と書かれていた。
これはショックを超えて、素早い動きをした被献本者に拍手を送りたくなった。ただ、それほど魅力がない本なのかと少し悲しくなった。
随分以前に、岡村重夫先生が亡くなられ、私が『福祉新聞』に追悼文を書かせて頂いた時に、朝日新聞であれば天声人語の欄に相当する「三念帖」というコーナーがあるが、ここに書かれていた内容が今も忘れられない。これは、当然この福祉新聞の記者が書かれたものであろう。
大学を卒業し、就職のため東京に出てくる時に、ボストンバックの中に、今まで何度も読んだ一冊の本を入れてきた。それが、岡村重夫の『社会福祉学原論』であったという。この本があれば、私が困った時に、助けてくれるであろうと思ったというような内容であったことを覚えている。
ちょうど、岡村先生が亡くなられた時であり、素晴らしい文章を書いていただいたと感激した。そして、私もいつか、学生の方々が就職のため家を出て行く時に是非持っていきたいと思ってもらえるような一冊の本を、いつかは書きたいと思った。これはまだまだ実現するものではないが、まずは献本して直ぐに中古に出されることのないよう、魅力にある著書を書いていきたい。