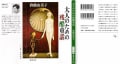「最後に、絵を語る。」(辻惟雄、集英社)の第4講「私の好きな絵」の後半部分(東山魁夷の評価部分)と、第5講「辻惟雄×山下裕二 師弟対談」を読み終えた。
私はどうしても東山魁夷の作品になじめないできた。現在も変わらない。この第4講は辻惟雄の評価を読んで、今後に鑑賞の一助にしたいものである。
「実景を丹念に観察しながら、それをまた別のものに変換する画家のマジックというものを痛感させられました。」(第4講)
「ナイーブさというものが共通してあります。ナイーブさと同時に写実の力を持っておられるんだけれども、たいてい写実性はあまり出さないで、後ろへしまっておくような感じです。」(第4講)
「天候なら薄曇り、光の柔らかい時間帯、あるいは薄暗い夕方などが多いですね。東山魁夷の描く風景は、寒いとまではいかないけれど、ちょっとひんやりするようなところがあります。私は奇想ばかりではなく、そういう表現にもやはり心惹かれるんです。」(第4講)
「山下:昨今は、日本美術というと『奇想の系譜』で先生が紹介された画家たちをはじめとする、「奇想」のほうに人気が偏っています。しかしやまと絵や狩野派といった「正統派」という本筋の存在があって「奇想」もあるわけだから、正統派について辻先生の味方をしりたい‥。」
「辻:『奇想の系譜』のあとがきに、‥奇想のほうが日本美術の主流なんじゃないか、。その言い方は「奇想」の価値を強調するために気負い過ぎた面があるにしても、この本は、それをまたもとへ戻そうとしているんです。」
「山下:正統派と奇想派の両方あるのが、日本美術のおもしろさなんだと思います。」
「辻:正統派と奇想派は対立しているわけではないんです。『奇想の系譜』のあとがきでも、奇想については「〈主流〉の中での前衛」という表現をしてました。」(以上第5講)
第5講については私が書くのはあまりに烏滸がましいのだが、次の視点を私から付け加えてみたい。
集団や師系の中に正統派、奇想派という人格を一人の人間に当てはめるのではなく、一人の画家の内面で「正統」への志向と、「奇想」への志向の両方の存在すること。あるいは一人の画家の内部での葛藤というものを見る、見つけるという視点を持ちたいと、感じた。