@「鎖国」時代でも幕府は世界情勢を把握しており、優秀な人材は諸外国の政局・変動などから日本における政治・貿易経済・防衛軍学・人材育成などに注力、諸外国との人材交流を模索していたことが分かる。だが、幕閣の官僚等が体制変化をこだわり(先送り)していたことが諸般の攘夷活動を活性化させてしまったことだ。 現代の政局と同じ、課題を先送りすることで難をとりあえず回避することがマンネリ化している。 日本独特の政治決断は「先送り」が常用化しているのは残念で、その結果全てが「時代遅れに」繋がっていることを知るべきだ。
『鎖国緩やかな情報革命』市村裕一
「鎖国によって日本の文明化は遅れた」ことが定説となっているが、事実か。幕府は海外の情報を独占・管理し、それを的確に解析できるシステムを作った。江戸期の情報管理を再評価する。
・幕府の体制は2つの柱 (連邦国家体制)
参勤交代制 (軍事権)1616年1年交代で江戸に出府義務
例:毛利(周防・長門)32万石 550人約1ヶ月の旅
鎖国体制 (外交権) 大名等の非武装化
長崎ーオランダ等への貿易のみ 銅の輸出(諸外国の軍備需要拡大)
・鎖国令(1633年)
オランダの宣教師からのヨーロッパ情報受信
オランダ商館から中国アジア情報を入手「和蘭風説書」(平均1ヶ月後の報告)
オランダ商館長の江戸参府1609年から170回
朝鮮通信使は1607年から12回(5百人規模の集団参府)
琉球ー薩摩藩を通じて1634年から18回(2百人規模の参府)
・諸外国が知った「日本の鎖国」はドイツ人エンゲルベルト・ケンペルの「廻国奇観」書物
・新井白石ーイタリヤ人宣教師ジョバン・シドッチ(西洋文化・哲学・宗教・神学・物理数学)
・カタカナの誕生は蘭学者杉田玄白らの「蘭学事始」
外国書物には画図(銅板画)も多く実物のリアリティーがあった
・ロシア情報
大黒屋光太夫(漂流してロシアに住む)の帰国によるロシアの詳細な情報
松前藩は暴利を貪り、ロシア情報を秘匿していた
最上徳内・間宮林蔵等の千島列島・樺太調査および日本国推奨
・将軍や幕閣が好んだ外国品
時計・望遠鏡・寒暖計・暗箱写真機・幻灯機・晴雨計・サングラス(観日玉)
ウニコウル(痘薬)・サフラン・ミイラ(健胃剤)
シーボルトの医学・地動説・エレキテル(平賀源内:現在逓信総合博物館所蔵)
・日本の危機感を書物で残した工藤平助・林子平「三国通覧図説」「海国兵談」
・本田利明の「経世秘策」「西域物語」は
煙硝(火薬)を利用して開墾するべき
金銀銅山の開発
海運船舶による産物交易の活性化
日本語の数十万語ある漢字を25文字のアルファベットを推奨
・渡辺崋山がオランダ商館から得た言葉「日本人は模倣ばかりで創造性に欠ける」
・佐賀藩高島秋帆によるオランダからの歩兵銃・大砲製造への執念
・幕末将軍家慶亡き後の水戸藩徳川斉昭ら参与らが決断できず、外交交渉はいつも先延ばしに
・蕃書調所による諸外国の情報発信・活版印刷技術による情報拡散(閣僚のみならず一般へ)
・幕府による留学生派遣
1862年の15名、オランダを皮切りに、その後150名が英仏露へ
諸藩の派遣(薩摩等)へと諸外国情報を入手する動き
幕府主導:フランス38.5%、オランダ24.5%、イギリス21.5%
諸藩主導:アメリカ43.5%、イギリス42.5%、フランス9%
明治政府:アメリカ38%、イギリス29.5%、ドイツ13.8%、フランス10%













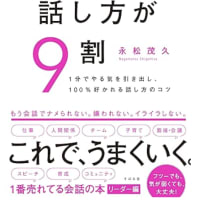
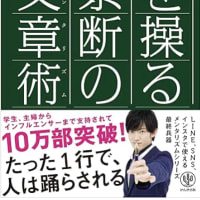
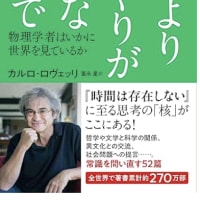


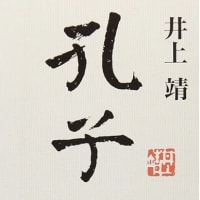

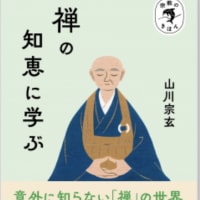
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます