@坐禅とは「考えない」心境にする「静」の修行、作務(生活のための働き)とは「動」の修行である、と言う。出家は仏門での全てが修行の積み重ねであり、甘え、褒められることは一切ない。仏法は師匠から弟子へ、心から心へ、以心伝心で伝えるものであり、仏門での「学び」は真似ることであり、一つ一つに無駄のない工夫を凝らして生活する事になる。考え方も変わる、例えば「1時間しか寝られない」から「1時間も寝られる」のように自分に厳しくしていくこととなる。一つ禅僧は肉を一切食べないのかと思ったが寺内では食べないが門外では食べるという。
修行者の1日:
午前3時半に起床、洗面、トイレを済ませて袈裟に着替え本堂に5分~10分以内
40~50分の朝課、梅肉の湯をのみ朝食(お粥)
禅堂に戻り坐禅、午前7時から作務(掃除・薪割り等)、托鉢に出かける
10時半過ぎに斎座(昼食)、休息(洗濯)、午後1時から作務開始、お経を読む
午後4時半から5時に作務、風呂、薬石(夕食)「基本的に食事は2食」、休息
午後4時半から7時まで坐禅、8時に茶礼、9時頃に開枕、夜座が深夜まで続く
・時と行動を告げるのは振鈴、大鐘、木板隣「時計はない」
『禅の知恵に学ぶ』山川宗玄
「概要」心が不安定になりやすい現代で、その教えを日常に取り入れやすいことから世界中で注目を浴びる「禅」。2500年の伝統をもつ仏教において、禅はどのように生まれ現在に至るのか。その歴史と思想の要点のみをコンパクトに概説。禅僧が目指す、豊かに生きることや幸せに生きることとは異なる「己事究明」の道とは何か。「坐禅」「読経」「作務」「食事」……その修行法を理解し、禅における人生の捉え方を体感する。「五分坐れば、五分の仏」「それと一つになる」「他の力で生かしていただく」……40 年以上もの修行を経た高僧が、体得した禅の知恵を実感を込めて語る
ー仏教の智慧<>知恵 心理を明らかにし、悟りを開く働き=生き方を悟る
「悟り」とは「本来無一物、いずれかのところにか塵埃あらん」
ー日本の禅宗の礎は栄西(臨済宗)方や曹洞宗の開祖は道元禅師(永平寺)
ー「禅」の精神を象徴する4つの言葉
不立文学・教外別伝・直指人心・見性成仏
法は師匠から弟子へ、心から心へ、以心伝心で伝えるもの
難しいお経を読めなくとも、厳しい修行を積まなくても瞬時に成仏する事は誰にでも平等
ー出家・修行
仏門修行に入る前に門前で約10日間の試練(門前払い・坐禅等を強いられる)
「褒める」は仏門の世界では通じない「すべてが厳しい作法と礼儀」
「窮すれば通ず」追い詰められ限界を越えることこそ修行となる
出家・修行する理由:世を捨て生きている事を実感する(体得すること)
修行は約1年で「人を変える」
百丈禅師「百丈清規」修行の手順や作法を定めた書物
「威儀即仏法」学びの教本では「学ぶ」を「真似る」こととある
考え方を変える「1時間しか寝られない」から「1時間も寝られる」
ー坐禅
「静」の修行:考えることをやめる「考えない」心境にする
ー作務(必要不可欠な修行)
「動」の修行:風呂を沸かし、稲和を植え、行事の準備をしたり
「行道」とは耳で聞いて、目で見て、口で唱えて、足を動かす
無駄を省くこと「1日作さざれば、1日食らわず」
「三昧」仏教では集中した精神状態
「精進料理」にはニンニクやラッキョなど精がつくものは食べれない
肉等は増堂では食べれないが門外では食べれる
増堂では「三黙堂」と言って食事中は音を立てない、喋らない
ーブッダの「八正道」正しく行う実践徳目
知見・思惟・言葉・行い・生活・努力・精神・精神統一
「そのままを受け入れる」(正しい生き方)













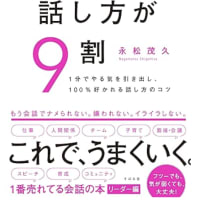
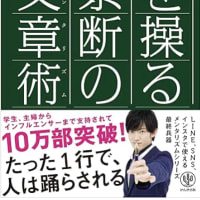
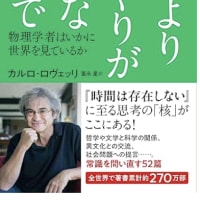


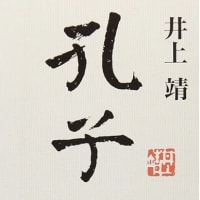

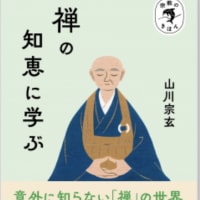
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます