@「古典」として著名な「論語」「中庸」取り上げ、人それぞれの環境において「解釈」することだ、と言う。「切磋琢磨」では教祖うる事ではなく、自分の在り方に合ったやり方で自分を磨くこと、であり、「温故知新」では古いものを大切にする事だけではなく、古いものを知ることで新たな視点・考え方を生むだすことだ、と言う新たな「解釈」をすることが「古典的魅力を引き出す」手法だと教えている。中でも「中庸の5つの理解」(博学:知の空白を一つ埋めていく、審問:詳細な問いを立てる、慎思:じっくり思考する、明弁:答えを分けていく、篤行:丁寧に行う)である現代的な解釈をしてみると、疑問を持ち、詳細を調べ、思考し、仮説を立て、実行してみる、と解釈できる。
『役に立つ古典』安田登
「概要」私たちは、あの名著を「誤読」していた。
『古事記』『論語』『おくのほそ道』『中庸』──代表的4古典に書かれている「本当のこと」とは? 私たちは何を知っていて何を知らないのか。古典の「要点」さえ理解できれば自分だけの生きる「道」が見えてくる。自分なりの価値観を見出していくために。古今東西の名著に精通する能楽師による、常識をくつがえす古典講義!
ー「学びの基本」古典からいかに学ぶか(転ばぬ先の杖よりも、転んだ後の絆創膏)
ー「論語」孔子 不安はこうすれば和らぐと言う処方箋を伝授「心のマニュアル」
「我十五にして学に志、三十にして立ち、四十にして迷わず、五十にして天明を知る。六十にして耳順雨、七十にして心の欲するところに従いて矩を踰えず」では「解釈」の仕方次第 「四十にして迷わず」は40にして区切らずと理解、それまで手を出さなかったことをあえてやってみる事を解釈する
・「切磋琢磨」(仲間と競い合って向上する)
手を加えて付加価値をつけること・人の在り方に合ったやり方で磨く
・「過てば則ちあらたむるに憚ること勿れ」
悪いところだけを観る
・「己に如かざるものを共とすること勿れ」
自分と共感ができる人を共とすべき
・「温故知新」(ぐつぐつ煮て知識等を温める)
煮詰め温かくすることで全く新しい視点や方法が突如浮かぶ
・「仁」人を超えた人
AI時代に求められる人材「超人」価値観の限界を超えた考えを持った人
ー「奥の細道」松尾芭蕉 俳句を作ると言う環境・旅に出る・リセット(亡霊に出会う能の旅)
芭蕉の旅「深川~北関東~東北~北陸~大垣」
体験は受け止め方次第(出来事をどう解釈するか)
・「夏草や兵どもが夢の跡」(義経主従と藤原氏の鎮魂)
・芭蕉の流儀 場所を変える・古典を知る・俳諧的に生きる
ー「中庸」(誠・誠実)
時代的には新撰組と二宮尊徳「誠」を大切にした人物
「常にピッタリ」な行動をとれる人、選択ができる人
「喜怒哀楽」の究極の感情を「中」(中和)と言う
自分を知り他人に尽くす













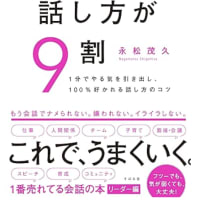
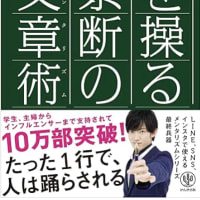
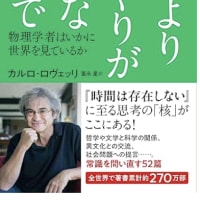


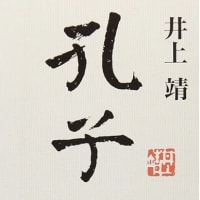

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます