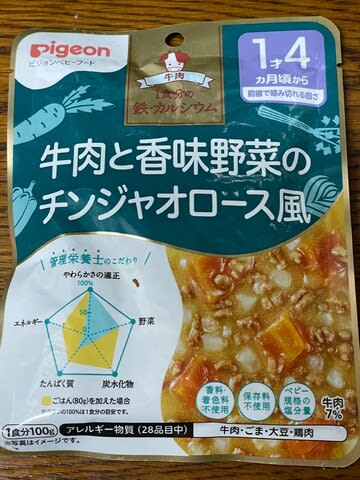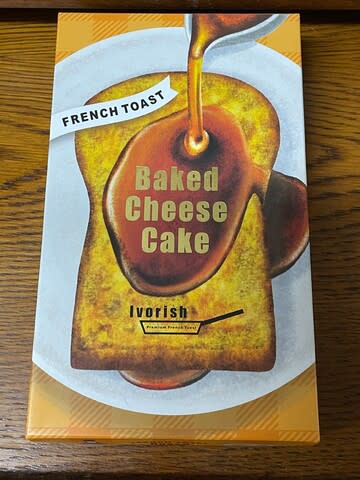「女房に惚れてお家繁盛?」
亭主が女房に惚れ込んでいると、外で浮気や道楽もせず家庭円満になるということ、という意味。
昭和31年(1956)春
寅子と優未が、星家へ。
新しい生活が始まります。
寅子、航一、朋一、のどかで、麻雀。
祖父の教えのようです。
優未と航一が仲良しの話を聞いて複雑な表情の朋一とのどか。
二人は、おそらく、航一に可愛がってもらった記憶がないのでは。
新潟時代は、航一、単身赴任でしたよね。
朝、早く起きて朝ご飯の支度をする百合。
手伝うのは、優未。のどかは、手伝う気もなく。
朋一は、ごはん、のどかは、パン。
そのときの気分で、ごはんかパンを選んでいる様子。
それが、当たり前のように行われてきたのでしょうね、星家。
不審がる寅子。
☆心に翼
何か言おうとする寅子に、優未は、「気になることがあるなら、仲良くなって、それから、聞いていけばいいんだよ。」
優未は、大人です。
なかなか進まない原爆裁判準備手続き。
職場の後輩・秋山真理子、新婚のようです。
姑について、「どんどん嫌いになります。」
嫁姑問題、秋山のように思っている人、大勢でしょう。
昭和31年女性裁判官は、寅子を含めて全国に12名。
今は、どれぐらいいるのでしょうね。
朋一が、百合に何も言わず、食べてきたと聞いて、寅子は、前もって百合に伝えるように苦言を呈します。
「母親づらするは、やめてください。」
本音でしょうね。家族のようなものであって、家族ではないという認識。
のどかは、もっとやっかいかも。父親がいてもいなくても良いとか。
子供を連れての再婚、簡単なものではないと思います。
詳しく描くと観ている方が、辛いかもしれません。
なんとか今週末には解決できるのか。航一が、子供たちに何も言わなかったところが気になります。
※次回への期待度○○○○○○○○(8点)
他のお菓子 いろはもみじ(藤井屋)
軸 涼風 筆:大徳寺派宗雲
お花 金みずひき 露草 宗旦むくげ
花入れ 竹
棗 形:平棗 蒔絵:雲錦 作:中村宗悦
茶杓 作:不見斎 銘:虫の声
茶箱 作:利斎
茶箱・卯の花点前を習いました。
源氏物語のことでしょう。
元々は、帝へ献上するため。
寛弘二(1005年)
脩子内親王の裳着が、行われました。
一条天皇の真の目的は、道長のけん制。
まひろは、帝へ献上する物語をきっかけに、書きたいものが、どんどん湧き上がってくる、私のために書きたい。
副題の誰がために書くは、自分自身のためになっていったのですね。
だからこそ、物語を書き続けられたのだと思います。
帝は道長に、陣定に、伊周をよぶように願います。
いまだに、定子への執着が強いのでしょう。
難しいが努力してみると答える道長。
差し上げた物語については、まだ読んでないらしいです。
そのことをまひろに伝える道長。
落胆しないまひろ。
一条天皇は、まひろが書いた物語を読んで、まひろに興味をもったようです。
会ってみたいと。その前に続きを読みたいと。
道長は、まひろに、「中宮様の女房にならぬか。」。
あまりに突然でびっくりしましたが。
帝が物語を読みたいと中宮の元を訪ねるのではないかという策略。
それは、良いことを考えたものだと納得です。
どういう経緯で、紫式部が、彰子の女房になるのか、とても興味がありました。家庭教師になったというのを読んだことがあるのですが。
真相は、わかりません。
まひろは、自分たちの生活のことを考え、藤壺にあがることを決めます。
気がかりなのは、賢子のこと。7歳とか言ってましたよね。まだまだ母が恋しいときだと思いますが、永遠の別れというわけでもなさそうです。
まひろは、藤壺で物語を書くために出仕。
その前に挨拶にいき、赤染衛門と話をします。
「人の運不運は、どうにもなりませんわね。」
赤染衛門という名前は、知っていましたが、倫子の女房だったのですね。
彰子のことを謎という表現をしていました。
まひろが、彰子については、赤染衛門から引き継ぐという格好になるのでしょうか。
道長の元に、安倍晴明、危篤の知らせ。
安倍晴明は、「あなた様の家からは、帝も皇后も関白も出られましょう。」「光が強ければ闇も濃くなります。」
安倍晴明の予言どおりになります。
何かもっている人だったのかもしれません。
自らの予言どおり、亡くなるのも、不思議な気がします。
道長は、今後、安倍晴明の代わりに誰を頼りにするのか。
一条天皇は、伊周を陣定によびだします。
その夜、皆既月食と火事が起きます。
一条天皇は、逃げない彰子の手をひいて、逃げます。
帝は、いい人なのでしょうが、定子のことを忘れるには、時間が必要なのでしょう。
まひろは、藤壺で働くため、家を出ます。
為時に、賢子のことを頼みます。
為時が、「おまえが、おなごであって良かった。」と言います。
今までは、まひろが男であったらと何度も言ってましたよね。
いよいよ、まひろ、藤壺へ。
ちょっと江戸時代の大奥を思い出しました。
女の園みたいで、怖いですね。
法服を着た面々の前で、寅子と航一が、申立人。
主文は、寅子と航一が、それぞれの姓で婚姻関係を結ぶことを認めるというもの。
理由は、姓を変えることによって、夫婦どちらかの社会生活での不利益や不都合をもたらす恐れがあるから。
事実婚を認めるという判断。今の社会に対する警鐘なのかもしれません。
個人的に、なぜ、選択的夫婦別性が認められないのか、わかりません。
全員が夫婦別姓だと反対ですが、選択的ですから。
姓を変えたい人は変え、変えたくない人は、変えなくてもよいと思います。
一方で、社会生活での不都合だけであれば、現在のように、戸籍上と違っても良いと認められているなら、問題ないのかもと思ったりしますが。
社会生活での不都合だけの理由でない場合もありますよね。
無事に結婚を祝う会終了。
明律大学同窓会?
五人娘がそろって、嬉しいです。しかも、先輩二人も加わって。
なぜか、轟もいるというのが、違和感です。轟をよぶなら、なぜ稲垣や小橋をよばなかったのかとか思います。
☆心に翼
崔香淑が、「あの頃のなりたい自分とは違うかもしれないけれど、でも、私たち、最後には、良い方に流れます。」
きっとそうだと思います。
人生、思うようにいかないことも多いけれど、最後は、良いようになると思いたいです。
次は、みんなで、海に行きましょうと寅子が提案。
実現できると良いですね。
この日、寅子たちは、のどがかれるまで笑って泣きました、みんな良かったね、おめでとうというナレ。
昭和31年(1956)春
寅子と優未は、猪爪家を出て、星家へ。
優未は、「航一さんは、お母さんと優未が大好きなんだもん。」と安心しているようですけど。世の中、そんなに甘くないと思います。
二人を待つ航一の子供たちの表情が暗い、暗すぎます。
※次週への期待度○○○○○○○○(8点)
航一は、「お互いが考えていることを想いのままに書いた遺言書を取り交わして、それを僕らの婚姻届とします。」「僕は、寅子さんの夫のようなものを名乗ります。」
斬新なアイデアです。
寅子が言うように、のようなものをつけない選択肢もあったと思うのですが。
星家でも、猪爪家でも、事実婚に対する抵抗がなかったことに違和感を覚えます。事実婚は、法律で守られない夫婦ということになるのではないでしょうか。法律を職とする者が、それで良いのかとも思います。
ドラマ上、二人は事実婚することになります。
史実は、違っているようですが、あえてこのような形にした意味が、よくわかりません。
寅子と優未は、優未が、中学生になるときに、星家に住むこととなるようです。
上手くいくのかな。花江同様、心配です。
昭和30年10月 原爆裁判の第2回準備手続き。
裁判って、時間がかかりますよね。
しかも、国を相手取っての裁判ですからね。
直明と玲美の結婚式が、無事に行われます。
結婚式の様子は、描かれませんでした。
竹もとにて。
直明に呼び出される寅子と航一。
☆心に翼
直明の最後の親孝行として、寅子の結婚を祝いたいと。
現れたのは、明律大学の面々。
サプライズです。皆が、直明の案に協力してくれたこと、なんて、良い仲間をもったのでしょう、寅子は。寅子の人徳なのでしょう。
※次回への期待度○○○○○○○○(8点)
前回の続き
航一の発言に大反対の百合。朋一とのどかは、容認。
寅子が、「いつ私が佐田姓になって欲しいと言いましたか?」
そうですよね。寅子は、航一にも名字を変えて欲しくはなかったはず。
☆心に翼
航一の結婚したい本当の理由は、「寅子さんの夫と名乗りたい。僕の妻ですと紹介したいのです。」「世界中の人に、この人が愛する人だと伝えることです。」
そこまで、言われたら、寅子が折れないわけには、いきませんよね。
寅子は、桂場に直談判。
「仕事の上で、佐田寅子と名乗ることはできないでしょうか。」
桂場は、即却下。理由は、寅子が、裁判官だから。
仕事上で旧姓を名乗ることは、私の記憶の中では、わりと昔から行われていることだと思っていました。
裁判官という職業は、特別なのですね。裁判官が、仕事の上で、旧姓が使えるようになるのは、平成29年からだそうです。ビックリ。
次の休み、轟から誘われ、ある会に、寅子は、優未と航一と一緒に参加します。ある会とは、同性愛の人たちの会というものなのでしょうか。
中には、性転換手術をしたという人もいましたが。当時、実際にいたものでしょうか。
航一はともかく、優未には、ショックが大きすぎないか心配になりました。
いずれにしても、性的マイノリティの人たちには、生きにくい世の中でしょう。それは、令和の時代の今でも、そうだと思います。
よねは、同性愛者ではなく、恋愛に興味がない中性的な人だったのですね。
そういう人も、たぶんいるのでしょう。
航一が寅子に、「僕たち結婚するのをやめましょう。」「婚姻届をだす結婚のことです。」
って、事実婚ということですか。
これにも、ビックリ。当時、事実婚という言葉はなかったと思いますが。
寅子と優未が、東京に戻ってきて、いろいろありすぎて混乱してます。
※次回への期待度○○○○○○○○(8点)