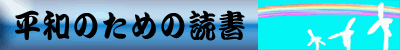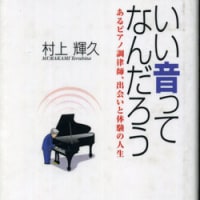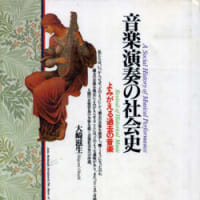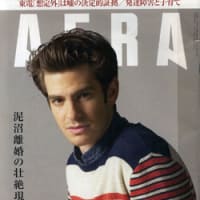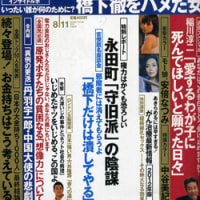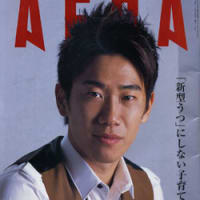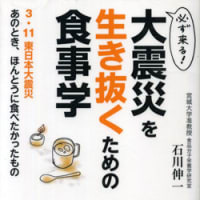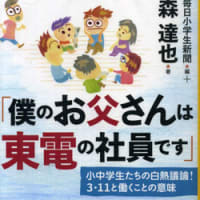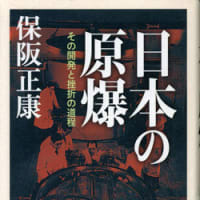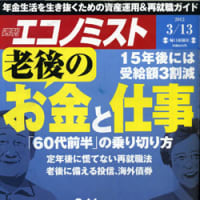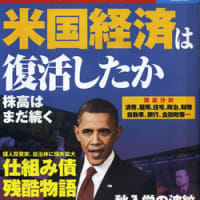『敗北を抱きしめて 上 第二次大戦後の日本人』
ジョン・ダワー(著)/三浦陽一、高杉忠明(訳)/
岩波書店2001年、2001年5刷
帯に書かれてあります。下「」引用。
「敗北の「奇蹟」
戦後の惨状の中を歩み始めた民衆は、「平和と民主主義」への希求を抱きしめて、上からの革命に力強く呼応した。」

表紙の裏に書かれてあります。下「」引用。
「一九四五年八月、焦土と化した日本に上陸した占領軍兵士がそこに見出したのは、驚くべきことに、敗者の卑屈や憎悪ではなく、平和な世界への希望に満ちた民衆の姿であった。勝者による上からの革命に、敗北を抱きしめながら民衆が力強く呼応したこの奇蹟的な「敗北の物語」を、米国最高の歴史家が描く。二○世紀の叙事詩。ビュリッツァー賞受賞。」
この本で、神の国でない日本とアメリカ人は読んだという。
この本はアメリカがベトナム戦争に敗戦した時に、敗戦の傷をいやすために、歓迎されたようです。下「」引用。
「天皇の兵隊たちは敗戦後、軽蔑をもって故郷に迎えられることが珍しくなかったが、ベトナム戦争に参加したアメリカの復員軍人たちがこのことを知れば、まちがいなく心をうたれるであろう。同様に、多くの日本人たちは自分自身の悲惨さに心を奪われたために、自分たちが他者に与えた苦痛を無視しがちであったが、このことは、あらゆる団体や民族が自分自身のために作りあげるアイデンティティが、いかに被害者意識によつて染め上げられるものであるかを理解するのに役立つ。」
アメリカ人は敗戦したとて、日本のように無惨ではなかったと思ったことでしょう。
「生きている英霊」と表現。下「」引用。
「元兵隊が帰郷してみると、はるか以前に自分は死んだことになっていて、葬式も終わり、墓標まで立っていたということは珍しくなかった。当時、こういう兵隊を冷笑して、「生きている英霊」と言った。」
1946年10月、大衆雑誌で、林芙美子「孤児や浮浪児の苦境に無関心な国が、文化的であろうはずがないと論じた。」という。
パンパンの話すアメリカ語を、「パングリッシュ」。
米軍にかかわる男たちのアメリカ語は、「スキャッパニーズSCAPanese」[「占領軍用ちゃんぽん英語」]。と書かれています。
この表現はあくまでも、差別用語です。
--あきれたものですね。
「長崎の鐘」のことが書かれてありました。下「」引用。
「日本の大胆な改革を望んでいた人々にとっては、永井の宗数的な運命論は、くだらないとはいわないまでも、とても受け入れるわけにはいかないものであった。しかし、永井が日本人の平和への願いを高めたことは、誰も否定できなかった。」
大胆な革命をすると、多くの人の血が流されます。
そんな手法をとらないで頂きたいと平和主義の方で書いておられた方もいました。
敗戦国

戦勝国

 Index
Index
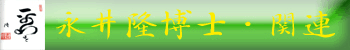 Index
Index
 目 次
目 次

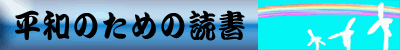

ジョン・ダワー(著)/三浦陽一、高杉忠明(訳)/
岩波書店2001年、2001年5刷
帯に書かれてあります。下「」引用。
「敗北の「奇蹟」
戦後の惨状の中を歩み始めた民衆は、「平和と民主主義」への希求を抱きしめて、上からの革命に力強く呼応した。」

表紙の裏に書かれてあります。下「」引用。
「一九四五年八月、焦土と化した日本に上陸した占領軍兵士がそこに見出したのは、驚くべきことに、敗者の卑屈や憎悪ではなく、平和な世界への希望に満ちた民衆の姿であった。勝者による上からの革命に、敗北を抱きしめながら民衆が力強く呼応したこの奇蹟的な「敗北の物語」を、米国最高の歴史家が描く。二○世紀の叙事詩。ビュリッツァー賞受賞。」
この本で、神の国でない日本とアメリカ人は読んだという。
この本はアメリカがベトナム戦争に敗戦した時に、敗戦の傷をいやすために、歓迎されたようです。下「」引用。
「天皇の兵隊たちは敗戦後、軽蔑をもって故郷に迎えられることが珍しくなかったが、ベトナム戦争に参加したアメリカの復員軍人たちがこのことを知れば、まちがいなく心をうたれるであろう。同様に、多くの日本人たちは自分自身の悲惨さに心を奪われたために、自分たちが他者に与えた苦痛を無視しがちであったが、このことは、あらゆる団体や民族が自分自身のために作りあげるアイデンティティが、いかに被害者意識によつて染め上げられるものであるかを理解するのに役立つ。」
アメリカ人は敗戦したとて、日本のように無惨ではなかったと思ったことでしょう。
「生きている英霊」と表現。下「」引用。
「元兵隊が帰郷してみると、はるか以前に自分は死んだことになっていて、葬式も終わり、墓標まで立っていたということは珍しくなかった。当時、こういう兵隊を冷笑して、「生きている英霊」と言った。」
1946年10月、大衆雑誌で、林芙美子「孤児や浮浪児の苦境に無関心な国が、文化的であろうはずがないと論じた。」という。
パンパンの話すアメリカ語を、「パングリッシュ」。
米軍にかかわる男たちのアメリカ語は、「スキャッパニーズSCAPanese」[「占領軍用ちゃんぽん英語」]。と書かれています。
この表現はあくまでも、差別用語です。
--あきれたものですね。
「長崎の鐘」のことが書かれてありました。下「」引用。
「日本の大胆な改革を望んでいた人々にとっては、永井の宗数的な運命論は、くだらないとはいわないまでも、とても受け入れるわけにはいかないものであった。しかし、永井が日本人の平和への願いを高めたことは、誰も否定できなかった。」
大胆な革命をすると、多くの人の血が流されます。
そんな手法をとらないで頂きたいと平和主義の方で書いておられた方もいました。


 Index
Index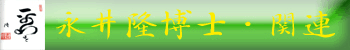 Index
Index 目 次
目 次