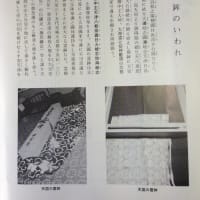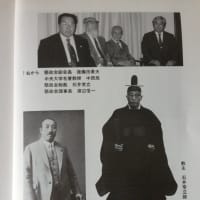物言い(ものいい)とは、大相撲において、行司が下した判定(軍配)に対し、勝負審判や控え力士が異議を唱えること。またそれから転じて、異議を申し立てること全般を「物言いをつける」ともいう。
対戦(取組)後の行司軍配に異議のある(ほとんどは、両者の体勢が微妙な状態での決着など)場合、勝負審判は、即座に手を挙げることによって意思表示をする。その後5人の勝負審判が土俵上で協議を行う。この際、ビデオ室と連絡を取り、ビデオ映像も参考にする。協議が合意に達すると、行司の下した判定の如何を問わず、改めて勝負の結果が審判長から発表される。
多くの場合は、体が落ちる、あるいは土俵を割る瞬間が同時(同体)として、勝敗の決定をせず、取り直し(再試合)となるか、そのまま行司軍配通りの結果となるが、稀に行司の軍配と逆の結果となる場合もあり、このケースは行司差し違え(もしくは行司軍配差し違え)という。なお、行司は必ずどちらかに軍配を上げねばならず、同体という判定は行司にとっては存在しない。また行司は禁じ手の有無を判断することは出来ない。
また、土俵下に控えている現役力士も、物言いをつけるための挙手をする事が出来る。審判委員は控え力士から物言いが出た場合、必ず土俵上で協議を行わなければならないが、その控え力士自身は協議に参加することは出来ない。なお、行司は取組の状況を述べる以外は協議に参加できない。
審判長から協議内容の説明の際、十両以上の取組の場合は四股名を用いて説明を行うが、幕下以下の場合は原則として四股名ではなく「東方力士」「西方力士」と呼ばれる事が有る。また「只今の協議は確認のための物言いでありまして、軍配どおり○○の勝ちといたします。」と説明する時もある。
アマチュア相撲においては「異議申し立て」という。控え力士に物言いの権利のないことや、大会にもよるが、ビデオ判定は用いられないことなどを除き、形態は大相撲とほぼ同じである。
この大相撲の「物言い」は複数の元一流選手が審判の判定をチェックするため、場外に控えているシステムはあまり他のスポーツには例の無いものである。
さて、有名な「行司、ひげの伊之助 涙の抗議」についてであるが、1958年9月場所初日、前頭7枚目北の洋-横綱栃錦の物言いで立行司の19代式守伊之助が土俵を叩いて自分の軍配の正当性を主張した。いわゆる「ヒゲの伊之助涙の抗議」である。
問題の箇所は北の洋の方が下になっていて頭からダイヴしている。また栃錦は上から突き落としているものの体は飛んでいる。この時伊之助は一旦北の洋に挙げかけた軍配を回し団扇で栃錦に挙げた。行司の心得のひとつに「負けを見て勝ちにあげる」という言葉があるそうだが、伊之助が必死に訴えている声も「先に体が落ちている」を繰り返している。物言いの際、行司は取組の状況を述べる以外は協議に参加出来ない。これは今も昔も変わらない。そして伊之助の抗議は、行司の本分をわきまえないという事で、出場停止処分となった(当初は9月場所中出場停止だったが、14日目から再出場した)
なお、この北の洋-栃錦戦の一件で、次の1958年11月場所より物言いに行司も検査役の協議に加わり発言できるようになった。