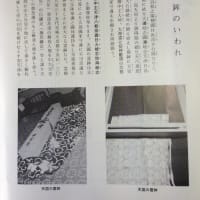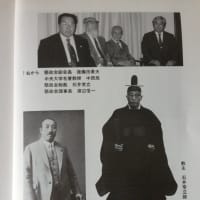◎永遠の別れ涙松
五月十六日には、門下生の岡部富太郎、福原又四郎、松浦松洞の三人が獄を訪れ、最後の別れに臨んだ。その時松陰は『人間として至誠がなければ真の人間ではない。孟子の言った〃至誠にして動かざるもの未だ、之有らず〃これが私の守礼である。どうか諸君もこの言葉を深く覚えておいてほしい』と言って別れを惜しんだ。
松陰は、倒れても倒れても起ち上がる不屈の闘志は、〃吾れは忠義を為すつもり、諸友は功業を為すつもり〃の心が深く信念として根ざしていたものと思われる。このことが、父の妹佐々木叔母や野村和作、品川弥二郎、妹たちにおくった詩からも、はっきりとくみとれる。
佐々木叔母には、『今更におどろくべくもあらぬなりかねて待ち来しこのたびの旅』とうたい、和作には『君のみは言はでも和らむわが心心のほどは筆もつくさじ』、又、弥二郎には『逢ふことは是れやかぎりの旅なるか世に限りなき恨なるらん』と詠み、妹たちへは『心あれや人の母たる人達よかからん事は武士の常』と、夫々詠んでいる。これらの詩によって、松陰の国を想う心情と温かい人柄がよくわかる。
父母とも別れ、塾生とも最後の惜別した松陰は、駕籠に乗って五月雨の降る中を萩を後にした。その時、詠んだ詩が有名な『涙松』の句である。
『帰らじと思ひさだめし旅なればひとしほぬるる涙松かな』
萩から山口に出る途中、鹿瀬ケ峠に向うところに涙松と言われた古い松の木立がある。ここを過ぎれば、もう萩は視界から遠ざかる。松陰はなつかしい故郷の萩の風情や肉親、塾生等の永久の別れに、はらはらと流れる涙に言葉もなかったのである。
筆者はなぜかこの松陰の江戸護送を考える時に菅原道真公の太宰府への流人の状況と重なってしまうのである。菅原道真公は、宇多、醍醐天皇からも信任厚く、五十六歳の時、右大臣兼右近衛大将に任ぜられ異例の昇進によって、藤原一門の嫉み烈しく、中でも藤原時平のざん言により、ついに太宰権帥に左遷のうき目となった。その時、道真公は庭の紅梅を見つめ、あの有名な『東風吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ』と詠み、妻子や民衆に送られながら京をあとにした。この時の道真公の心中と今の松陰の無念やるかたない心中は甲乙つけがたいものがあったろう。奇しくも、道真公も松陰もともに『学問の神様』として夫々の神社に祭祀されている。
◎江戸獄中での手記
松陰を乗せた駕籠の一行は、一ヶ月間かかって江戸に着き、幕府最高の裁判所たる評定所にて厳しい取り調べを受けた。幕府側は、安政の大獄によって、幕府に楯突いた水戸、土佐藩の他、佐久間象山、梅田雲浜、橋本左内、頼三樹三郎等の反幕府思想家に対して強烈な弾圧が施された。そのため奉行所では、松陰に対しても過激思想家として想像以上に重く罰せられた。しかし松陰は臆することなく國を思う至誠の前に堂々と自己の信念を貫いた。
松陰、三十歳の誕生日の八月四日に次のような詩を詠んでいる。
『國を許すの身敢へて親を顧はんや、安然獄に坐す亦吾が真。忽ち逢ふ父母苦労の日、復た被る西風の人を愁殺するを』
と、松陰は国に捧げた身とはいえ、故郷の父母をしのんだ詩である。既に松陰は、この頃死を覚悟したものと思われる。
松下村塾門下生の高杉晋作が江戸の獄に面会に訪ねた折、松陰は
『死は好むべきにも非ず。亦悪(にく)むべきにも非ず。道尽き心安ずる。便(すなわ)ち是死所。世に身生きて心死する者あり。身亡びて魂存する者あり。心死すれば生くるも益なし。魂存すれば亡ぶるも損なきなり。死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらばいつまでも生くべし。』
と、松陰は淡々と生死を超えた心中を語った。さながら宗教家の死を超越した〃悟り〃の境涯である。
心の定まった松陰は郷里萩の父兄へ最後の手紙を書いている。
『平生の学問浅薄にして至誠天地を感格すること出来申さず、非常の変に立到り申候。さぞさぞ御愁傷も遊ばさるべく拝察仕り候。
親思ふこころにまさる親ごころけふの音づれ何ときくらん
さりながら去年十月六日差上げ置き候書、得と御覧遊ばされ候はば、左まで御愁傷にも及び申さずと存じ奉り候。尚又当五月出立の節心事一々申上げ置き候事に付き、今更何も思ひ残し候事御座なく候。・・・幕府正議は丸に御取用ひ之れなく、夷狄は縦横自在に御府内を跋扈致し候へども、神国未だ地に堕ち申さず、上に、聖天子あり、下に忠魂義魄充々致し候へば、天下の事も余り御力御落し之なく候様願ひ奉り候。随分御気分御大切に遊ばれ、御長寿を御保ち成さるべく候。以上』
松陰が十月二十日に書いた手紙である。
子の自分が親より先に逝くということは、どれほど親に心労を与えるか。そのはり裂けるような胸中を松陰は、
『親思ふこころにまさる親ごころけふの音づれ何ときくらん』
の名文句を切々と詠んだのである。
現在、松陰神社の境内にその碑が建っている。
◎不滅の『留魂録』
松陰は十月二十五日から二十六日にかけて、あの有名な『留魂録』を書いた。松陰最後の訣別の記録である。
筆者はこの『留魂録』を松陰遺墨展示館で直接拝観した時、あまりの小さな帳面と字に驚いたほどである。これから推察しても、斬刑前夜、看囚人の目を盗みながら黄昏の頃、記録したものと思われる。『留魂録』の最初の出だしが、あの有名な
『身はたとひ武蔵野の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂』
の一首である。
この『留魂録』は門人達への遺書である。幕府取調べの模様、死に臨む心境、獄中同志の消息、門下生たちへの委託等書かれている。この原本は同囚沼崎吉五郎に托されたが沼崎は後三宅島へ流罪となり、明治九年頃、三宅島から帰るや、松陰門下の野村和作(当時神奈川県令)に手交した由緒あるものである。
とくにこの中で松陰は、肉体は武蔵野原に朽ち果てても、天皇国日本への燃ゆるわが胸の思いは、永久にとどめておきたい。自分はこうやって死の運命を静かに迎え得るのは、平生の学問の賜であると冷静沈着に筆を運んでいる。洵に堂々たる不動心である。そして『留魂録』の最後には、更に五首の歌を認めた。
『心なることの種々書き置きぬ思ひ残せることなかりけり』
『呼びだしの声まつ外に今の世に待つべき事のなかりかるかな』
『討たれたる吾れをあはれと見ん人は君を崇めて夷払へよ』
『愚かなる吾れをも友とめづとも友とめでよ人々』
『幾たびも生きかへりつつ夷をぞ攘はんこころ吾れ忘れめや』
この五首から拝察して、松陰はもう思い残すことなく、後は呼びだしを待つのみの淡々とした諦観の境地になっていたのではなかろうか。さしずめ仏典の『大無量壽経』の如来の〃使命は己に為せり〃の気持になっていたのではないかと思われるのである。
◎武蔵野の野辺に散る
安政六年十月二十七日遂にその日は来た。今上最後の日である。
松陰は評定所から最後の呼び出しに衣服を改めて伝馬町の獄を出た。出るにあたって、
『此の程に思い定めし出立はけふきくこそ嬉しかりける』
と、一首書き留めた。松陰は死刑の恐怖や生への未練はいささかもなく、むしろ新たなる出立の今日を待ち望むかのような透徹した境地である。さらにお世話になった看守人には丁重に別れの挨拶をし、獄の部屋もきれいに片付けた。ここが松陰の〃人となり〃の言行一致の誠の姿であり、偉大さである。
この松陰と同様、後の明治の軍人乃木希典もまた自決と斬刑との違いこそあれ、死を直前にしていささかも心乱すことなく見事に散った人である。この二人はともに親類にあたり、ともに尊皇崇拝であり、限りなく国を愛し、又教育者でもあり、至誠〃忠〃に生ききった人であった。
遺書となる『留魂録』といい、乃木希典の二首 (『神あかりましぬる大君のみあとはるかにをろかみまつる』 『うつし世を神さりましし大君のみあとしたひて我はゆくなり』) の辞世他遺書の筆跡は、ともに最初から最後まで心乱れることなく安静の筆致、光風霽月(こうふうせいげつ)、砥ぎ澄まされた日本刀のような清澄にして不動心が表れている筆運びである。
筆者は、松陰の『留魂録』を萩の松陰神社境内にある松陰遺墨展示館で、乃木希典の遺書は下関市の長府町にある乃木神社境内にある乃木展示館で夫々拝観したのであるが、ともに達人の境地に到る筆運びに唯々驚嘆したほどである。
さて松陰は、十月二十七日朝、幕府の評定所において松平、久貝、石谷の三奉行から死刑を宣告された。当初流罪の刑であったが、過激な尊皇思想家を嫌う井伊大老によって死刑となったとのことである。
刑場に引かれる時、松陰は声高らかに皇国の大精神を辞世の詩として朗誦した。ここが普通の武人や軍人と違うところである。例え殺されても、最後の最後まで天皇を仰慕し、国を愛してやまない松陰魂に驚くのである。
『吾今国の為に死す、死して君親に負かず。悠々たり、天地の事、鑑照、明神に在り』
と青天白日のように澄みきった心で、武蔵野の露と消えたのである。自分は今、国のために死するが、死んでも大君や親の心持にそむくものではない。悠々に続く天地の事、わが〃忠〃の心は神のみぞ知ることゆえ、死しても心に何も残ることはない。自分が滅した後の光輝く万乗の世界を期待してやまないという、松陰の赤き心が脈々と流れている空前絶後の尊皇愛国の名歌である。
とくに、ここで注目したいことは〃悠々たり、天地の事〃という言葉の意味である。この真義は、日本の国は天地の始まりとともに肇国以来万世一系の天子さまによる国柄によって悠久不滅であるとともに、わが心も日本国と同様、この場になってもいささか恐れることなく悠々たる境地であり、この精神は永遠不滅であるという深い深い掛け言葉であると拝察されるのである。
松陰のこの美しいまでも烈しい尊皇、愛国の精神は時代が移り変わろうとも、吾々日本民族は忘れることなく永遠に残していかなくてはならない道統精神の遺産である。そして、松陰はこの日潔く散っていったのである。
世の愛国者と呼ばれる人々よ。今こそ松陰精神の何分の一でも、わが心とし、ただひたすらに『天皇国日本』実現をめざして祈り且つ行動にうつることを希うのである。真の愛国者には名もいらぬ。地位もいらぬ。ただ天皇を仰慕してやまぬ愛国熱情の松陰精神と団結心が何よりも大切である。
世に愛国者と言われる人は多い。しかし残念なことに団結心が乏しいゆえに、力が分散し脆弱である。それは似非愛国者か、遺物的愛国者にすぎない。或いは、自己の主張にこだわるあまりに自己の領域を固守して同志を批評する識別的愛国者である。もう、そういう議論した時代は過ぎたのである。
真の愛国者は道義に生き広々とした心で大同団結できる包容精神をもち、至誠を貫き、炎のごとく燃え熱き血潮で祖国日本を守らんがために決起する勇者でなければならない。
現下の日本をみるときに、真の愛国者は今こそ神国日本復活をめざし、眠れる心に松陰魂を吹き込み、心を一つにして立上る秋(とき)が〃今〃来たのである。
<完>