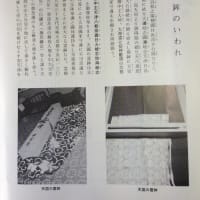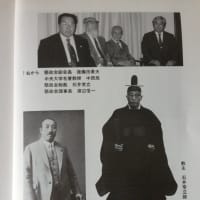禅語に「絶後甦生(ぜつごそせい)」という言葉があります。
禅学辞典によれば「大死一番して後、初めて真に生きること。
煩悩を絶断しつくしたところに、真実の生き方があること」だと出ていました。
絶後は、「空前絶後の事件」などと使われ、将来二度と起こらないことに用いられる語となっていますね。
でも元々は、息が絶えた後ということです。
夏目漱石は禅に詳しいお方でしたから、〈我が輩は猫である〉の中で「絶後に蘇る底の気魄がなければ駄目だ・・」と、本来の意味で用いております。
また再甦の甦は、更と生が合わさった字でソとも読み、蘇と同義です。
再甦の字義からしても、漱石の言う〈絶後に蘇る底の気魄〉は、禅語の絶後再甦を踏まえて表現した文だと言えるでしょう。
禅で言う絶後の再甦とはあくまで精神的なことで、「煩悩だらけの貴方は死にました。
そして本来の貴方として生まれ変わってきました。
そのようなつもりで、今後しっかりやりなさい!」ということだと思います。
ちなみに近年では、再甦とか再蘇という語はあまり使われず、再生とか更生という語に置き換えられて来ました。
また、再甦を置き換えた再生も、甦を二字にした更生も、蘇生と違う意味を表すことになりましたね。
一度死んだ者が、使い古しの体に甦っても、そんな体では、また死ぬしかないでしょう。
新しい体・新しい気魄に変わってこそ、再生した甲斐があろうというものです。
録音・録画されたものの再生のように、同じものの繰り返しは仏教的再生ではありません。
再生紙のように、新しく別のものになって生き返るのが本来の再生です。
私達の体の再生はともかく、心くらいは生前のうちに「絶後の再生」をして、向上の一路を辿ることに致しましょう。
「絶後甦生の事例」
自己を滅却すると言うことは、「私は私である」という自己意識を滅却すること。この大切な意識を停止しなくてはならない。それを」大死一番」と言っている。実際に、長い間不眠不休の座電をして意識を絶滅するのだから、禅修業は命がけでされなければならない。
そして何かの機縁、たとえば太陽に光り輝く椿の花とか、石が当たって響く竹の音とかによって、無意識が破られ、ふたたび意識が復活してなされる「絶後蘇生」という体験がある。そういう体験を「悟り」とか、「見性」とか言っている。