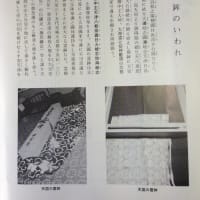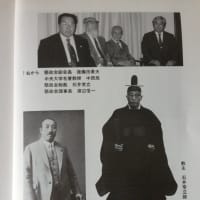◎政教分離と祭政一致とは、
「政教分離」の経緯についてである。昭和二十年(終戦)十二月十五日、連合国軍総司令部が日本政府に対し国家神道の禁止と政教分離の徹底を指示する覚書(神道指令)を出した。これは神道を一宗教と位置付け、他の宗教と同列においたものであり、明らかにわが国体の変更を意図したものであった。そしてこれに基ずいて作られたのが、現憲法(第二十条)信教の自由である。「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体からも国からの特権を受け又は政治上の権力を行使してはならない。何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」その意味では、この政教分離違反に最も当てはまる宗教団体は、「公明党創価学会」となる。創価学会は、明らかに現憲法違反であり、政府は即刻宗教法人の資格を剥奪すべきである。自公政権など論外である。何故政治家はこれを正さないのか。「喝―ッ!」
次に「祭政一致」についてであるが、谷口雅春先生は下記の如く説かれている。「祭政一致とは、建国の祖 神武天皇が『天津神、国を授け給ふ徳にこたへ・・・』と建国の詔勅に迎せられているのである。日本国においては、政治は神意が政権担当者に天降り、天意と人意とが真釣り合った(真に一致せる)政治であるのが本来の姿である。それ故に政事をマツリゴトというのである。これが祭政一致、大日本真理国家の本来の姿である。またわが国は、天皇を内なる生命体の中核としている国家である。そして国民はその生命体の細胞として天皇を仰慕し、この国体を護持して、その生成発展のために力をつくし精神をつくし生命をつくして仕えることが使命である。」
ここで重要なのは神道の位置づけである。神道とは何か!神道とは、神代から続くわが国体の根本理念である。この国体の根本理念を果たして一宗教と位置付け、他の宗教と同列におくことが出来るのか否か。現に今日もなお国家的な意味をもって斎行され連綿として続けられている伊勢神宮新嘗祭の勅使差遣や皇室祭祀の現実を如何にみればよいのか。日本人ならば問答無用で、「政教分離」と「祭政一致」との次元の違いが解るはずである。祭政一致の政治を回復することこそ、わが国が世界の範たる国家として歩むべく道である。
「政教分離」の経緯についてである。昭和二十年(終戦)十二月十五日、連合国軍総司令部が日本政府に対し国家神道の禁止と政教分離の徹底を指示する覚書(神道指令)を出した。これは神道を一宗教と位置付け、他の宗教と同列においたものであり、明らかにわが国体の変更を意図したものであった。そしてこれに基ずいて作られたのが、現憲法(第二十条)信教の自由である。「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体からも国からの特権を受け又は政治上の権力を行使してはならない。何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」その意味では、この政教分離違反に最も当てはまる宗教団体は、「公明党創価学会」となる。創価学会は、明らかに現憲法違反であり、政府は即刻宗教法人の資格を剥奪すべきである。自公政権など論外である。何故政治家はこれを正さないのか。「喝―ッ!」
次に「祭政一致」についてであるが、谷口雅春先生は下記の如く説かれている。「祭政一致とは、建国の祖 神武天皇が『天津神、国を授け給ふ徳にこたへ・・・』と建国の詔勅に迎せられているのである。日本国においては、政治は神意が政権担当者に天降り、天意と人意とが真釣り合った(真に一致せる)政治であるのが本来の姿である。それ故に政事をマツリゴトというのである。これが祭政一致、大日本真理国家の本来の姿である。またわが国は、天皇を内なる生命体の中核としている国家である。そして国民はその生命体の細胞として天皇を仰慕し、この国体を護持して、その生成発展のために力をつくし精神をつくし生命をつくして仕えることが使命である。」
ここで重要なのは神道の位置づけである。神道とは何か!神道とは、神代から続くわが国体の根本理念である。この国体の根本理念を果たして一宗教と位置付け、他の宗教と同列におくことが出来るのか否か。現に今日もなお国家的な意味をもって斎行され連綿として続けられている伊勢神宮新嘗祭の勅使差遣や皇室祭祀の現実を如何にみればよいのか。日本人ならば問答無用で、「政教分離」と「祭政一致」との次元の違いが解るはずである。祭政一致の政治を回復することこそ、わが国が世界の範たる国家として歩むべく道である。