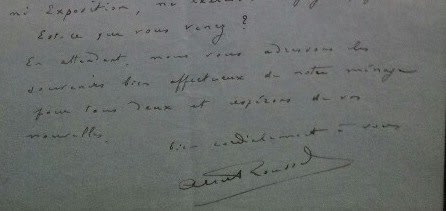ネルソヴァ(Vc)作曲家指揮LPO(decca/pearl)1950・CD
ブロッホの代表作。二十世紀のチェロ協奏曲の代表作のひとつでもある。ユダヤ音律の支配するかなりクセの強い作品だが、ネルソヴァはほぼ旋律的な崩しや指のズラしを使わず正確に音をとっていくことにより、この音階の特質をイデオロギーと切り離して聞く者に問うてくる。もちろん作曲家晩年の指揮がバックにあっての演奏で、晩年はそれほどこだわらずアメリカの新古典主義に立っていたブロッホの、過去作品に対峙した解釈と理解することもできる。録音的には正直勧められるものではないが、ネルソヴァのブレない演奏ぶりや、見本的な全体設計を聴くにはよい。
ブロッホの代表作。二十世紀のチェロ協奏曲の代表作のひとつでもある。ユダヤ音律の支配するかなりクセの強い作品だが、ネルソヴァはほぼ旋律的な崩しや指のズラしを使わず正確に音をとっていくことにより、この音階の特質をイデオロギーと切り離して聞く者に問うてくる。もちろん作曲家晩年の指揮がバックにあっての演奏で、晩年はそれほどこだわらずアメリカの新古典主義に立っていたブロッホの、過去作品に対峙した解釈と理解することもできる。録音的には正直勧められるものではないが、ネルソヴァのブレない演奏ぶりや、見本的な全体設計を聴くにはよい。