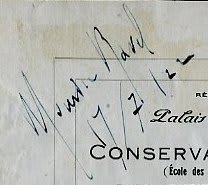◎ジュイユ(Vn)ロジェ(PL)(ACCORD)CD
同盤に併録されているアンサンブルのヴァイオリニストとはやはり違う高みにあることを感じさせるシャンタル・ジュイユ、ソリストというのは選ばれた人種である。この曲はまったく不安はない。この人は冷え冷えした現代的な作品もしくは東欧北欧的な作品に向くと思う。パスカル・ロジェはまったく危なげなくチェンバロふうの音を振りまく。きらきらしたピアノ・リュテアルが実に民族的で、バルトークらの音楽と接近していることを感じさせるが、そこにラヴェル特有の古雅で異界的な音響世界が展開され、民族音楽との交錯がくらくらとさせる。演奏設計が素晴らしく、このなかなか充実した演奏に出くわさない曲の、ボレロ的な一直線な駆け上がりを完璧に表現している。もっと熱してもいい曲だがスタジオ録音ではこれで十分だろう。十分に抽象的でもあり、◎にするに躊躇は無い。女流ヴァイオリニストにピアノ・リュテアルと原作に忠実な編成で模範たる名演。超絶技巧がそうは聴こえないところが凄い。
同盤に併録されているアンサンブルのヴァイオリニストとはやはり違う高みにあることを感じさせるシャンタル・ジュイユ、ソリストというのは選ばれた人種である。この曲はまったく不安はない。この人は冷え冷えした現代的な作品もしくは東欧北欧的な作品に向くと思う。パスカル・ロジェはまったく危なげなくチェンバロふうの音を振りまく。きらきらしたピアノ・リュテアルが実に民族的で、バルトークらの音楽と接近していることを感じさせるが、そこにラヴェル特有の古雅で異界的な音響世界が展開され、民族音楽との交錯がくらくらとさせる。演奏設計が素晴らしく、このなかなか充実した演奏に出くわさない曲の、ボレロ的な一直線な駆け上がりを完璧に表現している。もっと熱してもいい曲だがスタジオ録音ではこれで十分だろう。十分に抽象的でもあり、◎にするに躊躇は無い。女流ヴァイオリニストにピアノ・リュテアルと原作に忠実な編成で模範たる名演。超絶技巧がそうは聴こえないところが凄い。