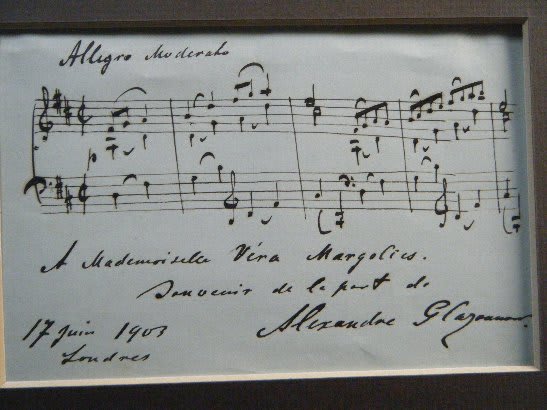○グラズノフ四重奏団(MUStrust)1930年代?・SP
速い。かつこの演奏精度は素晴らしい。テンポが前のめりだがそれがグラズノフの畳み掛けるような書法とピタリとあっていて正統な演奏であると感じさせる。ワルツ主題はそれにも増して速くびっくりするが、音の切り方、アーティキュレーションの付け方が巧緻でなかなかに聴かせる。ワルツ主題が優雅に展開する場面で初めてオールドスタイルの甘い音が耳を安らがせる。ここは理想的な歌い方だった。ショスタコーヴィチ四重奏団も歌いまくるがそれとは違う、優雅で西欧的な洗練すら感じさせる。その後テンポが激しくコントラストを付けて変わり、慌ただしくもあるが、冒頭主題が戻るとかなり落ち着く。その後はうまくまとめている。これほど達者で洗練された団体だとはあのボロディン2番からは想像できなかった。○。新グラズノフ四重奏団とは違う団体です。
速い。かつこの演奏精度は素晴らしい。テンポが前のめりだがそれがグラズノフの畳み掛けるような書法とピタリとあっていて正統な演奏であると感じさせる。ワルツ主題はそれにも増して速くびっくりするが、音の切り方、アーティキュレーションの付け方が巧緻でなかなかに聴かせる。ワルツ主題が優雅に展開する場面で初めてオールドスタイルの甘い音が耳を安らがせる。ここは理想的な歌い方だった。ショスタコーヴィチ四重奏団も歌いまくるがそれとは違う、優雅で西欧的な洗練すら感じさせる。その後テンポが激しくコントラストを付けて変わり、慌ただしくもあるが、冒頭主題が戻るとかなり落ち着く。その後はうまくまとめている。これほど達者で洗練された団体だとはあのボロディン2番からは想像できなかった。○。新グラズノフ四重奏団とは違う団体です。