森のこども祭、どのように
情報プラットフォーム、No.332、5月号、2015、掲載
地域の名前を冠した「こども祭」は、今のところ、鏡川、潮江、仁淀川、物部川の4つがある。5番目は、高知城東側の丸の内緑地での「森のこど も祭」であり、さらに同所での「木のこども祭」(2015/5/10(日))を予定している。びっくりするほどに少ない経費で、どれも数千人のこ どもや父母・祖父母が参加する数少ない参加型・体験型のイベントとして定着してきたと言える。ここでは最低限の経費でも運営して行ける仕組みを説 明する。
こども祭の特徴の第一は、ステージでこども文化を発信し、ものづくり・昔遊びなどの経験を積んで貰うことである。いの町波川公園での「仁淀川 こども祭」では、「川と河川敷でのこども遊び」、「水切り大会」と魅力的なイベントを盛り沢山にした。


こども祭の第二の特徴は、地域ごとに開催の特徴を持ち、流域の交流促進を図ることである。多様性のある仁淀川流域だからこそ、流域市町村の” 元気”を持ち寄る「お国自慢大会」として、「うまいもの自慢大会」、「流域内の伝統文化・郷土芸能の発表」を加えた。潮江地区では防災は避けて通 れない課題である。「防災フェスティバル」の副題を付けた。
こども祭の特徴の第三は、何れの「こども祭」も毎年開催するが、年一回と言わず、出来れば年二回も、そして何よりも続けることが前提である。 中枢となる実行委員会はその地域活動に詳しいグループ・個人で構成している。来年に引き継がれることが期待できるようにPTA、町内会、老人クラ ブ、趣味グループ、地域消防団などの地域活動の延長上で構成することを必須としている。「こども祭」を切っ掛けに、流域の(地域の)交流促進と活 性化を実現するための日常的な取り組みへと広がることを期待しているからである。
こども祭の特徴の第四は、どちらかと言えば企画先行であり、資金調達が後である。例え公的資金の支給がなくても、実施できる自己完結方式であ る。テントは出店(展)者が決められた場所に自分で設置し、熱源、ごみ処理も自分持ちとなる。売上の10%を原則として出展料とし、物づくり体験 などは無料である。なお、出展料は利益が計上できた時に納めて頂く仕組みである。ステージの準備、音響、出展(店)の配置、駐車場、トイレ、届出 業務などが企画者側の役目である。繰り返しになるが、公的基金などの獲得に最大限の努力はするが、例え基金が得られなくても遂行できる仕組みと なっている。
「こども祭」を、何時、何処で開催するかを周知させることが成功の秘訣である。A4裏表のチラシを要所へ配布することから始まる。関連地域に 関わる情報を掲載したA4 or A3三つ折りの広報誌を年4回程度の発行している。「鏡川の情報誌<いろいろかいろ>」、「クリーングリーン物部川<どんぶらこ>」、「森のネットワー ク」などである。これらには広告欄を設け、広報の発行・配布経費に充当している。
情報交流館(香美市)や月見山こどもの森(香南市)では、毎日が「森のこども祭」、「木のこども祭」と名付けても良い活動をしている。要請があれば小学校等へ「一日派遣先生」で職員が出向いている。また、情報交流館ネットワークの役員が音頭を取り、その地域の多くの団体と連携して進める「各地のこ ども祭」は、箱物ではない「森や木の体験館」と位置づけることが出来る。各地域の「こども祭実行委員会」は順次、指定管理の委託を受けた情報交流 館ネットワークの加盟団体の一つとして運営の一角を担っている。
本年は「森の検定こうち」に活動範囲を広げる予定で、その中の一つが「夏休みの自由研究~森の仲間が応援します」である。熱心な先生からの、 関心の高い両親からの、宿題を考える子供からの、要望に応えられるように、子供達への多面的な接近を心掛けている
ご感想、ご意見、耳寄りな情報をお聞かせ下さい。
〒718-0054 高知県香美市土佐山田町植718 Tel 0887-52-5154、
携帯 090-3461-6571
鈴木朝夫の「ぷらっとウオーク」 目次(2002~2007年 )
鈴木朝夫の「ぷらっとウオーク」 目次のつづき(2008年~2011年)

















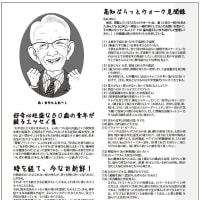
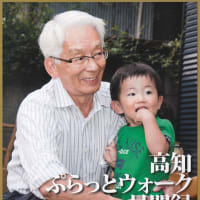

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます