彼女は「原告47番」と呼ばれた。薬害C型肝炎大阪訴訟で、滋賀県内で唯一の原告だった女性(50)である。出産時に投与された止血剤で感染し、06年8月に訴訟に参加。今年3月末に他の原告37人とともに国と和解した。病気への偏見などから、全国で770人を超える原告の大半が、この女性のように、氏名を公表せず匿名で訴訟に加わっており、その背後には、さらに多くの無名の患者がいる。私はこの女性への取材を通じ、匿名被害者たちの苦悩を知った。
「ああ、こんなものか」。3月31日午後1時40分すぎ、大阪地裁の508号法廷を出た女性は、深いため息をついた。1年半の訴訟の末に迎えた和解の場は、わずか10分で終わった。
女性は86年、出産の際の大量出血で血液製剤「フィブリノゲン」を投与され、C型肝炎に感染した。約35~30以下で肝機能が正常とされる「AST値」と「ALT値」は十数年前から80を超えていた。「仕事が忙しくて体の事は、ほったらかし」だったが、鏡に映る自分の異常に疲れた顔が気になっていたという。
やがて坂を上るのも苦痛なほど体力は落ち、2年前に病院で検査すると数値は3けたになっていた。アレルギー体質のため副作用が心配で現在も治療のめどが立たず、いずれ肝硬変に悪化する病状への不安を抱えたままだ。
◇
C型やB型肝炎は血液を介して感染するため、注意していれば、日常生活で他人にうつすことはまずない。感染経路は汚染薬剤のほか、輸血や集団予防接種の注射器の使い回しなどで、「医原病」と言われる理由がそこにある。
しかし、空気感染するとの誤解や偏見は根強い。滋賀県内の患者や家族らでつくる「滋賀肝臓友の会」によると、ある患者はC型肝炎と周囲に知られ、家に生卵をぶつけられて「出ていけ」と書いた紙が投げ込まれたり、「近寄ったらうつる」とうわさされた。ホームヘルパーだった別の患者は、派遣先で「他のヘルパーに代えて」と言われ、仕事を辞めた。患者のホームページに「うざい」「死ね」と書き込まれたこともある。
「47番」の女性も原告になるか迷った。家族を巻き込みたくなかった。それでも提訴を決意したのは、投与の証明という高いハードルのため、患者の大半が原告になりたくてもなれない現状を弁護団から聞いたからだ。
「なんで、こんな病気で苦しまなあかん。どうして僕は原告になれんの」と悔し涙をにじませた初老の男性患者。うつや皮膚のかゆみなど治療の副作用に悩まされ、駅のホームから投身自殺を考えた女性患者。友の会の交流会などで、そんな悲痛な声を度々耳にした。
女性の場合、出産の担当医は死亡し、病院もなくなっていたが、生命保険会社に残っていた診断書で投与が証明できた。「患者を助ける手伝いができるかもしれない」。義母の「闘えるところまで闘いなさい」との言葉にも後押しされ、匿名で原告団に加わった。田舎暮らしということもあり、名前の公表には踏み切れなかった。
しかし女性は提訴後、新しい悩みを抱えることになった。家族の介護もあり、国会議員への陳情や会議など、原告団の活動にあまり参加できなかった。メディアに顔も名前も出して解決を訴える実名原告らを間近に見ながら、「結局、匿名じゃ力になれない」と無力感にさいなまれた。
◇
被害者救済法が1月に成立し、ウイルスを駆除するインターフェロン治療の医療費助成も始まるなど、肝炎を巡る問題は一歩ずつ進んでいる。友の会の会員も04年10月の発足時は十数人だったが、今は50人を超える。だが田中守代表(54)は「これで解決したと思われるのでは」と不安でならないという。
肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、肝炎に感染しても自覚症状がないまま20~30年たつことも珍しくない。そのため、肝炎と分かった時には患者の多くは高齢になっており、リスクを伴うウイルスの駆除よりも、病状の進行を防いで発がん率を抑える治療を選ぶ人が多い。ところが4月に始まった医療費助成では、この療法は対象外だ。治療期間も1年間(48週)に限定されており、1年以上かけて治療する場合は助成を受けられない。
さらに、B型と合わせて全国350万人と推定される肝炎患者のうち、フィブリノゲンの投与が証明できて救済法で救われるのは、わずか0・03%の1000人程度とみられる。実際、2万4000人のC型肝炎患者がいるとされる滋賀県で提訴できたのは、この女性と5月末に新たに集団訴訟に加わった女性の2人だけだ。
◇
女性は親しい人と話していても、病気を打ち明けた場合をふと想像し、「この人は家に来て、私の料理を食べてくれるだろうか」と考え込んでしまうという。和解の直後、女性は「お金なんて、どうでもいい。元の状態に戻してくれるなら、いくら差し出してもいい」とつぶやいた。その悲痛な言葉は私の胸に深く突き刺さった。
毎日新聞 2008年6月11日 大阪朝刊
「ああ、こんなものか」。3月31日午後1時40分すぎ、大阪地裁の508号法廷を出た女性は、深いため息をついた。1年半の訴訟の末に迎えた和解の場は、わずか10分で終わった。
女性は86年、出産の際の大量出血で血液製剤「フィブリノゲン」を投与され、C型肝炎に感染した。約35~30以下で肝機能が正常とされる「AST値」と「ALT値」は十数年前から80を超えていた。「仕事が忙しくて体の事は、ほったらかし」だったが、鏡に映る自分の異常に疲れた顔が気になっていたという。
やがて坂を上るのも苦痛なほど体力は落ち、2年前に病院で検査すると数値は3けたになっていた。アレルギー体質のため副作用が心配で現在も治療のめどが立たず、いずれ肝硬変に悪化する病状への不安を抱えたままだ。
◇
C型やB型肝炎は血液を介して感染するため、注意していれば、日常生活で他人にうつすことはまずない。感染経路は汚染薬剤のほか、輸血や集団予防接種の注射器の使い回しなどで、「医原病」と言われる理由がそこにある。
しかし、空気感染するとの誤解や偏見は根強い。滋賀県内の患者や家族らでつくる「滋賀肝臓友の会」によると、ある患者はC型肝炎と周囲に知られ、家に生卵をぶつけられて「出ていけ」と書いた紙が投げ込まれたり、「近寄ったらうつる」とうわさされた。ホームヘルパーだった別の患者は、派遣先で「他のヘルパーに代えて」と言われ、仕事を辞めた。患者のホームページに「うざい」「死ね」と書き込まれたこともある。
「47番」の女性も原告になるか迷った。家族を巻き込みたくなかった。それでも提訴を決意したのは、投与の証明という高いハードルのため、患者の大半が原告になりたくてもなれない現状を弁護団から聞いたからだ。
「なんで、こんな病気で苦しまなあかん。どうして僕は原告になれんの」と悔し涙をにじませた初老の男性患者。うつや皮膚のかゆみなど治療の副作用に悩まされ、駅のホームから投身自殺を考えた女性患者。友の会の交流会などで、そんな悲痛な声を度々耳にした。
女性の場合、出産の担当医は死亡し、病院もなくなっていたが、生命保険会社に残っていた診断書で投与が証明できた。「患者を助ける手伝いができるかもしれない」。義母の「闘えるところまで闘いなさい」との言葉にも後押しされ、匿名で原告団に加わった。田舎暮らしということもあり、名前の公表には踏み切れなかった。
しかし女性は提訴後、新しい悩みを抱えることになった。家族の介護もあり、国会議員への陳情や会議など、原告団の活動にあまり参加できなかった。メディアに顔も名前も出して解決を訴える実名原告らを間近に見ながら、「結局、匿名じゃ力になれない」と無力感にさいなまれた。
◇
被害者救済法が1月に成立し、ウイルスを駆除するインターフェロン治療の医療費助成も始まるなど、肝炎を巡る問題は一歩ずつ進んでいる。友の会の会員も04年10月の発足時は十数人だったが、今は50人を超える。だが田中守代表(54)は「これで解決したと思われるのでは」と不安でならないという。
肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、肝炎に感染しても自覚症状がないまま20~30年たつことも珍しくない。そのため、肝炎と分かった時には患者の多くは高齢になっており、リスクを伴うウイルスの駆除よりも、病状の進行を防いで発がん率を抑える治療を選ぶ人が多い。ところが4月に始まった医療費助成では、この療法は対象外だ。治療期間も1年間(48週)に限定されており、1年以上かけて治療する場合は助成を受けられない。
さらに、B型と合わせて全国350万人と推定される肝炎患者のうち、フィブリノゲンの投与が証明できて救済法で救われるのは、わずか0・03%の1000人程度とみられる。実際、2万4000人のC型肝炎患者がいるとされる滋賀県で提訴できたのは、この女性と5月末に新たに集団訴訟に加わった女性の2人だけだ。
◇
女性は親しい人と話していても、病気を打ち明けた場合をふと想像し、「この人は家に来て、私の料理を食べてくれるだろうか」と考え込んでしまうという。和解の直後、女性は「お金なんて、どうでもいい。元の状態に戻してくれるなら、いくら差し出してもいい」とつぶやいた。その悲痛な言葉は私の胸に深く突き刺さった。
毎日新聞 2008年6月11日 大阪朝刊

















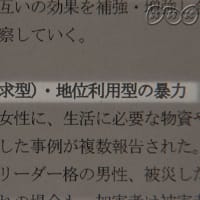

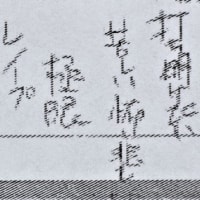
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます