先日の日曜日(6/7)に川崎第1導水ずい道巡りランを行ってきました。
この導水ずい道は小山田地区において、「源流の泉」の水はこの導水ずい道からの漏水ではないかとか、山中地区の「何だこれはと思っていた」のが導水ずい道監視塔で、それが最近道路の拡幅で移動したなどと気になっていました。
調べたところ、この導水ずい道は下九沢分水池という所から、私の実家近くで実家がお世話になっている長沢浄水場まで続いていることが分かり、興味が湧いて巡ってみようということになりました。

第1導水ずい道は相模原市緑区の下九沢分水池(標高112m)から川崎市多摩区の長沢浄水場(標高78m)まで、高さ・幅共2.6mの馬蹄形をした無筋コンクリート製の延長21.6kmの水路トンネルです。そして、この水路トンネルは圧力管路ではなく、玉川上水のような自然流下式水路だそうです。
1942年(昭和17年)に着工されましたが、地質や戦争による資材不足、人出不足で中断し、戦後1952年(昭和27年)に漸く完成したそうです。現在では耐震化などのため、ずい道にすっぽり入るような鋼管が挿入され、すきまをモルタルで充填された構造になっているそうです。
導水ずい道の位置は、普段よく利用するグーグルマップなどには記載はありませんが、国土地理院の地図には記載があります(一部は欠落)のでこれを利用し、別の情報で得た、所々で地上に出ている監視孔などを巡って行くことになります。
当然のことですが、70年前に作られた水路トンネルは現在の道路などとは殆ど無関係なので、同じようにトレースはできません。近い経路を地図上で概略計測すると27~28kmあり、一部をショートカットすることにしました。
また、導水ずい道巡りランは、始めは2回に分けようかと思ったのですが、1度でやった方が達成感はあるだろうということで1日で行いました。
これが今回の第1導水ずい道巡りランのガーミンの実際の走行データです。
中央付近で少し直線部分が見られますが、ここは尾根幹線を走った部分(2km程)です。前の導水ずい道図で右から1/3程度の所の「千代が丘配水塔」付近が上に山となっていますが、一方、ガーミンの走行図では相当する右から1/4辺りが逆に少し谷になっており、ここがショートカットした部分です。しかし、結局ショートカットしたにも関わらず実際の走行距離は31kmありました。
なお、導水ずい道図でショートカットした、大きく導水ずい道が上に迂回している部分のその理由が良く分からなかったのですが、国土地理院のデジタル標高地図を見て、鶴見川の支流の麻生川が新百合ヶ丘付近で作った谷を避けているのではないかと思いました。何かブラタモリ風ですが、実際、ブラタモリは私が一番好きなTV番組です。
さて、橋本駅から2km程の所にある下九沢分水池です。ここで津久井湖の方から来た水を川崎市側と横浜市側に分水しています。
円筒分水という形式で、3重構造です。外側の円筒の直径は35mあり巨大です。すり鉢状の底にあり、粛々と分水されるのかと思っていましたが、ゴウゴウと水が流れていて、少し離れた場所でも水音が聞こえていました。
今では周りを住宅に取り囲まれていますが、完成当時は畑や山林の中の泉という感じだったのでしょう。草など生えていて70年前の産業遺産という感じですが現役です。
流出口のアップです。手前が川崎市側、奥が横浜市側の流出口です。(少しブレた画像です。)
この分水池から原水は、川崎市側は第1導水ずい道として、ほぼ東へ、横浜市側は南東方向に向かいます。
円筒分水では通常中央部からサイフォンなどで湧き出るそうで、そうだったら壮観だったでしょうが、ここでは右上方向から流入しています。3重水槽の水面の高さの違いが良く分かりますが、その流入水の勢いをどう制御して等分に分水しているのだろうかと気になりましたが、ここが目的地ではなく出発点なので出発することにしました。
分水池から2km程の距離にある16号線上の2つのずい道交差部。丁度画面が向いている方向に第1ずい道、16号の向こう側で道路と平行に後からできた第2ずい道があります。
念のため、その付近の地上部を少し探してみましたが、特に何の表示もありませんでした。
その付近の地理院地図です。いずれも青い点線です。第1ずい道は交差部分が消えていますが、「川崎二号水道」の「川」の字辺りで交差しているようです。
横浜線を越える部分ですが、地図上ではずい道も少し右辺りで越えています。
監視孔は約4km毎にあるそうですが、最初の「堺監視孔」です。圧送ではなく自然流下式のずい道なので開けても水が噴き出すことはないはずです。これは尾根幹線が町田街道に接続する辺りにありますが、セキュリティ上から川崎市ではこれらの場所の詳細情報は開示していないので私もボカした感じにしておきます。しかし、街中は地図を確認しながら走る(実走行距離5.8km程)ので、ここまで1時間程掛かってしまい先が思いやられます。
シンボルとして中々良い感じです。
尾根緑道を越える部分で、導水ずい道もこの付近で通過しています。
鶴見川の「源流の泉」です。付近を流れる導水ずい道からの漏水疑惑は水の成分が異なるということで水道局から否定されています。
画面中央の道路屈曲部付近が「源流の泉」なので、導水ずい道(左から右上にかけての点線)はかなり離れていて源源流に近い所ですね。
「源流の泉」から「山中監視孔」までは勝手知ったる場所なので、トレイル主体で進みます。
「山中監視孔」です。最近の道路の拡幅(2倍程)で5m程後ろに下がったようです。こげ茶色の柵で囲われた部分です。
以前のずんぐりした丸形郵便ポストのような形状から単なる点検孔となってしまい、つまりません。
「山中点検孔」からは尾根幹線を進みました。南野に水素ステーションができていました。今年の春の様です。ただ私は水素自動車のMIRAIは2回しか見たことがありません。
多摩ニュータウン市場近くの「別所監視孔」です。尾根幹線を通ってきたので、ここには早く着きました。
ここから「よこやまの道」に入ります。
「よこやまの道」を離れて黒川地区に下りてゆきます。
黒川の営農地に出ました。
畑です。
田植えが終わったばかりの田んぼです。
道端にはハナショウブ?が咲いていました。
奥に果樹園が見えます。ランナーが走ってきました。
柿生発電所です。無人の地下の発電所なので目立ちませんが、第1導水ずい道上にあり、その水を利用した水力発電所です。
中央部にあるのが柿生発電所で導水ずい道の点線が左上から右下に伸びています。
川崎市HPより
「柿生発電所は、川崎市営水道の導水路途中にあります有効落差12.2m、最大使用水量6.94m3/s、出力680kWという、とても小さな水力発電所です。川崎市は昭和15年度からの上水道第4期拡張事業において、津久井分水池(相模湖)より受水した水を下九沢分水井(川崎市と横浜市に分ける)を経て、長沢浄水場に至るまでの途中、黒川に地形の関係から落差ができるため、当初からこの地に低落差発電所の計画をたて、その構造物を建設していました。昭和27年、導水路は完成しましたが、川崎市が発電事業を開始するに至らず、発電所の建設と維持管理は県企業庁に引き継がれました。昭和37年8月に工事が完成し、営業運転を開始しました。
発電設備としては、小さな発電所に適する横軸円筒可動羽根プロペラ水車(チューブラ・タービン)〔回転数500r.p.m.〕と、横軸かご形3相交流誘導発電機(共に日立製作所製)を備えています。また、水道用水利用という特殊な事情から、できるだけ汚損しないように、水中にある箇所は油のいらない構造とし、漏油防止が施されています。」
水は左上方から流れてきます。奥の丸い筒状のものは水槽で、手前の三角部分が発電機がある地下に下りる入口です。
なお、ここで昼食を取りました。
この黒川地区にはリンゴ畑があることを思い出して見に行きました。まだ直径4cm程でした。
少し色づいているものもありました。
こちらは梨だと思います。
農業振興地域に指定されているので、このままの景観が残るでしょう。また、来たいと思います。
導水ずい道は黒川駅そばのここで小田急多摩線を越えますが、道はないので私はぐるっと回り道をしてゆきます。
稲城の里山地区は造成されてすっかり景色が変わっていました。
稲城第2中学校。この辺は以前来た時と変わっていませんでした。
4番目の「平嶽監視孔」。中学校の傍ですが目立たない所にあります。半地下のような感じです。
導水ずい道の残りは6,7km程ですが、このような監視塔はこれで終わりのようです。
ここから導水ずい道を離れショートカットコースに入りました。広い道を新百合ヶ丘駅方面に進み、その後、小田急線沿いに百合ヶ丘駅に向かいました。
導水ずい道は百合ヶ丘駅の近くで小田急線を越えます。ここがそうで高石伏越といわれ、「伏越」という逆サイフォン構造の水路で道路と線路の下をくぐっています。画面中央の白い部分の向こうが線路です。奥の緑地部分の上が高石伏越の上流側点検部、手前画面左のフェンス部分が高石伏越の下流側点検部です。
高石伏越の下流側点検部(孔)です。
ここの百合ヶ丘駅から南生田までは苦労しました。長い真っ直ぐな道はなく短い曲がった道ばかりで、特に導水ずい道が向かう東西方向には短い道しかありません。多分、尾根と谷が南北方向に走っているのだろうと想像していましたが、その通りで急坂や急な階段が多く出現し、アミダクジのような道を進みました。また、そのような地形のため、導水ずい道には何か所も伏越がありました。
半郡谷伏越の下流側(左側フェンス内)から上流側(向こうの森の中)を見ています。
猫三谷伏越の上流側点検部です。点検部分がはっきり見られたのはここ位です。
猫三谷伏越の下流側点検部ですが、点検部(孔)は上がっても見えませんでした。
栗谷伏越の上流側点検部。辛うじて青い点検孔の蓋が見えます。
道路を挟んだ反対側にある栗谷伏越の下流側点検部。
ここからは、長沢浄水場まで1本道になるので元気が出てきました。
もうすぐ浄水場という所で、最後になって初めて地上に出た第1導水ずい道です。これを見たかったのです。
でも実は、この直ぐ近くの墓地が実家の墓がある所で、ここは今まで何度も車で通ったはずなのに全く記憶がありません。
前の写真のずい道を傍の公園から見下ろしたところです。上面は開放されておらず水面は見えません。上部の左右の角がカットされているので、断面が馬蹄形という導水ずい道がそのまま地上に現れているのだと思います。
長沢浄水場(西門)に着きました。下九沢分水地からここまで6時間50分も掛かりました。達成感というより漸く着いたという感じです。導水ずい道の平均流速は4.5km程度ということなので原水の方が早かったですね。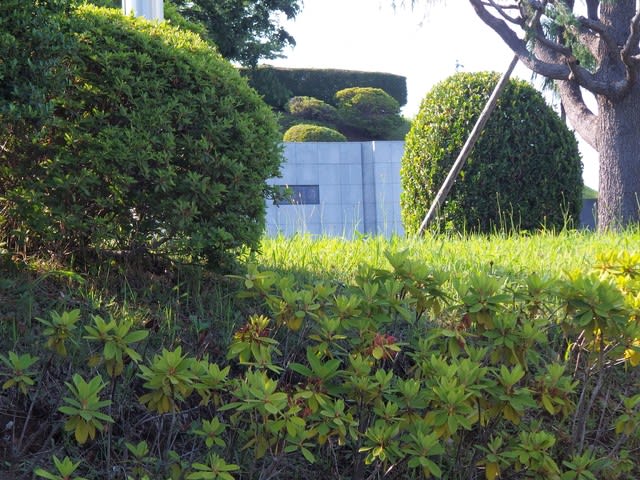
浄水場西門から覗くと木の間から、第1導水ずい道の出口である「着水井」の上部の白い花こう岩が見えました。生垣の向こうに開口部があるはずです。
今回、31kmと思ったより距離が長かったです。百合ヶ丘駅以降は歩きが主体となってしまいましたが、スタート/ゴールと駅までの距離も入れると35km程度あり、また暑くて久し振りに疲れました。目的を持ったジョグは飽きませんが、柿生発電所までが良かったです。
また、第1導水ずい道の建設についてはネット上には殆ど情報がありませんでしたが、川崎水道〇〇年史などの資料はあるはずなので、機会があれば図書館ででも確認したいと思います。
トレイルF



























35kmは辛そうですね!故障に気をつけてください。
またお邪魔したいと思います。
テーマを決めて走るのは楽しいです。
この水道は前から興味あったので、参考になりました。
やはり、鶴見川源流の水はこれが使われていると聞いたことがありますが、違うのかな?
横浜へ行くのも複雑に交差しているんですね。
国土地理院の地図に載っていると言うのは参考になりました。