友人が 最近観た映画と 観たい映画を 知らせてくれました
①柘榴坂の仇討
②蜩ノ記
③ジャージーボーイズ
時間的な制約がなくなった生活ですので 映画だって 自由に行けるのですが
案外 なんだかんだで 行けないものです
隣市の映画館で上映中だから 是非 観てこようと思いながら ずるずると日を過ごしています
それじゃ まず 原作を読んでしまおうと 今日は ブックオフに行って探してきました
これは すぐに見つかりました
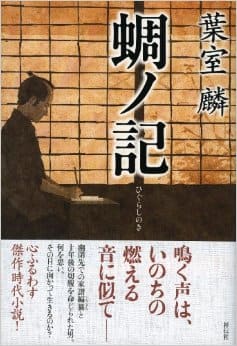
410円です あまり安くなっていません
「柘榴坂の仇討」は 見つかりませんでした
帰ってきてから 調べたら 「柘榴坂の仇討」という書名ではなく
新潮文庫の「五郎治殿御始末」という短編集の中の一編なんだそうです

明日 もう一度 ブックオフに行って 探してきます
ブックオフの 本の並べ方が 理解できていないので 探すのに 時間がかかってしまいます
いつも 夫に頼んでいたのですが これからは 自分で探せるようになりたいです
少しでも 安く 買いたいですから ブックオフを利用します
①柘榴坂の仇討
②蜩ノ記
③ジャージーボーイズ
時間的な制約がなくなった生活ですので 映画だって 自由に行けるのですが
案外 なんだかんだで 行けないものです
隣市の映画館で上映中だから 是非 観てこようと思いながら ずるずると日を過ごしています
それじゃ まず 原作を読んでしまおうと 今日は ブックオフに行って探してきました
これは すぐに見つかりました
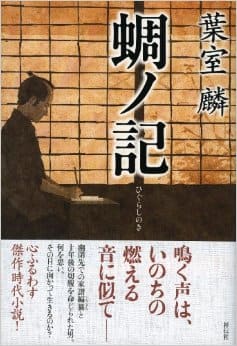
410円です あまり安くなっていません
「柘榴坂の仇討」は 見つかりませんでした
帰ってきてから 調べたら 「柘榴坂の仇討」という書名ではなく
新潮文庫の「五郎治殿御始末」という短編集の中の一編なんだそうです

明日 もう一度 ブックオフに行って 探してきます
ブックオフの 本の並べ方が 理解できていないので 探すのに 時間がかかってしまいます
いつも 夫に頼んでいたのですが これからは 自分で探せるようになりたいです
少しでも 安く 買いたいですから ブックオフを利用します



















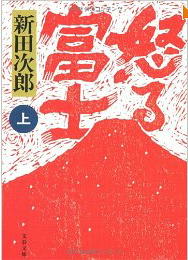
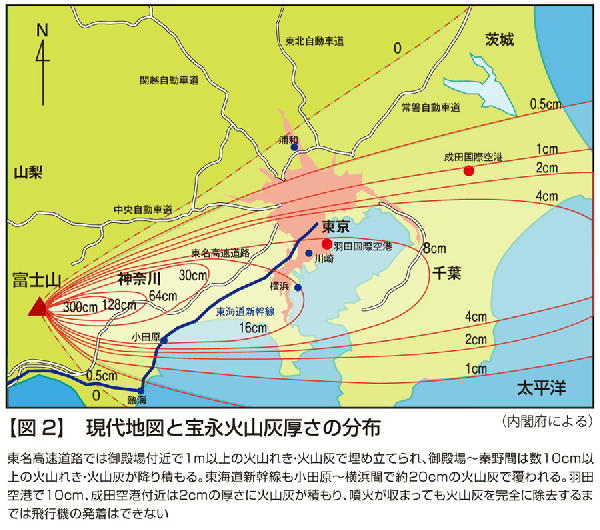
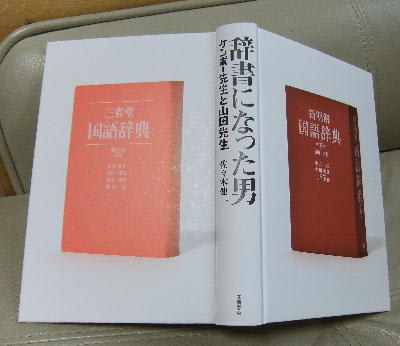



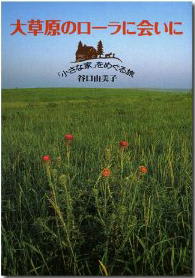
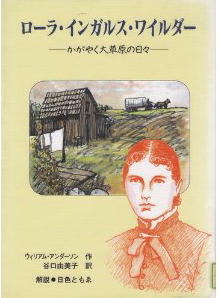
 ネット画像
ネット画像



