早期の療育について書いた記事に
さくらさく さんから、こんなコメントをいただきました。





はじめまして。うちの2番目ちゃんも上の子となんか違う、皆よりもごゆっくりさんと思って、保育園に相談したりしましたが「普通ですよ」と言われてました。
年長になって発達支援センターに連れて行ったところ、特定できない軽度発達障害と診断されました。
それ以来、いろんな本を読み、自分なりにかかわり方を変えて試行錯誤を続けています。
療育にも月2回のペースで通っています。
「もっと早くに、療育的にかかわったら子供がもっと伸びたのでは」という思いがあります。年長途中ではありますが、思い切ってたくさん遊んでくれる幼稚園に転園することにしました。(今の園は勉強系でつめこみのように思いました)
なおみさんもいつか書かれていましたが、「母親のかん」ってとても大事だと思います。
微妙なところにいる子供たちを助ける手だてがあるといいなと、いつも思っています。






診断を受けたものの、療育が受けられない…

療育を受けているには受けているけれど、内容は集団に慣れることが中心で、
診断別の対応法がわからない…

自分の今受けている療育だけで良いのか疑問を感じる
といった話をよく聞きます。

私も教室に通ってきてくれているアスペルガー症候群やその周辺部にいるグレーゾーンの子供たちを見て、
就学後に役に立つと思われる療育がきちんと行なわれていないことを痛切に感じます。
療育に通っている子と親御さんといっしょに
遊んだり勉強したりしていると、
親御さんが子どもに教えなければならない大切なポイントから
かなり離れた部分を強調して教えているシーンによくぶつかるのです。

注意の向け方や
情報の入力の仕方にハンディーがある子らは、
注目させるときに工夫して気持ちを引きつけたり、
視覚的なアプローチを加えたり、
何から手をつけたらよいのかわかりやすくさせたりするポイントをはずすと、
いくら教えても少しも身につかないことがあります。

また、就学後、具体的な困難を想定して、
練習を積んでおくと、助かることもたくさんあります。
たとえば、プリントが配られた時、
自分の1枚を取って、後ろの人に回す練習。
「教科書の3ページを開いてください」と先生が言ったら、
どうすれば良いのか、
教科書をぺらぺらめくり続けてはいけない、
などを学ぶ練習。

社会性を教えるという課題も、ただ集団ですごす練習を
続けるだけでは足りない気がします。
親御さんと遊んでいる時に毎回ズルをして
勝とうとするとき、どう教えればよいのか?
恥ずかしい…という感覚がわかりずらい子に、
みんなの前でどういう行為をするのが恥ずかしいことなのか、わからせるにはどう教えればいいのか?
そうしたことを、どのように教えたら子どもが理解するのか、
療育の場で具体的に何も教えてもらっていない親御さんが多いのです。

これでは診断を受けて途方に暮れている親御さんが
本当に困ってしまうと思います。

きちんとした集団での過し方を学べずに、就学を迎える子供達も困りますし、

集団を乱しがちな子を引き受ける小学校の先生も困ってしまうはずです。

今後、少しずつでも
早期療育の質が向上していくことを願っています。


web拍手を送る















 大人の話に耳を傾けること、
大人の話に耳を傾けること、






 かなり困った状況ですね。
かなり困った状況ですね。
 。
。
 )
)
 診断を受けたものの、療育が受けられない…
診断を受けたものの、療育が受けられない…





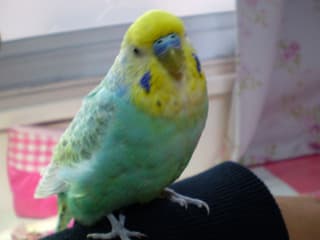

 この2~3日、とても多忙だったので、メールのお返事が遅れています。
この2~3日、とても多忙だったので、メールのお返事が遅れています。
