
「女は女である」(Une Femme est Une Femme)
1961年フランス・イタリア
監督:ジャン=リュック・ゴダール
音楽:ミシェル・ルグラン
出演:アンナ・カリーナ、ジャン=クロード・ブリアリ、
ジャン=ポール・ベルモンド
ゴダールは1962年のインタビューで、「女は女である」をこれが本当の処女作だと言い、必ずしも自分らしい映画ではないが、最も好きな映画だと答えている。そのとき、ひとは病気の子どもを最もかわいがるものだとつけくわえているので、出来栄えについては必ずしも満足していたわけではないようだ。
実際、「女は女である」のシナリオは「勝手にしやがれ」以前に書かれており、1959年にシャブロルの製作で「愛の戯れ」として一度映画化されたことがある。
この映画の撮影でゴダールは色彩の発見と同時録音の発見とシネマスコープの発見をしたと語っていて、シネマスコープについては「すべてを撮ることができるサイズ」だと言っている。
しかしながら1985年のインタビューでゴダールは「女は女である」について、今ではあまり好きではないと答えている。1978年の「テレラマ」誌においては、この映画を「あれはまったくくだらない映画だ。あそこには力強さが、生気がない。だれに対しても恨みを抱いていなかったから、どこからも攻撃されていなかったからだ。あれはなんとも甘っちょろい映画なんだ」と激しく否定してもいる。1968年の五月革命から始まる政治の季節をくぐり抜けた後のゴダールの発言としてはわからないでもないが、案外とトリュフォーとの友情の記録(ドキュメント)でもあるこの映画に対して、トリュフォーと絶縁した後のゴダールが複雑な感情を持ってしまうということなのかもしれない。
トリュフォーとの友情の記録であるとともに、「女は女である」はトリュフォーの「ピアニストを撃て」の言わば姉妹作と言っていいと思う。シャルル・アズナヴールの歌が使われていたり、マリー・デュボワが端役で出演し、グーディスの原作を読んでいたり、ジューク・ボックスの中に「ピアニストを撃て」のシングル・レコードのジャケットが飾られていたり、外から部屋の中にネオンサインの瞬きが入りこんだりするだけでなく、「ピアニストを撃て」のなかでギャングの一人が言う「女はいつも欲しがっている。そして必ず手に入れる」という台詞はそのまま「女は女である」にもあてはまるものだろう。
「女は女である」は公開当時さほどヒットしなかったそうだ。その理由としてゴダールは、連続性に欠けていたり、リズムが変化したり、調子が途切れたりするせいだと答えているが、トリュフォーがゴダールの「勝手にしやがれ」の型破りで活き活きとした画面をねらって、ラウル・クタールと組んだ「ピアニストを撃て」も同様の理由で当時の批評家から酷評されたのだった。
「女は女である」には、結局は発売されずに終わったものの、その音声部分を収録し、その合間にゴダールがコメントを加えたものを10インチのレコードとして発売するという企画があった。そこでのコメントはとても興味深いものなので、いくつか抜き出してみる。
「女はやはり女であることを証明しながら、映画はやはり映画であることを証明する」
「誤りを犯すは映画の性なり」
「カメラというのはまず撮影の道具であり、演出するというのはなによりもまず慎ましやかに物に加担すること」
「ひとはほとんどつねに、最初に計画したこととは正反対のことをしてしまう。しかし、結局は出発点において想像したことに似ている」
「芸術とはそれを通して形式がスタイルになるもののことだ」
「女は女である」は「悲劇とはクロース・アップでとらえられた人生であり、喜劇とはロング・ショットでとらえられた人生である」というチャップリンの言葉を受け、クロース・アップでとらえられた喜劇を撮ればそれは悲喜劇になる、という考えからつくられたものだ。ネオ・リアリズム的なミュージカルをねらったというが、ゴダールはジャンルとしてのミュージカル映画はすでに死んだと認識しており、「女は女である」はミュージカル映画についての観念であり、死んでしまったミュージカル映画へのノスタルジーであるという。これをプラトン的に言い換えれば、霊魂が地上の肉体に宿る以前に見たはずのイデアを自ら想起(アナムネーシス)することによる真理の認識みたいなことになるだろう。ゴダールはダイナミックなダンスや感情の高まりがほとばしりでるような歌なしで、つまり、それらの欠如において、かつて銀幕を活き活きと彩ったミュージカル映画の記憶を、きれぎれの断片やミュージカルスター、振付師などの固有名によって喚起させ、それらに憧れるエロスに導かれるようにしてミュージカルに近づこうとする。おそらくは不自然さによって。ミュージカルでは乱闘シーンもまた、グループでの計算されたダンスとなり、逃げる相手を追いかけるときも踊りながらだったりして、そこに不自然さを感じることがある。「女は女である」も俳優たちの演技や演出に不自然なところがある。見る者に不自然さを与えることはミュージカル映画にとっては致命的なことで、ダンスや歌がイリュージョンを喪失したということである。それゆえにミュージカル映画は死んだということになるのだろうが、この不自然さを強調することで、逆説的にミュージカル映画と結びつくことができるのではないか。
ミュージカルに対するゴダールのこのようなスタンスはワーグナーの楽劇に対するブレヒトのスタンスと共通する面がある。ミュージカルはワーグナーの「総合芸術」の持つイリュージョンを保持しつつ、大衆化させたものであると言えるからだ。
ブレヒトは観客が舞台で起きていることを様々な角度から眺め、そこから変革の可能性を見出すことを期待した。そのためには、観客が演劇に同化せず、常に距離をおき、冷静であることが必要で、登場人物への感情移入や舞台への同化をさせないためにブレヒトは様々に工夫をした。彼の演劇は最後のクライマックスで観客にカタルシスを与えるようなものではなく、ばらばらなエピソードが散りばめられるようなものになった。これが音楽や文学、演劇といった諸芸術を一体化した「総合芸術」を掲げ、観客を感覚的に幻惑しながら舞台上のできごとに同化させようとしたワーグナーの楽劇に対するアンチとしてのブレヒトの演劇である。また、ブレヒトは俳優の演技に対しても、役に同化するのではなく、役を演じている俳優であることを忘れないよう注意し、台詞の後に「~と彼は言った」とト書きを含めて言わせたりした。「女は女である」にもそのような場面があるし、俳優たちはカメラに向かってお辞儀をしたりするなど、カメラを意識しながら行動している。俳優は俳優である自己と役柄の二重化を生きる存在であり、ゴダールにとって映画はフィクションであると同時にドキュメンタリーでもある。
→「人生を出発点とする芸術―アラン・ベルガラによるジャン=リュック・ゴダールへの新しいインタビュー」1985年
→「『女は女である』―ジュヌヴィエーヴ・クリュニーのアイディアにもとづくシナリオ」
→「『女は女である』―映画『女は女である』のレコードのなかのコメント」
→「ジャン=リュック・ゴダールに聞く―初期の四本の映画がつくられたあとで」1962年
(いずれも「ゴダール全評論・全発言1」(筑摩書房)所収)
 Open, to love
Open, to love









 NOW HE SINGS, NOW HE SOBS
NOW HE SINGS, NOW HE SOBS SOMEWHERE BEFORE
SOMEWHERE BEFORE CHILDHOOD IS FOREVER
CHILDHOOD IS FOREVER 「女は女である」(Une Femme est Une Femme)
「女は女である」(Une Femme est Une Femme)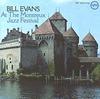 At The Montreux Jazz Festival
At The Montreux Jazz Festival 「ピアニストを撃て」(Tirez sur le Pianiste)
「ピアニストを撃て」(Tirez sur le Pianiste)


 「彼らが利用できたのは素朴だがたよりになる材料―つまり、木材とハンマーとノコギリと自分たちの荒けずりな創意工夫だけであった。彼らはこれらを用いて名匠が達した壮大なヴィジョンに自分たちのささやかな独自性を加えて、それを人間らしい規模にまで縮小させたのだった。要するに、奇想と借用と嘘の寄せ集めだった」
「彼らが利用できたのは素朴だがたよりになる材料―つまり、木材とハンマーとノコギリと自分たちの荒けずりな創意工夫だけであった。彼らはこれらを用いて名匠が達した壮大なヴィジョンに自分たちのささやかな独自性を加えて、それを人間らしい規模にまで縮小させたのだった。要するに、奇想と借用と嘘の寄せ集めだった」