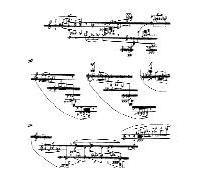STRAVINSKY
STRAVINSKYThree Greek Ballets Apollo Agon Orpheus
Robert Craft
London Symphony Orchestra
Orchestra of St Luke's
「彼はN.A.リムスキー=コルサコフから秩序の方法を受け継いで、それを自分用に変形する。リムスキーのテーブルの上では、インク瓶やペン軸や定規が官僚臭を現している。ストラヴィンスキーでは、秩序が人をおどかす。それは外科医の道具箱だ。
仕事と一しょくたになり、仕事を着込んで、老ぼれのちんどん屋のように作品を身に飾ったこの作曲家は、身の周りに音楽の皮を厚くして行くので、彼と部屋とはもはやひとつにすぎない。モルジュにおける、レイザンにおける、パリの彼の住居のプレイエルにおける、ストラヴィンスキーを見ることは、殻の中の動物を見るようなものだ。ピアノ、太鼓、メトロノーム、シンバル、五線引き、アメリカ式鉛筆削り、譜面台、平太鼓、大太鼓などが、彼を引き延ばす。それらはパイロットの座席であり、映画が千倍にも拡大して見せてくれる時の、交尾期の昆虫を蔽うている武器だ」(ジャン・コクトー「雄鶏とアルルカン」)
イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)はペテルブルク近郊のオラニエンバウムに生まれた。9歳からピアノを学び、十代後半からは音楽理論も学んだが、音楽院には入学せず、大学では法律を学んだ。22歳のときにリムスキー=コルサコフと出会い、彼のもとで作曲と管弦楽法を学び、ストラヴィンスキーは音楽の道に進むことになった。1908年に作曲した「花火」がロシア・バレエ団のディアギレフに認められたことがきっかけで、ロシア・バレエ団の音楽を担当するようになると、1910年に「火の鳥」、その翌年に「ペトルーシュカ」、そして1913年に初演がスキャンダルを巻き起こした「春の祭典」をあいついで作曲し、ストラヴィンスキーは前衛的な作曲家として注目されることとなった。しかし、ロシア・バレエ団の天才舞踊家ニジンスキーとの関係はうまくいかなかったようで、ニジンスキーはその手記のなかでストラヴィンスキーのことをずるがしこく、冷たい男であるとし、「ストラヴィンスキーはよい作曲家だが、人生について考えない。彼の作曲は目的を持っていない」と書き記している。
エリック・サティはストラヴィンスキーについて「こと音楽に関する限り、かつて存在したなかで最も傑出した天才のひとりである」と絶賛し、パレストリーナやモーツァルトにも比肩し得るとして、その音楽の特徴について次のように書いている。
「ストラヴィンスキーの音楽の特徴のひとつは、音の響きの「透明さ」にある。純粋な巨匠たちの作品につねに見出されるあの特徴である。巨匠たちは自作の響きのなかにけっして「残り滓」を残さない」
「ストラヴィンスキーがその音楽的能力の豊かさをあますところなく私たちに見せてくれるのは、「不協和音」の使い方においてである。そこでこそ彼は真に本領を発揮し、私たちを広大な知的陶酔におとし入れる」
「彼の作曲法は新しく&大胆である。オーケストラの使い方が「ぼやけている」ことはけっしてない。「オーケストラの穴」と「もや」を避けながら――後者は船乗りに負けないほど多くの音楽家を破滅におとし入れる――彼は自分の望む方向に突き進む」
「ストラヴィンスキーのオーケストレーションが、深く的確な楽器編成から生み出されるということである。彼の「オーケストラ曲」はあげて、楽器の音色を基盤に構築されている」
ストラヴィンスキーの創作活動はそのスタイルの変化において次の3つの時期に区分される。
1.ロシア時代(1910-1918)
2.新古典主義時代(1918-1950)
3.セリー時代(1951-1971)
ロシア時代においては、リムスキー=コルサコフ的なエキゾティズムと色彩感あふれる管弦楽、幾つかのブロックを組み合わせたキュビスム的な構造、鋭い輪郭を持った旋律、二つの調を重ね合わせる複調、不協和音、絶え間なく変化し続ける拍子、原始主義的な荒々しさなどを特徴とし、ロシア・バレエ団のために書いた「火の鳥」「ペトルーシュカ」「春の祭典」といったいわゆる三大バレエ音楽が代表的な作品である。この頃の作品を通じてロシア音楽の諸要素は多くのモダニストの共有するところとなっていった。
20世紀の音楽はそれまでの音楽の既成概念を覆す試みがなされたが、シェーンベルクによる「調性」の破壊と未来派による「楽音」の破壊と並んで特筆されるのはストラヴィンスキーによる「拍子の一定性」の破壊である。
そして1918年からストラヴィンスキーは新古典主義に転向した。この新古典主義は、ロマン派以前の音楽が備えていた客観性や明晰さに回帰するもので、音楽からロマン主義的な主観性や感情を排し、均整の取れた形式や合理的な手法を重視する。そしてこの年、ジャン・コクトーは「雄鶏とアルルカン」を書いた。
ストラヴィンスキーの新古典主義は「兵士の物語」やペルゴレージの作品をアレンジした「プルチネルラ」から始まる。これらの作品は様々な音楽様式がコラージュのように引用され、並列され、耳慣れた素材を用い、引用とアレンジだけで作曲する試みであった。しかし、そこには巧妙なパロディ化がなされてもいる。ストラヴィンスキーの新古典主義は単なる懐古趣味ではなく、音楽史の終焉を見つめながら、進歩的歴史観と独創性を否定し、既知のものを微妙な文脈のずらし方によって換骨奪胎することで独自性を生み出そうとするものであった。
ストラヴィンスキーは、古典主義とロマン主義に結びつけて秩序と無秩序、普遍主義と個人主義、服従と不服従といった対立概念を論じた。「普遍主義は必然的に既成の秩序への服従を定める。その理由は十分納得のいくものである」とストラヴィンスキーは言い、あるひとつの様式、個々人の表現を総括する時代の集団的な表現を通してのみ、芸術家は、「ひとつの文化を構成しているこの伝統の束」に参与することができると考えた。ロシア時代に自らも破壊に加担した秩序を再構築するためにストラヴィンスキーは古典主義を見い出したのである。
ジャンケレヴィッチはストラヴィンスキーの新古典主義への転向について次のように書いた。
「のちにストラヴィンスキーが『春の祭典』のアジア趣向、『ペトルーシュカ』のロシア主義、『結婚』の民俗調を否認するとき、それはムーサたちを支配するアポロに到達するためだった。ギリシアには、たしかに、この音楽家は民族舞踊のリズムあるいは民謡を認めず、遍在と理想境とから成り立っている現状離脱を求める」
しかし、このようなストラヴィンスキーの新古典主義はアドルノによって批判されることになる。「シェーンベルクの進歩」そして「ストラヴィンスキーの復古」は、19世紀のヴァーグナー派とブラームス派の論争さながらに展開されていくことになる。
「彼らはかつて彼らの青春を充たし、彼らの魅力の種であったものに、多少とも公然と背を向けてしまったのであった。彼らの復古主義的な試みは、二三の改宗したシュールレアリスムの画家たちのそれと同じように、文化哲学的な思惑から新音楽の概念そのものと手を切ってしまっている。彼らは永遠の音楽という幻を追っているのである」
シェーンベルクの死後1951年からストラヴィンスキーは音列(セリー)技法を用いた作品を書くようになり、ウェーベルンを「音楽的対象と我々自身の間の新しい距離の発見者 音楽的時間に対する新しい尺度の発見者」として賞賛するようになった。この転向については1948年にシェーンベルクやウェーベルンの信奉者でもあったロバート・クラフトと出会い、彼をアシスタントにしたことも影響したかもしれないが、シェーンベルクの十二音技法がウェーベルンや彼の後継者たちによって、ひとつの集団的な音楽現象となり、様式の普遍主義を備えていたことが認められたということがあった。
ブークールシュリエフは次のように書いている。彼はストラヴィンスキーの変化の中に様式上の秩序を求める根源的な要求があるとし、そこにストラヴィンスキーの統一性を見い出した。
「ストラヴィンスキーが音列の原理の中に、彼自身の相変わらぬ要求にも開かれた、新しい領野を認識していたということである。その要求とは、様式上の秩序を求める根源的な要求であり、彼にとっては作曲ということであるこの想像力の力を自由に行使することのできる、厳密な約定の網の目を設定する――あるいはあらかじめ設定しておく――必要である」
ストラヴィンスキーの音楽はしばしばピカソの絵画との類縁性について語られる。例えばブーレーズは次のように言っている。
 「画家たちと音楽家たちの照応関係は、20世紀においていっそう顕著であるように思われる。
「画家たちと音楽家たちの照応関係は、20世紀においていっそう顕著であるように思われる。ストラヴィンスキーとピカソとの並行関係はひとつの典型である。彼らは緊密なやり方で一緒に仕事をしはしなかったが、『プルチネルラ』は舞台における共同作業の一例としてあらゆる人々の記憶に刻み込まれている。まったく同様に『ラグタイム』の表紙は完全な共生のモデル例である。ロシア・バレエ団の残したイメージがあまりにも強烈であり、あまりにも強力だったので、彼ら二人の名は、いわば接合されてしまっている。それも、ストラヴィンスキーの有名なバレエ音楽『狐』、『春の祭典』、『花火』、『火の鳥』、『ペトルーシュカ』、『夜うぐいすの歌』、『結婚』が、他の画家たち、ラリオーノフ、リョーリフ、バルラ、ゴロヴィーン、ブノワ、マティス、ゴンチャローヴァとの共同作業で実現されたにもかかわらず、である。ストラヴィンスキーとピカソにおいては、同じ時期における彼らの軌道の根本的な類似性を否定することが不可能だからだ。『春の祭典』と『アヴィニョンの娘たち』の間には、同じ態度、同じ視点が観察される。もっと後になって、『プルチネルラ』は新古典主義の始まりを画しているが、そうした新古典主義はストラヴィンスキーにもピカソにも同じようにはっきりと認められる。もっと以前では音楽史や絵画史から「引用された」モデルの同じような扱い方が見い出される。明らかにドラクロワから出発したピカソは、『放蕩児の遍歴』の作曲に際して『ドン・ジョヴァンニ』を念頭に置いていたストラヴィンスキーと比べられる」
それでは、ストラヴィンスキーの音楽と文学の類縁性はどこに見い出せるか。例えばエズラ・パウンドは「ストラヴィンスキーは、ぼく自身の仕事の面でいろいろと学び取ることができる唯一の現存する音楽家である」と言い、T.S.エリオットは「春の祭典」を聴きに行き、それについて次のように書いている。
「ストラヴィンスキーの音楽が永続的なものか短命なのかどうか、ぼくにはわからない。しかし、その音楽は、踊りのステップのリズムを、自動車の警笛のけたたましい音や、機械類の騒々しい音や、車輪のきしる音や、鉄や鋼を打ちつける音や、地下鉄の轟音や、さらには現代生活の他の野蛮な叫び声と化しているように思われる。しかもこれらのどう仕様もない騒音が音楽と化しているのである」
エリオットのストラヴィンスキー体験は彼が「荒地」に着手する直前のできごとであった。「過去と現在、古代と現代とを重置する方法、つまり神話や伝説や古典からの断片的な引用や引喩のコラージュによって構成され」た「荒地」はキュビズムや映画のモンタージュ技法との類縁性が指摘されることが多いが、ストラヴィンスキーの音楽からも深い影響を受けたと見ることもできる。
四月は残酷きわまる月だ
リラの花を死んだ土から生み出し
追憶に欲情をかきまぜたり
春の雨で鈍重な草根をふるい起すのだ。
(T.S.エリオット「荒地」西脇順三郎訳)
エリオットが「伝統と個人の才能」を書いたのは1919年のことであった。
「祖先から後世へ伝えるという伝統のただ一つの形式が、すぐ前の世代に属する人たちの残した成果をめくらめっぽうにさもなければおそるおそる守ってそのしきたりに追従することだとすれば、「伝統」はきっと力を失ってしまう。こういうたくさんの単純な流れがほんのしばらくのあいだに砂の中に埋もれてしまうのをわれわれは実際に見てきたが、新しい変わったものはくりかえしよりもましである。伝統というものはこれよりはるかに広い意義を持つものだ。伝統を相続することはできない、それを望むならば、たいへんな労力を払って手に入れなければならない。伝統はまず第一に、二十五歳をすぎても詩人たることを続けたい人なら誰にでもまあ欠くべからざるものであるといってよい歴史的意識を含んでいる。この歴史的意識は過去が過去としてあるばかりでなく、それが現在にもあるという感じ方を含んでいて、作家がものを書く場合には、自分の世代が自分の骨髄の中にあるというだけでなく、ホーマー以来のヨーロッパ文学全体とその中にある自分の国の文学全体が同時に存在し、同時的な秩序をつくっているということを強く感じさせるのである。この歴史的意識は一時的なものに対する意識でもあり、永続的なものに対する意識であり、また一時的なものと永続的なものとをいっしょに意識するもので、そのために作家が伝統的になれるのだ。またその歴史的意識によって作家は時代の中にある自分の位置、自分の現代性をきわめて鋭敏に感じることができるのである」
ストラヴィンスキーは1939年からアメリカに渡り、大学で教鞭を取りながら、機会があれば自作の指揮や演奏をしていた。1969年にはニューヨークに移り、その2年後の1971年に死去、ヴェネチアに葬られた。
「「イゴール・ストラヴィンスキー」彼はゆっくりと読んだ。「確かに、そうだ」同じようにゆっくり読んで、サクソン人が言った。「彼は、この墓地に葬られることを望んだらしい」アントニオが応じて、「優れた音楽家だが、時折、その楽想に非常に古めかしいものが感じられる。彼は有りふれた題材に想を求めた。たとえばアポローン、オルペウス、ペルセポネー、……。こんなことが、いつまで続くのだ?」「彼の『オイディプース王』を知っている」とサクソン人が言った。「第一幕の終わりの、グローリア、グローリア、グローリア、オイディプース・ウクソル! という個所はわたしの音楽にそっくりだと聞いた」「それにしても、ラテン語のテキストに基づいて異教的なカンタータを作るという妙なことを、なぜ思いついたのだろう?」とアントニオが言った。ゲオルク・フリードリッヒが、「当地のサン・マルコ寺院でも彼の『聖歌』が歌われたとか。つまり、われわれがとっくに捨てた中世風のメロディーが、いまだに聞かれているわけだ」「前衛と呼ばれている音楽家が、過去の楽匠たちがやったことに強い関心を示しているということだな。時にはそのスタイルを蘇らせようとさえしている。そういう意味では、われわれのほうがモダンでもある。わたし自身は、百年前のオペラや協奏曲がどんなものだったか、そんなことは、これっぽちも気にならない。自分の才能と感覚にしたがって、わたし自身の音楽を作る。これで十分だと思っている」(アレッホ・カルペンティエール「バロック協奏曲」)
→ジャン・コクトー「雄鶏とアルルカン」(「ジャン・コクトー全集4」東京創元社所収)
→「ニジンスキーの手記」(現代思潮社)
→「エリック・サティ文集」(白水社)
→岡田暁生「西洋音楽史」(中公新書)
→ヴラジミール・ジャンケレヴィッチ「音楽と筆舌に尽くせないもの」(国文社)
→Th.W.アドルノ「不協和音」(平凡社ライブラリー)
→ブークールシュリエフ「ストラヴィンスキーの統一性」
(ユリイカ1978年8月号特集=現代音楽)
→ピエール・ブーレーズ「クレーの絵と音楽」(筑摩書房)
→富士川義之「音楽と神話 パウンドとエリオット」
(現代思想臨時増刊総特集=1920年代の光と影)
→T.S.エリオット「伝統と個人の才能」(「文芸批評論」岩波文庫所収)
→T.S.エリオット「荒地」(「世界文学全集48世界近代詩十人集」河出書房新社所収)
→アレッホ・カルペンティエール「バロック協奏曲」(サンリオSF文庫)