
「野獣死すべし」1980年日本
監督 村川 透
出演 松田優作 室田日出男 鹿賀丈史 小林麻美
この映画は大藪春彦の同名小説が原作ということになっているが、内容は全く違ったものとなった。しかし、だからといって駄作というわけではなく、それはそれとして見るべきものが多い問題作たりえている。そうなったのは松田優作という個性的な俳優によるところが大きいだろう。
彼がこの映画のために体重を10㎏落とし、奥歯を4本抜いたのはよく知られているが、脚本も彼によって大きく変えられているのである。そのためこの映画は破綻寸前となっているが、言い換えれば、破綻一歩手前で踏みとどまることができたということでもあり、ここにこの映画の魅力もあるのである。
この映画はガード下の映像から始まる。スクリーンの奥から現れる一人の男。彼はすぐに刑事であることがわかるのだが、どことなく周囲を気にしているようだ。
次の非合法カジノの場面でも店員が外の不審な気配に気づき、そのことを報告している。
これら二つの場面からわかることは、この映画は見えない存在の気配を描くことでスクリーンの外を意識させているということである。
主人公伊達邦彦がようやく現れるのはその次の大雨のシーンからである。まるでスクリーンの外から中へ飛び込むように現れ、転げまわりながら刑事を刺殺し、非合法カジノを襲撃し、のたうちまわりながらもその売上金を手に入れる。
伊達邦彦。東京大学卒。射撃部。学生時代は図書館と名曲喫茶を往復するような生活で、半年でニーチェを読破し、チャンドラーやハメットを読み散らかす。通信社に勤務し、カメラマンとして各国の激戦地をくぐりぬける。日本に帰国後は通信社をやめ、知り合いの出版社で翻訳の仕事を手伝う。それ以外はクラシック音楽を聴くか、読書をするかで社会とはかかわりを持たないように生活している。しかしその心中では銀行強盗を企てている。これが我々のアンチ・ヒーローである。
ここで、この映画に使用された楽曲をみてみると、自宅のオーディオ装置から鳴り響くショスタコーヴィチ「交響曲第5番『革命』」、そしてほんの一瞬聞こえるモーツァルト「ピアノ協奏曲第21番」、レコード店の試聴室でのベートーヴェン「ピアノ協奏曲第5番『皇帝』」、コンサートホールでのショパン「ピアノ協奏曲第1番」(ピアノは花房晴美)。この曲にはショパンの、故郷への決別と飛翔への想いがこめられているという。
理想的な美は現実の汚辱にまみれなければならないとでもいうように、クラシックコンサートの後、伊達は全裸女性の自慰行為を眺めながらトマトジュースをちびちびと舐め、頭の中で萩原朔太郎の「漂泊者の歌」を吟じている。この詩はニーチェからの影響を強く受けたものであるが、この中には伊達とこの映画をとらえるための重要なキーワードが散りばめられている。例えば「かつて何物をも汝は愛せず」という詩句は、伊達の孤独な生活と結びつく。また、「石をもて蛇を殺すごとく/一つの輪廻を断絶して/意志なき寂寥を踏み切れかし」という詩句は、この映画の転回点の一つである、相棒の真田に向けられた「あの輪廻という忌まわしい長い歴史をたった一発の銃弾できみは否定してしまったんだ」という一節と結びつくだろう。
しかしながら、松田優作が脚本を書き換えた部分には、この映画と伊達にとって重要なキーワードがちりばめられているものの、超人思想を披歴した長広舌は概念が短絡したものでしかない。人を殺すことで神をも超越する?この思想に共感できるものは少ないだろう。こうして伊達邦彦は我々のアンチヒーローから逸脱し、何を考えているのかわからない存在になっていく。
萩原朔太郎の「漂泊者の歌」とニーチェというよりは、ドストエフスキー「罪と罰」のラスコーリニコフに近しい超人思想と、後半に出てくるリップ・ヴァン・ウィンクルの伝説(どんな狩りでも許されるという素晴らしい夢)はこの映画を破綻寸前でつなぎとめる紐帯の役割を果たしている。
日本映画史に残るロシアン・ルーレットの場面から伊達に撃たれるまで、伊達を追い続けた柏木は刑事として、つまりは体制側として伊達に対峙していたが、ついに伊達に勝つことができなかった。権力からも逃れてますます野獣性を開放していく伊達。我々を遠く置き去りにし、ここから映画は現実とも夢ともつかぬ、映画としか言いようのない展開を見せる。繰り返し挿入される戦場の惨劇と銃声、戦闘機の爆音。そして伊達は狂乱の中、自らが経巡った戦場の記憶と今ある現在を混沌の中に落とし込み、日常を戦場化していくのだった。
ラストシーンについて
伊達邦彦がコンサートホールで居眠りをし、一人きりで取り残されたとき、大声を2回出して自分がいる場所のリアリティを試す場面がある。リップ・ヴァン・ウィンクルの眠りのように、眠っているうちに何十年も経過してしまったのかどうか。
この映画のラストシーンは、伊達邦彦が見えない銃弾に撃たれ、もんどりうって倒れこむところで映像が止まり、カメラが次第に引いていくというものである。このシーンが「明日に向って撃て!」のラストシーンにインスパイアされたものだということは否定できないだろう。ブッチとサンダンスが外へ飛び出した瞬間、待ち構えていた州兵たちから一斉射撃を受ける。その射撃音は次第に遠ざかり、映像もまた次第に小さくなっていく。
西部開拓時代は反抗するものと抑圧するものとの関係がわかりやすいものであった。60年代後半であってもそれは同様で、反体制運動は権力によって抑圧されていった。この図式はしかし、1980年代の日本においてはすでにあてはまらないものになっていた。個人の中に奥深く内面化された管理、自らを抑圧するものたち、ニーチェ的に言えば現代の末人たちに反抗は抑圧され、野獣は殺されるのである。つまり、伊達邦彦を殺したのは、スクリーンの外で息をひそめている存在、つまり、映画を見ている我々なのである。我々が何食わぬ顔をして日常生活に戻るために、自らの野獣性を封じ込めるために、我々が伊達邦彦を殺したのである。










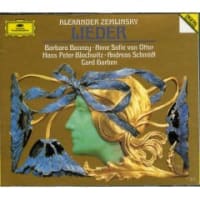
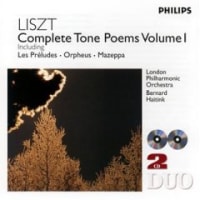
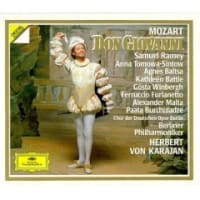
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます