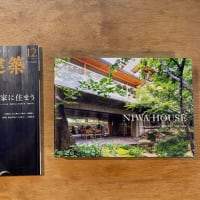今年の高松宮殿下記念世界文化賞は、デンマークの建築家、ヘニング・ラーセン。
ヘニング・ラーセン。
正直、それほど知っていた訳ではないのだけれど、作品はちらほら昔から見た事があった。
最近では、アーティストのオラファーエリアソンとの共作、レイキャビィークのホール『Harpa』が良くて、実は、オラファーエリアソンとして注目していた建築だった。

Harpa きらめくファサードが素敵。
昨日、恒例の講演会があって赤坂の鹿島へ。
今回はヘニングラーセン氏が高齢の為、体調不良で来日できず、代わりに40年来のパートナーのトロールズ・トロールゼン氏ら、数名のスタッフが来られていた。
第一部は、映画『ヘニング・ラーセン 光と空間の回廊』
第二部は、対談『ヘニング・ラーセン建築』を語る。 トロールズ・トロールゼン氏+馬場璋造氏
建築評論家の馬場璋造氏は毎年コーディネーターで入られている。
本当に、様々な場所でよくお会いし、お話をさせて頂く機会がある。素敵な方である。
ヘニング・ラーセンは1959年に事務所を開設し、いまや210名程のスタッフがいるらしい。
自分もそう思ったんだけど、デンマークの丹下健三的な存在とのこと。
アイスランド、シリア、サウジアラビアに支所があり、中近東の仕事が多いそうだ。
やはり若き日のサウジアラビア・デンマーク大使館や、サウジアラビアの外務省の仕事が繋がっているんだろう。
第一部の映画では、ヘニングラーセンが自身の作品を振り返りながら、建築論を語る、美しい映像の絵巻であった。
中東での仕事の光の扱いが難しかったと。北欧の光の考え方と真逆であるし、開口部には非常に時間をかけたそうだ。如何に光を効果的に遮断し、コントロールするか。
完成した作品は、穏やかに光が充満する、陰影の美しい石のたてものとなっていた。
昔は、アルネヤコブセンの事務所に在籍していたそうで、その後は、ヨーンウッツォンの事務所にもいた。
シドニーのオペラハウスで有名なヨーンウッツォンの事は非常に憧れがあったようで、特に誉め讃えていた。
最後に会った日の事を楽しそうに語る姿が印象的だった。

ヘニングラーセン自体は、穏やかな老人といった感じで、今は、床を白く塗って光の反射がきもちいい、お気に入りの自宅で猫に囲まれて生活している。
宇宙の存在、生き生きとした生命力を常に意識している。
開口部が重要、厚みでなく、その大きさ。
交流の場が建築には必要。
ガラスの魅力を感じる。時に写り込み、時に透けている不思議な存在であり、物質である。
光へ向け上昇するエレベーターを重要視している。
建築家は、批判精神、物事を整理をし、感受性を鋭敏に保つ事が重要だ。
などなど、多くの心に残る言葉を語っている。
最後に、コペンハーゲンのオペラハウスの事を話していた。

この物件のクライアントが芸術の領域に意見をし、自身のエゴの為に権力を行使する事に落胆しているとのことだった。
アメリエンボー宮殿に運河を挟んで対峙するこの建物は、地下5階、地上9階、総面積が41000平米。
500億円ともいわれる総工費で作られたビックプロジェクト。
そこには、1人の建築家ではとうてい抗えない、ハードパワーが渦巻いていたようだ。
形状は、ジャンヌーベルのルツェルン文化会議センターに非常によく似ている。

この写真がルツェルン文化会議センター。シルエットは酷似。
クライアントは、先に完成していた、それと同じ物を求めていたのかもしれない。
そこが、ヘニングラーセンを落胆させた部分なのだろう。
第二部のトロールズ・トロールゼン氏と馬場璋造氏のトークセッション。
異国でのコンペが多いが、気をつける事は何かという質問では、心をオープンに異国の文化をあらゆる手段をもって学んでいくということだった。常に0からのスタートで、毎回、新たにチャレンジすると。
実際にその国を歩き、実際に見て感じて知る。
直感的にも、科学的にも、人類学的にもあらゆる方向からアプローチする。
部外者であるからこそ、出来る事があり、開ける事があるそうだ。
オフィスはオープンオフィスで、移動式。意識的に、あまり固定的な場所で作業をしないようにしている。
これは、デンマークスタイルだそうだ。
ともかく、様々な事が感じられた二時間であった。
帰宅前に、一緒に行ったイタリア帰りの友人らとイタリアンを食す。
モツの蜂の巣部分のトマト煮が特に旨かった。
ヘニング・ラーセン。
正直、それほど知っていた訳ではないのだけれど、作品はちらほら昔から見た事があった。
最近では、アーティストのオラファーエリアソンとの共作、レイキャビィークのホール『Harpa』が良くて、実は、オラファーエリアソンとして注目していた建築だった。

Harpa きらめくファサードが素敵。
昨日、恒例の講演会があって赤坂の鹿島へ。
今回はヘニングラーセン氏が高齢の為、体調不良で来日できず、代わりに40年来のパートナーのトロールズ・トロールゼン氏ら、数名のスタッフが来られていた。
第一部は、映画『ヘニング・ラーセン 光と空間の回廊』
第二部は、対談『ヘニング・ラーセン建築』を語る。 トロールズ・トロールゼン氏+馬場璋造氏
建築評論家の馬場璋造氏は毎年コーディネーターで入られている。
本当に、様々な場所でよくお会いし、お話をさせて頂く機会がある。素敵な方である。
ヘニング・ラーセンは1959年に事務所を開設し、いまや210名程のスタッフがいるらしい。
自分もそう思ったんだけど、デンマークの丹下健三的な存在とのこと。
アイスランド、シリア、サウジアラビアに支所があり、中近東の仕事が多いそうだ。
やはり若き日のサウジアラビア・デンマーク大使館や、サウジアラビアの外務省の仕事が繋がっているんだろう。
第一部の映画では、ヘニングラーセンが自身の作品を振り返りながら、建築論を語る、美しい映像の絵巻であった。
中東での仕事の光の扱いが難しかったと。北欧の光の考え方と真逆であるし、開口部には非常に時間をかけたそうだ。如何に光を効果的に遮断し、コントロールするか。
完成した作品は、穏やかに光が充満する、陰影の美しい石のたてものとなっていた。
昔は、アルネヤコブセンの事務所に在籍していたそうで、その後は、ヨーンウッツォンの事務所にもいた。
シドニーのオペラハウスで有名なヨーンウッツォンの事は非常に憧れがあったようで、特に誉め讃えていた。
最後に会った日の事を楽しそうに語る姿が印象的だった。

ヘニングラーセン自体は、穏やかな老人といった感じで、今は、床を白く塗って光の反射がきもちいい、お気に入りの自宅で猫に囲まれて生活している。
宇宙の存在、生き生きとした生命力を常に意識している。
開口部が重要、厚みでなく、その大きさ。
交流の場が建築には必要。
ガラスの魅力を感じる。時に写り込み、時に透けている不思議な存在であり、物質である。
光へ向け上昇するエレベーターを重要視している。
建築家は、批判精神、物事を整理をし、感受性を鋭敏に保つ事が重要だ。
などなど、多くの心に残る言葉を語っている。
最後に、コペンハーゲンのオペラハウスの事を話していた。

この物件のクライアントが芸術の領域に意見をし、自身のエゴの為に権力を行使する事に落胆しているとのことだった。
アメリエンボー宮殿に運河を挟んで対峙するこの建物は、地下5階、地上9階、総面積が41000平米。
500億円ともいわれる総工費で作られたビックプロジェクト。
そこには、1人の建築家ではとうてい抗えない、ハードパワーが渦巻いていたようだ。
形状は、ジャンヌーベルのルツェルン文化会議センターに非常によく似ている。

この写真がルツェルン文化会議センター。シルエットは酷似。
クライアントは、先に完成していた、それと同じ物を求めていたのかもしれない。
そこが、ヘニングラーセンを落胆させた部分なのだろう。
第二部のトロールズ・トロールゼン氏と馬場璋造氏のトークセッション。
異国でのコンペが多いが、気をつける事は何かという質問では、心をオープンに異国の文化をあらゆる手段をもって学んでいくということだった。常に0からのスタートで、毎回、新たにチャレンジすると。
実際にその国を歩き、実際に見て感じて知る。
直感的にも、科学的にも、人類学的にもあらゆる方向からアプローチする。
部外者であるからこそ、出来る事があり、開ける事があるそうだ。
オフィスはオープンオフィスで、移動式。意識的に、あまり固定的な場所で作業をしないようにしている。
これは、デンマークスタイルだそうだ。
ともかく、様々な事が感じられた二時間であった。
帰宅前に、一緒に行ったイタリア帰りの友人らとイタリアンを食す。
モツの蜂の巣部分のトマト煮が特に旨かった。