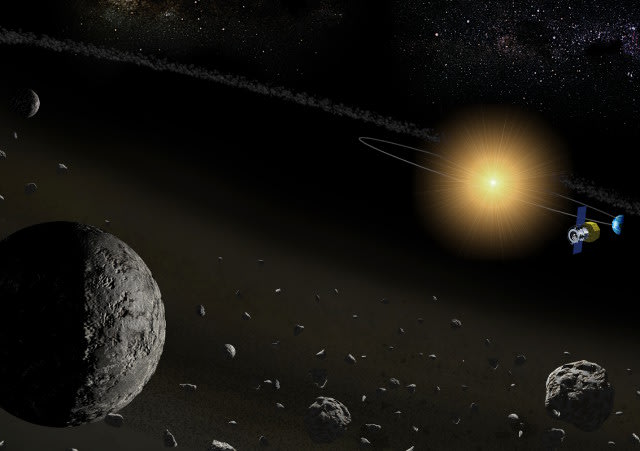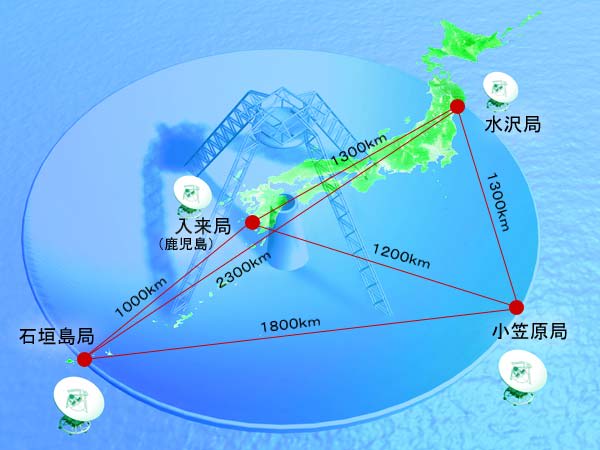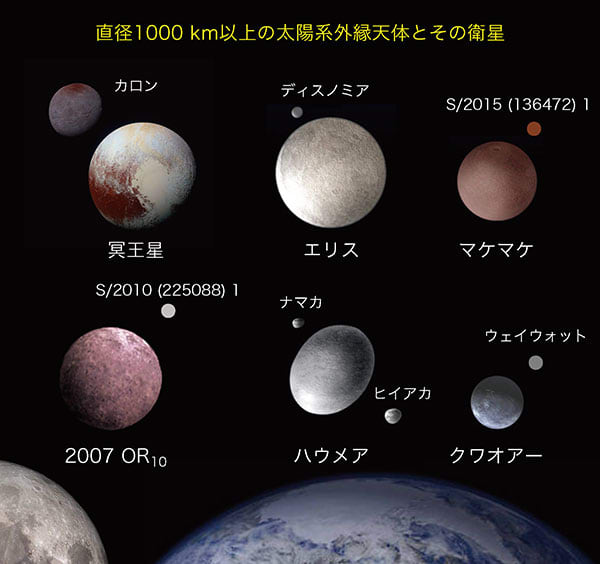岩石天体同士が高速で衝突した際に起こると予測されてきた“衝突脱ガス”現象。
この現象について、新たな化学分析法が開発され、火星で実際に同現象が起こり得ることが実証されたそうです。
岩石天体同士の衝突
太陽系の岩石天体同士が秒速数キロ以上の高速度で衝突すると、衝突地点の岩石は過熱され、含まれていた水蒸気や有機物などの揮発性成分が失われてしまいます。
このような現象は“衝突脱ガス”と呼ばれ、地球大気の形成や海の発生、6500万年前の恐竜絶滅に代表される環境大変動の原因として古くから研究されてきました。
これまで、天体衝突で発生する超高圧・高温条件を再現するのに有効なのは、“二段式ガス衝撃銃”と呼ばれる装置で実際に高速飛翔体を衝突させること。
でも、この装置だと加速時に発生する化学ガスが実験系を汚染してしまう問題があり、“衝突脱ガス”の研究で用いることができていませんでした。
今回、千葉工業大学惑星探査研究センターの研究チームは、化学汚染の影響を受けずに“衝突脱ガス”を分析する“2バルブ法”という新手法を開発。
この手法により、装置由来の化学汚染ガスを飛翔体質量の0.01~0.1%まで抑えることに成功したそうです。
火星の古い塩湖を想定した天体衝突実験
今回研究チームが実施したのは、“2バルブ法”による岩塩と二水石膏を用いた“衝突脱ガス”実験。
過去に干上がった火星の古い塩湖への天体衝突を想定していました。
そして実証したのが、火星への典型的な衝突の際に岩塩からは塩化ナトリウムの蒸気が、二水石膏からは水蒸気が発生すること。
これは、古い塩湖に固定された揮発性成分が天体衝突によって再び大気水圏に戻されることを意味するものであり、天体衝突が火星上での物質循環・化学反応を促すことを示唆する結果でした。
2020年末には探査機“はやぶさ2”が小惑星リュウグウの試料を持ち帰ってきます。
リュウグウもしくはその母天体が“衝突脱ガス”を経験している可能性があることを踏まえて、リュウグウを想定した模擬物質への“衝突脱ガス”実験も実施される予定です。
実験で得られる結果は、リュウグウの研究を進めるうえで不可欠な基礎データになると期待されているようですよ。
こちらの記事もどうぞ
赤外線天文衛星“あかり”が実現した、探査に行かなくても小惑星に水が存在するかを知る方法
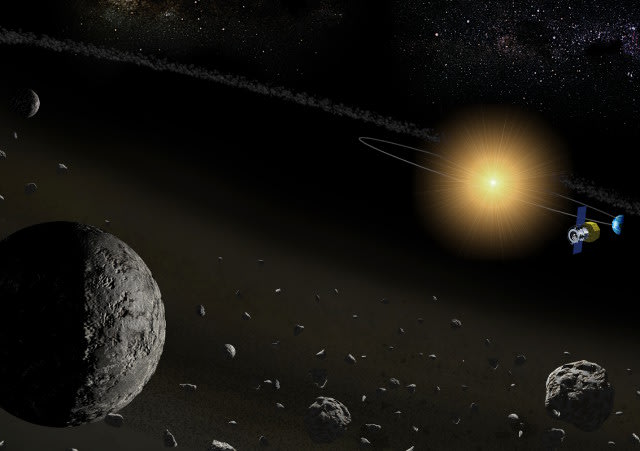
この現象について、新たな化学分析法が開発され、火星で実際に同現象が起こり得ることが実証されたそうです。
 |
岩石天体同士の衝突
太陽系の岩石天体同士が秒速数キロ以上の高速度で衝突すると、衝突地点の岩石は過熱され、含まれていた水蒸気や有機物などの揮発性成分が失われてしまいます。
このような現象は“衝突脱ガス”と呼ばれ、地球大気の形成や海の発生、6500万年前の恐竜絶滅に代表される環境大変動の原因として古くから研究されてきました。
これまで、天体衝突で発生する超高圧・高温条件を再現するのに有効なのは、“二段式ガス衝撃銃”と呼ばれる装置で実際に高速飛翔体を衝突させること。
でも、この装置だと加速時に発生する化学ガスが実験系を汚染してしまう問題があり、“衝突脱ガス”の研究で用いることができていませんでした。
今回、千葉工業大学惑星探査研究センターの研究チームは、化学汚染の影響を受けずに“衝突脱ガス”を分析する“2バルブ法”という新手法を開発。
この手法により、装置由来の化学汚染ガスを飛翔体質量の0.01~0.1%まで抑えることに成功したそうです。
 |
| 高速度衝突実験装置の概略図。 “2バルブ法”では2つのゲートバルブと二段式水素ガス銃を、 事前検討と予備実験で決定した時間差をつけて信号制御する。 これにより銃由来の化学汚染ガスを遮断し、 衝突発生ガスのみをガス分析装置に送って計測することができる。 |
火星の古い塩湖を想定した天体衝突実験
今回研究チームが実施したのは、“2バルブ法”による岩塩と二水石膏を用いた“衝突脱ガス”実験。
過去に干上がった火星の古い塩湖への天体衝突を想定していました。
そして実証したのが、火星への典型的な衝突の際に岩塩からは塩化ナトリウムの蒸気が、二水石膏からは水蒸気が発生すること。
これは、古い塩湖に固定された揮発性成分が天体衝突によって再び大気水圏に戻されることを意味するものであり、天体衝突が火星上での物質循環・化学反応を促すことを示唆する結果でした。
 |
| ガス分析結果の例。 (a)岩塩を標的にした場合に発生した塩化ナトリウム蒸気分圧の変化 (b)二水石膏を標的にした場合に発生した水蒸気分圧の変化 岩塩は31万気圧、二水石膏は11万気圧の衝撃圧力がかかった場合にガスを放出することが分かる。 この衝撃圧力は火星への典型的な天体衝突条件で容易に達成される。 |
リュウグウもしくはその母天体が“衝突脱ガス”を経験している可能性があることを踏まえて、リュウグウを想定した模擬物質への“衝突脱ガス”実験も実施される予定です。
実験で得られる結果は、リュウグウの研究を進めるうえで不可欠な基礎データになると期待されているようですよ。
こちらの記事もどうぞ
赤外線天文衛星“あかり”が実現した、探査に行かなくても小惑星に水が存在するかを知る方法