前回からのつづき
8月16日(月)
3日目のスタートです。
まずこの日、向かったのは立待岬。

函館山の南東から突き出た形となっている立待岬は、
寛政年間には外国船を監視するための台場が設置され、
第二次世界大戦中は要塞地帯法により一般市民の立ち入りが禁止されるなど、
昔から軍事的な要所として位置づけられておりました。

もちろん現在ではそんな事もなく、こうして自由に立ち入ることが出来ます。

函館山のふもとは海へと続く断崖絶壁となっており、
なかなかの景勝地でもあります。

天気さえよければ見えるはずの、津軽海峡の向こうにある
下北半島は雲がかかっていて望めませんでしたが、
函館市街から湯の川方面は眺めることが出来ました。

ところで、立待の名はアイヌ語のヨコウシが意味する「待ち伏せするところ」より、
「ここで魚を獲ろうと立って待つという所」という意味に
転じたところから来ているそうです。

夜になると、海上にはイカ釣り漁船の漁火が見えるそうですよ。

静かに波が押し寄せる静かな朝でした。

<この日の走行距離>ホテルからここまで3キロ
↓一日一回ポチッとクリックしてね
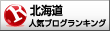
(北海道部門90位あたりにおりましたが、今日はどうでしょう?)
↓こちらもよろしく

8月16日(月)
3日目のスタートです。
まずこの日、向かったのは立待岬。

函館山の南東から突き出た形となっている立待岬は、
寛政年間には外国船を監視するための台場が設置され、
第二次世界大戦中は要塞地帯法により一般市民の立ち入りが禁止されるなど、
昔から軍事的な要所として位置づけられておりました。

もちろん現在ではそんな事もなく、こうして自由に立ち入ることが出来ます。

函館山のふもとは海へと続く断崖絶壁となっており、
なかなかの景勝地でもあります。

天気さえよければ見えるはずの、津軽海峡の向こうにある
下北半島は雲がかかっていて望めませんでしたが、
函館市街から湯の川方面は眺めることが出来ました。

ところで、立待の名はアイヌ語のヨコウシが意味する「待ち伏せするところ」より、
「ここで魚を獲ろうと立って待つという所」という意味に
転じたところから来ているそうです。

夜になると、海上にはイカ釣り漁船の漁火が見えるそうですよ。

静かに波が押し寄せる静かな朝でした。

<この日の走行距離>ホテルからここまで3キロ
↓一日一回ポチッとクリックしてね
(北海道部門90位あたりにおりましたが、今日はどうでしょう?)
↓こちらもよろしく





















































