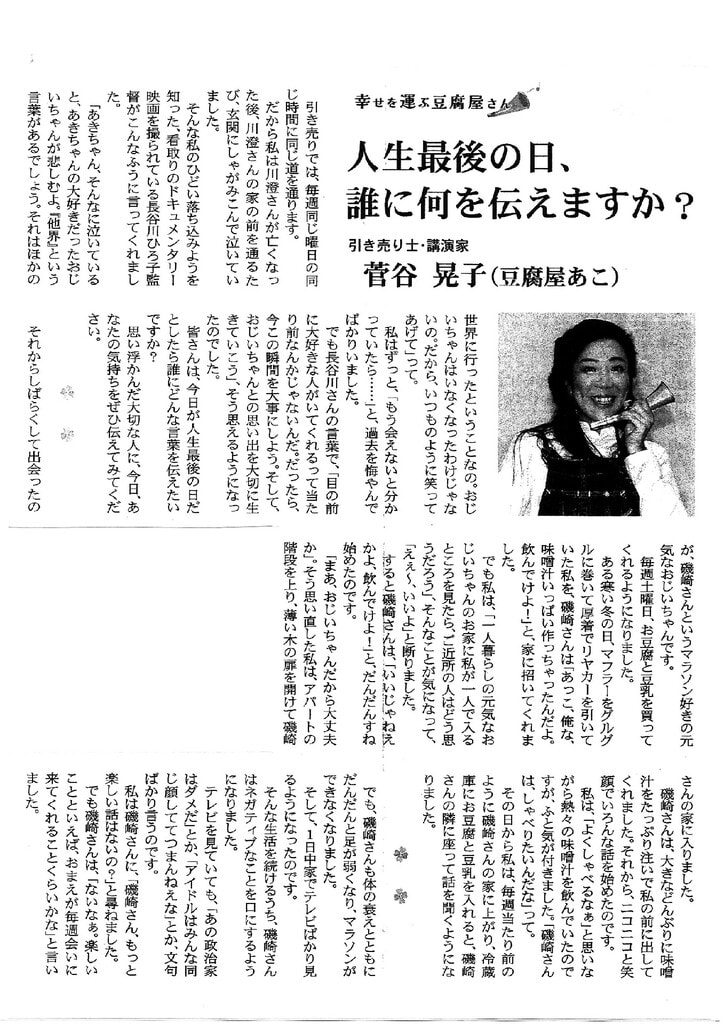あなたと会うと元気になる、という人になりたい
薬屋稼業をしていると、心の悩み事をカウンセリングすることがとても多いです。“病は気から”と申しますが、体調が悪いからとの相談も、その症状に合った薬なり滋養の漢方薬や健康食品をおすすめしてもなかなか効かないこともあります。そうした場合の根本の原因は心の悩みにありそうです。そこで、じっくりお話を聞き、心の悩みが原因と分かったら、全く別の漢方薬や健康食品をおすすめしています。すると、思いのほか良く効くことがしばしば。
そして、それより重要なのは、そうしたお客様に「あなたと会うと元気になる」と言っていただけるようなアドバイスができるか否か、です。
18年前に出版された、齋藤茂太(歌人齋藤茂吉の長男:故人:精神科医・文筆家)著『「あなたと会うと元気になる」といわれる人の共通点』、これを今一度読み直してみて、小生ももうちょっと親身になってお客様に対応せねばいかんなあ、と思ったところです。
この本には95話載せられています。その中から小生の独断と偏見で、読者の皆様に見てもらいたい話を10話選び、部分抜粋しました。これをじっくりお読みになれば「あなたも元気になる」こと請け合いです。
7 欠点をあげつらえば、長所を見失う
人の欠点をあげつらうのは簡単である。しかし、長所をきちんとほめるのは、意外にむずかしいものだ。このむずかしいことが、人を元気にさせるのである。
七十代のある婦人は今でも料理、裁縫をし、短歌に精進している。
「娘におだてられ、豚も木に登っているんですよ」と楽しそうだ。
彼女は娘さん家族と暮らしているが、みんなほめ上手なのだそうだ。
「おばあちゃんの料理がおいしい」「おばあちゃんの歌が載っていたんだよ」「これおばあちゃんが縫ってくれたの」と、娘や孫が世間の人に自慢するので、張り切らざるをえない。
「仕事を続けたい娘に、いいように使われているんですよ」という口ぶりはグチではなく、「まだまだ私がいなくてはダメね」という気概にあふれている。
こういう人を見ると、「年寄りはほめて育てよう」といいたくなる。
…欠点があるのは、あなたも私も同じ。しかし、自分には甘く、人には厳しい」という人は多いのではないだろうか。
他人の欠点ばかり見ていると、「あの人はずるい人」とか「だらしなくて」と嫌うことになるのだから、もう無理矢理にでも視点をずらして長所を見つけてみよう。
何かある。なければ、それは、あなたの「目のつけどころ」が間違っている。
「ずるいところもあるけど、それは、気の弱さからきているんだな。小心な人なんだな。はにかんだ笑顔はかわいいじゃないか」
そう思い始めると、その人との関係もかわってくるものだ。
10 心がケチな人よ、愛情の「出し惜しみ」はするな
お金の扱い方で「ケチな人」がいる。同じように、自分の心の扱い方で「ケチな人」もいる。よく目につくのが、「親切な心」を出し惜しみしている人だ。
電車の中で、お年寄りに席を譲ろう……と思いながらも、恥ずかしい。それで結局、「私がしなくたって誰かするだろう」と思って動かない。なんというケチな人だろう。
(中略)ある人の話だ。通勤する道にゴミが落ちている。拾えば気持ちもすっきりするのだが、「誰かがきれにするだろう。」とほうっておいた。しかし、半年経っても、そのゴミは朽ち果てながらそこにある。
それがどうしても気になって、ある日曜日に、意を決してゴミ袋をもって行って、捨てた。それだけのことをするのに半年もかかった。しかし次の月曜日からは、すっきりした気持ちで通勤できたとのこと。
(中略)みんな、気持ちはある。しかし、ケチなのか、なかなか実行できない。
(中略)心がケチな人ほど、心の中にすっきりしないものを抱えているものだ。
15 「いいなあ」と思ったところに、居場所がある
落語家をやっている医者という人がいるらしく、「病気は笑いで治す」のだそうだ。趣味の落語というより、師匠に弟子入りして、名前ももらった本格派らしい。こんな医者なら、患者さんも元気が出るだろう。
何かやりたい、趣味を持ちたいとは、誰もが考えている。
ただ、時間がない、経済的に苦しいなどの理由ならまだしも、「今さらやっても遅いのでは」と考える人がいるから困る。いくつになっても遅いということはない。また、趣味なのだから飽きてもいい、と考えてはどうか。
昔からやりたかったことを、とりあえず始めてみるのも手だ。
五十歳にしてピアノをやり始めた知人(男性医師)がいる。
子どもの頃、母親にいわれてピアノを習ったが、嫌で嫌でたまらなかった。音楽は好きだったが、母親にがみがみいわれるのがつらく、反抗してやめた。
そのまま実家に置かれた、誰も弾かないピアノを見るたびに、「弾けたら楽しいだろうなぁ」と思い続けて40年もたっていたのだ。
「でも、こんな気持ちのままで一生を終わりたくないと思ったのです」
せめて一曲ぐらいは弾けるようにと、大決心をし、病院から近い教室に入ってみたら、「この年になって、覚えは悪いけど、新しいことを覚えるのは楽しい。今まで以上に音楽を聞くのが楽しくなった」のだそうだ。
教室に来ているのは3歳の子どもから、60代の女性まで幅ひろい。初めての発表会では幼稚園の子の次に弾いたり、よその子に受験の相談をされたりと、ピアノ教室は、「医者ではない自分」の居場所のような感じがするらしい。
「初めは恥ずかしいと思ったけどね、なに、誰も私に上手になれなんて期待もしていないから、幼いときに習ったより楽な気分でいける」
楽な気持ちでやれるから趣味なのである。深刻に考えないことだ。そのうち彼も、「病気はピアノで治す」といい出すかもしれない。
21 迷い込むな、逃げ場をつくれ
仕事以外に夢中になれるものがあれば、おおらかな気持ちでいられるものだ。
スキー好きの知人がいる。もうだいぶ年はとったが、冬は休みになると、ひとりスキー場へ向かう。
「とにかく滑っている間は無心になれるのがいい」
のだそうで、…くよくよと悩んでいたこともすっかり消えてなくなってしまうという。
雪のない季節は、…嫌なことがあると、「目をつぶってスキーで滑っている体の感覚を思い出すんだ。そうやって心を落ち着かせる…」のだそうだ。
また、知人がひらいている句会には、サラリーマンが集まっている。そこでは、人事の悲哀、家族への思いやグチを俳句にして競っては、笑い合っているということだ。みんな、俳句のねた探しをしているから、家庭でも会社でも観察は怠りなく、何かあると、「俳句にしてやれ」と思うのだそうだ。
頭下げ ありの数かぞえる はげ頭
ある倉庫勤務の人が、失敗を謝っている自分の姿を詠んだものとか。…
別の世界を持つことは、自分に逃げ場をつくることにもなる。逃げ場がなければ、落ち込んで、傷ついてもなかなか癒されず、立ち直りにくいだろう。
逃げ場があるから、笑顔でいつもの生活に戻り、楽しんで生きようという元気にもつながるのだ。そう考えれば、趣味は健康のもとだ。
趣味があるから、嫌なことがあっても、自分の心をむしゃくしゃさせないですむ。すぐに気分転換ができる。人生の袋小路に迷い込むこともない。これが、ありがたい。
26 笑顔でいたほうが、うまくいく理由
「人を元気にさせる技術」といえば、まず笑顔だ。
赤ちゃんを思い出してほしい。愛らしい笑顔で大人たちもホッとし、元気にさせてもらっているではないか。もしこの世に、赤ちゃんがひとりもいなくなったら、大人たちは生きていく気力もなくなっていくのではないだろうか。
看護婦さんの笑顔もいい。夜中にナースコールを呼んでも、嫌な顔ひとつせず、「どうしましたか」と来てくれる。
評判の悪い病院というのは、看護婦さんの評判が悪い所が多い。
評判が悪い看護婦さんも、仕事は懸命にやっているのだろう。夜勤もあり責任も重い彼女たちに「にこにこしなさい」というのは酷かもしれない。「忙しいのに、いちいち愛想よくしていられないわ」という気持ちにもなるだろう。
しかし、仕事は熱心なのに人に好かれないというのは、大いなる損である。愛想のいい人に変われなくても、まずにこやかに挨拶をするように心がけてみてはどうか。それだけでも、だいぶ評判は上がるはずだ。
誰にもさわやかな挨拶をする新米の看護婦さんがいた。気のきいたことをいえるタイプではないが、病院に来ると患者さん一人ひとりに元気よく笑顔を振りまくので、あっという間に人気者となり、彼女が休むと、
「あの看護婦さんはいないのかね、病気なの?」
と、逆に心配されるようになる。こうなれば、点滴の針がうまく刺さらなくても、患者さんは大目に見てくれる。普段からぶっきらぼうで笑顔のない看護婦さんだと、
「何やってんだ、看護婦代えろ」
と怒りだす患者さんもいる。
どっちが得でどっちが損かは、いうまでもあるまい。普段の笑顔というのは実に大事なのだ。
27 福の神をだまして、いい面をつくろう
…ある老舗のお菓子屋…今では押しも押されもせぬ女将さんだが、実家はサラリーマンの家だった。商家へ嫁いでみると…アテがはずれて、ほとほと参って実家に帰りたい、でも帰れないと迷っていたとき、隠居していた夫のおばあさまに、こういわれたそうだ。
「そんな暗い顔していたら、寄って来る福も逃げていってしまいますよ。…1年間笑顔で頑張ってみたらどうか。疲れた顔は隠して、本心なんて人には絶対見せないぞと、やってみなさい。福の神様にも嘘をつくつもりで」
福の神様をだまして面つくれ、という言葉がおもしろくて、次の日から笑顔と挨拶だけは心がけたという。
案の定、お嫁さんの評判はあがり、客も、「いい人がきたわね」と話していくと、お姑さんたちも機嫌がよくなり、店の人たちの態度も変わってきた。
「福の神様をだますつもりで商売用の笑顔をつくってやってきたつもりだけど、今ではこれが地になって、落ち込んでいても、人様の前で素直に落ち込めないのが難点ですわ」
と笑う。まるで女将さんが、福の神になってしまったようだ。…
34 微笑みは、元気の特効薬
笑顔のいい人は、人の心に新風を吹きこみ、人を元気にしてくれる。あの人の笑顔を見るだけで、「気持ち」が元気になる……という人が、あなたの身近にいることを祈る。
(中略)
もうひとつ。自然の微笑みもまた、私たちを元気にしてくれる。
俳句の歳時記に「山笑う」という春の季語がある。
春の山を形容する言葉で、北宋の山水画家の文「春山澹冶(たんや)にして笑うがごとく」から取ったものらしい。
たんやというのは、「あわくなまめかしい」ということらしいが、私には春の山は静かに微笑むというより、「それ、春だぞ」という楽しげな子どもたちの笑い声が聞こえてくるようで、この「山笑う」という言葉が好きである。
もし、あなたが少し笑顔を忘れていて、不幸にも「笑顔が似合う人」も周りにはいないというときには、ひとりで自然の中に出かけてみよう。
自然の微笑みも、またあなたを元気にしてくれるはずだ。
35 イヤミをいわれたぐらいで、いちいち落ち込みなさんな
イヤミを言われたら「イヤミ返し」するぐらいの気力を持ってほしい。
ある家の嫁は結婚したばかりのころ、たまに会う姑のイヤミにしゅんとなったり、いらいらしたり…で、腹が立ってしかたがない。(中略)
なぜ、姑はイヤミばかりを言うのか。折にふれて考え、はっと気がついたことは、「心のさびしさ」だった。(中略)
それから数年後、子どももでき、肝っ玉が少し座ってきた嫁は、イヤミに落ち込まなくなった。何かいわれても、「私、下手だから、お義母さんやって」と笑い飛ばす。それにつれて、イヤミは減ってきたそうだ。
イヤミというのは、相手が落ち込んだり、怒ったりするから「やりがい」があるという面もあるのだろう。いちいち反応していたら、相手は増長するばかりだ。イヤミをいわれても、
「何が気に入らないのか。遠まわしにいわれても、バカだからわかりません」
と、切り返す言葉を吐けるくらいに強くなろう。そうなって初めて、姑と嫁は対等になり、信頼できる家族になっていくのではないだろうか。
67 食べよ!されば開かれん
ある家庭に招かれて食事をしたときのこと。奥様は料理好きということで、たくさんの手料理が並んだ。なかなかおいしそうだと思って食べ始めると、
「これには胡麻が入っていて、どこそこから取り寄せて……」
奥様が話し出した。(中略)と、食材の由来から、それが健康にどんなによいのかをひととおり話した。
知人である夫は、そんな話題は何回となく聞かされているのであろう。(中略) 奥様は、私に「集中攻撃」だ。
実は私もおいしければ何でもいい派である。おいしく食べるのが健康のもとだ。
さて、そのときの料理はおいしかったかというと、奥様の話を聞きながらであまり印象に残っていない。
食事をすすめるときには、講釈はいらない。
「おいしいから、食べてみて。うちの定番料理です」
とすすめてくれれば、こちらから、
「おいしいですね。何を使っているのですか」
と聞きたくもなってくるものだ。
若い知人が、恋人の家に食事に呼ばれた。初めて恋人の父親に会うので緊張していたが、知人はラクビー選手というだけあって大食漢である。「おいしい、おいしい」と恋人が恥ずかしくなるくらい元気よく食べまくったそうだ。
父親は一回で、彼を気に入ってしまった。「実にうれしそうに飯を食う奴だ」というわけだ。きっと見ているほうがうれしくなる食べっぷりだったのだろう。
「食べよ、されば開かれん」だ。喜んで食べるだけで、人は人を元気にする。
75 おしゃべりの楽しさは女性たちに学ぼう
あるホテルのロビーでのこと。後ろに陣どった奥様たちの声が聞こえてくる。
「本当にうちの兄嫁はずうずうしくて、ああだこうだ……」
「ずうずうしいといえば、本当にうちの姑はああだこうだ……」
「でも、このごろの私って若いって、みんなにいわれるのよ、これも海草の健康法のおかげよ、ああだこうだ……(と健康法をひとくさり)」
健康法で話は盛り上がっているのに、いきなり次は、
「ところで、甥の結婚式でね」
と話が弾み、弾んでどこへ転がるのやら……と思うのだが、四人の奥様方がただただ好きなことをしゃべり、相手が話しきらないうちに、もう自分の話を始め、話し終わらないうちに、もう次の人の話が始まっている。声はますます大きくなり、その勢いは止まるところを知らない。
こんな一方的な会話がえんえんと続くのも困ったものだが、しばらくすると、
「今日は本当に楽しかったわ、ねえ」
「うん、胸がスカッとしたわ」
と口々にいいながら、満面の笑みをたたえて出て行った。一方的なおしゃべりでも、ストレス解消になったようである。おそらく、気心の知れた者同士の集まりだから会話が一方通行でも盛り上がれるのであろう。
しかし仕事場で、きちんとした話をしようとするとき、自己主張の強い人、自慢話ばかりする人……などとは、なかなか会話が成り立たない。
ある仕事のことで上司に相談に行ったら、「若いとき、僕はこうだった。こんなことも分からないなんて、今の若いもんは、私のときはああだこうだ……」と1時間半も話したあと、「話は何だっけ? ああ、そうだったね。まあ……自分で考えるんだな」といわれ、ますますストレスがたまったという。
おしゃべりの楽しさについては、女性たちに習ったほうがよさそうだ。
95 人と比べるな!「むかしの自分」と比べよう
良寛さんも、酒を飲んで気が大きくなり、ぺらぺらしゃべりすぎ、翌日に
「なんだか自慢話めいたことを話してしまった。理屈をこねていたな」
と恥ずかしくなって、反省する日がたびたびあったのだろう。
それでも自分を律し、明日はもっとよい人間でいたいと祈ったことだろう。そういう日々を越えて、あの無邪気な良寛さんをつくったのだ。
「本当にあの人はいい人だ。素敵で、会えば元気になる」と思われる人も、生まれたときから純粋さを持っていたわけではなく、悩み、妬み、落ち込み……などを自分なりに克服して得た「明るさ」なのではなかろうか。
生きるというのは、それだけで修行みたいなものだ。宗教家や哲学者ではなくても、「自分は何で生きているのだろう」と思うことは一度はあるだろう。生活の雑事の中で悩み、苦しみはつきることがない。
そんな中で、会えば元気にさせてくれる人は、あなたにとってかけがえがない財産だ。そんな「人を元気にする人」の特徴を見ると、悩みながらも、
「自分に素直に生きよう」
と心がけている人だ。だから、人と比べたり、妬んだり、グチをいったりしない。そこが、人を安心させてくれる。
誰のせいにもしない、自分がつくる生活、自分がつくる人生、人と比べてああだこうだといったところで何の意味もないことを心得ている。
ここで忘れてはならないことは、
「良寛さんも、若いときにはいろいろ失敗をし、恥をかいてきた」
ということだ。私たちには「子どもと鞠をついて遊んでいるやさしい人」というイメージしかないが、それは「晩年の姿」である。
良寛さんも、あなたと「同じ年」のときがあった。良寛さんの20代はどうだったのか、30代は……40代は……と、今の自分の年と照らし合わせて想像してみよう。それだけで、じゅうぶんに楽しい時間が過ごせよう。
どうしても人と「比べてしまう」という人がいる。人と比べて「自分は……」と考え、自分の悩みを自分で大きくしている。そんな、「比べ癖」の治らない人は、思いきって、「むかしの自分」と比べてみてはいかがか。
生まれてからこれまで、自分がどのように「進歩してきたか」「何ができるようになったか」をじっくりと検証してみよう。
●5年前にはできなかったことが、今は簡単にできる
●2年前、どうしてあんなことで悩んでいたのだろう
●去年は失敗したが、今年は楽々と成功した
……と、自分で獲得したものをひとつずつ並べてみよう。トロフィーを棚に飾るように、である。
これまた、じゅうぶんに楽しい時間を過ごせるのではあるまいか。なかなか楽しい時間なのではあるまいか。
そうやって、また元気にやっていこう。
いかがでしたでしょうか。これで「あなたも元気になる」心の状態に大きく近づいたことでしょう。そして、日頃これを心がければ、「あなたと会うと元気になる」という人に変身することができましょう。