戦争は必ずしも、正しい者が勝って悪しきものが負けるとは限らない。
勝った者が正しき者として君臨する。
負けた者がその事で迎合してしまうのです。
それが正しい歴史となってしまっては駄目なのです。
勝った者が正しき者として君臨する。
負けた者がその事で迎合してしまうのです。
それが正しい歴史となってしまっては駄目なのです。
南京軍事法廷
終戦の翌年、昭和二十一年の春であった。
陸軍大尉向井敏明氏は、長い戦場生活を終え復員し、宇治山田市の自宅に落ち着いた。そして三月ほどがたち、やがて夏を迎えようとする六月の末に、一人の警察官がやって来たのである。
「実は米軍が、向井敏明という人を捜しているのですが、あなたは北岡さんですよね」
と、言う。この時すでに、彼は北岡家の養子となっていたからで、それで向井敏明という人物の存在がなかなか分らなかった、というのだ。
「それなら、北岡さんでいいじゃないですか」
と、警察官はつけ加えた。出頭しなくても、それで通してしまったらいい、ということだ。この頃は、巣鴨の拘置所には多くの戦争犯罪人容疑者が収容されていたし、横浜の軍事法廷ではBC級の戦犯が次々と裁かれ、すでに極刑も相次いでいた。そうした状況下での、米軍呼び出しである。警察官も同じ日本人として、逃亡をすすめたくなるのも人情であった。だが向井氏は、「いや、私は別に悪いことはしていません。それに、私が行かなかったため困る人がいてもいけませんし、出頭しましょう」
と、答えたのである。まっ正直な彼は、戦犯裁判にも正義はあると思っていたのかもしれない。
だがすでに横浜の軍事法廷でも、無実の青年が死刑になった例は多い。「私は貝になりたい」という劇(ドラマ)が後に有名になったが、これなどもそうした裁判の実情をよく物語っている。
七月の一日、向井氏は上京し市ヶ谷にあった米軍の検事局へ出頭したのである。心配した実弟の向井猛氏が同道したのだが、米軍の尋問は呆っ気ないほど簡単に終った。そこでは南京攻略戦当時の新聞記事について聞かれたのだが、その百人斬りの話は記者が勝手に書いたもので、事実ではないと説明すると、すぐ分ってくれたのである。そして、「記事によって迷惑を受けるということは、米国でもたくさんあります」
と、パーキンソン米軍検事は、かえって慰めの言葉をかけてくれたのであった。それほど記事には信憑性がないということだが、またここには正義がいまだ存在したということでもあった。
それから一年の余、向井氏とその家族は平和な日々を送り、このまま何事もなく過ぎていくかに見えた。しかし昭和二十二年の夏も、ようやく終ろうとする九月の二日に、またも向井氏は呼び出しを受けたのである。
しかも今度は、いきなり地元の警察に留置されるという、ただならぬ雰囲気であった。後にして思えば、はじめから重要戦犯としての指名が、中国側からなされていたものとみえる。
やがて向井氏は東京へ護送され、巣鴨の拘置所に拘留された。容疑はやはり前回と同じ、南京戦当時の百人斬りの記事が元で、それが残虐行為にあたるというらしい。弟の猛氏が、やっとの思いで面会にこぎつけると、戦犯用の囚人服を着せられた向井氏は、
「とにかくあの記事は、本当のことではない、ただの創作なんだということを、記事を書いた浅海(あさみ)という人に証明してもらってくれ。それと、戦友たちの証言もほしい」
と、小声でしかも口早に言う。盗聴マイクがありうっかりしたことは言えないというのだ。やはりかつてない緊張した雰囲気であった。ではその問題の記事というのは、いったいどのようなものであったのか。
(紫金山麓にて十二日浅海、鈴木両特派員発)
南京入りまで「百人斬り競争」といふ珍競争をはじめた例の片桐部隊の勇士、向井敏明、野田巌両少尉は、十日の紫金山攻略戦のどさくさに、百六対百五といふレコードを作って、十日正午両少尉はさすがに刃こぼれした日本刀を片手に対面した。
野田「おいおれは百五だが、貴様は?」向井「おれは百六だ」両少尉アハハ。結局いつま
でに、いづれが先に百人斬ったかこれは不問、結局「ぢゃドロンゲームと致さう、だが改め百五十人はどうぢゃ」と忽ち意見一致して十一日からいよいよ百五十人斬りがはじまった。
十一日昼、中山陵を眼下に見下ろす紫金山で敗残兵狩真っ最中の向井少尉が「百人斬りドロンゲーム」の顛末を語ってのち、「知らぬうちに両方で百人を超えていたのは愉快ぢゃ。俺の関の孫六が刃こぼれしたのは、一人を鉄兜もろともに唐竹割りにしたからぢゃ。戦ひ済んだらこの日本刀は貴社に寄贈すると約束したよ。十一日の午後三時、友軍の珍戦術、紫金山残敵あぶり出しに、俺もあぶり出されて、弾雨の中を「えい、ままよ」と刀をかついで棒立ちになっていたが、一つもあたらずさ。これもこの孫六のおかげだ」
と飛来する敵弾の中で、百六の生血を吸った関の孫六を記者に示した。
これがその当時、東京日日新聞に載った記事なのである。だがこれを読んでまず感ずることは、話があまりにも荒唐無稽、講談本ならいさ知らず、真面目に戦況を案じている読者にしたら、肩すかしを喰ったような記事だということだ。
人問を鉄兜ごと真向唐竹割りに切れるものかどうか、そんなことは子供だって分ることだ。武勇伝をでっち上げようと思ったのだろうが、実際に日本刀を手にしたことのある人問なら、こうした発想は決して出てこないものだ。
それに一人の敵を倒すということが、どんなに困難なことかに思いをいたすからでもある。ばったばったと敵を斬りまくるなどというのは、あくまで日本刀を知らぬ人問の創り話でしかないのである。
当然ながら、当時すでに良識ある人々から、この記事にたいしては痛烈な批判がなされていた。
いかに軍国調華やかな時とはいえ、そうした声が雑誌などに出てくるのは当り前で、新聞は面白ければいいというものではない。
米軍の検事が、記事に現実性なしと判断するのも当然であった。
しかし今回は状況一変し、その記事を証拠として残虐行為の責を問われそうなのである。となれば、記事を書いた浅海一男氏自身に、ただの創作であったと一筆書いてもらうほかはない。記者として立場上具合の悪い思いをさせることになるが、今はそんなことは言っていられない。
実弟向井猛氏の証言集めの行脚が、この日から始められた。もちろんまっ先に訪れたのは、毎日新聞の浅海一男氏であったが、何故か氏にはなかなか会えなかった。そしてやっと会えたと思ったら氏は言を左右し、何としても記事は創作であったという、大事な一行を書いてくれないのである。
そうこうしているうちに、向井敏明氏は南京へ送られてしまった。そそして、市内の戦犯留置所へ入れられたのである。そこにはすでに三十人ほどの日本人が戦犯容疑ということで収容されていたのだが、新たに送られてきた向井氏と野田毅氏、そしてもう一人同じような三百人斬りという容疑の田中軍吉氏、この三人は初めから他の人々とは扱いが明らかに違っていた。
やはりこの二人は、南京大虐殺の犯人とすることで、中国側にとっては重要な戦犯だったのである。
十一月六日、第一回の国防部 審判戦犯軍事法廷なるものが開かれた。
法廷は、南京飛行場のすぐ前にある洋風の大きな建物で、旧日本軍の防疫給水部が入っていたところであった。他の人々は皆、いずれも収容されている建物のすぐ二階が法廷にあてられていたのだが、法廷からして三人は別格の扱いであった。
この三十人ほどの人々の中には、香港総督だった磯貝廉介、北支軍参謀長の高橋亘氏など中将が四人いたし、男装の麗人と言われた川島芳子なども、一時ここに収容されていたという。だが中国側にとっては向井氏たちのほうがはるかに重要人物だったのである。彼らがいかに南京事件なるものを立件しようとしていたかが、こうしたところからもよく窺い知れるのであった。
法廷は普通の裁判所と同じように、前の一段高いところに五人の裁判官が並んでいた。中央が裁判長の石美瑜少将、そして左右に二人ずつ大佐級の法務官が並ぶ。また検事と弁護人、それに通訳もつけられているから、一応外見上からは法廷としての体裁は整えていた。
だがその内容たるや、とても法廷などと言えるようなものではなかった。もっともこれは、南京の法廷だけではなく、他の上海、広州などの戦犯法廷とて同じだが、そのでたらめさ、いい加減さはとても尋常一様のものではなかった。それは、これら裁判経験者の手記を見ても、また話を聞いても、よくうなずけるのだが今はそれを詳述している暇はない。
とにかく二時間ほどの問、単なる尋問なのか公判なのか、さっぱり分らぬ進行ぶりで、ただがやがやとしているうちに終ってしまった。中国人の弁護人が、三人の主張を代弁してくれるはずなのだが、それもどうであったのかよく分らない。
たとえ言葉は分らなくとも、通訳がいるのだから、通常の公判としての秩序が保たれていれば、およその見当はつくはずである。とにかく、何とも言いようのない裁判ではあった。
十日ほどたつと、第二回目が開かれたのだが、この日も状況は似たりよったりで、ただもう彼らどうしが互いに言い合っているうちに終ってしまった。もちろん三人の主張は、記事はただの創作であるということ、それに向井氏は負傷中で、前線にはいなかったこと等、弁護人を通じて強く主張したのであった。いや、それは確認できないから、したはずであったとしておこう。
結局三度こうした法廷が開かれただけで、裁判は終りだという。後は一週間後に、判決が下されるがら、それを待っだけだというのである。
昭和二十二年十二月十八日、判決が言い渡された。向井敏明、野田毅、田中軍吉の三人全員が死刑であった。
四日の後、二十二日にはその判決文なるものが三人の手元に届けられたのだが、それには、「百人斬りという残虐なる獣行によって、日本女性の関心を買おうとしたことは、現代人類史上聞いたことがない」
と、ある。武勇をたてて有名になり日本に帰ったおり、女性にもてようとしたのだということらしい。野田毅氏の手記によれば、「これを読んで、思わず吹き出してしまった」とあるのだが、これが結局死刑を言い渡すための骨子となっているのだから、とにかくいい加減であることは間違いない。
だがそれにしても、浅海一男氏がこんなよた記事を書きさえしなければ、南京大虐殺の犯人とする口実を、彼らに与えることはなかったのだ。とにかくその記事が唯一の証拠であり、起訴の口実となっているのだから。
こうして三人は、南京大虐殺の実行犯として死刑を宣告された。最高責任者としては、すでにこの年の四月処刑された第六師団長の谷寿夫氏がいる。これで南京大虐殺は、実際にあったことだと主張するお膳立てができたことになる。
しかし谷寿夫氏は、第六師団長である。それに属するのは田中軍吉氏一人であり、向井、野田両氏は十六師団所属である。こうしたところも、辻棲は合っていない。とにかく、たとえまともな審査をしたとて、二度や三度の法廷で、いったいどれだけのことが分るというのか。ましてその一回一回があのとおりの運用である。そして三人とも死刑というのだから、これは法廷ではなく、まさに報復への儀式でしかなかった。
判決後も向井氏は、
「あの記事は創作であるということを、現在執筆した記者に証明してもらっている。間もなくそれらの書類が届くと思うので、それから上訴申弁書を提出する」
との申し立てを行なった。こうすれば、その間は刑の執行ができない。そして書類さえ届けば、無罪は証明される。
判決後、三人は死刑囚として他の人々と離され、別の房に移された。だが幸いにも、同じく収容されていた人々との面会や差し入れは許されたのであった。現在島根県におられる小西正明氏も、三人を最後まで励ましたお一人だが、特に小西氏は、浅海氏の証明書を早く送るようにと、越田に柱む弟の向井猛氏に幾度も航空便を出していた。
当時は航空便の費用もままならず、小西氏は自分の持っていた背広を看守に売り、それでその費用を捻出していたのであった。憲兵であった小西氏は、私服も常備していたのである。また台湾出身者は、向井氏らの主張を入れた申弁書を書き、小西氏がそれを清書したりもした。
とにかく、同胞相援けるで、死刑判決後も皆で協力し、三人の死刑撤回を目指したのであった。
そして時には、向井氏の好きな煙草や甘い物まで差し入れしたりと、背広を売った金は、こうして最後まで役にたったのであった。
そして、その待望の郵便物が着いたのである。皆は、思わず歓声をあげた。小西氏も万感の思いをこめ、その封を切ったのである。それは小西氏への返書という意味からか、宛名が小西氏の名になっていたからである。
しかし、その歓びは、たちまち打ち消されてしまった。それは、重要な「記事は創作であった」という字句がどこにもみられなかったからである。
「そんなはずはない」
と、幾度も読み直してみたが、やはり書いてはない。浅海一男と署名捺印したその証明書には、二人は人格高潔な将校であったとか、記事は向井、野田両氏から聞いて書いたが、その現場は見ていないとか、すでに米軍によって不問に付された、等が書いてあるだけで、大事な創作の二字は書かれていないのであった。実弟猛氏の再三の頼みにもかかわらずついに浅海氏はそれを書いてくれなかったのである。
しかし同封された、富山武雄大隊長が書いてくれた証明書には重みがあった。それにはこう記されていた。
一、向井少尉は、無錫で一度浅海記者と会っただけである。
二、その後十二月二日、砲弾によって脚および右手に盲貫弾片創を受け、看護班に 収容され、十五日まで治療を受けていた。
三、向井少尉は聯隊砲指揮官であり、白兵戦に参加する機会などない。
(以上証明書の要約は鈴木明著『南京大虐殺のまぼろし』より)
これらは、かねてより向井氏自身が主張していたもので、もちろん書類にして提出もしていた。
それを、事実であると証明してくれたのであった。
百人斬りをやったというその間、向井少尉は後方で手当を受けていたのである。そして隊に復帰したのは、南京陥落後の十五日であり、しかもその時も担架に乗せられての帰隊であった。
敵弾飛び交う紫金山の麓で、日本刀を見せながら百人斬りを語った、などというのは、これをもってしても、明らかに事実ではないことが分る。
またこれはきわめて常識的なことだが、砲兵小隊長が白兵戦を演ずる機会などそう滅多にあるものではない。砲兵は兵隊ですら、満足に小銃も持っていない。ましてその指揮官が、奇襲でも受けないかぎり、敵と直接渡りあうことはありえないのだ、そねに、野田氏とて同じで、大隊副官の野田少尉が、これまた接敵の機会などないことも明白である。副官は大隊長のそばにいて、その任を補佐しなければならないのだ。
とにかくどれ一つをとってみても、浅海氏の記事が想像的に書かれたものであるかが分るのだが、第一浅海氏自身、無錫か啄自動車で陥落後の南京へ入ったというのだから、第一線には出でいないのである。したがって戦闘中の紫金山山麓や、中山門付近には浅海氏が行っていないこり、は明らかで、それをさも敵前の取材で奮闘しているがの如く書こうとするから、こういう無理が生ずるのだ。
とにかくこの二通の証明書をつけ、向井、野田両氏は改めてその主張を盛った申弁書を出した。
しかし中国側は、これらをすべて無視したのである。
この頃、東京ではすでに極東国際軍事裁判、つまり言うところの東京裁判は始まって一年の余、南京大虐殺も俎上に乗り、これによって裁かれるのは、南京戦の総司令官松井石根であり、また時の外相広田弘毅であった。
東京裁判においても、連合国側の主張である人道上の罪を糾弾するには、南京大虐殺は好個の例として最重要視されていた。これによって日本軍の残虐性を広く世界に示すことができれば、それだけ連合国側の戦いは正義となるからだ。いわば、東京裁判の目玉商品なのだ。
だからこそ、国民政府当局は、その証拠となるべき被害者の証言を鋭意集めたのであった。だがそれでも市民の間から被害の申し出はいっこうに出てこない。やむなく当局は、係官を市中に出向かせ無理遣りにその証言を集めて廻った。
そしてそれらを元とし、第六師団長であった谷寿夫中将を裁き、虐殺の命令者として処刑した。
だがそれだけではいまだしと思ったのか、虐殺の実行者を処刑できれば、南京大虐殺はさらに現実性を帯びることになる。
そこで、眼をつけたのが、新聞に載っていた百人斬りの記事であった。百人もの中国人を殺したとなれば、これは虐殺の実行者としてよき存在となる。だがこの記事によっても、これは戦闘としての行為であり、武勇伝として描かれている。したがって虐殺実行者とするにはかなりの無理がある。
だからこそ一方的な裁判となったのだが、ここで考えられることは、いかに虐殺を構築しようとしても、記事を書いた本人である浅海氏自身が、
「実は、あれは創作だった」
と、告白してしまえば、いかに強引な中国側とはいえ、あるいはこれを諦めたかもしれない。
内外にそれを知られては、あまりにも虚構がすぎると見做(みな)されかねないからだ。
しかしその浅海一男氏は、創作だったということをとうとう告白しなかった。同じ房にいた多くの日本人も、それさえあれば助かると期待し、郵便物が到着するのを文字どおり鶴首していたにもかかわらず、浅海氏はその創作の一語をついに書かなかった。何故か。
誰もが、保身のためだと憤りをあらわにした。確かに、それ以外の理由は考えられない。しかし通常の場合ならともかく、今は二人の命がかかっているのである。
前線にも行かず、でっち上げの記事を送ったことがばれたら、もちろん面目丸潰れであり、また戦意昂揚のためとはいえ、こんな軍国調の文を書いていたことも、戦後になってみれば気恥ずかしいということもあろう。
だが今は、そんなことは言っていられないのである。人の命がかかっているとあれば、誰だって何をさし置いても創作だったと書くのが普通である。
だがそれでも書かなかったとなると、単なる面目や立場の問題ではなさそうだ。それは、記事捏造となれば、その責任は向井氏たちから、今度は自分のほうに廻ってくるのではないか。その危険性は、わずかなものではあるが、可能性はある、そう感じ取ったのではないか。
その頃横浜のBC級戦犯の法廷では、捕虜を殴った、食物を与えなかった程度のことでも虐待とし次々と有罪になり、極刑になった者も少なくない。事実無根であろうが、一度そう判定されたらそれを覆すことはできないのである。
東京本社にいた浅海氏が、その恐ろしさは充分に知っていたであろうことは容易に察しがつく。
対米放送の女性アナウンサー東京ローズも、裁かれている。向井氏たちを処罰できなくなったら、その振りあげた拳のやり場に困る中国軍は、その鉾先を自分に向けてきはしないか。そう思えば、それは恐ろしい。
しかしその可能性は、零と断定はできないまでも、きわめて少ないのだ。一方書かなければ向井、野田の両氏は確実に死刑になる。そして結局浅海氏は、書かなかった。いや、書けなかったのかもしれない。
昭和二十三年一月二十八日時折粉雪が舞う寒い朝であった。十時頃、房の中から大きな万歳の声が聞こえた。向井敏明、野田毅、田中軍吉の三氏が、唱えた最後の万歳であった。天皇陛下、大日本国、そして中国と三人は高らかに万歳を三唱した。
その声は、近くの房にいた他の日本人諸子の胸に、痛いほど突き刺さっていった。誰もが涙を流し、また改めて浅海氏の不実を思った。
向井氏はこの直前に、最後の書をしたためていた。それには、捕虜や住民を殺したことはないが、これをもって中国抗戦八年の苦杯と、その遺恨が流れ去り、日中親善、東洋平和の因となるなら、自分は喜んでその捨て石となろう。日本男子として、立派に中国の土になる。だが魂は、大八洲(おおやしま)に帰る。死して護国の鬼とならん、と結んでいる。またこれ以前にも、家族にあてた便りの中に、日本人には悪い人はいない。浅海氏にも書類を書いてくれた礼を伝えてくれ、と記しているのだ。十一時、三人は南京の南にある、かつての激戦地雨花台に連れていかれた。そして、正十二時激しい銃声があたりにこだました。
こうして三人は南京郊外雨花台において、その若き命を散らせたのであった。向井氏はこの時三十六歳、野田氏三十五歳であった。また中佐であった田中氏は四十三歳であった。
なお田中軍吉氏の罪は、中国人民を三百人も斬ったというもので、その証拠品として提出されたのが、氏の軍刀を写した一枚の写真であった。この写真は、当時出版された山中峯太郎編になる「皇兵」という本に収録されているもので、なるほどそれには「悲願三百人斬田中軍吉大尉の愛刀助広」という説明が、つけられている。
だがこれは、戦場で多くの敵を斬る、つまり活躍してほしいという願いをこめて、周囲の人がつけたもので、言うなれば武運長久と同じような意味あいのものだ。にもかかわらずこれをもって、市民の虐殺にするなど、どう考えても、これもただの言いがかりとしか思えない。
そして中華門から突入し、城内でこの大虐殺を働いたというのだが、田中大尉の属する鹿児島四十五聯隊は、第六師団のところで詳述したとおり、城内には一歩も足を踏み入れていない。とにかく、いずれの罪状もまったく児戯に等しい内容でしかないのだが、それでも無理遣りこうして極刑を課していったのである。
田中軍吉氏は、戦後復員し東京に在ったのだが、たまたま近くにいた第三国人から思わぬ逆恨みを買い、この三百人斬りの写真を元に、戦犯として訴えられたのだという。そしてそれを、そのまま中国側がとりあげたのであった。
その逆恨みというのは、借金の申し入れを断ったためというのだから、これまた何をか言わんやである。いかに終戦直後という特殊な世相とはいえ、まことにお気の毒としか言いようがない。















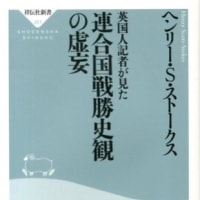
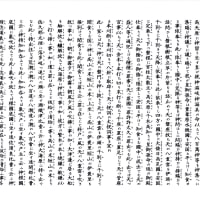
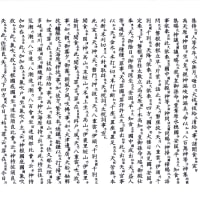
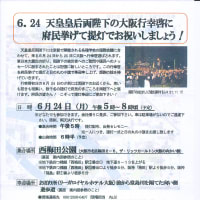

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます