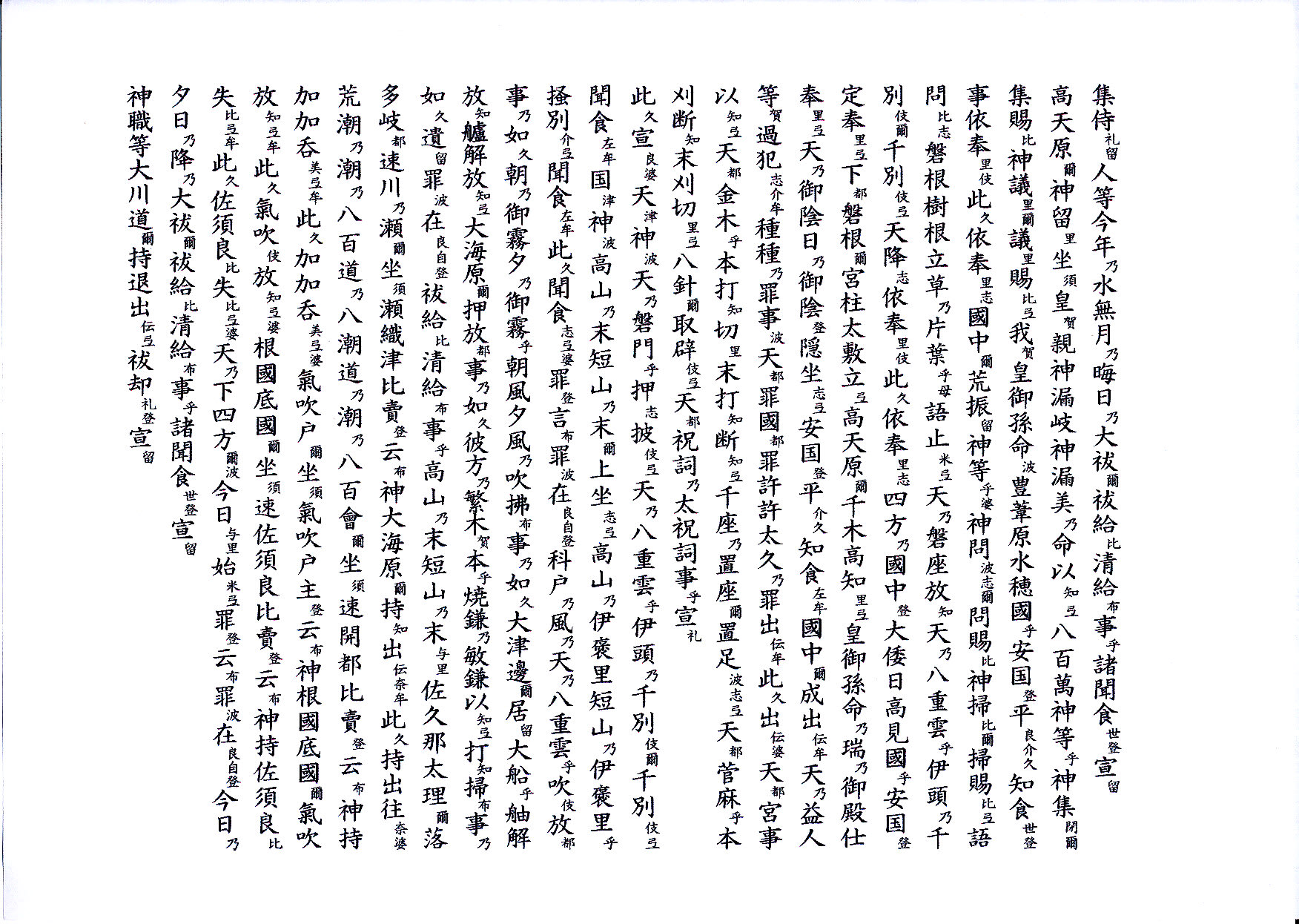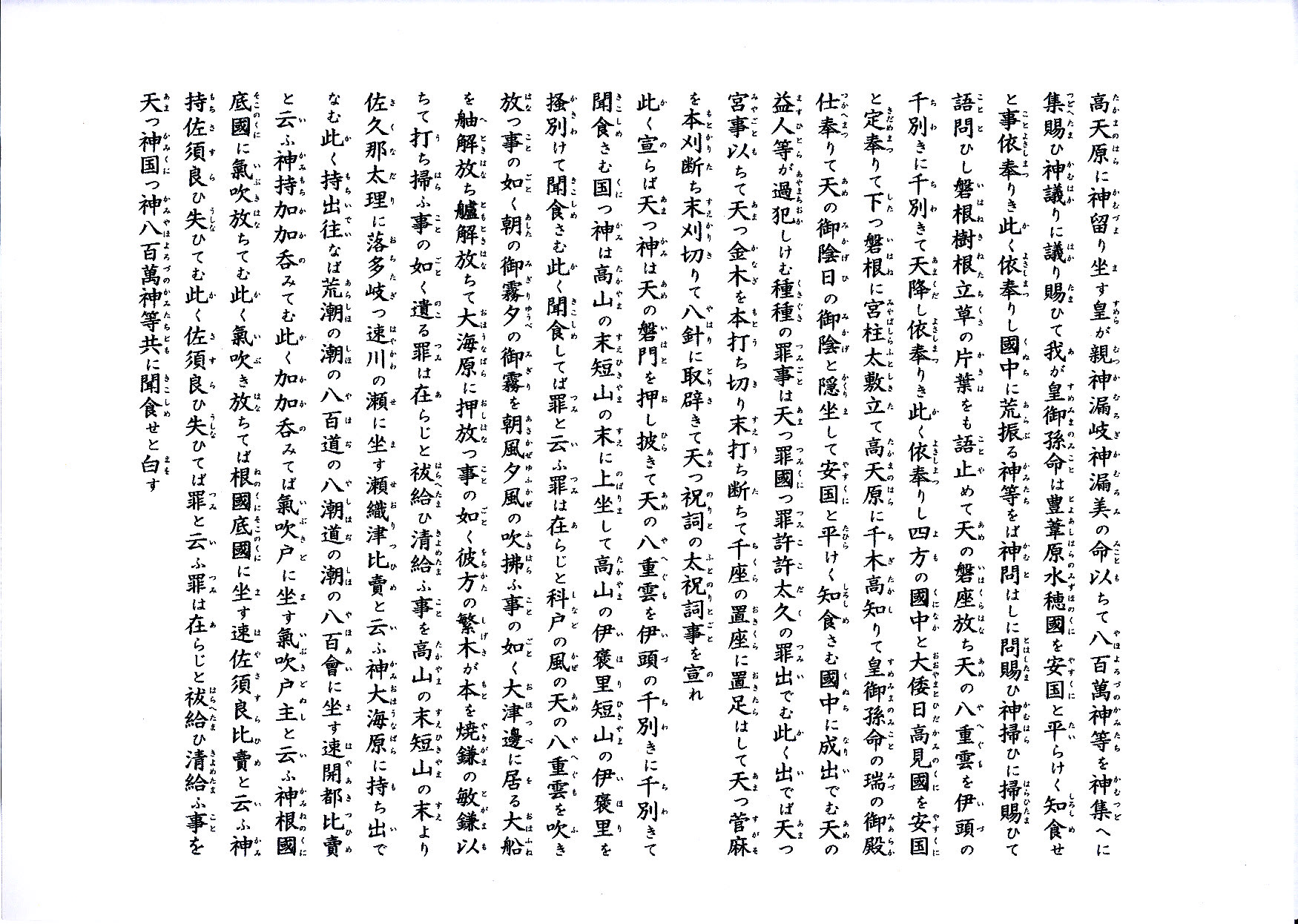5月5日。端午の節句。
祝日法では「こどもの日」です。
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」
母の日と言えば5月の第2日曜ですが、祝日法にでは5月5日が「母の日」でもあります。
母が子供を産んでくれたから世の中に存在します。
こどもの日を祝うと同時に母にも感謝しましょう。
祝日法では「こどもの日」です。
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」
母の日と言えば5月の第2日曜ですが、祝日法にでは5月5日が「母の日」でもあります。
母が子供を産んでくれたから世の中に存在します。
こどもの日を祝うと同時に母にも感謝しましょう。