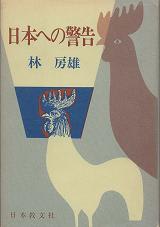「一度も植民地になったことがない日本」デュラン・れい子著 講談社
スウェーデン人と結婚し、スウェーデン・オランダ・ブラジルに住み、現在プロヴァンス在住。
夫や他のヨーロッパ人からみた日本やヨーロッパ人の考え方が、自身の体験を通して書かれています。
ヨーロッパはユーロで一つのようですが、それぞれ自分の国が一番で他国の悪口を言ったりしているのが現実のようです。
自衛隊のことが書かれていました。1974年に夫が初めて日本に来たとき、日本には軍隊が無いと説明されたそうです。
「日本人は頭がいいなぁ! 世界中の国々は莫大な金を軍隊に遣っている。だが軍隊がない日本は軍事費に予算をまわす必要がないから、こんなに経済発展ができるんだ」と思ったようです。
しかし、ある日新聞を見て日本にも自衛隊という軍隊が有ることを知って。
「彼らは口をそろえて『日本は平和憲法だから軍隊はない』と言ったんだぞ。だが自衛隊は結局、軍隊と同じじゃないか! なぜ『軍隊はないが、自衛隊がある』と言ってくれなかったんだろう」
一時『自衛隊は軍隊じゃない』と言われることがありました。しかし、世界の常識からすればどう見ても軍隊です。
名前や呼び方で誤魔化そうとするやり方は、ヨーロッパに限らず世界からみれば奇妙にしか見えません。
一つ雑学で、自衛隊の戦車には方向指示器が付いてるそうです。世界中の戦車で方向指示器が付いているのは日本だけです。
これは市街地を走ることを想定しているそうで、戦車に道路交通法が適用されるようです。
と言うことは、攻撃を受けている地域に応援に行くときに信号が赤になったら停車しなければならないと言うおかしな事がおきるのだろうかとも思ってしまいます。
マスターズ・カントリー(ご主人様の国)、ゲスト・ワーカー(外国人労働者おもに旧植民地)
スリナムの女性が著者に「あなたのマスターズ・カントリーだった国は何処?」と聞きます。
もちろん日本は一度も植民地になったことがないので、マスターズ・カントリーが無い事を言うとこの女性は驚きます。
つい最近までアジア・アフリカのほとんどの国は西洋諸国の植民地だったので、アジアの国で植民地になっていないことに驚くのですね。
著者の夫が「日本は、運がいい。いや、運がいいのでなく頭がよかったのだろう。だって織田信長のころ宣教師が来日したときや、徳川時代の終わりに西欧の国々が日本に開国をせまったときも、植民地になる危機があったわけだろ?」(このあたり日本人以上によく知っています)
歴史教育で戦国時代の頃や明治維新の頃に、対応を間違えれば日本も植民地になったかもしれないということを教えていません。
豊臣秀吉の切支丹追放令、徳川幕府の鎖国令は植民地になるのを防いだと言えます。こう言ったことをちゃんと歴史教育で教えるべきですね。
著者の夫が終身雇用についても発言しています。
「日本は昔からのいいものを捨てようとしていると僕には見えるね」。
この言葉、他のことにも当てはまる事が多々あります。
この本には他にも、子供のしつけの違いなど書かれています。
また、西洋人から見た日本や、西洋人に会う時の注意なども書かれています。
外国の人と結婚して海外在住者では、クライン孝子さんが有名ですが、このデュラン・れい子さんの著書も読まれてみてはいかがでしょうか。