8千メートル峰14座を今年達成した竹内さんが講演のため札幌市に来ました。
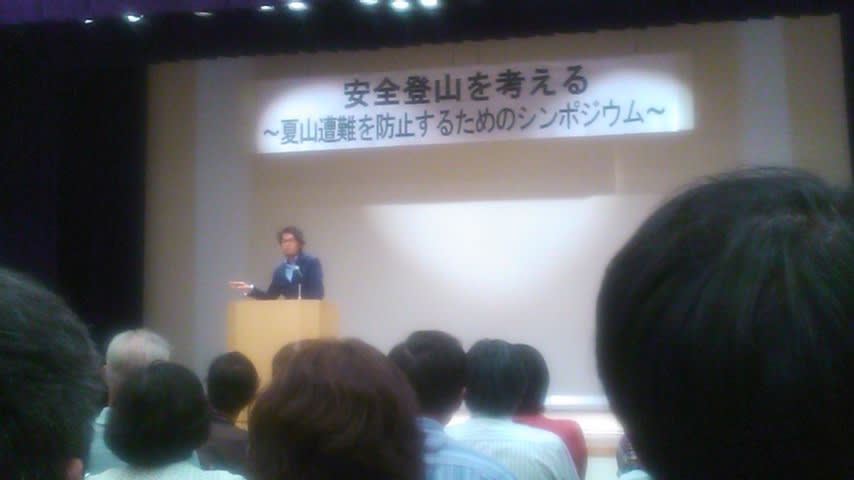
ケイタイの写真のためボケています。
6月13日(金)午後7時30分から
場所 エルプラザ
道警主催の「夏山遭難を防止するためのシンポジウム」において14座目となるダウラギリ登山の様子を中心にお話がありました。
気取らない語り口で臨場感タップリのお話でした。
約1時間がアッという間に過ぎていきます。
高度順応をアイランドピークで行ったと聞いて私が昨年登ったあのピークで1夜を過ごしたのかと思うと一層の親近感が湧いてきました。
ダウラギリもアンナプルナサーキットの後半はいつも目にしていた山です。
8千メートル峰最後のダウラギリも簡単には登らせてもらえなかったようです。
山頂を極めた後にテントもなしにビバーク、でも、本人にはちゃんと計算が立っていたようです。
下山して初めて登山が完結する。
それは山の高低に関係なく一番心に留め置かなければいけないことを教えてくれました。
この日は、道警の山岳遭難救助隊救助対策官の西村さんによる最近の遭難事例を統計から説明がありました。
次ぎに、大野病院で登山者外来を開設している大城和恵さんが、熱中症と低体温症について予防と対象方についての解説もありました。
全体を通してなかなか参考になるお話が聞けて良かったです。
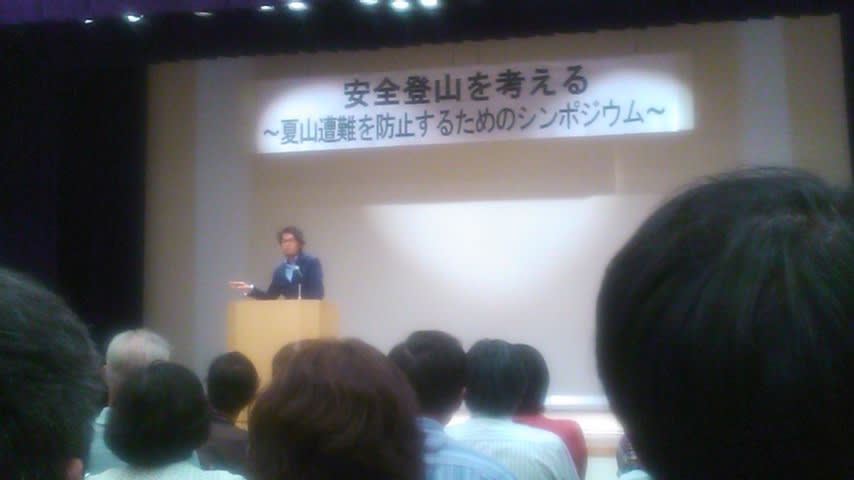
ケイタイの写真のためボケています。
6月13日(金)午後7時30分から
場所 エルプラザ
道警主催の「夏山遭難を防止するためのシンポジウム」において14座目となるダウラギリ登山の様子を中心にお話がありました。
気取らない語り口で臨場感タップリのお話でした。
約1時間がアッという間に過ぎていきます。
高度順応をアイランドピークで行ったと聞いて私が昨年登ったあのピークで1夜を過ごしたのかと思うと一層の親近感が湧いてきました。
ダウラギリもアンナプルナサーキットの後半はいつも目にしていた山です。
8千メートル峰最後のダウラギリも簡単には登らせてもらえなかったようです。
山頂を極めた後にテントもなしにビバーク、でも、本人にはちゃんと計算が立っていたようです。
下山して初めて登山が完結する。
それは山の高低に関係なく一番心に留め置かなければいけないことを教えてくれました。
この日は、道警の山岳遭難救助隊救助対策官の西村さんによる最近の遭難事例を統計から説明がありました。
次ぎに、大野病院で登山者外来を開設している大城和恵さんが、熱中症と低体温症について予防と対象方についての解説もありました。
全体を通してなかなか参考になるお話が聞けて良かったです。




















