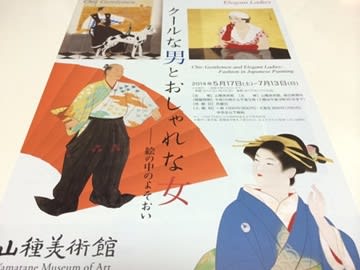見てきました
東京ステーションギャラリー
会期は2014年5月24日から2014年7月13日。
ジャン・フォートリエ(1898-1964)
フランスの画家、彫刻家です。
第二次世界大戦後のフランスの芸術運動であるアンフォルメルの創始者とされています。
今年は没後50年。
初期から晩年までを紹介する日本初の本格的な回顧展です。
主要な6つの個展での出品作を中心に約90点で構成されています。
《1.レアリスムから厚塗りへ 1922-1938》
ジャン・フォートリエはパリ生まれ。
少年時代にロンドンに移住しています。
美術学校に入学し、テート・ギャラリーでターナーの作品に感銘を受け、生涯高く評価していたそう。
第一次大戦のため1917年に通訳・救急看護隊員として応召。
毒ガスで負傷しています。
ここでは復員したフォートリエが制作を再開するところからになります。
1922年には"サロン・ドートンヌ"に出品。
著名な画商とも契約し順風満帆でしたが、1929年に始まった世界恐慌のあおりを受け、契約は打ち切り。
キャリアは中断されます。
このとき、アルプスでスキーのインストラクターをするなどして暮らしました。
パリに戻るのは第二次世界大戦中の1940年ごろとなります。
「管理人の肖像」
灰色の壁を背景に顔が緑色の老婆が描かれています。
黒いドレスを着、両手は前で組んでいますが、紫色。。
なぜこの色を選んだのか……
色に目がとらわれがちですが、その描写力はすごいです。
圧倒的な存在感。
だからこそ色が気になる。。。
笑っているようにも見える老婆の表情も異様です。
「静物」
こちらはセザンヌ風とでも言うべきか。
テーブルの上にはフライパン、果物、魚、カゴ、瓶……
重厚な印象。
「森の中の男」
森の中の木々を背景にこちらを見ている男性が描かれています。
深い緑色の帽子をかぶり、茶色のコートを着、両手はポケットに入れています。
ちょっと遠くを見ているような視線。
深い洞察力が伺えます。
ここからは肖像画がいくつか続いていました。
「左を向いて立つ裸婦」
サンギーヌによる素描です。
これがすごい。
こんなにもしっかりした描写ができるなんて、と。
リアルすぎます。
ここからは『黒の時代』とよばれているときの作品。
1920年代後半、特に1926年から27年の1年を「黒の時代」とフォートリエは言っています。
また、プリミティブなものに関心のあったということで、アフリカの黒人芸術にも着想を得ています。
このあたりの一連の作品ではリアリズムから遠ざかっていく様子が伺えます。
「美しい娘(灰色の裸婦)」
黒というよりも灰色の背景。
描かれている裸婦は背景の色と溶け込むようで、体の線ははっきりしません。
表情もなく、どこが美しいのか、と聞かれたら分からない作品。
「黒人女性の頭部」
絵の具が厚く塗られた作品。
力強さを感じます。
「黒い花」
黒い背景に赤や黄色の花が溶け込むかのよう。
闇に咲く花、といった感じです。
絵の具を削ってできた線が花瓶や花の形を縁取ってます。
「鍋に活けた花」
こちらも黒い背景に大きな鍋。
そこには白とオレンジの花。
輪郭は彫られています。
暗い背景に明るい色彩が花火のようでもありはかなくも見えます。
「羊の頭部」
暗い背景に浮かぶのは羊の頭部。
大きい筆致で描かれ、赤い肉の繊維がこびりついているかのように見えます。
「兎の皮」
こちらは暗い背景に吊るされた兎が描かれている作品。
少ない筆致で大胆に描かれていますが、その対象はしっかり描かれています。
見ていて少し怖くなってくる気もします。
このあとは彫刻が数点ありました。
フォートリエは1927年から29年と1935年から43年の2つの期間に彫刻を約20点ほど制作したのだそう。
《2.厚塗りから「人質」へ 1938-1945》
1929年の世界恐慌のあおりを受け、フォートリエは画業を中断。
アルプスへ行き、スキーのインストラクターをしたり、ナイトクラブを経営するなどして生活しました。
第二次世界大戦でドイツに占領されたパリに戻ったのは1940年ごろ。
アトリエを構えて以前より色彩豊かな厚塗りのマチエールを太い輪郭線で囲う独特の作品を生み出します。
カンヴァスはより絵の具を吸収しやすい紙になりました。
1943年にはドゥルーアン画廊で最初の回顧展を開催。
しかし同年、レジスタンス活動を疑われ、ゲシュタポ(ドイツの秘密国家警察)に拘束されます。
なんとか逃げ、パリ郊外のシャトネ=マラブリーに匿われます。
近くのフレーヌ監獄ではドイツ軍によってフランス人レジスタンスの処刑が行われていました。
これが代表作「人質」誕生のきっかけとなったのです。
「醸造用の林檎」
かなり絵の具が残っています。
緑色の背景に白い色を丸く重ね、一部が赤くなっています。
うーん、確かに林檎のようにもみえますが。。
「梨と葡萄のある静物」
こちらのほうがまだ形がわかるかな。
青系でまとめられ爽やかな印象です。
白い色も明るく見せています。
さて、ここからはちょっと重い作品ばかりになってきます。
「人質」は1945年10月解放後数ヶ月のパリで発表されました。
極限状態における人間の存在をマチエールとたどたどしい線描によって残そうとした作品。
アンドレ・マルロー(後のフランス文化相)の序文が掲載されたカタログも制作されました。
拷問を受け、片目がない人、口のない人、鼻のない人……
それは衝撃を与えました。
「銃殺された男」
灰色の背景になにかの塊。
白とピンク色で彩られた塊。
人と見ようとして考えて。
仰向けに倒れているようにも見えます。
「人質 No.3」
これも塊。
左向きの顔、かな。。
重苦しい雰囲気が漂っています。
「悲劇的な頭部(大)」
ブロンズの彫刻。
人の頭部ですが、左半分顔がありません。
衝撃的です。
「人質の頭部」
ポスターにも使われている作品。
暗い背景に白い絵の具の厚塗りで表現されたのは人の頭部。
暗い部分は目でしょうか。
虚ろで絶望を見ている、、というか絶望しかないのでしょう。。
《3.第二次世界大戦後 1945-1964》
「人質」は解放直後のパリに衝撃を与えました。
そして1952年、批評家のミシェル・タピエはアンフォルメルの先駆者としてフォートリエを位置づけます。
1959年には来日し南画廊で個展も開催しました。
1960年にはヴェネチア・ビエンナーレ内で回顧展を開催し大賞を受賞。
1964年にはパリ市立近代美術館で大回顧展。
同年、66歳で亡くなりました。
「糸巻き」
淡い水色の背景に糸巻きを描いたもの。
戦後、と知ったからかもしれませんが穏やかに見えてきます。
ですが、絵の具は厚いです。
「籠」
薄い緑の背景に黒い塊。
マチエールで形を表現しています。
「オール・アローン」
フォートリエはジャズを好みました。
ホテルを経営していた際にはアメリカからジャズ奏者を紹介したりもしていたそうです。
この作品もジャズの曲名から。
色は茶色ですが軽やかな印象です。
ただしこの辺りからは何を描いているのか分からなくなってきました。
抽象的で、よく知られたアンフォルメルの画家としてのフォートリエの作品です。
ジャズを好んだフォートリエでしたが、制作時は静寂を好みました。
アトリエには誰も入れなかったそう。
「こちょこちょ」
これは名前の響きがかわいらしくて。
青い色が使われ爽やかな印象です。
「黒の青」
これ好き。
薄い灰色の地に、明るい青色が載せられ、ひっかいたような跡が入っています。
少し黄色も入っていて明るい世界が見えるような気がするのです。
以上になります。
とてもとても面白い展示でした。
もちろん、「人質」シリーズなど見るのも重い作品がありましたが、それらを含め画業を辿って見ることができ、勉強にもなりました。
初期のリアリズムからアンフォルメルへ至るまで。
大変興味深いものでした。
ブログランキングよかったらお願いします


東京ステーションギャラリー

会期は2014年5月24日から2014年7月13日。
ジャン・フォートリエ(1898-1964)
フランスの画家、彫刻家です。
第二次世界大戦後のフランスの芸術運動であるアンフォルメルの創始者とされています。
今年は没後50年。
初期から晩年までを紹介する日本初の本格的な回顧展です。
主要な6つの個展での出品作を中心に約90点で構成されています。
《1.レアリスムから厚塗りへ 1922-1938》
ジャン・フォートリエはパリ生まれ。
少年時代にロンドンに移住しています。
美術学校に入学し、テート・ギャラリーでターナーの作品に感銘を受け、生涯高く評価していたそう。
第一次大戦のため1917年に通訳・救急看護隊員として応召。
毒ガスで負傷しています。
ここでは復員したフォートリエが制作を再開するところからになります。
1922年には"サロン・ドートンヌ"に出品。
著名な画商とも契約し順風満帆でしたが、1929年に始まった世界恐慌のあおりを受け、契約は打ち切り。
キャリアは中断されます。
このとき、アルプスでスキーのインストラクターをするなどして暮らしました。
パリに戻るのは第二次世界大戦中の1940年ごろとなります。
「管理人の肖像」
灰色の壁を背景に顔が緑色の老婆が描かれています。
黒いドレスを着、両手は前で組んでいますが、紫色。。
なぜこの色を選んだのか……
色に目がとらわれがちですが、その描写力はすごいです。
圧倒的な存在感。
だからこそ色が気になる。。。
笑っているようにも見える老婆の表情も異様です。
「静物」
こちらはセザンヌ風とでも言うべきか。
テーブルの上にはフライパン、果物、魚、カゴ、瓶……
重厚な印象。
「森の中の男」
森の中の木々を背景にこちらを見ている男性が描かれています。
深い緑色の帽子をかぶり、茶色のコートを着、両手はポケットに入れています。
ちょっと遠くを見ているような視線。
深い洞察力が伺えます。
ここからは肖像画がいくつか続いていました。
「左を向いて立つ裸婦」
サンギーヌによる素描です。
これがすごい。
こんなにもしっかりした描写ができるなんて、と。
リアルすぎます。
ここからは『黒の時代』とよばれているときの作品。
1920年代後半、特に1926年から27年の1年を「黒の時代」とフォートリエは言っています。
また、プリミティブなものに関心のあったということで、アフリカの黒人芸術にも着想を得ています。
このあたりの一連の作品ではリアリズムから遠ざかっていく様子が伺えます。
「美しい娘(灰色の裸婦)」
黒というよりも灰色の背景。
描かれている裸婦は背景の色と溶け込むようで、体の線ははっきりしません。
表情もなく、どこが美しいのか、と聞かれたら分からない作品。
「黒人女性の頭部」
絵の具が厚く塗られた作品。
力強さを感じます。
「黒い花」
黒い背景に赤や黄色の花が溶け込むかのよう。
闇に咲く花、といった感じです。
絵の具を削ってできた線が花瓶や花の形を縁取ってます。
「鍋に活けた花」
こちらも黒い背景に大きな鍋。
そこには白とオレンジの花。
輪郭は彫られています。
暗い背景に明るい色彩が花火のようでもありはかなくも見えます。
「羊の頭部」
暗い背景に浮かぶのは羊の頭部。
大きい筆致で描かれ、赤い肉の繊維がこびりついているかのように見えます。
「兎の皮」
こちらは暗い背景に吊るされた兎が描かれている作品。
少ない筆致で大胆に描かれていますが、その対象はしっかり描かれています。
見ていて少し怖くなってくる気もします。
このあとは彫刻が数点ありました。
フォートリエは1927年から29年と1935年から43年の2つの期間に彫刻を約20点ほど制作したのだそう。
《2.厚塗りから「人質」へ 1938-1945》
1929年の世界恐慌のあおりを受け、フォートリエは画業を中断。
アルプスへ行き、スキーのインストラクターをしたり、ナイトクラブを経営するなどして生活しました。
第二次世界大戦でドイツに占領されたパリに戻ったのは1940年ごろ。
アトリエを構えて以前より色彩豊かな厚塗りのマチエールを太い輪郭線で囲う独特の作品を生み出します。
カンヴァスはより絵の具を吸収しやすい紙になりました。
1943年にはドゥルーアン画廊で最初の回顧展を開催。
しかし同年、レジスタンス活動を疑われ、ゲシュタポ(ドイツの秘密国家警察)に拘束されます。
なんとか逃げ、パリ郊外のシャトネ=マラブリーに匿われます。
近くのフレーヌ監獄ではドイツ軍によってフランス人レジスタンスの処刑が行われていました。
これが代表作「人質」誕生のきっかけとなったのです。
「醸造用の林檎」
かなり絵の具が残っています。
緑色の背景に白い色を丸く重ね、一部が赤くなっています。
うーん、確かに林檎のようにもみえますが。。
「梨と葡萄のある静物」
こちらのほうがまだ形がわかるかな。
青系でまとめられ爽やかな印象です。
白い色も明るく見せています。
さて、ここからはちょっと重い作品ばかりになってきます。
「人質」は1945年10月解放後数ヶ月のパリで発表されました。
極限状態における人間の存在をマチエールとたどたどしい線描によって残そうとした作品。
アンドレ・マルロー(後のフランス文化相)の序文が掲載されたカタログも制作されました。
拷問を受け、片目がない人、口のない人、鼻のない人……
それは衝撃を与えました。
「銃殺された男」
灰色の背景になにかの塊。
白とピンク色で彩られた塊。
人と見ようとして考えて。
仰向けに倒れているようにも見えます。
「人質 No.3」
これも塊。
左向きの顔、かな。。
重苦しい雰囲気が漂っています。
「悲劇的な頭部(大)」
ブロンズの彫刻。
人の頭部ですが、左半分顔がありません。
衝撃的です。
「人質の頭部」
ポスターにも使われている作品。
暗い背景に白い絵の具の厚塗りで表現されたのは人の頭部。
暗い部分は目でしょうか。
虚ろで絶望を見ている、、というか絶望しかないのでしょう。。
《3.第二次世界大戦後 1945-1964》
「人質」は解放直後のパリに衝撃を与えました。
そして1952年、批評家のミシェル・タピエはアンフォルメルの先駆者としてフォートリエを位置づけます。
1959年には来日し南画廊で個展も開催しました。
1960年にはヴェネチア・ビエンナーレ内で回顧展を開催し大賞を受賞。
1964年にはパリ市立近代美術館で大回顧展。
同年、66歳で亡くなりました。
「糸巻き」
淡い水色の背景に糸巻きを描いたもの。
戦後、と知ったからかもしれませんが穏やかに見えてきます。
ですが、絵の具は厚いです。
「籠」
薄い緑の背景に黒い塊。
マチエールで形を表現しています。
「オール・アローン」
フォートリエはジャズを好みました。
ホテルを経営していた際にはアメリカからジャズ奏者を紹介したりもしていたそうです。
この作品もジャズの曲名から。
色は茶色ですが軽やかな印象です。
ただしこの辺りからは何を描いているのか分からなくなってきました。
抽象的で、よく知られたアンフォルメルの画家としてのフォートリエの作品です。
ジャズを好んだフォートリエでしたが、制作時は静寂を好みました。
アトリエには誰も入れなかったそう。
「こちょこちょ」
これは名前の響きがかわいらしくて。
青い色が使われ爽やかな印象です。
「黒の青」
これ好き。
薄い灰色の地に、明るい青色が載せられ、ひっかいたような跡が入っています。
少し黄色も入っていて明るい世界が見えるような気がするのです。
以上になります。
とてもとても面白い展示でした。
もちろん、「人質」シリーズなど見るのも重い作品がありましたが、それらを含め画業を辿って見ることができ、勉強にもなりました。
初期のリアリズムからアンフォルメルへ至るまで。
大変興味深いものでした。
ブログランキングよかったらお願いします