
今日の記事は、先日アップしたNHK人間講座「空海 平安のマルチ文化人」(2003年放送)を講義した頼富本宏先生におよる密教をテーマとした新書の、ただただ“まとめ”です!
「密教 悟りとほとけへの道」頼富本宏(講談社現代新書)
1.密教の不思議な魅力
(1)さまざまなアプローチ
①生命肯定の思想として ②直接参加の実践行法として ③芸術的なアプローチ(マンダラ) ④能力開発の可能性として ⑤現世利益の信仰として(結果功徳)
(2)密教の三層構造
◆密教のピラミッド型三層構造・・・広義→宗教レベルの密教(イスラム=スーフィ、ユダヤ教=カバラー、神秘的・呪術的要素) 中義→仏教レベルの密教(チベット仏教、インド中後期密教) 狭義→真言・天台レベルの密教(空海、最澄による)
◆神秘主義…聖なるものと俗なるものの神秘的合一を、教義と実践の基本に置く(如来秘密、衆生秘密)
◆呪術性…現世利益を求める加持祈祷において、俗なるわれわれから聖なるほとけたちに対して積極的な働きかけがなされるのであるから呪術的要素は不可欠の特徴
2.流伝の道をたどる
(1)密教の歴史的分類法
◆純密と雑密
雑密・・・雑然とした未整備の密教(①本尊は伝統的な如来や変化観音など ②諸尊の陀羅尼=神秘的な威力をもつとされる呪句を唱える ③現世的御利益が目的 ④マンダラは不完全)
純密・・・真言・天台の両密教(①本尊が大日如来 ②身・口・意という三密を総合的に駆使する全身的行法 ③直接にほとけを体現する成仏の思想が究極目的 ④大日如来を中心にいただくマンダラ)
◆初期・中期・後期の分類
初期・・・インド4〜6世紀、陀羅尼を中心とする未体系な密教
中期・・・インド7世紀、「大日経」「金剛頂経」などの経典を基盤とする体系的な密教
後期・・・インド8世紀、タントラ仏教(性的行法や生理的行法も大胆に導入)、中国・日本では左道密教として嫌悪された
◆タントラ4分類法
秘教的・実践的要素の強い密教系の聖典をタントラと称する
①所作タントラ ②行儀タントラ ③瑜伽タントラ ④無上瑜伽タントラ(最高のタントラ・インド、チベットで大流行)
(2)インドに誕生した密教
◆初期インド密教・・・4〜5世紀、ヒンドゥー教の復興とともに仏教の中でも儀礼やパンティオンにウエイトを置く密教的要素が濃厚となった。 6世紀、真言、印相、マンダラの大部分が揃った「陀羅尼集経」が編集。
◆「大日経」と「金剛頂経」の成立
・「大日経」→①ヴァイローチャナ(大日如来)・・・宇宙に遍満する真理の当体、真理の全体的象徴。「大日経」①住心品・・・存在するものには固有の本性がない=空性の思想、心によってのみすべてが存在するのであり修行する心を通してのみ存在を知ることが可能=唯心・唯識の思想②具縁品・・・密教に不可欠の実践体系の諸要素(印相、真言、マンダラ、三密、護摩法、供養法、灌頂法など)
・「金剛頂経」→一群の経典の総称。五段階の瞑想法(五相成身観)を経て、宇宙の当体ともいうべき大日如来と一体となる。「理趣経」「悪趣清浄軌」
・インドにおける中期密教はそれまでの大乗仏教とは明確に一線を画した本格的な密教が確立した。三密を通してほとけになることができるという瑜伽の思想と実践は、インド仏教全体の中でも重要な位置を占めるに至る。
◆無上瑜伽密教へ ①方便・父タントラ・・・自己の身体として象徴される小宇宙の中に聖なる世界を実現するために、如来や菩薩の降臨を瞑想することを説いた生理的要素のつよう行法が中心 ②般若・母タントラ・・・身体世界のなかに、超生理的な微細身という存在を感じ、身体の中央脊柱に沿って四つから七つのチャクラとそれらを結んでいる三種の脈菅(ナーディー)を想定し、最下部のチャクラから思念のエネルギーを上昇させ最高存在との合一体験を味わおうとする。(生理的な呼吸、心理的な思念、性的な精液のコントロール) ③不二タントラ・・・無上瑜伽密教、仏教とヒンドゥー教の大同団結、「カーラチャクラ・タントラ(時輪タントラ)」→時間と空間の統合・止揚を意図、占星法、六段階のヨーガ修行法。
※1203年イスラーム教徒の仏教寺院の猛攻をうけてインド仏教は姿を消す。
(3)中国への密教流伝
◆はじめは、遊牧民によって現世利益を求める呪術的な要素を持つ経典が歓迎された。やがて、インドからの渡来僧によって変化観音系密教経典が訳出された。
◆請来期・・・楊貴妃とのロマンスで親しい玄宗の時代に、インド僧・善無畏による「大日経」の、インド僧・金剛智による「金剛頂経」の訳出されたが、経典の内容よりも密教儀礼の効果としての効験力に関心が集中した。
◆確立期・・・一行禅師は善無畏の訳した「大日経」を中国、朝鮮半島、日本にも利用できるようにした。不空三蔵はインドから多数の密教経典を請来し、護国的密教を完成させた。不空が訳した経典は空海によって大量に日本にもたらされ現在でも密教行法の基本テキストとして大きな役割をはたしている。
◆維持期・・・恵香は「大日経」「金剛頂経」という両部の大経をひとつのセットとして確立し教義化したち推測される。さらにこの教えを充実させたのが空海である。しかしその後は、道教のようなよく似た性格を持つ宗教に溶け込む以外は道がなかった。
(4)日本密教の成立と展開
◆奈良時代の密教・・・空海以前、経典や仏像などは断片的に伝わっていた。虚空蔵菩薩求聞持法
◆最澄と天台密教・・・遣唐使として天台山の参拝と法華天台の経論の収集に務めたが、順暁から密教を相承した。
◆空海と真言密教・・・青竜寺の恵香は金剛界、胎蔵界両部の法を日本からやってきた空海に付法した。帰国後、高野山を開創し東寺(教王護国寺)を賜る。高野山は行を重んじた「即身成仏」的志向性が強いのに対し、東寺は対社会的、国家守護的な「密厳国土」の寺であった。空海は即身成仏と密厳国土という垂直と水平の二軸構造を基本とする真言密教を築く。
(5)チベットに生き続ける密教
◆8世紀ころインド後期の密教がチベットに伝わった。11世紀以降多くの高僧が輩出し宗派が数多く成立した(カーギュ派、コンチョクゲルポ派、ゲールック派など)。
3.「即身成仏」と「密厳国土」
(1)密教の思想的特徴
①密教そのものが多重的・複合的構造を持っているため、他の思想や文化に対して寛容であり融和的にそれらを取り込もうとする。 ②密教は<聖なるもの>に対して常に大きな関心を払い、それとの全身的合一を思想的にも実践敵にも基本とする宗教体系(即身成仏) ③密教は現実の現象面にも積極的、現象と実在の間には本質的な差異はないとする発送(密厳国土)
(2)即身成仏
◆「即身成仏義」(空海)・・・六大無礙にして常に瑜伽なり。四種曼荼各各離れず。三密加持すれば速疾に顕わる。重重帝網なるを即身と名づく。法然にの薩般若を具足し、心数心王刹塵に過ぎたり。→実在も現象もいずれも本体としては六つの存在要素(地・水・火・風・空・認識)から成り立っている。様相は四種のマンダラ(尊像=大、象徴物=三麻耶、文字=法、立体=羯磨)として表現される。作用としては三種の行為形態(身体・言葉・心)によって把握される。本体、様相、作用という三種の次元から見ることにより、「即身」という言葉で抽象的に表現されている聖なるものと俗なるものの直接的関わりを論証しようとした。(六大・四曼・三密/本体・様相・作用)
◆三種即身成仏論→①理具成仏・・・人間にはほとけたる資質が本来そなわっている=即ち身成れる仏 ②加持成仏・・・理念としての即身成仏を現実のものとするため、実践を行う=即かに身成れる仏 ③顕得成仏・・・理念としての成仏が実際に実現されたのちに現われ出てくる結果を表現=身に即して仏となる→即身成仏という全体を理念と実践と結果の三つの段階から説く
◆われわれはほとけと異ならないという大前提(=本有の成仏)から、その可能性を可能性に終わらせず、現実のものとして実証すること(=修生の成仏)。みずからの身体と言葉と心を通して、ある状況下において実在的な聖なるものを感得することが肝要である。そうすれば、大日如来の世界の中に生かされているみずからの命を実感することができるのであり、これこそが「生かせ命」であり、広義な意味での即身成仏である。
(2)密厳国土→水平的構造
◆空海の「密厳国土」論・・・空海においては「密厳国土」とは大日如来の世界であるとともに我々がいま現に存在している世界でもある。表面的にはマンダラとして現れてくる。すべてが大日如来のあまねき光の中に映し出されている世界。「密厳国土」の思想は、現実の我々が住んでいる世界を少しでも良くしていくことであり、同じ世俗的世界に存在しているものの横の関係、つながりとして把握すること。
◆四恩 ①父母の恩・・・家庭と自身の関係 ②衆生の恩・・・社会と自身との関係 ③国王の恩・・・政治と自身の関係 ④三宝の恩・・・宗教と自身の関係 →水平の関係において良い関連を保とうとする密教の智恵
(2)インドにおける行法
4.聖俗一致の実践方法
(1)実践行法のカリキュラム
◆聖俗合一体験・・・四度加行、灌頂、阿字観、遍路信仰など
◆四度加行・・・●金剛界と胎蔵(界)という両部の修法、●特定の尊格(ほとけ)を本尊とする十八段階の基礎的修法(十八道)→護身法・・・修行者の身・口・意を清める荘厳行者法、結界法・・・世界を清めて修行の聖域空間を現出する、荘厳道場法・・・本尊の道場を設営する、勘請法・・・宝庫を送って本尊を迎える、結護法・・・道場の内外をもう一度堅固にする、供養法・・・本尊を供養、●護摩作法・・・バラモン教に起源、不動明王の護摩、①息災(マイナスをゼロに) ②増益(ゼロをプラスに) ③敬愛 ④調伏(プラスをマイナスに) 祈願がかのうとなるには、聖なるほとけたちの神秘的な加護力(加持力)と修法を行う行者がそなえている力(功徳力)と、それらの次元の異なる力が相即しうる場としての力(法界力)がうまく相互に作用しあうことが必要●灌頂・・・①結縁灌頂・・・密教入門 ②受命灌頂・・・特定のほとけや修法に限って修了の証明を得る儀式 ③伝法灌頂・・・密教のすべてを修得し終わったときに、免許皆伝のあかしとして受ける●阿字観・・・満月の輪の中に、あらゆる文字の最初であり、根源でもある「阿(a)字」を観じ、それと自己との同一を感得する行法、満月はインドにおいては最高の瞑想体験、<五字厳身観>身体の五つの部分に五字を配してみずからの身体をマンダラであると観想する行法
◆ヒンドゥー教の身体宇宙観・・・ヒンドゥー教のタントラ(ヨーガ・ウパニシャッド)、人間の身体は物理的な肉体(=粗大身)と、それと密接な関連を持ちながら、より高次の抽象的な身体(=微細身)の二種がある。微細身を構成しているのは六つ(もしくは七つ)のチャクラとそれをつなぐ無数のナーディー(脈菅)である。われわれの生命エネルギーは通常は潜在的な状態にある。これを象徴的にシンボライズすると、尾底骨部あたり(肛門と陰根の間)に想定されるムーラーダーラ・チャクラにとくろを巻いて眠っている蛇(クンダリーニ)として表される。下位に眠っているクンダリーニに刺激を与えて活性化させ、蛇の姿をとって活動を開始したクンダルーニをおのおのチャクラを経由させて上昇させる。頭頂の千弁蓮華に至り、そこに住している最高神のブラフマンと合一して至福の境地にひたることができるようにみずからの小宇宙をコントロールする。
(2)ほとけたちのプロフィール
◆仏・如来・・・仏=ブッダ=覚者→さとりをひらいたもの、如来=タターガタ→かくの如く来れるもの、さとりに到達したもの ①顕教仏・・・密教以前に成立、釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来、多宝如来など ②密教仏・・・大日如来 ③仏頂・・・仏陀の頭頂の肉髻を神格化(釈迦金輪、大日金輪)
◆菩薩・・・さとりを求めて努力しているもの(進行形の人)、王子のような優雅な姿、観音・金剛手・文殊・弥勒・普賢・虚空蔵・地蔵・除蓋障という八大菩薩
◆明王・・・忿怒形でしかも多面多臂の恐ろしげな尊格、呪術的降伏力がある、不動明王、愛染明王、孔雀明王
◆天部・・・大部分がヒンドゥー教の神々、四天王・梵天・帝釈天・吉祥天・聖天・大黒天・摩利支天など
(3)マンダラの中のほとけたち
◆中尊・・・マンダラの中央に位置する中心尊格、チベットでは歓喜仏(配偶女尊を抱いている)
◆眷属尊・・・中尊にしき従ってその役割を分担してひとつのグループを形成、二脇侍、八大菩薩など、薬師如来と十二神将、不動明王と二大童子
◆配偶尊・・・配偶という形而下的な発想、部母、仏母
◆供養尊・・・尊敬の念をこめて種々のものを捧げる、衣服・飲食物・寝具・薬品・花・香・装身具・旗など、密教では歌や踊りまで供養尊として人格化する
■護法尊・・・結界の要素、護法の要素を尊格化したもの、①四天王(持国・増長・広目・多聞) ②四大明王・八大明王 ③五大明王 ④四摂菩薩 ⑤八方天・十天・十二天 ⑥十忿怒尊
6.マンダラ世界への誘い
(1)マンダラとは何か?
「マンダ」→中心、心随、醍醐、「ラ」→所有を意味する接尾辞、心髄を円満するもの=エッセンスをもつもの=さとりを有する場=聖なる空間
◆特徴 ①空間、領域、場などの概念 ②複数性 ③調和性 ④動的な流れ
◆外のマンダラ(可視的マンダラ)・・・尊像マンダラ、象徴マンダラ、文字マンダラ、立体マンダラ 内のマンダラ(不可視的マンダラ)・・・精神マンダラ、肉体マンダラ
◆マンダラの性格 ①自性マンダラ・・・この世の世界に存するすべてが聖なるマンダラそのもの=法身 ②観想マンダラ・・・聖なる世界を眼前に現出し観想する。一定の行法によって完成された世界を一定の形に形象化=報身 ④形象マンダラ・・・具体的な姿・形をもった画像を借りて表現、その結果、あらゆる人々に聖なる世界を知らしめることが可能となる=化身
◆大・三・法・羯の四種のマンダラ ①尊像=大曼荼羅・・・図像として表現される諸尊のマンダラ ②象徴=三味耶曼荼羅・・・簡略化、各諸尊の性格や働きを象徴する持物や印相で置き換える ③文字=法曼荼羅・・・種字という単音節文字、もしくはそれを文章化した陀羅尼で表現、梵字 ④立体=羯曼荼羅・・・羯磨(カツマ)=行為
◆美術史での分類 ①都会マンダラ・・・すべての尊格からなるマンダラ ②部会マンダラ・・・諸尊のパンテオンのうちのひとつの部族(グループ)を描く、十一面観音マンダラなど ③別尊マンダラ・・・特定の尊格を本尊としてその眷属を配置したマンダラ、北斗マンダラなど
(2)多彩なほとけの誕生
◆両部・両界マンダラ・・・「大日経」に説く胎蔵(界)マンダラと「金剛頂経」に基づく金剛界マンダラを一対のセットとしたもの。
◆別尊マンダラ・・・大日如来以外の尊格を本尊とし、諸難を取り除く息災などのさまざまな修法を行う際の、本尊にあたるものとして。
◆神道マンダラ・・・神仏習合の初産として成立したマンダラ。
7.荘厳華麗な造形美術
(1)密教の絵画
◆密教美術の特徴・・・①新しいタイプの尊格が数多く登場している ②尊格の働きとして、悪しきものに対する威力を強調するため、ダイナミックな姿をした忿怒の明王像が重視される。③複数の尊格が並存するので、マンダラ的表現が有効な働きを果たしている。 ④人間のなまの感覚を肯定する結果として、造形表現の中に、官能的な要素が顕著に現れること。
◆祖師図・・・1.大日如来 2.金剛薩埵 3.竜猛菩薩 4.竜智菩薩 5.金剛智 6.不空 7.恵果 (善無畏、一行、) 8.空海
◆忿怒尊図・・・不動明王図(三不動→黄不動、青不動、赤不動)、五大力菩薩と五大明王
◆十二天図・・・帝釈天(東)、火天(東南)、焔魔天(南)、羅刹天(西南)水天(西)風天(西北)、毘沙門天(北)、伊舎那天(東北)梵天(天)、地天(地)、日天(日)月天(月)
(2)密教彫刻の尊像
◆中心は大日如来像、その他に、金剛薩埵像、五大明王像、五大虚空菩薩像、如意輪観音像など
(3)法具
①修法の場とその修法者を守る法具(結界、武器の要素) ②本尊、および修法者を浄める法具 ③本尊に供養するための法具 ④本尊を満足させる楽器系の法具
8.聖地・霊場の巡礼
(1)涅槃を目指す四国遍路
◆聖地・霊場の条件 霊場・・・霊験ある宗教的聖地、聖地・・・聖なる地域空間、巡礼・・・聖地や霊場を巡って信仰を深める宗教体験、条件として①タブーとされた場所 ②名刹・神祠など ③高僧・聖人などのゆかりの地 ④特定の尊格を祀る寺社
◆四国八十八ヵ所の遍路信仰 ①弘法大師空海・・・修行の場所 ②衛門三郎伝説・・・懺悔・贖罪の思想 阿波の国の霊山寺を第一番として、四石を右回りに巡拝し、讃岐の大窪寺を第八十八番の結願とするコース ①阿波の国=23ヶ所=発心道場 ②土佐の国=16ヶ所=修行の場 ③伊予の国=26ヶ所=菩提の場 ④讃岐の国=23ヶ所=涅槃の道場 本堂と大師堂、同行二人、遍路信仰は、治病や延命や学業成就などの諸願成就とともに、本人の犯した罪障の消滅のほか、父母兄弟など亡くなった有縁の人々の追善回向の役割をあわせ持つ傾向が強い。いわば、この世とあの世の祈願をともにそなえている。
◆遍路・巡礼は聖なる空間に直接参入する行為である。また、時間的に見ても、ある瞬間からは、身心を清めて聖なる時間を体験し、それが終われば、ある時点から元の俗なる時間に戻ってくるのである。その意味では巡礼は、聖なる空間と時間を体験する全身的行為であり、まさに密教の構図と異ならない。
9.現代に生きる密教
◆密教の4つの特徴 ①総合性・包容性 ②宇宙性・異次元性 ③体験性・直接性 ④芸術性・感覚性
 |
密教―悟りとほとけへの道 (講談社現代新書) |
| 頼富 本宏 | |
| 講談社 |

















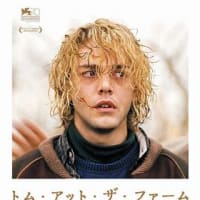







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます