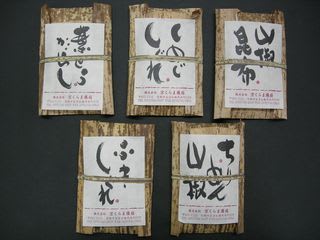今回の研修会において、特に私が興味を持ったのは、耐病性と収量増量を図る
ために開発さた、接木用の台木の種類の選定方法である。
以前、生産者の方々が、接木用の台木として
《トルバムは使い勝手がいいが赤なすはイマイチだ!》とかを聞いたので、
私はその先入観が有ったのであるが、タキイ種苗の研究とその使用用途の説明は
適宜使い分けするために台木の種類があるということを公表している。
すなわち、栽培手法や土壌性格に応じた台木の選定が必要であるという事に
気づいた。
で、
本日はなすの栽培方法について特に枝葉の伸展を促す方法について
参考とすることがあったので、記す事にする。
なすの果に傷がつきにくく、最良の方法かもしれない。

↑水茄子系のタキイ種苗開発品種で紫水である。
その姿は女性的で曲線美を持ち合わせている果の美しさは、
清楚でどこかかわいらしくもある。
私が原料として大阪府の泉州地域から直接買っているものとは少し果の形が
違うのであるが・・・・・。
以前この品種をトルバムの台木にて、淀の種苗農家に作ってもらい、
契約栽培で京都市北区上賀茂柊野で定植し栽培したときに、
良好な収量が確保できた事が有るので栽培が容易と考えられる品種でもある。
しかし、地温の管理が重要ということを栽培要点として捕らえすぎて、
収穫適期の後半に肥料切れを起こしたのであろうか急激に結実数が減って
あせった事がある。
即ち!肥料の管理と水管理に注意が必要である。
水は、絶えず圃場の土壌がぬめぬめでぬれていること、
株元に穴を開けて大量の穴肥えを施していたのであるが、
不良要因があったようである。
↓下記URLクリックで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4d/01/727fc1ec7039205c1cadf2bdd4d7598e.jpg

↑地面と平行にオレンジ色のネットが張られていて、なすの枝葉はその目の間を
伸張して、開花し結実している。合理的かつ効率的にも有利な栽培方法で
あると思う。以前のように枝を直接ナイロン紐で結ぶ手間も無く、
枝を誘引し網目にくぐらせるだけの作業ゆえ効率が良いと思うが・・・・。
↓下記URLクリックで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2f/04/6a6be31c161e8f83b565254a24e507e3.jpg

↑その、地面と平行に張られているオレンジ色のネットの状況をなすの木の上から
観察してみた。なすに干渉することなくその網は十分に枝を支え、
逆円錐状に広がるなすの枝の伸張を全方向にバランスを取りながら
促しているようである。
バランスが取れていることは、当然、風による揺れに強いわけで、
果皮の薄く傷から鮮度や商品価値の落ちる、水なすや賀茂なす、
山科なす等の高級なすについては、栽培方法としては最良の方法かもしれない。
↓下記URLで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/16/bf/4f9b14251923632ab85d5839b1468de4.jpg

↑水なす紫水の花である。強くカッと開いた展開した花弁は力強い。
いつも不思議に思うが、果菜の花はランダムな展開の向きであるが、
ひまわり等の一方向性に咲く花もあることを考えると植物の
自然界での決まり事は神秘的である。
何らかの開花ホルモンが作用しているのであろうが、
朝顔は朝に咲き、夕顔は夕に咲き、昼顔はカトリーヌドヌーブが主演で、
別のホルモンが作用し淫靡なイメージがある?ん。
↓下記URLクリックで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0d/c8/16d5207c2fdb88c4b54ed04dc353549b.jpg

↑長なすの品種で筑陽である収穫時に径で最大部3センチ以上、
長さが25センチほどになり、漬物用には少し使いにくいのであるが、
焼きなすやなす煮物、揚げ物に的確な品種であると思う。
果の短いうちに収穫を早めることによって漬物にも使用できるのであるが、
その容姿を生かすなれば加熱料理用に適していると考えられる。
私がなす栽培の基本を勉強させていただいたのが、この品種で、
京都府園部町船坂で実際に農地を借り受けて栽培しなすつくりの基本を
習得できた作りやすい品種である。
かの、普段の何処にでもいてる近所のおっちゃんだと思っていたが、
当時、官房長官に、圃場で声を掛けられた事がある。
《に~チャン何処の人?》《ええ、なすやな~。》
↓下記URLクリックで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/13/04/aec23f91f3849f193e1691659f03bfdd.jpg
ために開発さた、接木用の台木の種類の選定方法である。
以前、生産者の方々が、接木用の台木として
《トルバムは使い勝手がいいが赤なすはイマイチだ!》とかを聞いたので、
私はその先入観が有ったのであるが、タキイ種苗の研究とその使用用途の説明は
適宜使い分けするために台木の種類があるということを公表している。
すなわち、栽培手法や土壌性格に応じた台木の選定が必要であるという事に
気づいた。
で、
本日はなすの栽培方法について特に枝葉の伸展を促す方法について
参考とすることがあったので、記す事にする。
なすの果に傷がつきにくく、最良の方法かもしれない。

↑水茄子系のタキイ種苗開発品種で紫水である。
その姿は女性的で曲線美を持ち合わせている果の美しさは、
清楚でどこかかわいらしくもある。
私が原料として大阪府の泉州地域から直接買っているものとは少し果の形が
違うのであるが・・・・・。
以前この品種をトルバムの台木にて、淀の種苗農家に作ってもらい、
契約栽培で京都市北区上賀茂柊野で定植し栽培したときに、
良好な収量が確保できた事が有るので栽培が容易と考えられる品種でもある。
しかし、地温の管理が重要ということを栽培要点として捕らえすぎて、
収穫適期の後半に肥料切れを起こしたのであろうか急激に結実数が減って
あせった事がある。
即ち!肥料の管理と水管理に注意が必要である。
水は、絶えず圃場の土壌がぬめぬめでぬれていること、
株元に穴を開けて大量の穴肥えを施していたのであるが、
不良要因があったようである。
↓下記URLクリックで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4d/01/727fc1ec7039205c1cadf2bdd4d7598e.jpg

↑地面と平行にオレンジ色のネットが張られていて、なすの枝葉はその目の間を
伸張して、開花し結実している。合理的かつ効率的にも有利な栽培方法で
あると思う。以前のように枝を直接ナイロン紐で結ぶ手間も無く、
枝を誘引し網目にくぐらせるだけの作業ゆえ効率が良いと思うが・・・・。
↓下記URLクリックで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2f/04/6a6be31c161e8f83b565254a24e507e3.jpg

↑その、地面と平行に張られているオレンジ色のネットの状況をなすの木の上から
観察してみた。なすに干渉することなくその網は十分に枝を支え、
逆円錐状に広がるなすの枝の伸張を全方向にバランスを取りながら
促しているようである。
バランスが取れていることは、当然、風による揺れに強いわけで、
果皮の薄く傷から鮮度や商品価値の落ちる、水なすや賀茂なす、
山科なす等の高級なすについては、栽培方法としては最良の方法かもしれない。
↓下記URLで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/16/bf/4f9b14251923632ab85d5839b1468de4.jpg

↑水なす紫水の花である。強くカッと開いた展開した花弁は力強い。
いつも不思議に思うが、果菜の花はランダムな展開の向きであるが、
ひまわり等の一方向性に咲く花もあることを考えると植物の
自然界での決まり事は神秘的である。
何らかの開花ホルモンが作用しているのであろうが、
朝顔は朝に咲き、夕顔は夕に咲き、昼顔はカトリーヌドヌーブが主演で、
別のホルモンが作用し淫靡なイメージがある?ん。
↓下記URLクリックで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0d/c8/16d5207c2fdb88c4b54ed04dc353549b.jpg

↑長なすの品種で筑陽である収穫時に径で最大部3センチ以上、
長さが25センチほどになり、漬物用には少し使いにくいのであるが、
焼きなすやなす煮物、揚げ物に的確な品種であると思う。
果の短いうちに収穫を早めることによって漬物にも使用できるのであるが、
その容姿を生かすなれば加熱料理用に適していると考えられる。
私がなす栽培の基本を勉強させていただいたのが、この品種で、
京都府園部町船坂で実際に農地を借り受けて栽培しなすつくりの基本を
習得できた作りやすい品種である。
かの、普段の何処にでもいてる近所のおっちゃんだと思っていたが、
当時、官房長官に、圃場で声を掛けられた事がある。
《に~チャン何処の人?》《ええ、なすやな~。》
↓下記URLクリックで拡大画像
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/13/04/aec23f91f3849f193e1691659f03bfdd.jpg