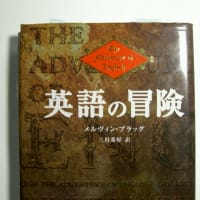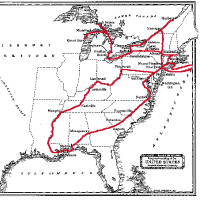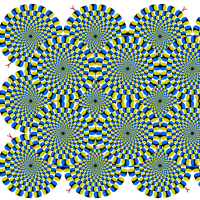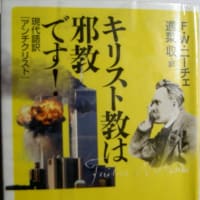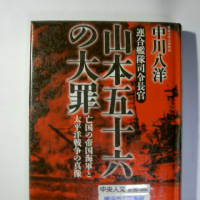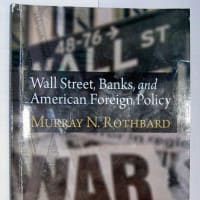言語がそれを使う民族の考え方や物のとらえ方を表していることは間違いのないことですが
西周(にしあまね、1829~1897)が意図してrational に理性を充てたのかはわからない。
もともとシナにおいての理とは、天理すなわち「宇宙がかくある根拠」であり「格物窮理」の理であろう。
・・
西洋人の考え方の代表をデカルトの「我思うゆえに我あり」と朱子学の「豁全貫通」(※1)は瓜二つの
ごとくである。デカルトは、「私」が疑わしいものを前に置き、その確実性を吟味しながら、突然その懐疑を
放棄して「私」という存在があるから疑うことができると、究極の論理のスリ替えをすずしい顔で成し遂げる。
朱子学における「格物窮理」のプロセスもほぼ同じで、静坐により絶え間なく動く心(「已発」の状態)を静坐により静めて、物の本質に迫る過程を「格物窮理」としているが、どんな状態になれば理に格するのかは一切説明できなず、あるとき突然に本質がわかることを「豁全貫通」とする。
英米人とシナ人はおなじ程度の浅い意識(第6識)での認識レベルにとどまっているのでしょう、
・・
なぜ、米国人がシナ人に親近感を無条件にもつのか、その大きな理由の一つが思索階級が同レベルということではと思います。
西周(にしあまね、1829~1897)が意図してrational に理性を充てたのかはわからない。
もともとシナにおいての理とは、天理すなわち「宇宙がかくある根拠」であり「格物窮理」の理であろう。
・・
西洋人の考え方の代表をデカルトの「我思うゆえに我あり」と朱子学の「豁全貫通」(※1)は瓜二つの
ごとくである。デカルトは、「私」が疑わしいものを前に置き、その確実性を吟味しながら、突然その懐疑を
放棄して「私」という存在があるから疑うことができると、究極の論理のスリ替えをすずしい顔で成し遂げる。
朱子学における「格物窮理」のプロセスもほぼ同じで、静坐により絶え間なく動く心(「已発」の状態)を静坐により静めて、物の本質に迫る過程を「格物窮理」としているが、どんな状態になれば理に格するのかは一切説明できなず、あるとき突然に本質がわかることを「豁全貫通」とする。
英米人とシナ人はおなじ程度の浅い意識(第6識)での認識レベルにとどまっているのでしょう、
・・
なぜ、米国人がシナ人に親近感を無条件にもつのか、その大きな理由の一つが思索階級が同レベルということではと思います。